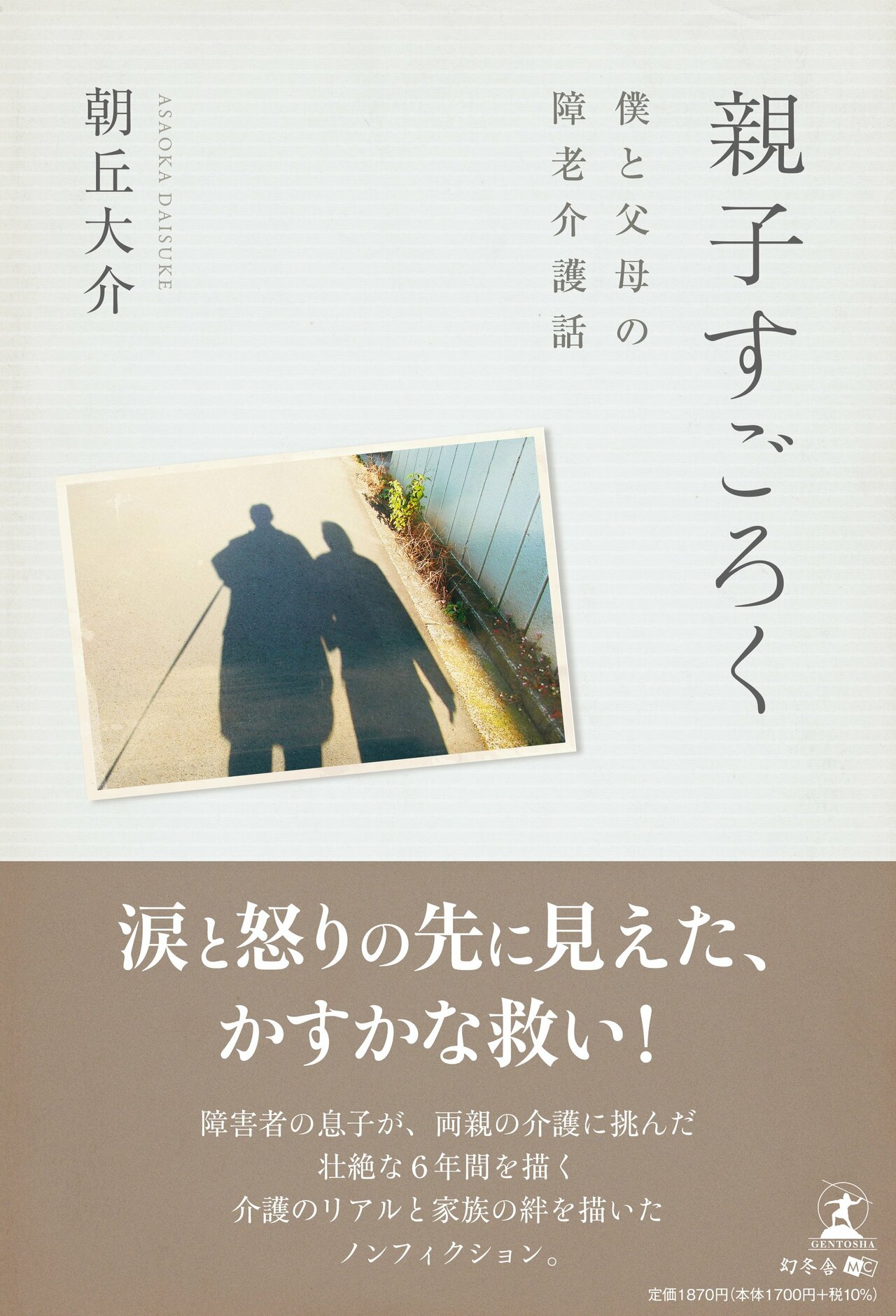毎食後に痛み止めを飲んでいたが、それでも損傷部の疼痛は消えない。アスファルトにえぐられた皮膚のヒリヒリとした痛み。骨の芯からズキンズキンくる骨折部の痛み。特に左の股関節と下腿がひどい。
時間はなかなか過ぎない。
体が疲れても寝返りがうてず、膝も曲げられず、下肢の重みがそのまま踵にかかるせいで踵の皮膚が爪のように硬くなり、床ずれができていた。
この病室ではみな、カーテンを閉ざしていた。
右のベッドから、クチャクチャと物を食べる音が聞こえる。左の患者は、イヤホンをしてテレビを見ているようだ。音はしないが、チャンネルを変えるたびにテレビの光がチカチカとカーテンに反射する。新聞をめくる音、寝つけないため息、片足だけ強い足音、ポテトチップスを食べる音、咳ばらい、おならの音……言葉はかわさなくても、互いの情報が筒抜けになっていた。
これが窓ぎわなら、すこしは気分転換を図れるのかもしれないが、生憎とベッドは左右のベッドに挟まれたど真ん中だ。僕は、必死に退屈を埋めようと試みた。時間は膨大にある。いろいろと試みるうちに“架空のライブ”という遊びをやるようになった。
これは、僕が学生の頃に聴いたロックやポップスをアルバムの一曲目から順番に歌っていくというものだ。もちろん六人部屋なので地声では歌えない。ほとんど口パクだ。なんとも馬鹿げた遊びなのだが、これがなかなかいい退屈しのぎになった。まったく体を動かせない状態で時間をやり過ごすには、打ってつけなのだ。
ブライアン・アダムスの「ヘヴン」を口ずさんでいると、遠くから複数の足音が足早に近づいてきた。サッとカーテンが開いて、五十を過ぎた黒縁眼鏡の白髪男が、看護師を数人従えて入ってきた。石橋院長だ。院長はショートカットの看護師に手渡されたカルテに目を通し、ぎろりと僕を見た。
「どうだね、調子は」
「特に変わりはないです」
ショートカットの看護師があわてて肘の包帯をほどき、若い小さな看護師が膝の包帯をほどく。
ほかの者は後ろに立ちつくしている。両膝に貼りついたガーゼが取られると、ぬめりと赤く血が光って傷口が現れた。
看護師が二人、同時に消毒を始めた。鼻眼鏡越しに傷口を見ながら院長が言った。
「キミは特殊な体質をしているんだな。弱いんだよ、キミの皮膚は。だから、血が固まらないんだ」
【前回の記事を読む】車に撥ねられ救命救急病棟へ。相手に業務上過失傷害をつけるかと聞かれて〇〇と即答