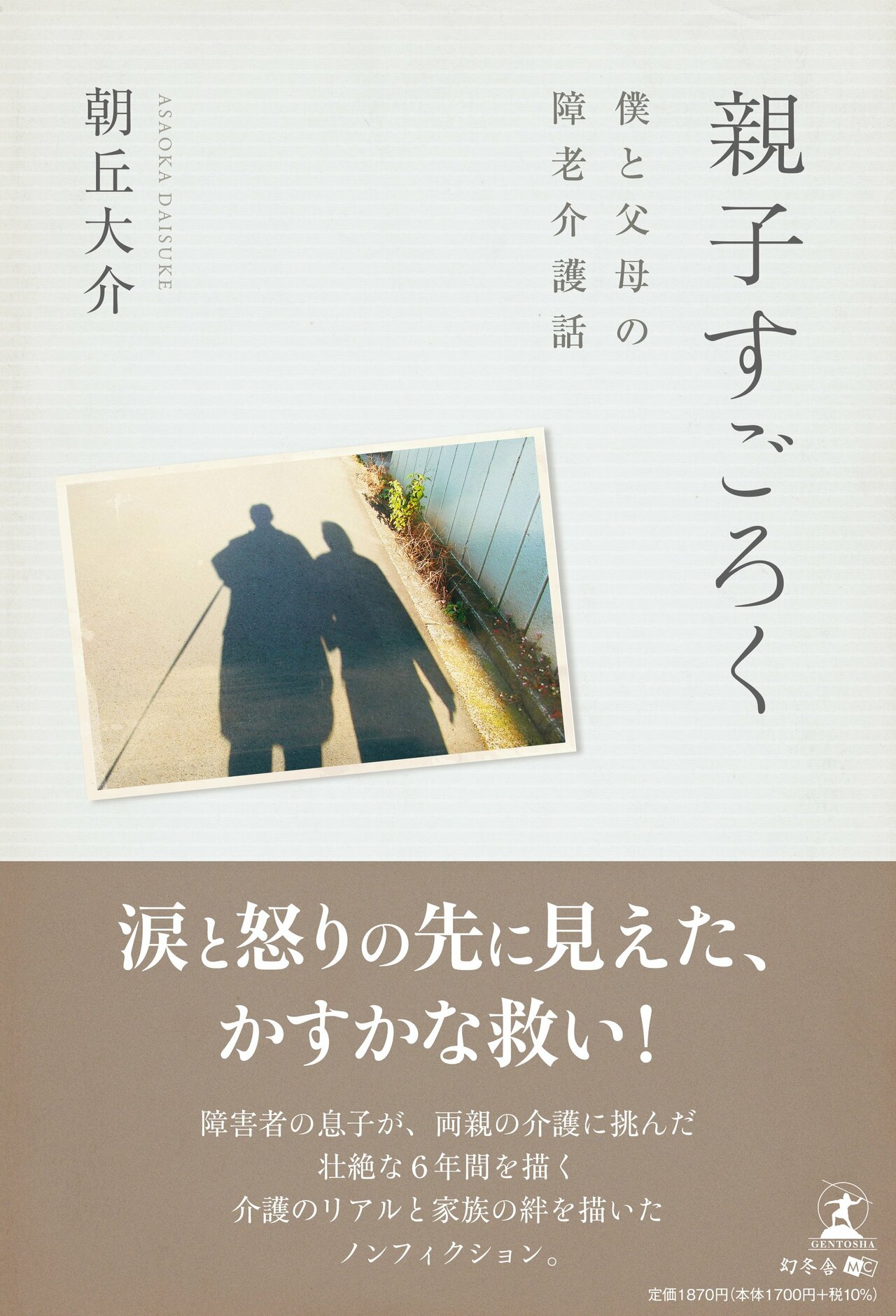【関連記事】新たな就職先が決まっても悪夢にうなされる僕は…「旅に出ることにした」
リセット
車椅子を押してもらいながら、僕は話しかけた。
「ねえ、お姉さん」
「お姉さんなんて呼ばないで。ここはキャバクラじゃないんだから」
「じゃあ、なんて呼べばいいの?」
「看護師さん」
「ああ、看護師さん。……いや、斉藤さんにしよう」
車椅子を押している斉藤さんは、担当の看護師だ。意識を取りもどしてからほぼ毎日、身のまわりの世話や検査のつき添いをしてくれている。新婚ほやほやで、充実したオーラが漂っている。北海道の人だからなのか、色が白かった。
「ねえ、斉藤さん。名前の横に貼ってある、あのシールは何?」
各部屋の入口には患者の名札があり、その横には赤や緑の丸いシールが貼られている。
「患者さんの状態よ」
「状態?」
「うん。赤は寝たきり。黄色は要介助。緑はある程度自立している患者さんだったかな」
「ふうん、だから僕は黄色なのか」
「詳しく知りたかったら、ほかの看護師さんに訊いてみて」
「いや、いいよ。……てっきり僕は、赤はハゲで緑はフサフサなのかと思っていたよ」
「内科に行ったら、そんなこと言えないよ。病気が重い人とか、たくさんいるんだから」
「……そうか」
「そうよ」
車椅子は廊下をまっすぐに進み、ナースステーションの前で右に折れた。
「でも、どうして僕は六人部屋とかの大部屋じゃないの?」
「まだ事故で神経が昂ぶっているからでしょ」
廊下を突きあたりまで行くと、分厚い金属の扉があった。壁の足元に四角い穴があり、斉藤さんがつま先を入れると、扉がゆっくりとスライドした。扉の向こうはピンク色のタイルが貼られた十畳ほどの浴室で、中央にリフトつきの浴槽が鎮座している。
消毒液のツンとした臭いがあたりに広がっていた。入ってすぐの所に車椅子用の洗面台があった。床屋でシャンプーするときのあれと、ほぼ同型のものだ。洗面台の正面に車椅子が停められ、僕は鏡に映った自分の顔を見た。寝たきりの状態が続いていたためか、前髪は逆立ち、真上に伸びている。まるでパイナップルだ。口元から顎にかけて、無精ひげが生い茂っていた。