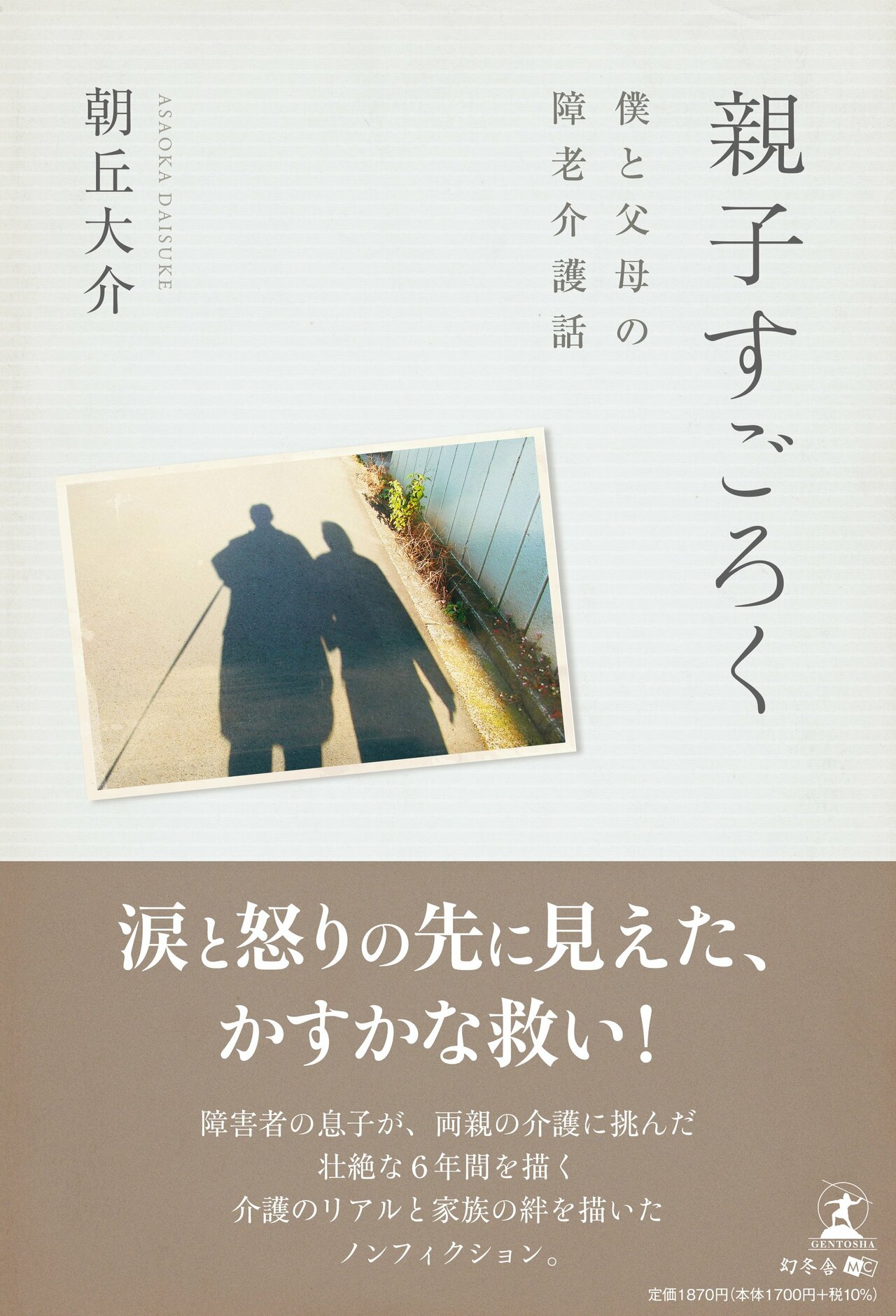事故前は鏡に向かえば視線はすぐに剃りこみへいったが、今は右の頬にできた、五百円玉大の赤黒い傷痕が強烈に目をひいた。轢かれた際、アスファルトに削られたのだろう。我ながらひどいものだ。
斉藤さんはシェービングクリームをゴルフボールほど手に取ると、僕の頬から顎にかけて泡で覆っていった。剃刀をスーッと滑らせていく。刃が通ったあとの肌がツルツルの無毛地帯になっていく。右の頬を剃るため頭を左側に向けたとき、僕は彼女にたずねた。
「ねえ、この傷痕は一生残るのかな」
「んもー、十六や十七の乙女じゃあるまいし。なに気にしてるの」
斉藤さんはそう言って、僕の頭を指でこづいた。
「来見谷さん、頭をもうすこし手前に出せる?」
シャンプーを手に取って、斉藤さんが言った。僕は黙って洗面台に頭をたれた。斉藤さんの手がマッサージするように、やさしく頭皮を揉んでいく。
「かゆいとこは?」
「ないです」
目を閉じたまま答える。
入院以来、初めての洗髪だ。そういえば、事故前は朝晩かならず頭を洗っていた。それが、ここ数週間洗っていないはずなのに、フケもかゆみもない。シャンプーは嬉しかったが、若い女性に真上から頭を見られることには、やや抵抗があった。薄くなってきていると自覚してから、人前で頭頂部を晒すことはなかった。いつも顎をあげ、お辞儀は顔を正面に向けたまました。斉藤さんがシャワーノズルを手に取り、湯加減を調節する。
「ねえ、斉藤さん。赤い髪の看護師さんって、この病棟にいる?」
「え。そんな人、ここにはいないよ。……どうして?」
「いや、なんでもない。僕の思い違いかなぁ」
それにしても、あの赤い髪の、白衣の女は誰だったのだろう。たしかにベッドサイドで僕を見下ろしていた。