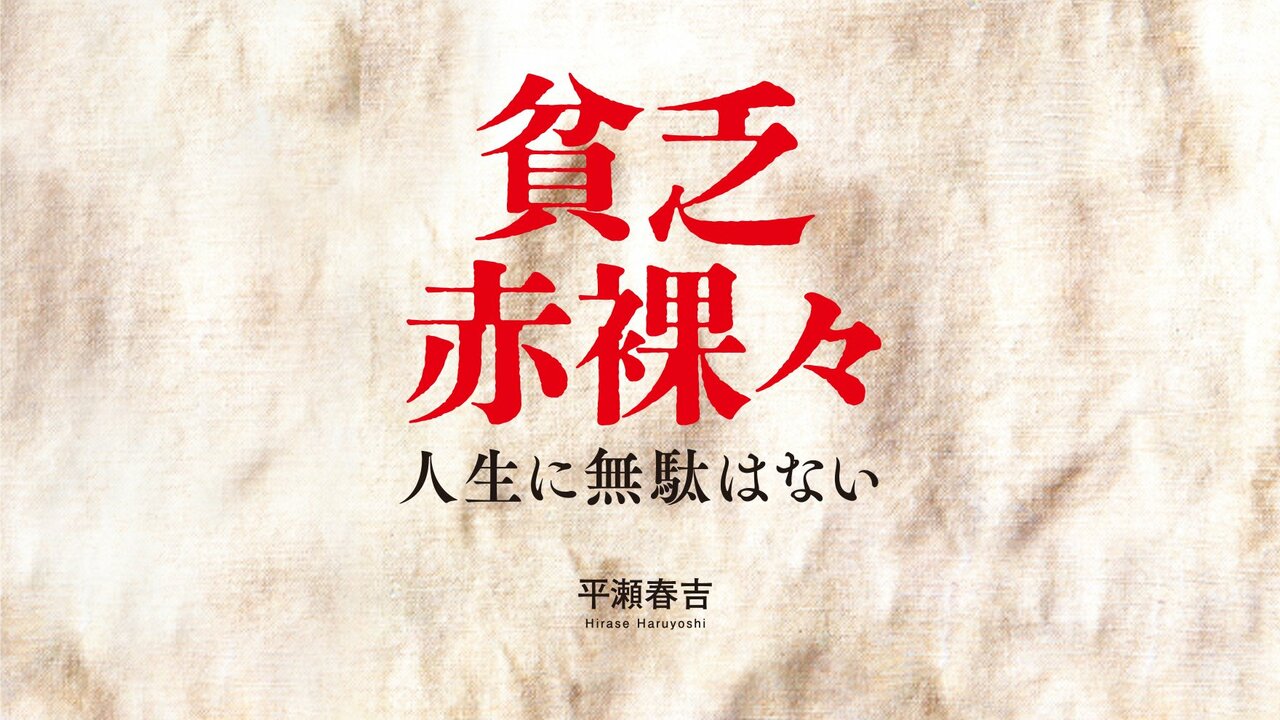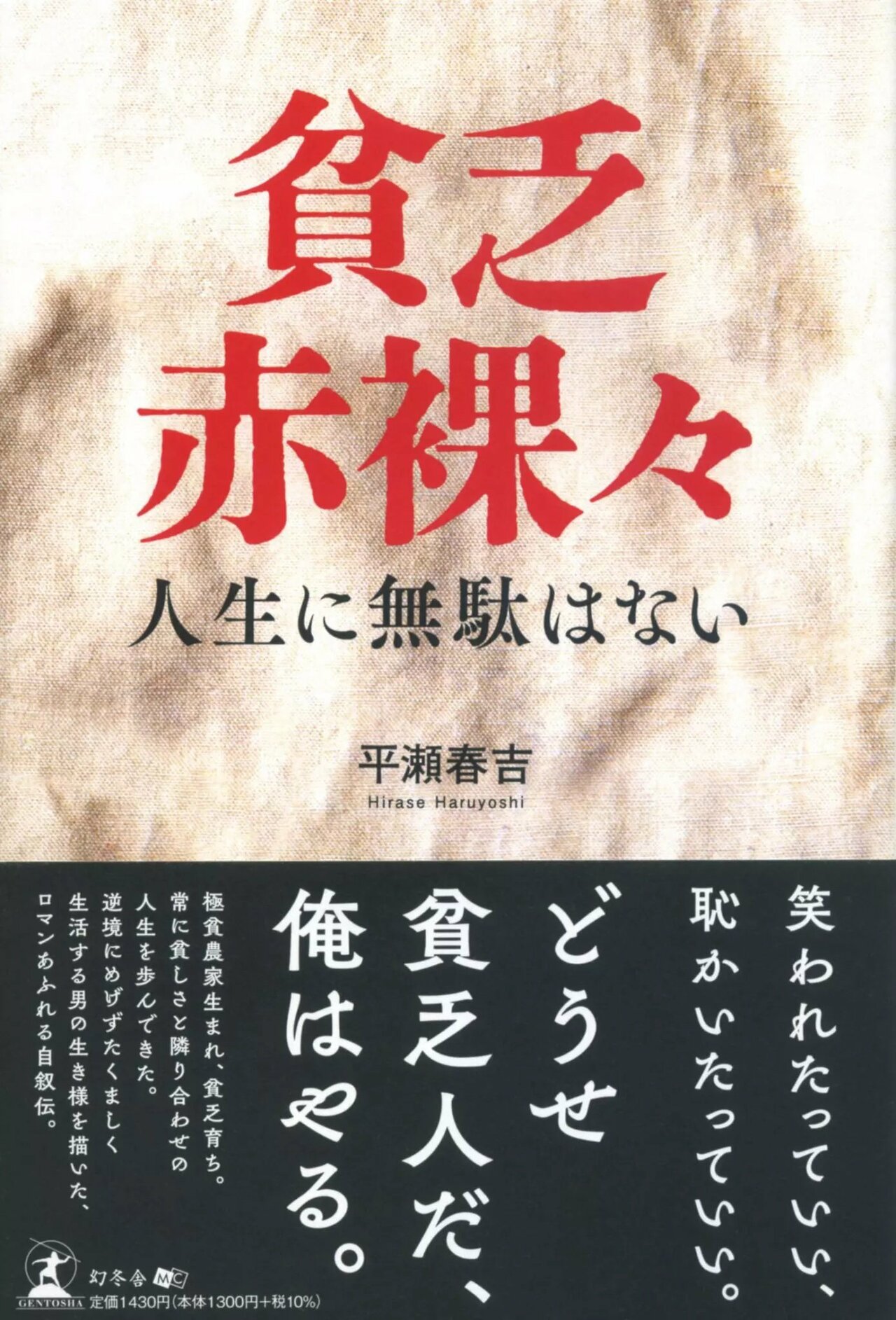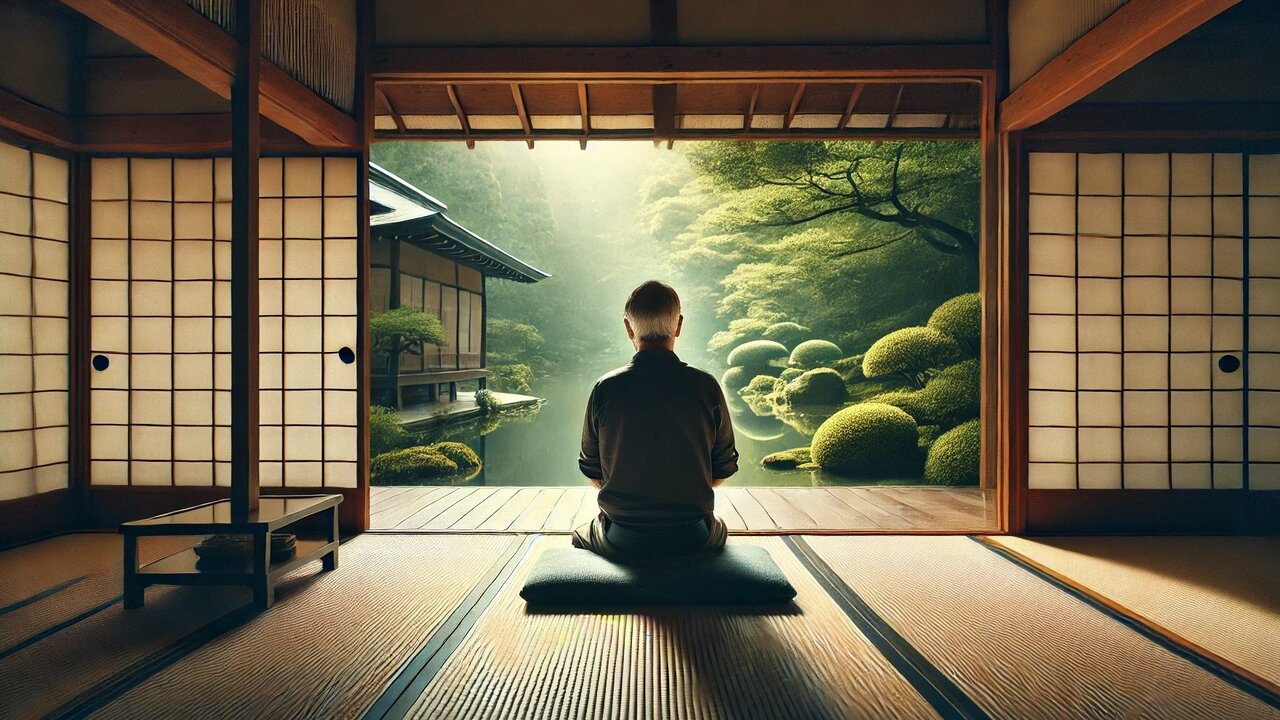【前回の記事を読む】「今夜はどこで寝られるか」六才か七才の子が自分の布団もなく、毎晩大人の顔色をうかがって…
極貧の足跡をたどる(昭和十八年~四十二年)
時計屋へ住み込む
初めて田舎を離れ、赤の他人の家に住み込み、時計修理を覚えることになった。親方は俺一人で間に合っていると言って他の店を紹介されたが、戻って再度お願いした。私の事情も汲んで頂き、給料は出せないが、それでよければ仕事はしっかり教えるとのこと。
二十歳近くであり他の人より大きく出遅れているため、手に職をつけることが先決。技術がお金になると考えた。素朴さが奥さんにもよかったようで、お世話になることに決めた。三年間の無給生活の始まりであった。親は余所ゆきの服が無いから挨拶に一度も来たことはなく、貧乏人の最たるものだ。田舎から急に街の生活に入り、何事も一からの勉強だった。
入店した次の日、ネジ巻き柱時計機械の側面の図を書かされ、動力の流れの仕組みを覚えた。すぐに時計を触らせる店は無いと聞いていたので、ありがたいと思った。お客や電話の応対、問屋の使いなど基本的なことを教わる。親方が丁稚小僧の頃は、子守りまでさせられた話をしていた。
下着の洗濯を生まれて初めてやったら、おばあちゃんが再度洗い直していた。それからはパンツ以外は洗ってもらった。私の襟をめくって
「お兄ちゃん、汚れているから脱ぎなさい」
と促された。入って四ヶ月目で正月、雑煮の餅は何個食べるかと聞かれたが、余分に食べることはできないと思った。お米を生産する田舎と、消費する街との違いなのだ。
正月に満二十歳になったとき、上等な背広を買ってもらった。背広を着るのは初めてだったので、写真店で記念に写真を撮ってもらった。日頃の言葉づかいは奥さんからの教育。
「知らなかったではなく、分からなかったと言いなさい」
「旨かったではなく、美味しかったと言いなさい」
何かで田舎へ行って時計屋へ帰ったとき、隣の歯医者の奥さんが遊びに来ていた。
「ただいまー」
と言ったのに、後からしっかり怒られた。一年後ぐらいに全く偶然に同じ場面になった。今度は手をついて
「ただいま帰りました」
と挨拶。歯医者の奥さんが
「お宅の若衆も、ずいぶん立派になりましたねー」
と言うと、時計屋の奥さんは
「ええ、お陰様で」
と笑顔を見せていた。このときの嬉しそうな顔を見て、自分の家の若者を人様から誉められることが、すごく嬉しいことなんだと初めて知った。