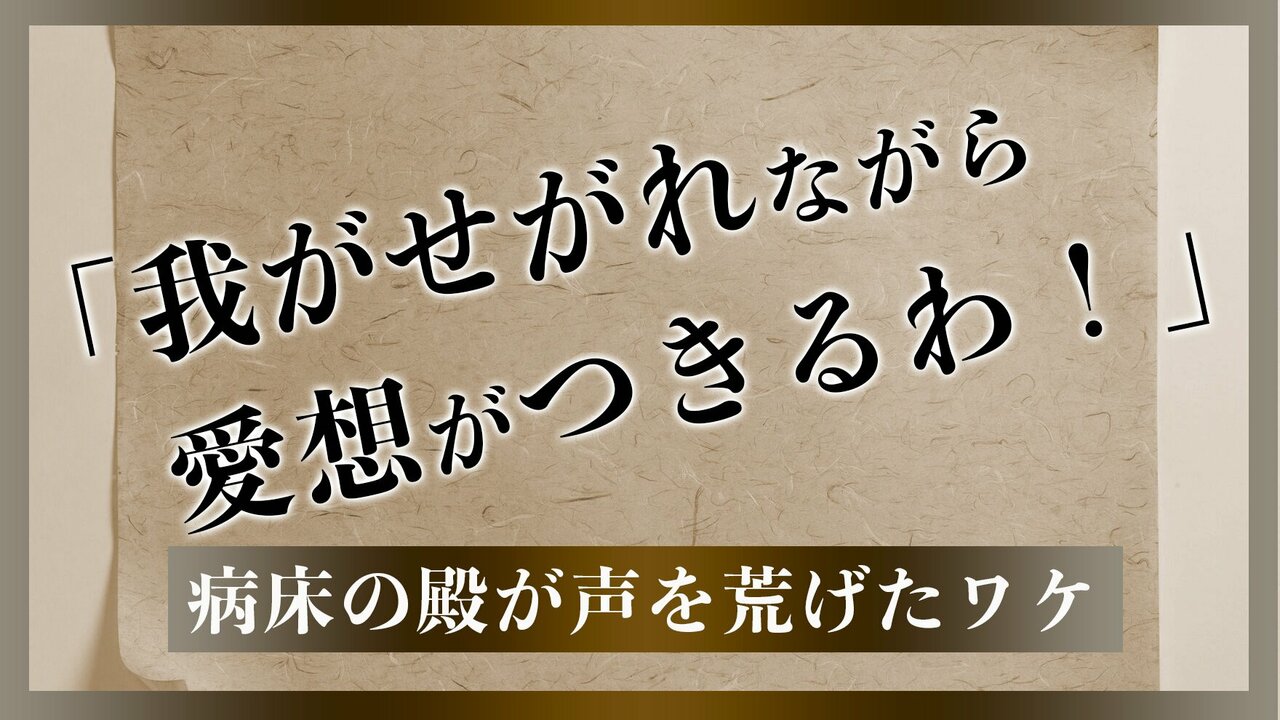第一章 阿梅という少女
七
片倉久米介と名乗った幼児が、実は真田左衛門佐どののご二男であることを知る者は、伊達陸奥守さま以外はお殿さまと重綱さま、阿梅姉妹とわたくし、そしてお供の二人だけだという。絶対に他に知られてはならない秘密であった。どこでどう間違って公儀の耳に届かないでもない。
残党狩りは七月のお布令をもって終わったそうだが、大八君が姓も名も変えて生きるということは、単純にお布令だけを信じてはならぬ、ということなのだろう。これから何十年先でも公儀に知られれば、片倉家にとどまらず伊達家をも揺るがす大事になると、肝に銘じなければならない。
お殿さまはもはや起き上がる体力も気力もない。命旦夕に迫っていた。片倉久米介をじっとご覧になって、お殿さまの落ちくぼんだ眼窩に心情の高揚の色がさすのを、わたくしははっきり見たような気がした。
枯れ枝のような手を動かして、言葉もなく大八君にもっと近づくようにと促しているようであった。大八君は作法どおりの膝行をしたが、なんとそのままお殿さまの手を、幼い両手で握りしめてしまったのだ。
わたくしは、はっと胸を突かれて阿梅を見やると、阿梅も心配そうに腰を浮かしている。作法なら、一度もっと手前でとどまり平伏すべきであった。大八君は一気に膝を進めて、お殿さまに体ごと投げ出すようにして、その手を握ったのだ。みなが息を呑んで見守った。
お殿さまはもはやこみ上げる感情を言葉に表すこともできず、何とも言えない慈愛に満ちたお目に涙をためて、じっと孫を見るように四歳の大八君を見つめられていた。お胸に去来するものは何だったろう。お殿さまが静かに息を引き取られたのは、それから間もない、元和元年十月十四日のことだった。
深々と息を吸い、ため息のように息を吐いて、片倉小十郎景綱さまは五十八歳の人生を終えられたのだった。