1.「みやけ」庶民には関係の無い「屯倉」の文字風土記の場合は、それが八・九世紀以降のものであるために、正倉(院)の造営によって、「屯倉」という言葉が死語になってしまった、とも考えられます。しかし、それでも風土記の昔の記述の中に「屯倉」の表記が一件もないということは、以前から民衆の間で「みやけ」は「穀物倉庫=御宅(豪族の屋敷)」であって、そもそも「屯倉」と表記するという意識がなかったことが考えられ…
日本書紀の記事一覧
タグ「日本書紀」の中で、絞り込み検索が行なえます。
探したいキーワード / 著者名 / 書籍名などを入力して検索してください。
複数キーワードで調べる場合は、単語ごとにスペースで区切って検索してください。
探したいキーワード / 著者名 / 書籍名などを入力して検索してください。
複数キーワードで調べる場合は、単語ごとにスペースで区切って検索してください。
-
歴史・地理『僕の古代史』【第4回】橋本 正浩

朝廷の直轄領を表す「屯倉(みやけ)」。民衆にとっては「穀物倉庫=御宅(豪族の屋敷)」
-
歴史・地理『6~7世紀の日本書紀編年の修正』【第14回】牧尾 一彦

持統元年正月に諸司に頒布された暦は新暦施行に向けた準備であった!
-
歴史・地理『僕の古代史』【第3回】橋本 正浩

故郷を「国」と呼ぶ理由は?古代の「みやけ」=里、郷=クニの名残!
-
歴史・地理『6~7世紀の日本書紀編年の修正』【第13回】牧尾 一彦

日本最古の暦「元嘉暦(げんかれき)」。持統天皇の代に使用された太陰太陽暦
-
歴史・地理『僕の古代史』【第2回】橋本 正浩

国家が先か屯倉(みやけ)が先か?「みやけ」の本来の意味は…
-
歴史・地理『6~7世紀の日本書紀編年の修正』【第12回】牧尾 一彦
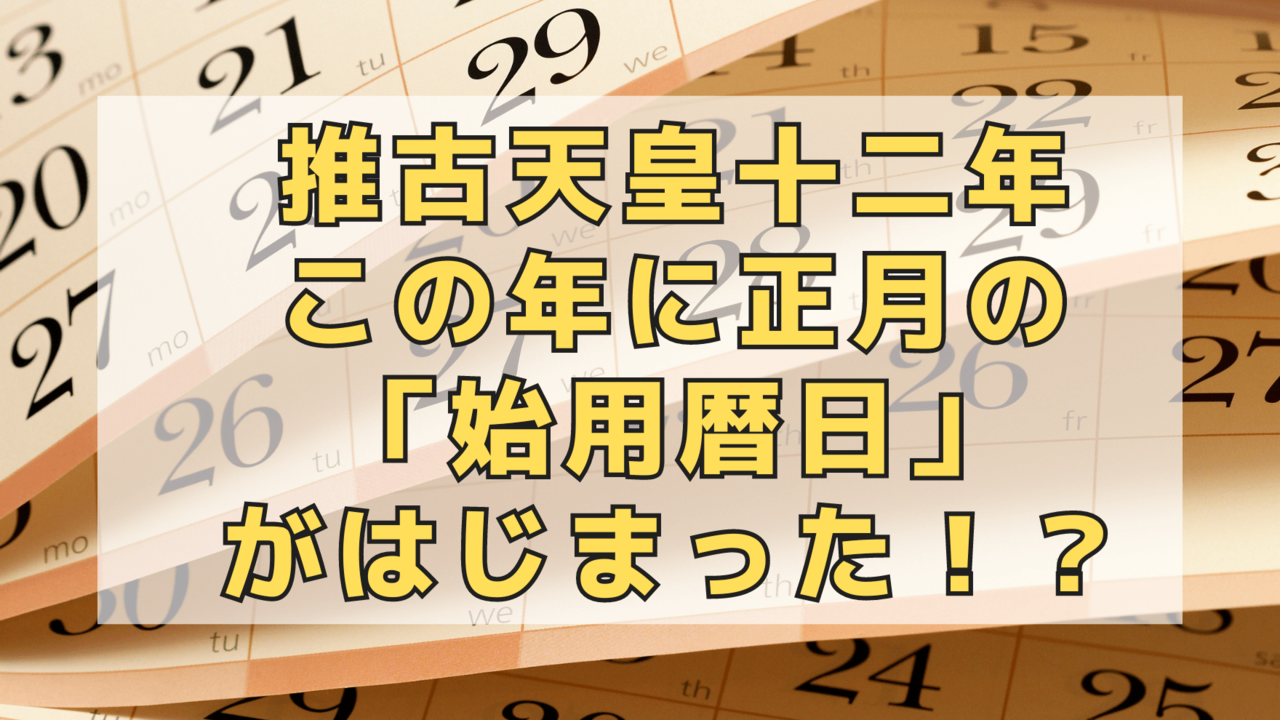
推古天皇十二年。この年に正月の「始用暦日」がはじまった!?
-
歴史・地理『僕の古代史』【新連載】橋本 正浩

稲作の広がりに併せて全国に広がった、古代社会の基盤と思われる「みやけ」の解明
-
歴史・地理『6~7世紀の日本書紀編年の修正』【第11回】牧尾 一彦
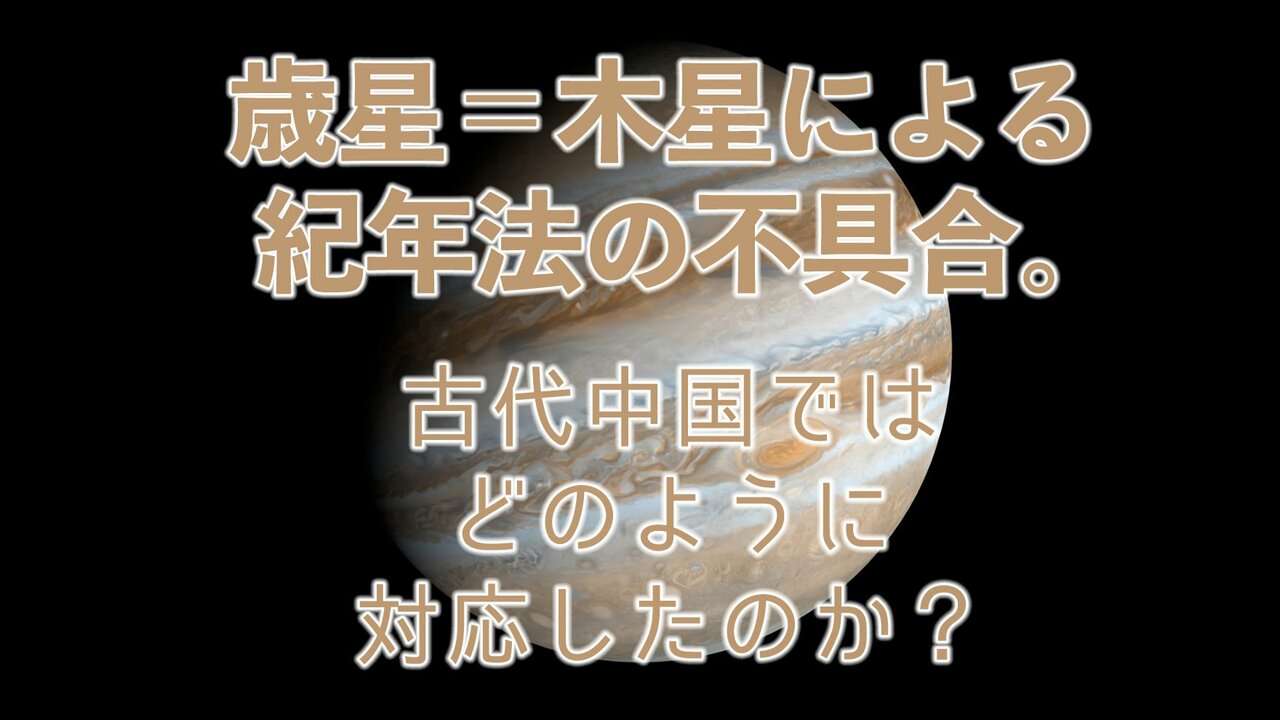
歳星=木星による紀年法の不具合。古代中国ではどのように対応したのか?
-
歴史・地理『6~7世紀の日本書紀編年の修正』【第10回】牧尾 一彦
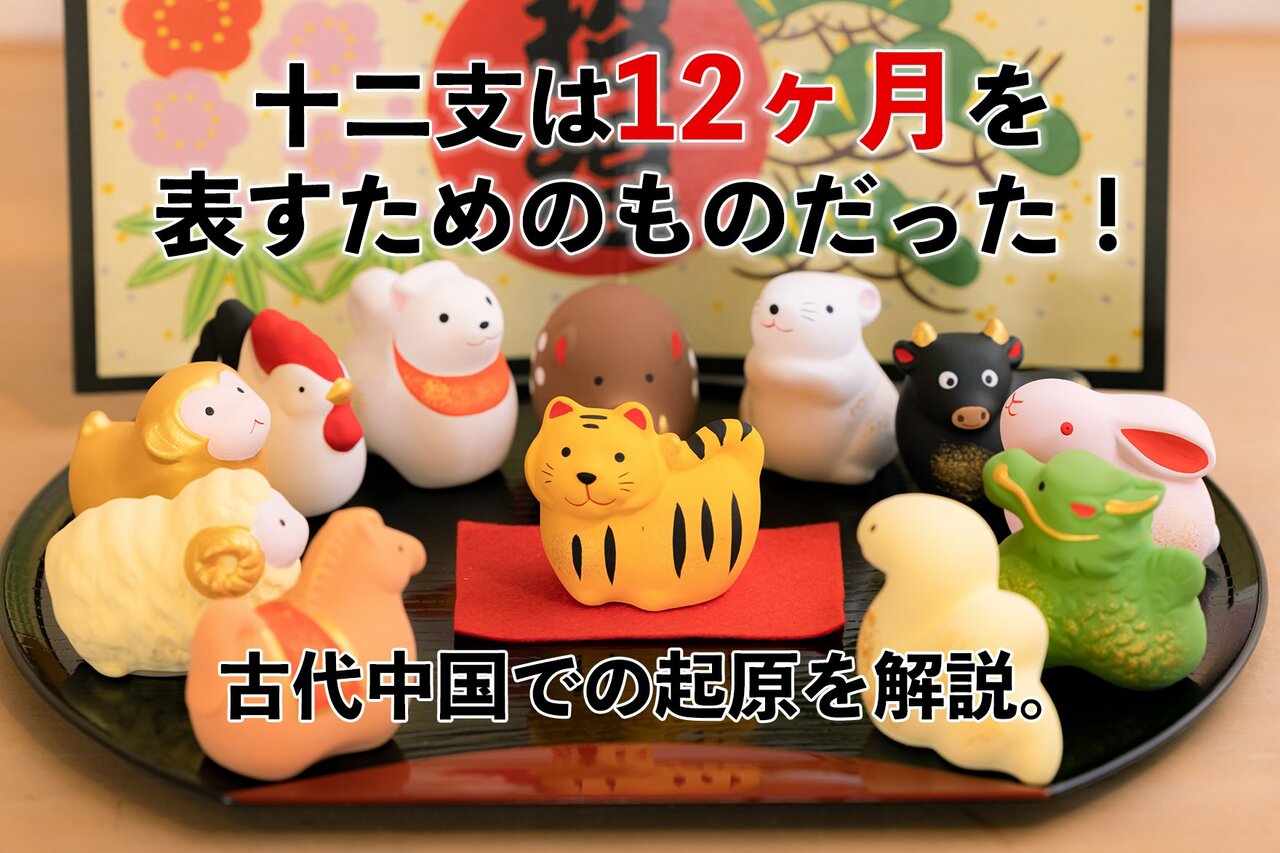
十二支は12ヶ月を表すためのものだった!古代中国での起源を解説。
-
歴史・地理『6~7世紀の日本書紀編年の修正』【第9回】牧尾 一彦

【日本書紀】顓頊暦を使って、古代人の手計算に近いものを体験!
-
歴史・地理『6~7世紀の日本書紀編年の修正』【第8回】牧尾 一彦
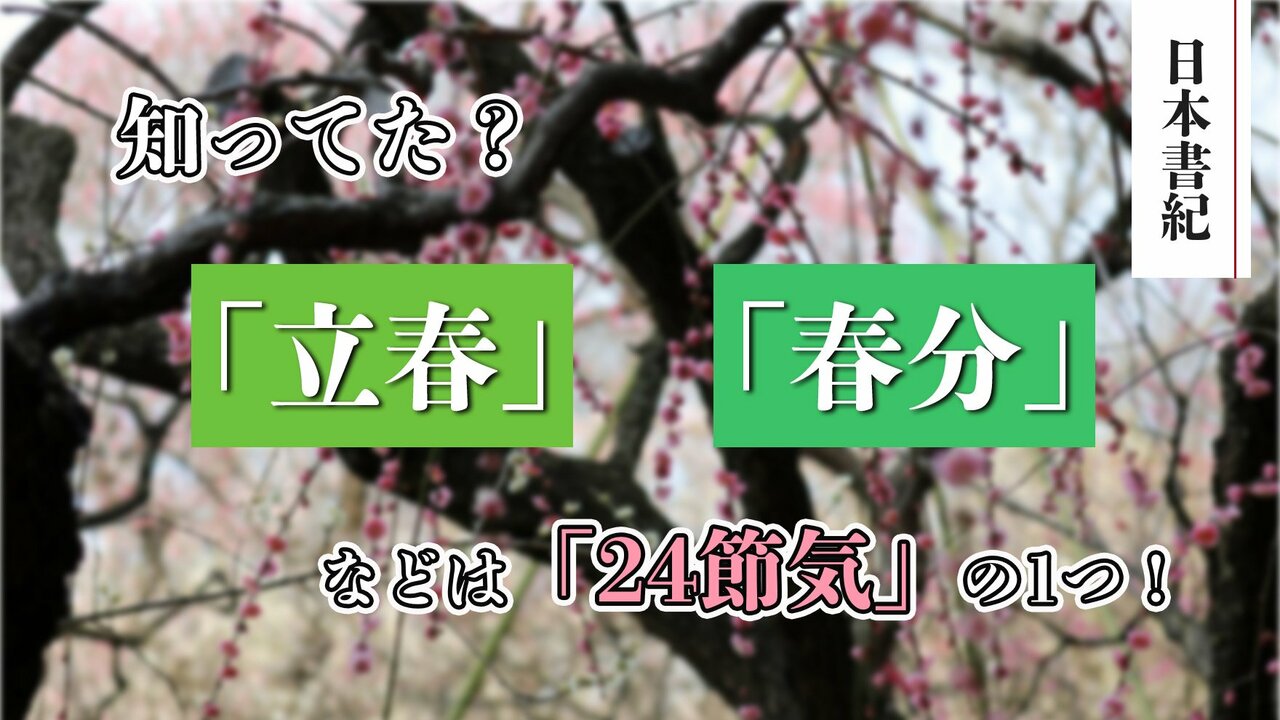
【日本書紀】知ってた?「立春」「春分」などは「24節気」の1つ!
-
歴史・地理『6~7世紀の日本書紀編年の修正』【第7回】牧尾 一彦
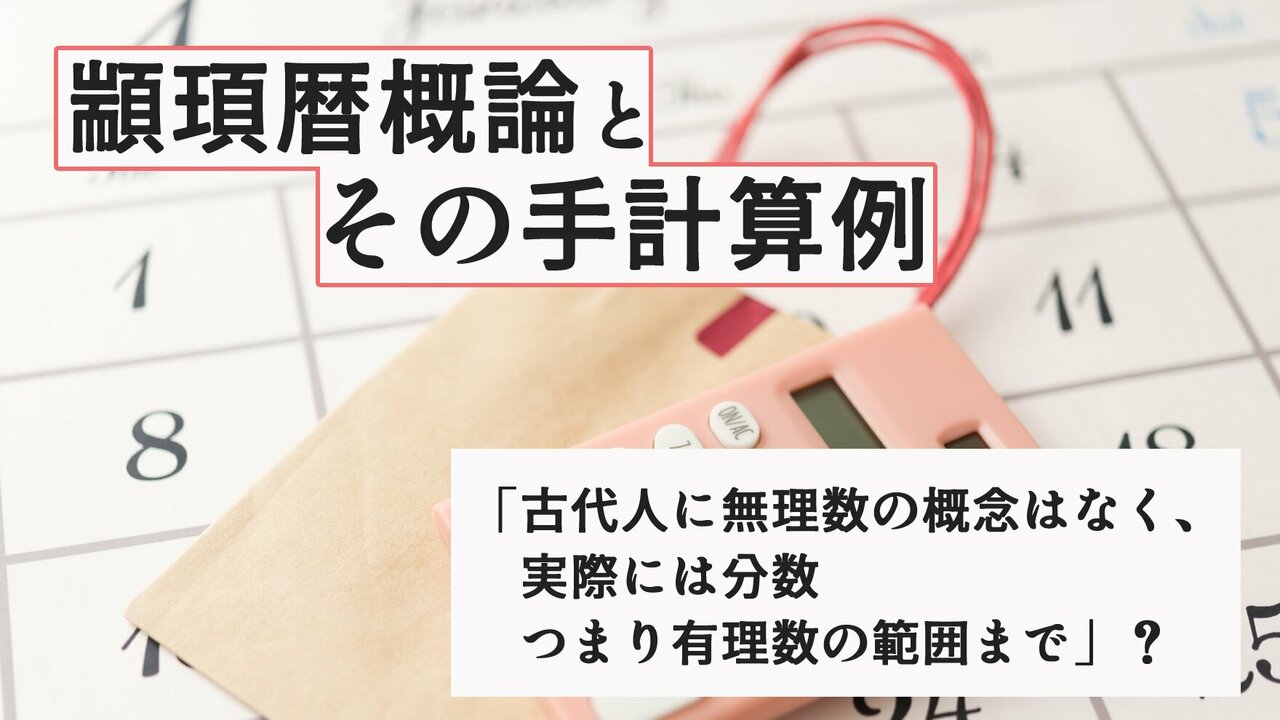
「古代人に無理数の概念はなかったから…」顓頊暦概論を手計算で算出!
-
歴史・地理『6~7世紀の日本書紀編年の修正』【第6回】牧尾 一彦
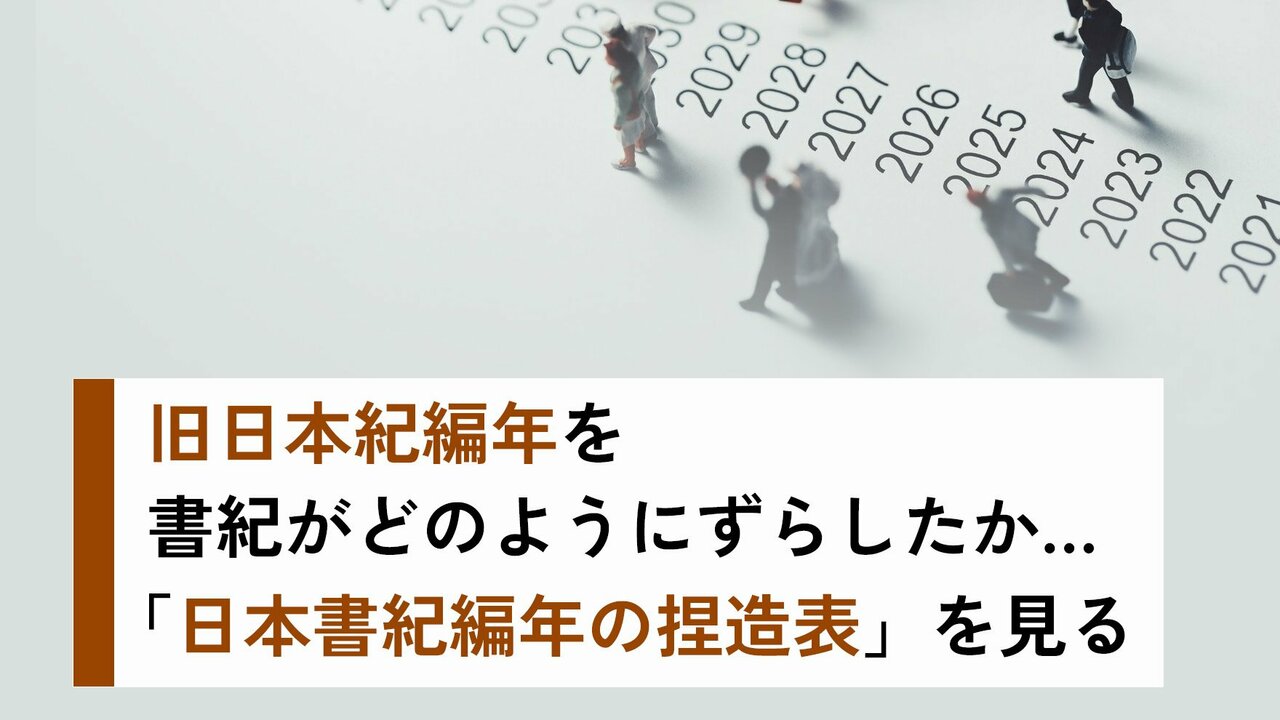
旧日本紀編年を書紀がどのようにずらしたか…「日本書紀編年の捏造表」を見る
-
歴史・地理『6~7世紀の日本書紀編年の修正』【第5回】牧尾 一彦
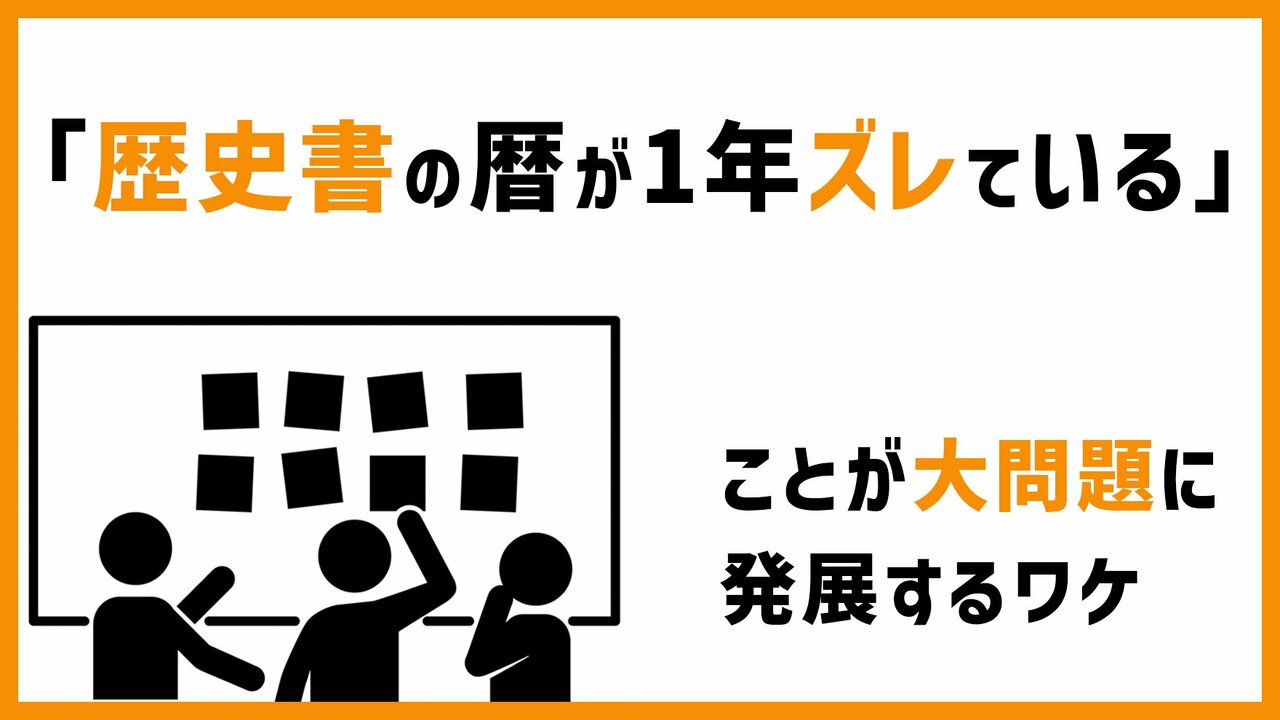
「歴史書の暦が1年ズレている」ことが大問題に発展するワケ
-
歴史・地理『6~7世紀の日本書紀編年の修正』【第4回】牧尾 一彦
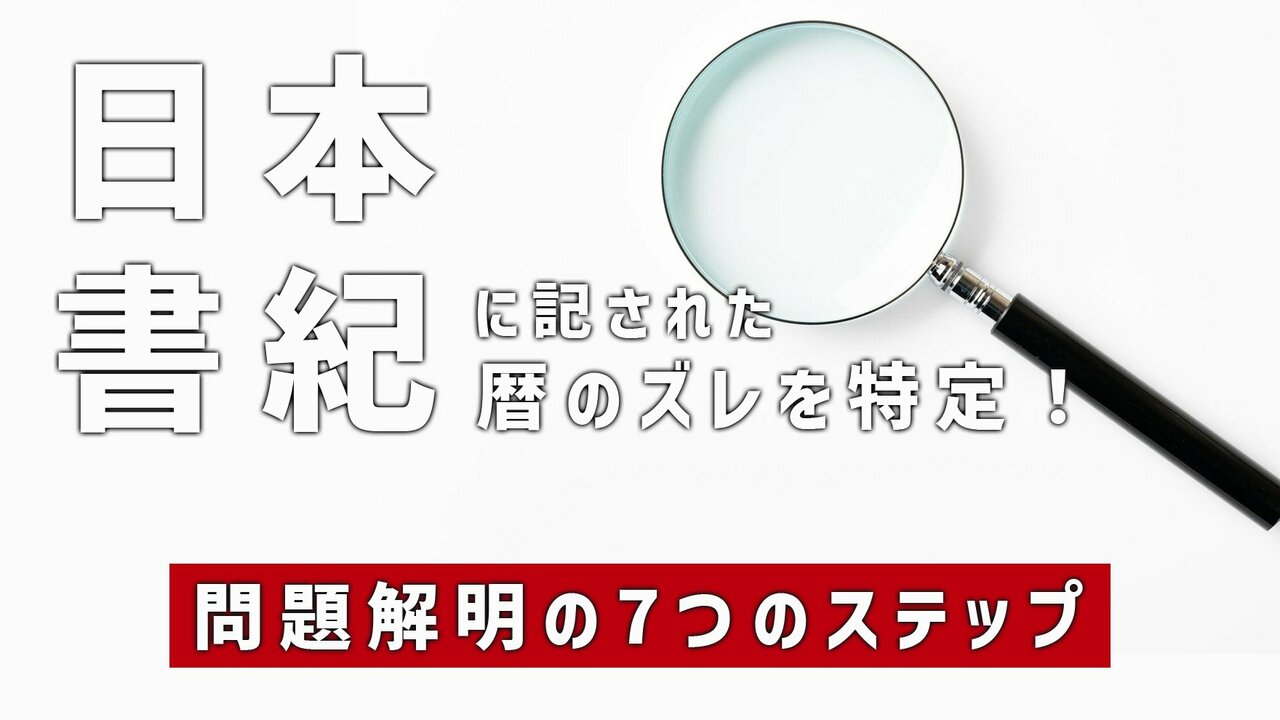
日本書紀に記された暦のズレを特定!問題解明の7つのステップ
-
歴史・地理『6~7世紀の日本書紀編年の修正』【第3回】牧尾 一彦
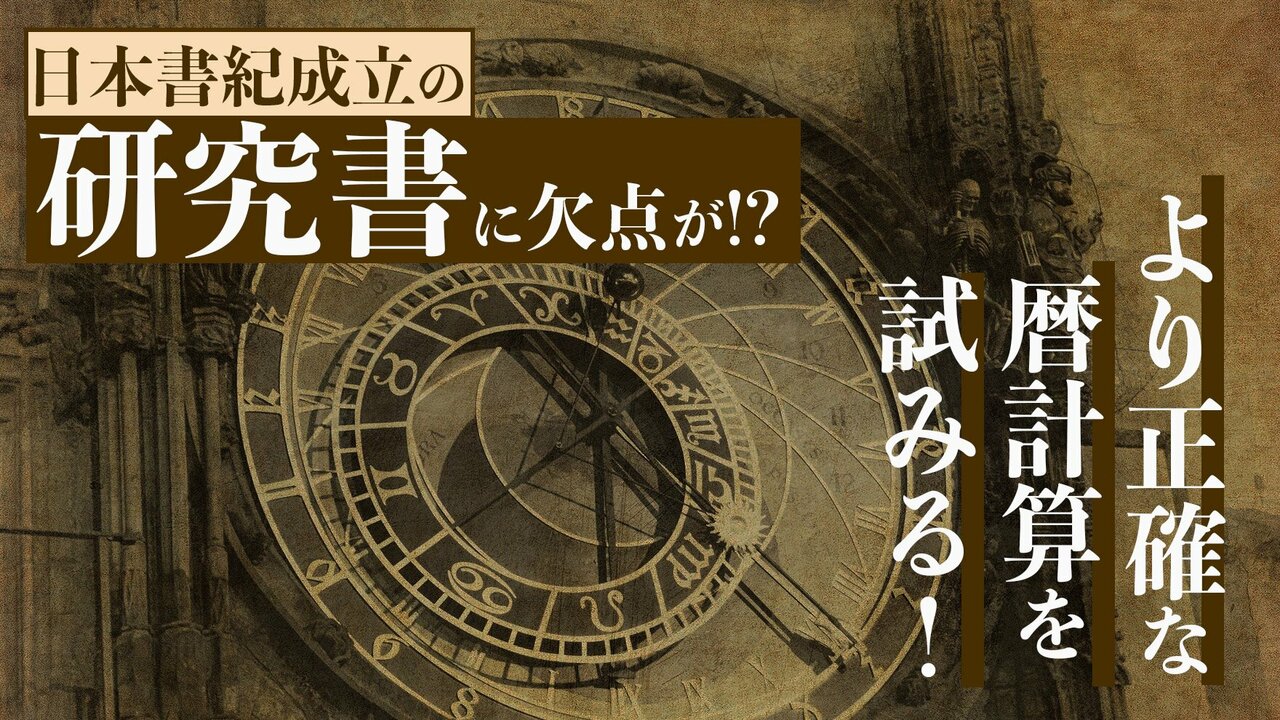
日本書紀成立の研究書に欠点が!? より正確な暦計算を試みる!
-
歴史・地理『6~7世紀の日本書紀編年の修正』【第2回】牧尾 一彦
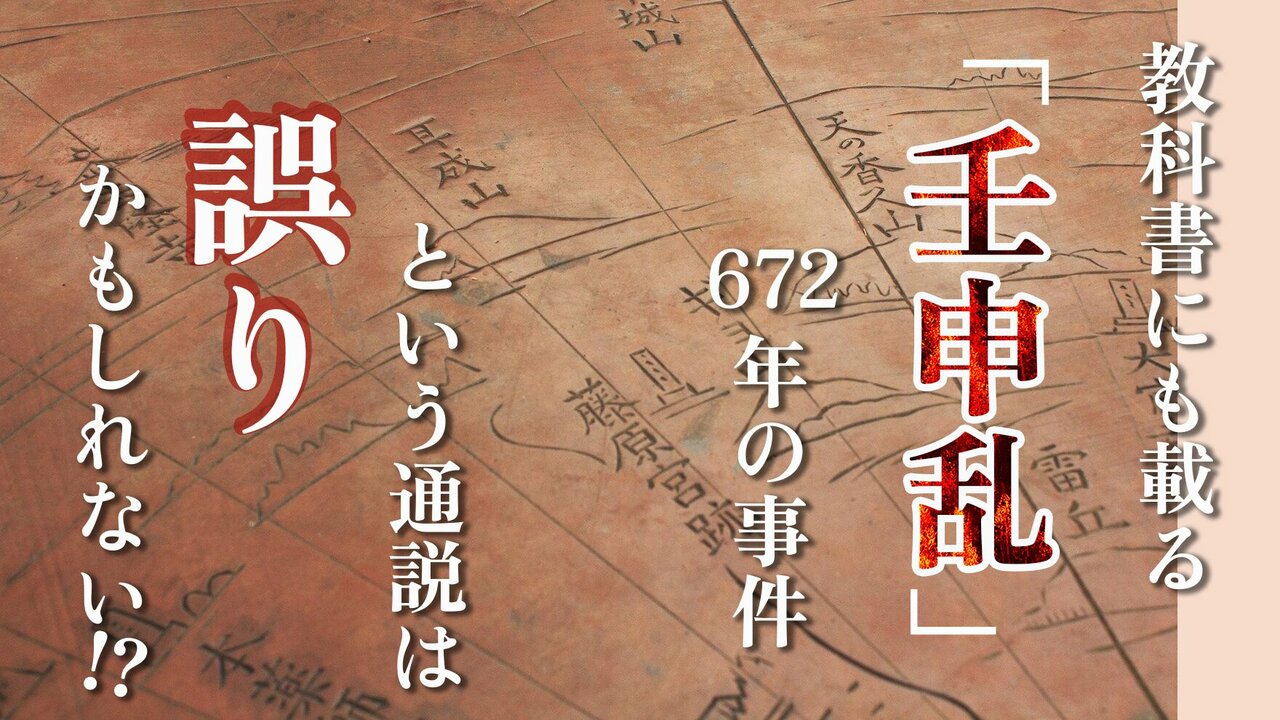
教科書にも載る「壬申乱」672年の事件という通説は誤りかもしれない!?
-
歴史・地理『6~7世紀の日本書紀編年の修正』【新連載】牧尾 一彦
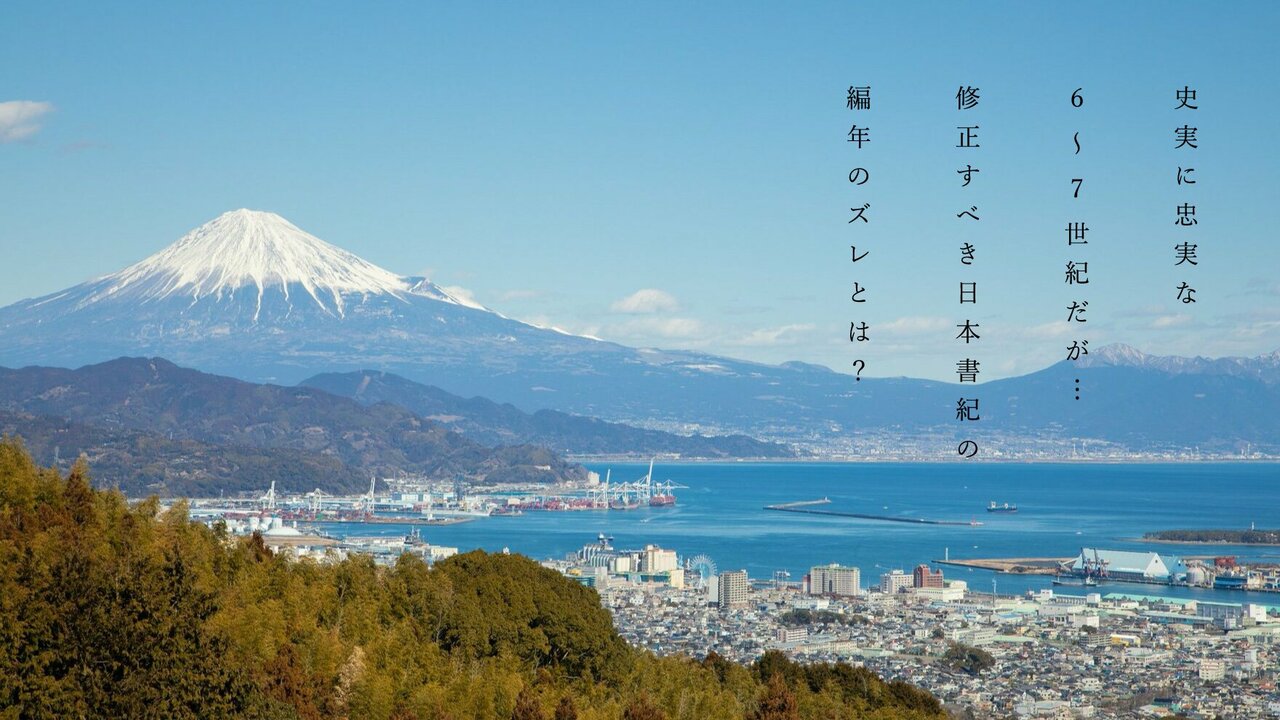
史実に忠実な6~7世紀だが…修正すべき日本書紀の編年のズレとは
-
歴史・地理『法隆寺は燃えているか 日本書紀の完全犯罪』【最終回】中村 真弓
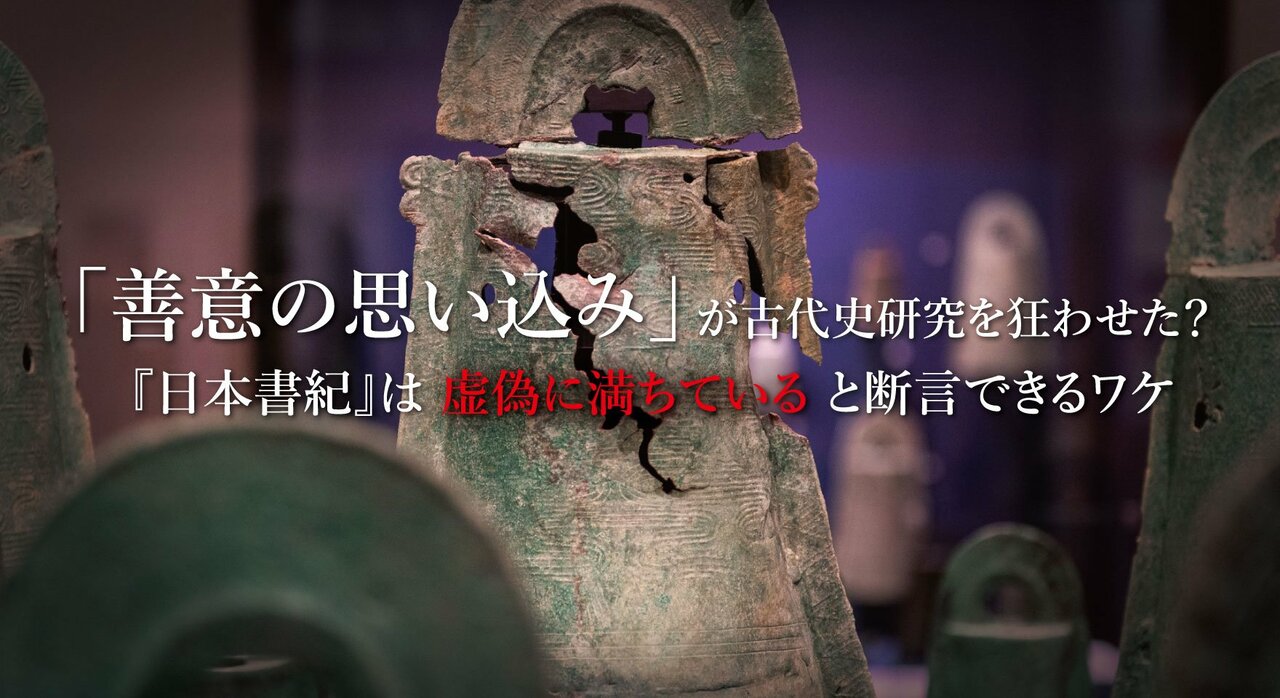
「善意の思い込み」が古代史研究を狂わせた?『日本書紀』は虚偽に満ちていると断言できるワケ
-
歴史・地理『法隆寺は燃えているか 日本書紀の完全犯罪』【第15回】中村 真弓

科学的知見が出揃っているのに…法隆寺大火災を否定できない「残念な事情」とは






