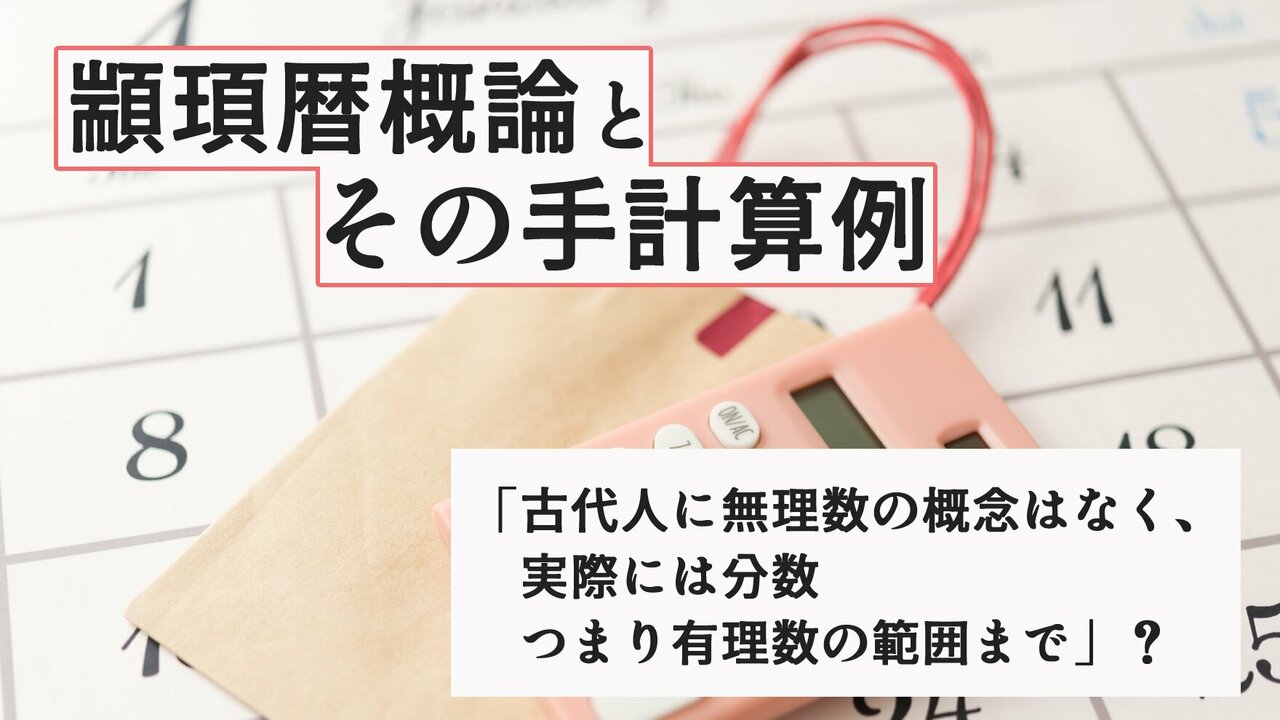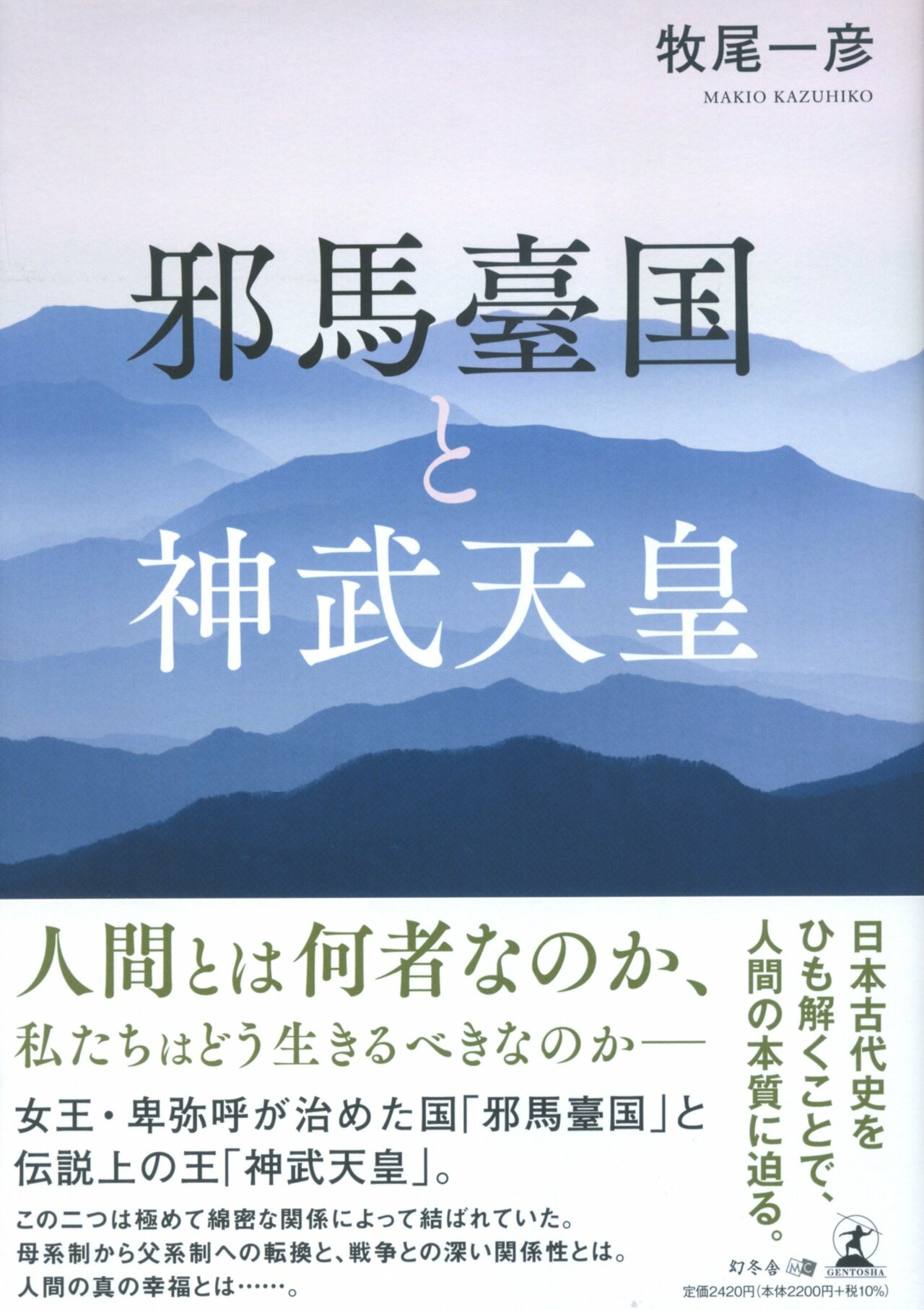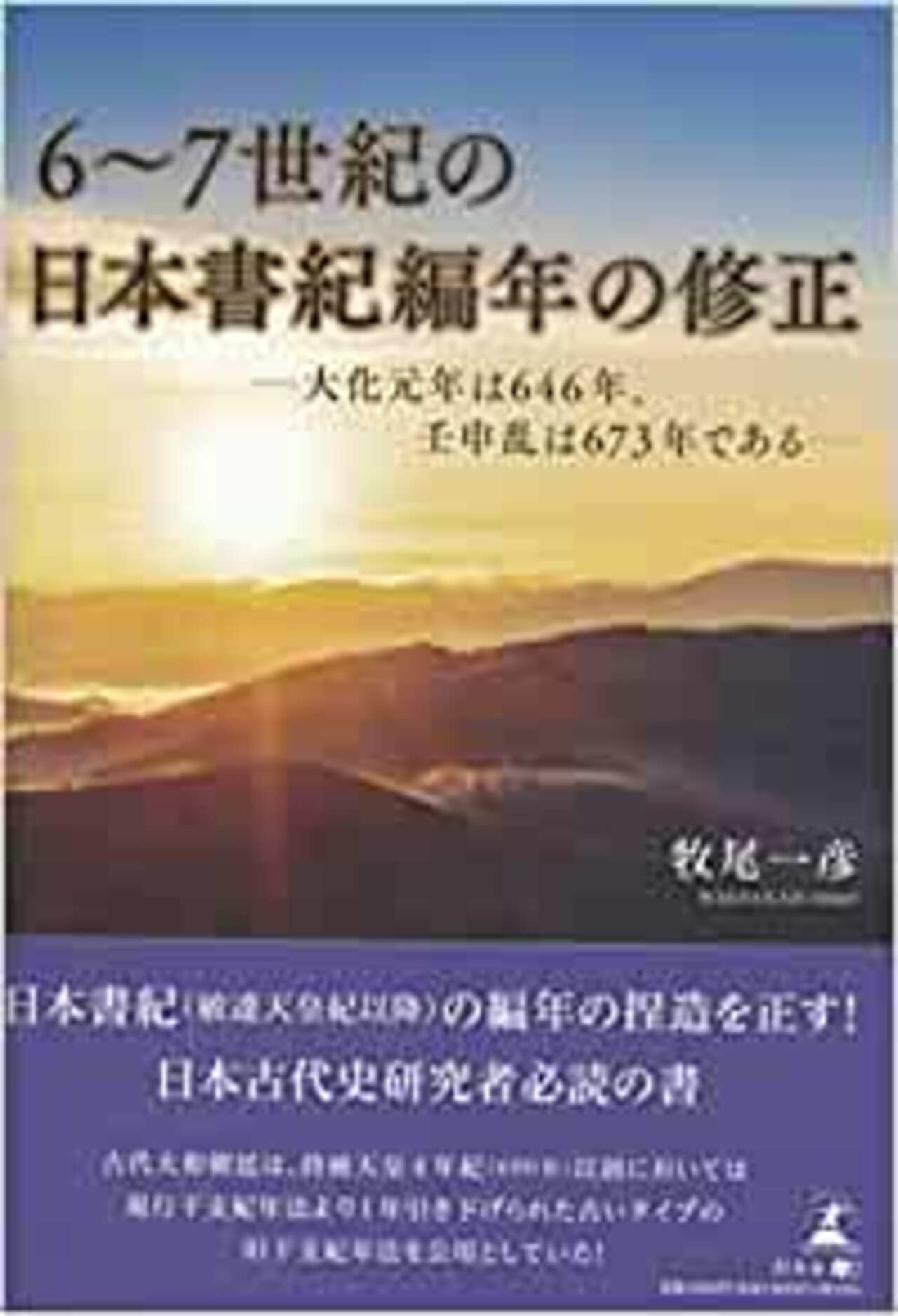【前回の記事を読む】旧日本紀編年を書紀がどのようにずらしたか…「日本書紀編年の捏造表」を見る
序節 日本書紀の編年のズレ
第1節 6~7世紀の日本書紀編年の捏造表
補論1 顓頊暦概論とその手計算例
顓頊暦は四分暦と呼ばれる最も古い太陰太陽暦の一つで、中国の秦王朝(紀元前221年~紀元前206年)と前漢王朝(紀元前202年~紀元後8年)の前半まで、即ち武王の時の紀元前104年に太初暦に変更されるまでの間、朔指数に0.5(つまり半日)を加える修正を施しつつ実用に供されていたことが確認されている暦法である(薮内清氏著『増補改訂中国の天文暦法』〔平凡社1990年〕のp.359~360、同氏著『科学史からみた中国文明』〔NHKブックス409昭和57年〕のp.202~210)。
地球は太陽のまわりを楕円軌道を描いて公転している。公転の向きは地球の北極側からみおろして反時計回りである。地球はまた地軸の周りを北極側からみてやはり反時計回りに自転している。
公転面に垂直で地軸を含む面が太陽の中心を通る場合は公転中に2回ある。冬至と夏至である。地軸が公転面の垂直線より23.4°傾いているので、冬至の瞬間に太陽が真南に来る地点に立っている北半球の人が観測すると、太陽は1年で最も低いところにあり、垂直に立てた棒の影は1年でもっとも長くなる。現在の冬至点は公転楕円軌道の近日点に近いところにあり、夏至は遠日点に近いところにある。
冬至から冬至までの時間を1太陽年という。これは地球が1回公転して元の場所に戻る時間である1恒星年より若干短い。地球が歳差運動という首ふり運動をしているためである。地球はこまの首ふり運動と同じように約26000年かけて1回転首をふる。その回転の向きは地球の北極から眺めたとき時計まわりである。そのため約6500年後にはもとの秋分点が冬至点になり、約13000年後にはもとの夏至点が冬至点になる。
つまり歳差運動のために冬至点は公転方向と反対向きに(つまり地球の北極から眺めて時計回りに)少しずつ位置を変えてゆく。そのため、冬至点から冬至点までの時間、1太陽年は、1恒星年よりやや短くなる。
今日の測定では1太陽年は約365.24219日とされる(2017年理科年表p.77。対して1恒星年は約365.25636日)。またひと月は月が地球をほぼ一回りする時間であるが、平均朔望月、つまり朔(新月)から望(満月)を経て再び朔にもどるまでの平均日数は、約29.530589日である。
この朔望月によって月を数えると、12か月は約354.37日ほどになる。1太陽年には11日ほど不足する。そこで、12か月を1年とすると3年も経てば1か月ほど足りなくなるので、月数と季節とのずれを調節するために、33~34か月ごとに1度の頻度で閏月を挿入する工夫がなされる。古くより19年に7か月の閏月を足せば、ほぼ収支の付くことが発見されており、四分暦法における19年7閏月法が定まった(19年を1章といい、19年7閏月法を章法ともいう)。
古代暦である四分暦は1太陽年を365日1/4日=365.25日と定めて計算する暦法である。365.24219日と比較するとかなりよい近似である。また平均朔望月は、19年7閏月法によって、19年=19×12+7月=235平均朔望月という関係があるので、1平均朔望月=29日+499/940日≒29.530851日となる。29.530589日と比較するとやはりかなりよい近似になっている。