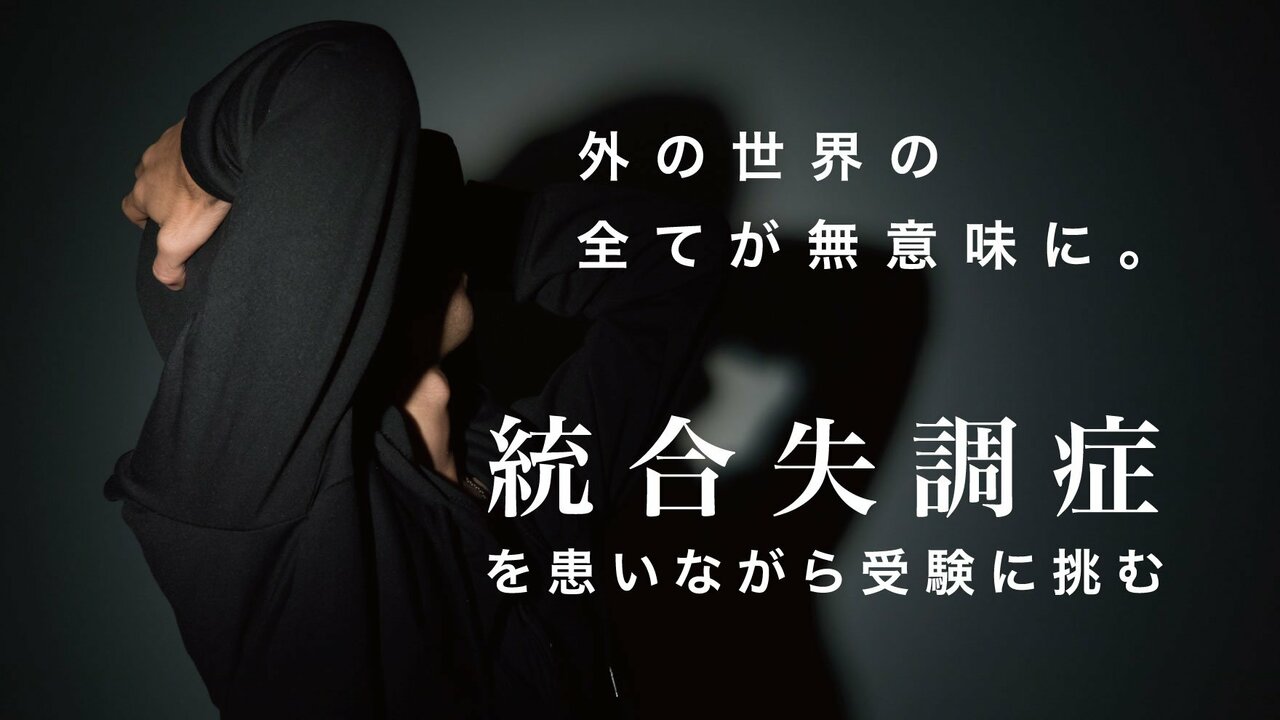第二章 原点への回帰
第二節 米子
そして、私のそんな平安の日々にも終わりが近づいていた。父は平滑筋肉腫という業病を患って苦しみながら死ぬことができないでいた。父の病状は悪化の一途を辿り、一家の経済は困窮し、苛立った父の不満は社会からの落伍者となった息子に向けられた。
私は父の怒りの暴発に怯えて、父の下を去ろうとするばかりだった。働きに出ればよかったのだろうが、当時の私には働くことはただ恐怖だった。学問を遣り直して身を立てる方がずっと遣り易いことに思われた。私は迂闊にも自分の能力の復活を信じたのだ。
私は自分の病気を意識してはいなかったのだ。無論、私はその年の医学部の受験に二度目の失敗をした。私は絶望の上に絶望を重ね、怒り狂う父の下にも、故郷にももういられなかった。私は家を出るしかなかったのだ。
あの日、故郷の教会に別れを告げようとした私の前に洗礼を授けてくれたU神父がいた。彼は物悲しい表情で私を見て「寂しくなる」と言った。そして「必ず帰って来るのだよ」と言った。神父はじっと私を見ると、呟くようにある思い出を話し出した。
ある日、病院から電話があって、死にかかった患者が神父を呼んでいるという。神父が駆けつけてみると、その男はすでに死んでいた。その見知らぬ男が誰なのか、考えあぐねていたが、ふと自分がかつて洗礼を施した「あの子」だったと思い当たった。その子は成長して東京へ行って、行方知れずになっていたが、病気になって故郷に帰って来ていたのだ。そして、死を前にして教会に帰ろうとしたのだ。
神父はその男について話し終えて、「誰であれ、神に招かれた者はどんなにその道を外れようと、最後には再び神の懐に帰って来るものだ」と言った。私は黙って肯き、自分も死ぬときには必ず教会に帰って来るだろうと思った。