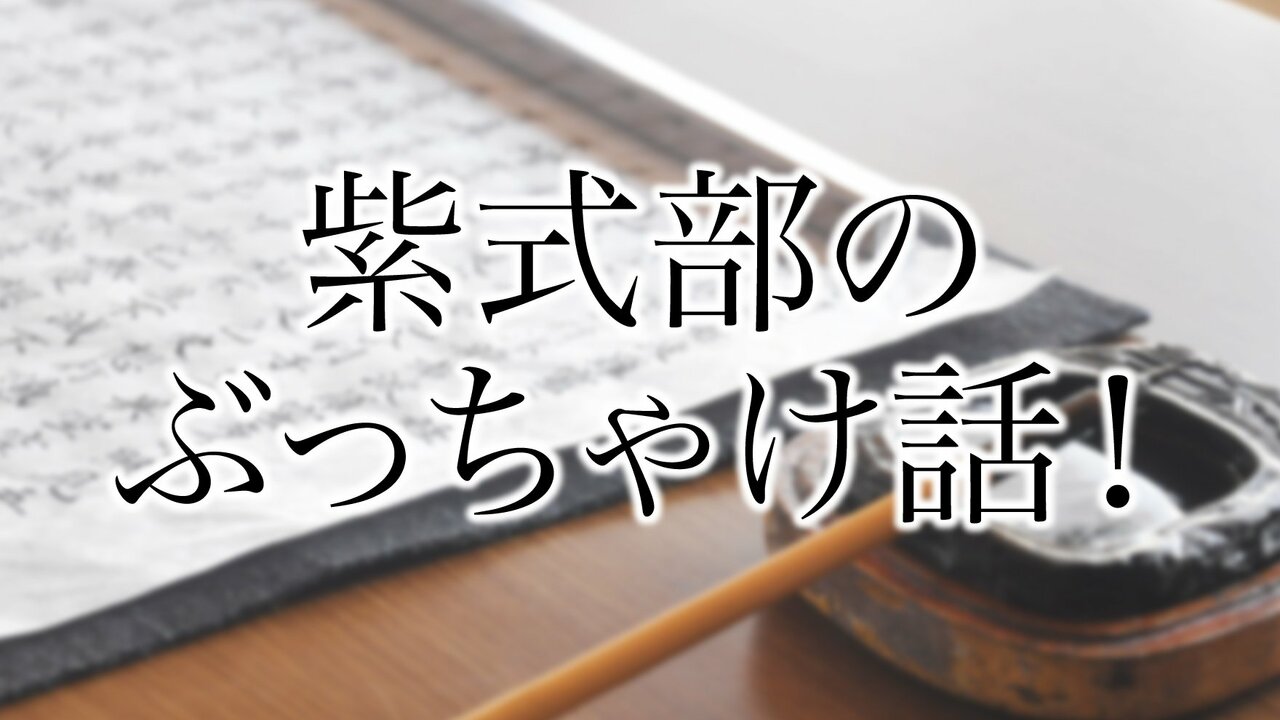朝顔の花のさかり
光源氏は、かつて朝顔と親交があったが、朝顔が神に仕える斎院であった八年間、朝顔に近づくことができなかった。
朝顔の父である式部卿宮が亡くなられて、朝顔が斎院の地位を退いたので、光源氏は、亡き式部卿宮の旧邸である桃園の宮に移った朝顔を訪ねた。
光源氏は、御簾の内に入れてもらえないことに苦情を言うが、朝顔は、取り合ってくれないし、光源氏が何を言っても、期待するような返事をしないので、光源氏は、嘆息しながら退散した。
いらだたしい思いで自邸に戻った光源氏は、夜も眠れないほど考え続けていたが、朝早く起き出して、霜枯れの前栽を這いまわっている朝顔の花で、とりわけ色どりの衰えているのを選び、それに手紙を添えて、朝顔に贈った。
光源氏「見しをりのつゆわすられぬ朝顔の花のさかりは過ぎやしぬらん」(昔見た朝顔の花〔昔お目にかかった折のあなたのこと〕を忘れることができませんが、朝顔の花〔あなた〕の盛りは、もう過ぎてしまったのでしょうか)
朝顔は、返事を書かないわけにはいかないと思い、朝顔が光源氏と結ばれることを願っている女房たちも、硯を用意して、返事を書くように勧めるので、朝顔は返事を書いた。
朝顔「秋はてて霧のまがきにむすぼほれあるかなきかにうつる朝顔 似つかはしき御よそへにつけても、露けく」(秋も暮れ、朝顔の花は、霧がたちこめる垣根にまつわって、あるかなきかの姿で枯れてゆきます。私にふさわしい譬たとえで、涙がこぼれるほどです)
光源氏は、いらだたしい思いで、「花のさかりは過ぎやしぬらん」と精一杯の皮肉を言ったのだが、朝顔は、「私は、仰せのとおり、枯れてゆく朝顔の花のようです」と、素直に応じた。光源氏は、墓穴を掘ったようなものである。
物語は、朝顔の歌を、「何のをかしきふしもなきを」と知らぬ顔をしているが、光源氏はあっけに取られて、朝顔の返事をしげしげと眺めるほかない。