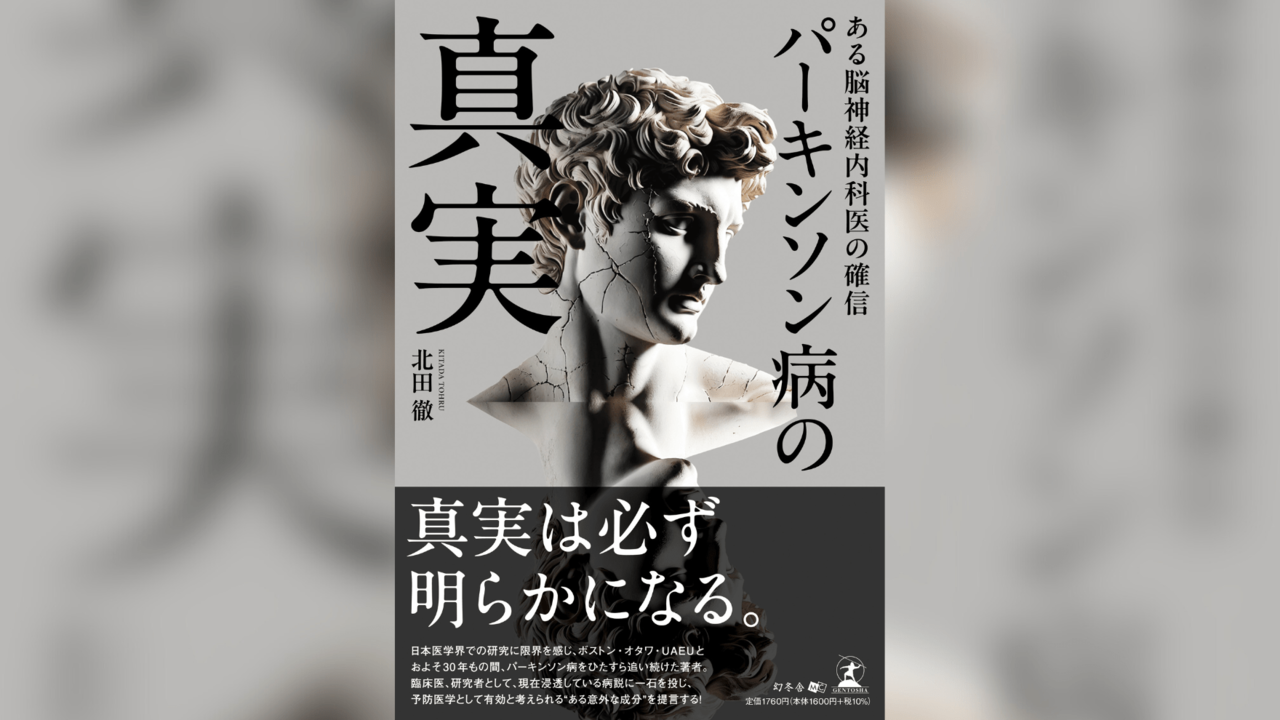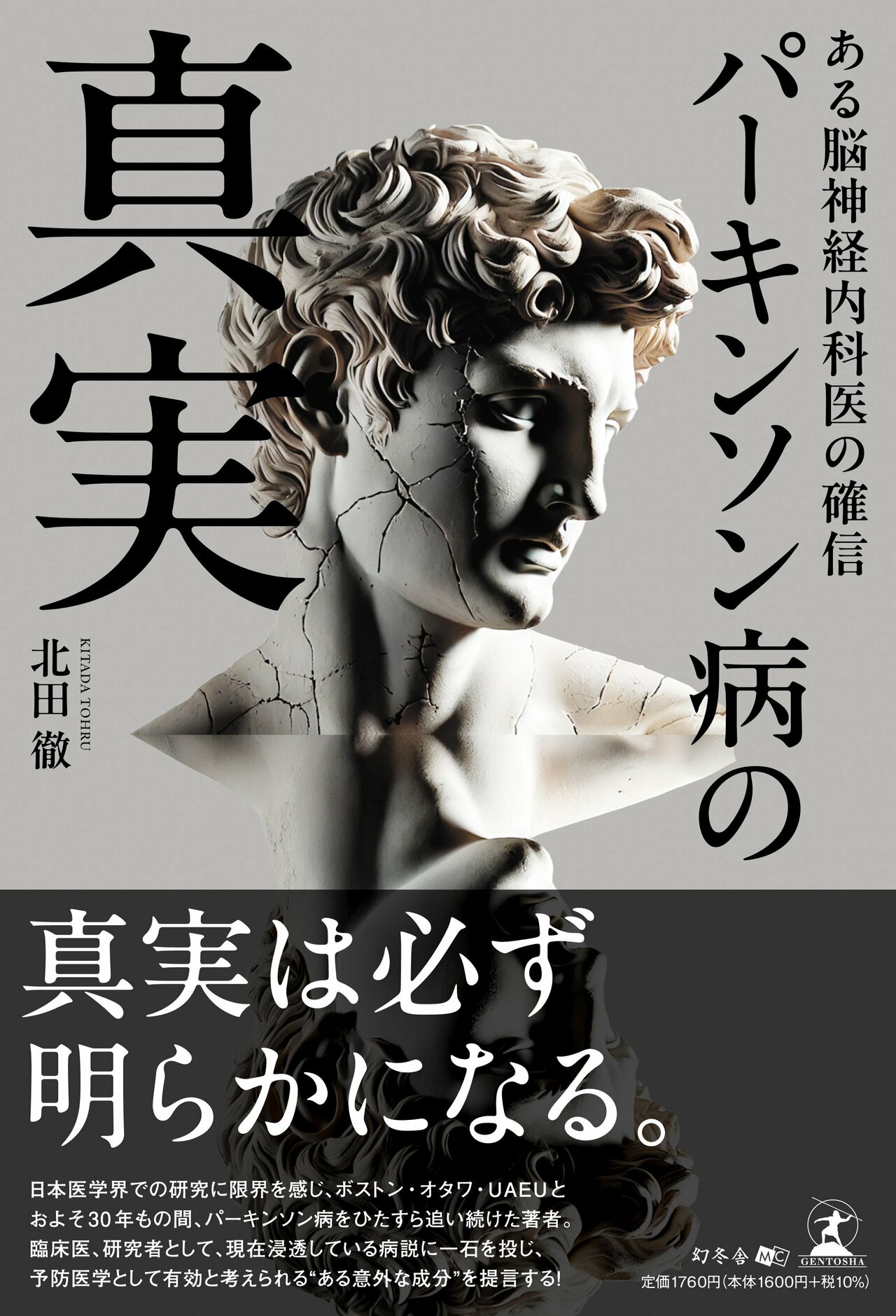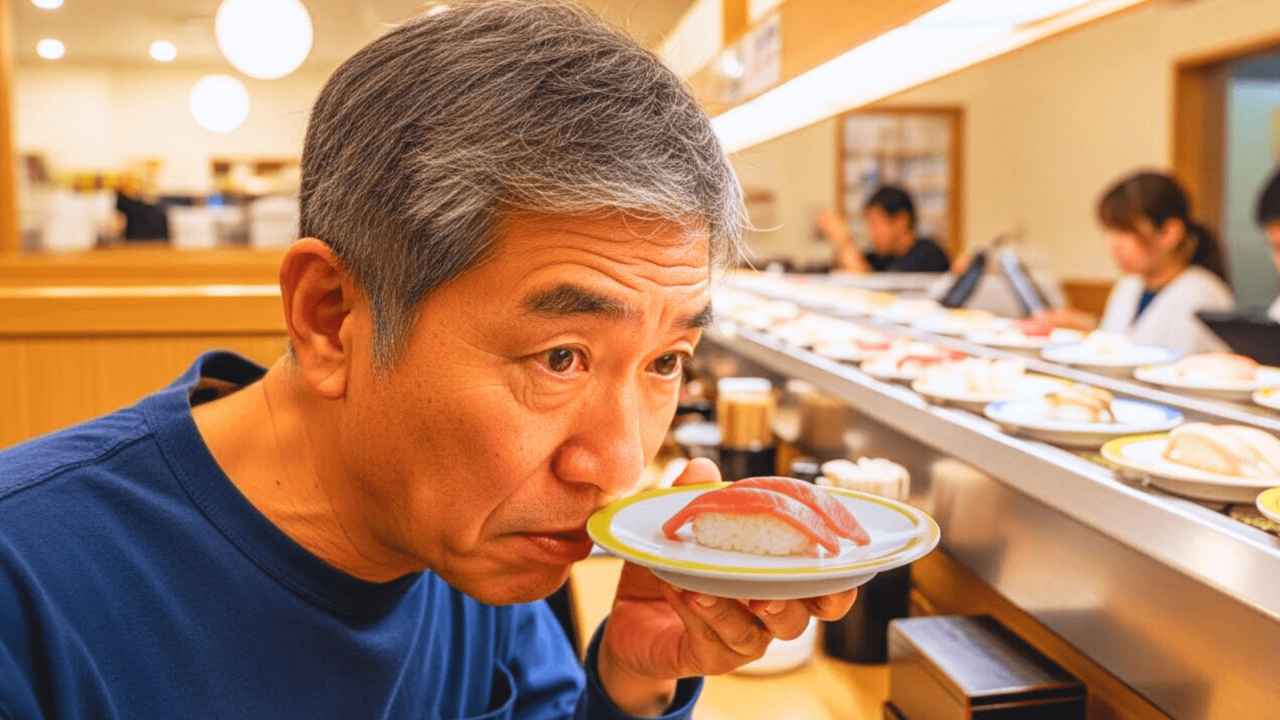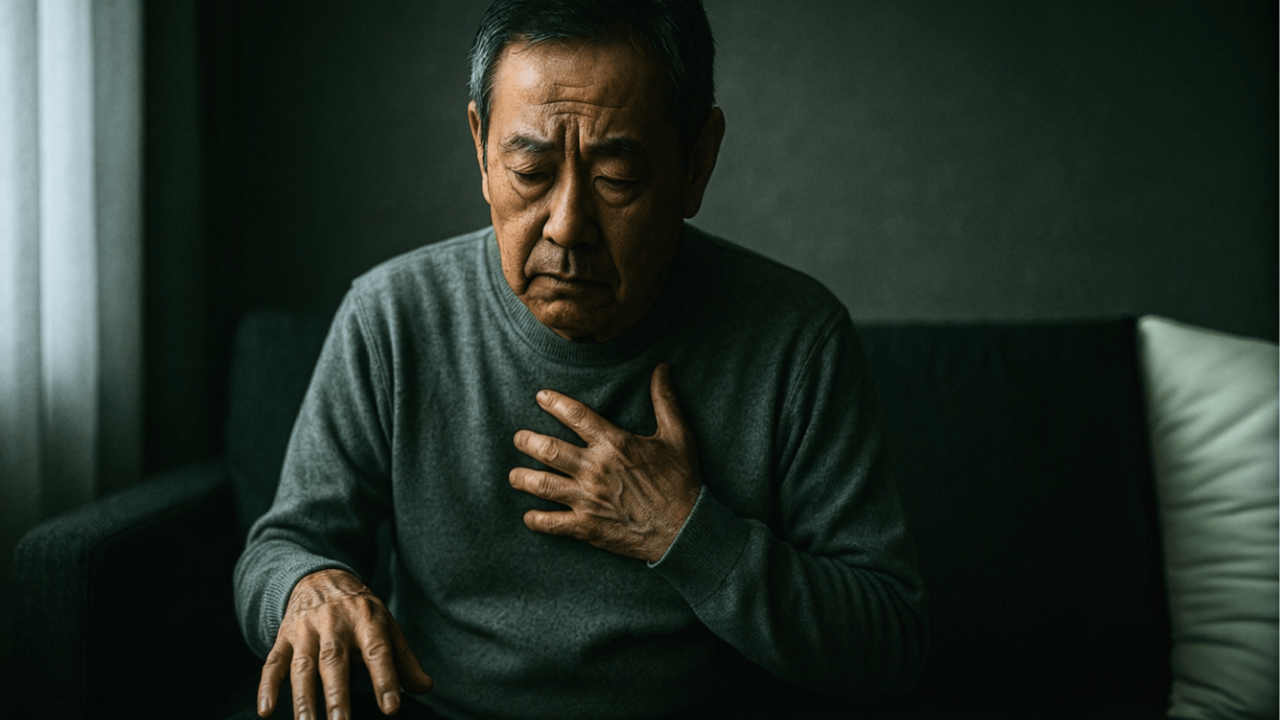【前回記事を読む】「パーキンソン病」と「パーキンソン症候群」の違いとは?——症状・進行度・診断法などを徹底解説!
第1章 パーキンソン病の基礎知識
多彩な症状と進行の度合い
診断2 補助診断
パーキンソン病では、便秘、嗅覚低下、レム睡眠行動異常が高頻度で見られ、嗅覚障害は90%の患者様に認められるという報告もあり、補助診断と組み合わせることが、他疾患との鑑別や早期発見に有用と考えられます。
平山正明博士によれば(文献1)、パーキンソン病に罹患された方の臨床経過を辿っていくと、運動症状が発症する20年前から便秘、10年前から悪夢やレム睡眠行動異常、5年前からうつ症状が始まる傾向があるということです。レム睡眠行動異常では、無意識のうちに大声で寝言を言う、奇声を発する、蹴るような暴力的な体動があるなどが特徴的です。
これらの早期の非運動症状の出現は、アルファ・シヌクレイン(α-synuclein,α-syn)の病理(文献2、3)が末梢の鼻粘膜や消化管から発症し、末梢神経を上行し、脳幹部から大脳半球へ上行するというBraakらの病理学的仮説と一致します(文献4、5)。
孤発型(=遺伝性のない)パーキンソン病の特徴的病理像としてレビー小体(Lewy body)と呼ばれる細胞内封入体が観察されますが、その主要構成成分はα-synであることが判明しています 3 )(文献2、3)。
診断3 バイオマーカー(biomarker)
近年、パーキンソン病の診断法・治療法の応用として種々のバイオマーカーが注目されており、補助診断としての利用が期待されます。バイオマーカーとは、ある疾患の有無や、進行状態、治療の効果を示す目安となる生理学的指標や生体内物質のことです。
孤発型パーキンソン病の脳病理から、レビー小体の主要構成成分であるα-syn蛋白の異常蓄積が、運動症状の出現以前から始まっていることがわかってきています。
こうした運動症状出現前の段階の病理変化を感知するバイオマーカーが開発されれば、早期の診断と治療が可能になるのではと期待されます。髄液中、そして最近では血液中の微量のα-synの量や構造変化をバイオマーカーとして応用できないか、盛んに研究が行われています。
すでにパーキンソン病の診断がついている(または疑い)ならば、このバイオマーカーが補助診断として、さらなる確定診断や治療の効果判定に役立つ可能性があります。
α-syn seed amplification assays(SAAs)は病的なα-syn・シード(α-synの病的な構造を持つ凝集体)を検出する方法ですが、このSAAs法がさらに改良され発展したことにより、血液からも検出可能となっています(文献6)。