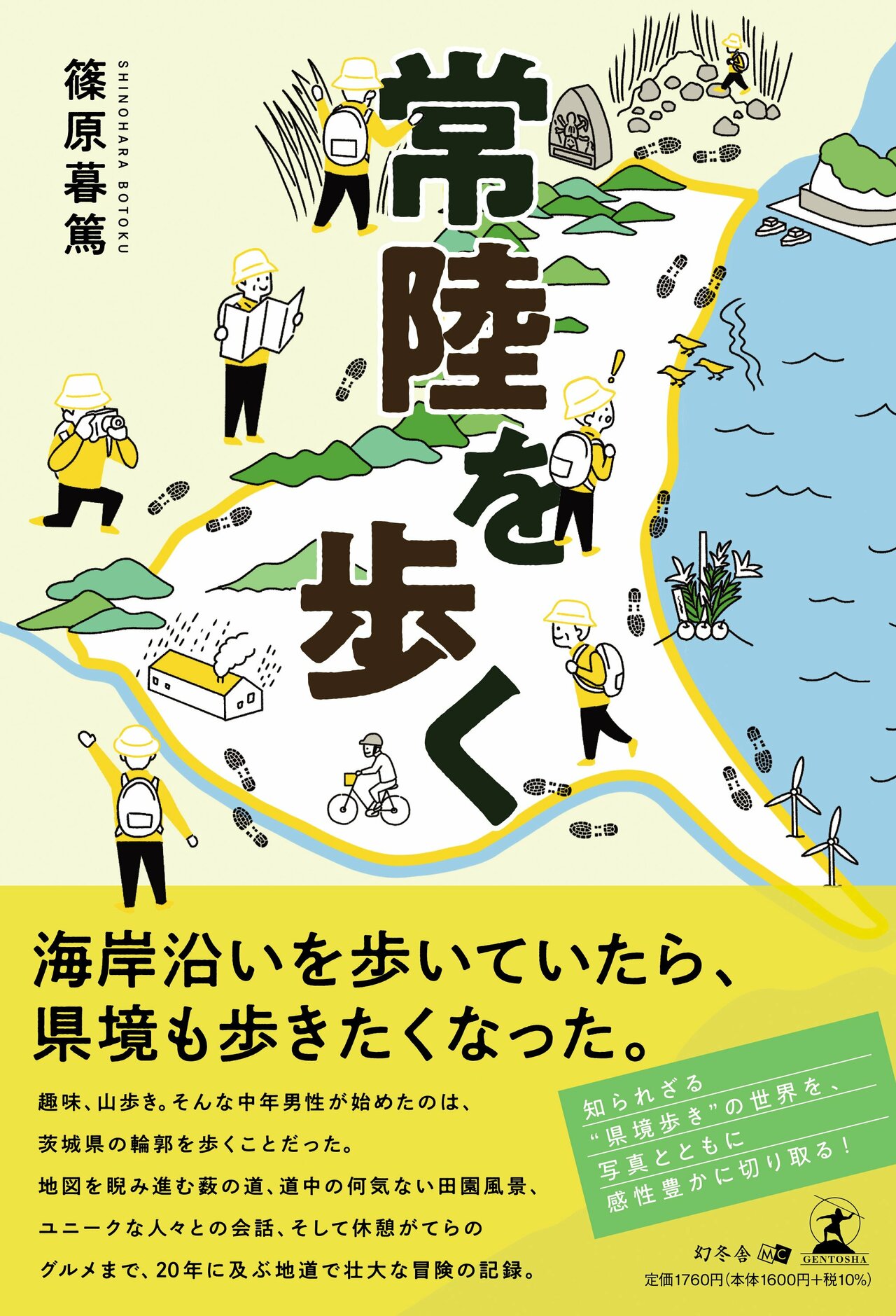昼になり、大洗神社下の磯料理屋で昼食。那珂湊の魚市場で見かけた岩牡蠣を注文する。
少し待ったけれど、この季節に生の牡蠣をレモン汁で食べる幸せを感ずる。あっという間に胃の中に消えていった。
小さな大洗灯台がある。北海道とを結ぶ沿岸フェリー埠頭がある。大洗漁港がある。いずれも典型的な港風景だ。ここにも漁具入れの小屋の壁に大きな文字が書いてある。
阿字ヶ浦の和歌とは違い、ここは「立小便禁止」という無粋なもの。しかし漁船に書かれた手書き文字には人間味がある。
大洗マリンタワーを過ぎ、海水浴場は家族連れとサーファーの天国である。子供たちが波と戯れ、それを見守る人たち。
これまでの海岸歩きでもたびたび見た光景である。この子供たちには今日のここでの体験が、ある心象として残ることは私の体験からも確かである。
私は茨城県をすべてカバーする紙の地形図を多数所有していて、山歩きやサイクリングに出かけたあとには日付とその踏破ルートを赤鉛筆で書き込んでいる。
その古い地形図を見ると、ここが人工の砂浜であることがわかる。更に南に下っていくと、人もまばらになり、防波堤が出現してコンクリートの道になると人影が消えた。
波はテトラポッドに当たって砕け散る。浸食を防ぐために、砂浜をコンクリートで固めているのだが、どこまでも続く砂浜を期待して歩き始めた私には、何とも味気ない景色に見えてしまう。

本日の海岸線上の終点に到着する。ここから松林をぬけて小高い丘にでると、そこは夏の別荘地区となる。人の気配がなく、どの家もかたく門を閉ざしている。
薩摩芋を植えるためだろうか、畑土を耕す人たちの横を通り、国道を横断して西に向かって疲れた足を運ぶ。
ようやく最終地点の鹿島臨海鉄道の涸沼駅に着いた。水戸行きの電車が来るまで30分ほど待たなければならないようだ。
(2005年4月23日)