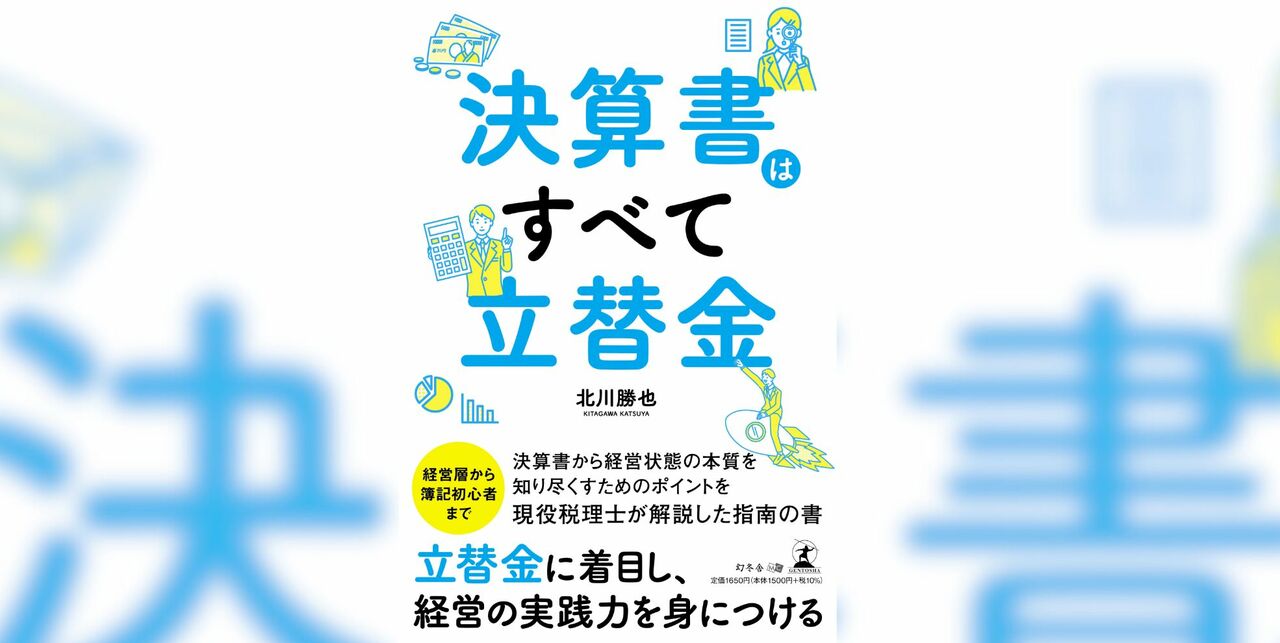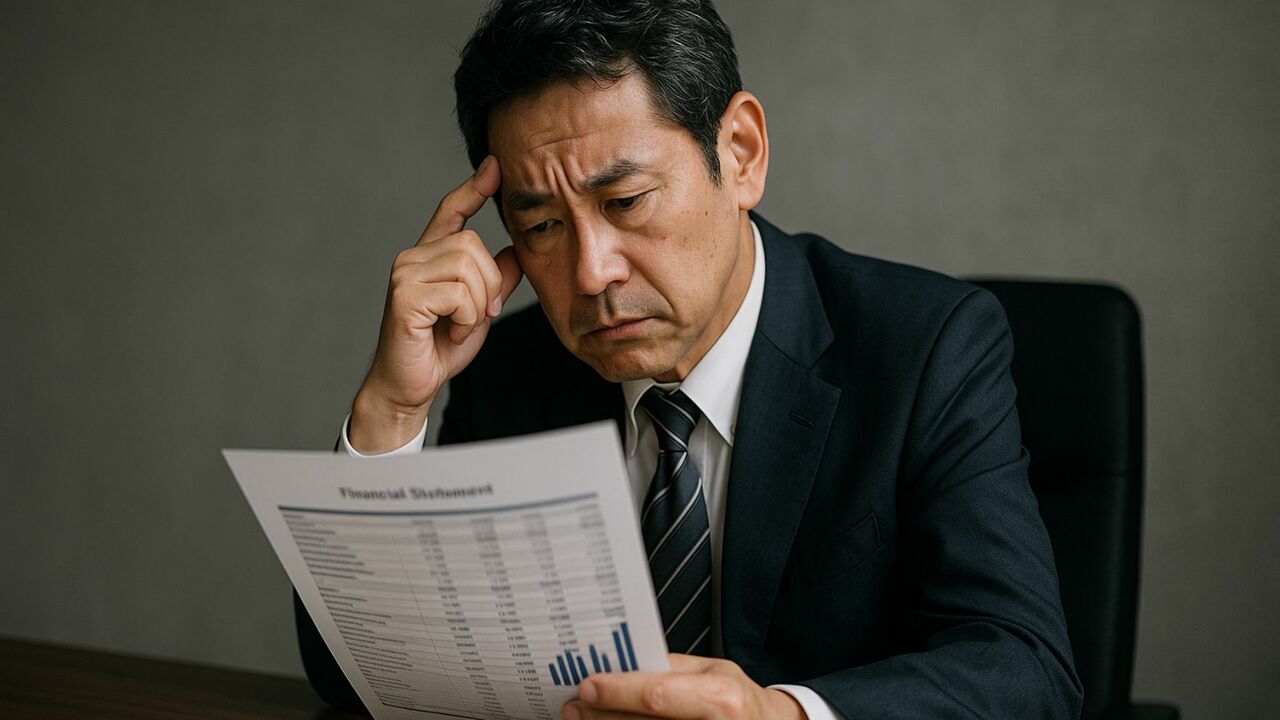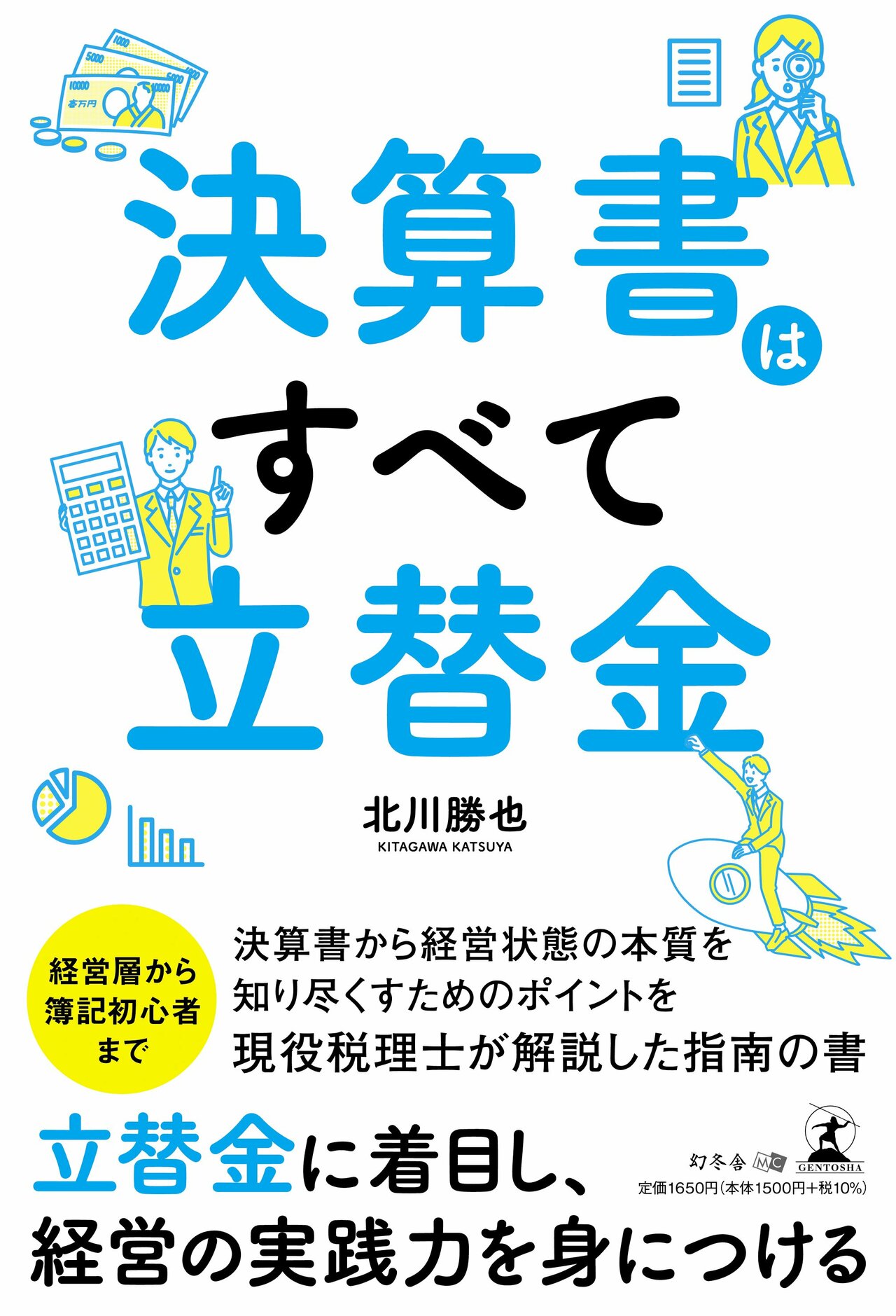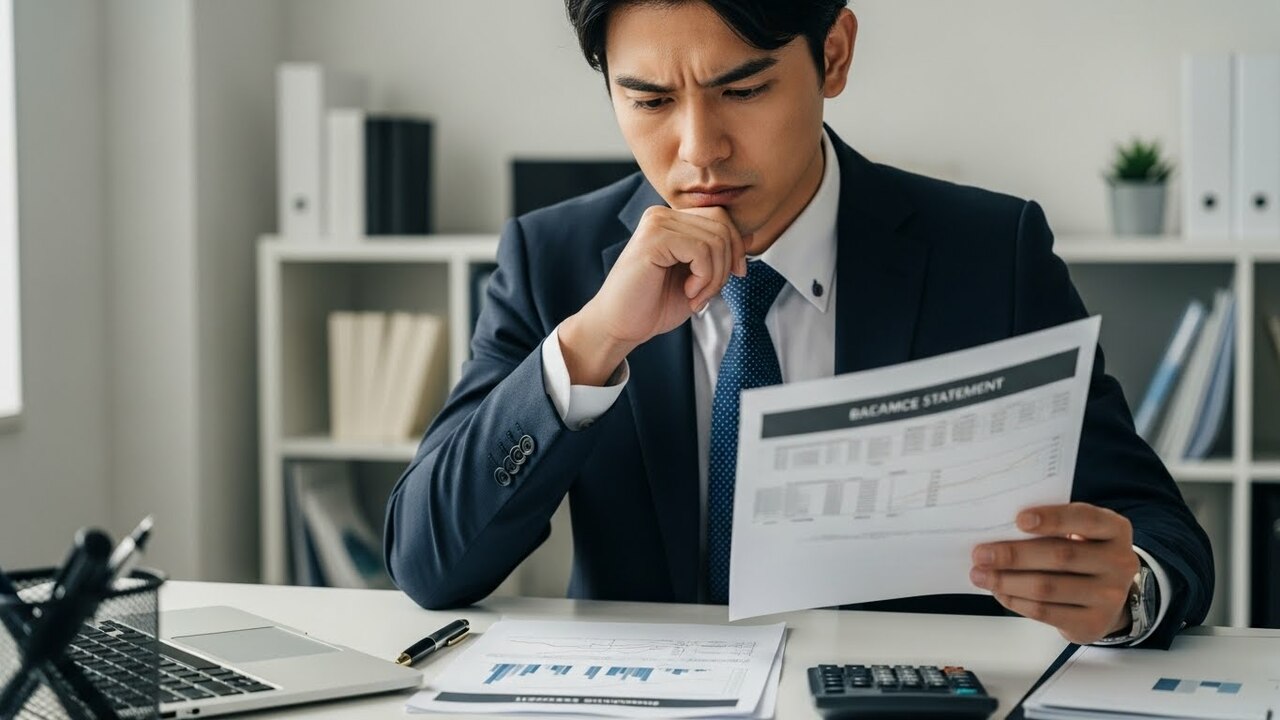【前回の記事を読む】利益を最大化するためには「顧客想定利益」を正確に理解し、適正な「立替金の支出(費用)」を計算して経営戦略を立てることが不可欠
第2章 利益の本質とその再定義
6 「利益の本質」を踏まえた経営計画を認識しない場合の問題点
①誤解を招く利益の認識:決算書上で利益が出ている場合でも、実際の「立替金の支出(費用)」が競合他社より少ない特殊要因によるものである場合、実質的な「顧客想定利益」は競合他社よりマイナスになっている可能性があります。つまり、本来の「立替金の回収(売上)」が十分にできていないという問題が生じます。
②実質的な健全性の見落とし:一方で、決算書上では赤字であっても、実際の「立替金の支出(費用)」が競合他社より多い特殊要因がある場合、「顧客想定利益」は競合他社よりプラスであり、実質的には優良な状態である可能性もあります。
しかし、この状態にもかかわらず、利益が出ていないというだけで、価格の引き上げや過度な効率化を進めると、お客様や従業員、供給者の離脱などの問題が発生する恐れがあります。これらの問題を避けるためには、「利益の本質」を正しく理解し、それに基づいた経営計画を立てることが不可欠です。
7 適正化された「立替金の支出(費用)」を考慮した経営計画の要素
適正な「立替金の支出(費用)」を算出するためには、次の具体的な要素を考慮する必要があります。
①減価償却資産の評価:減価償却資産については、償却が完了しており損益計算書上では0円であっても、新規に取得した場合の取得価格を見積もり、そして法定耐用年数ではなく、実質的利用可能年数から必要な回収額を見積もります。
②役員報酬や特殊支出の適正化:役員報酬の過大や過少、節税対策としての保険加入、特殊な関係から生じる支出などについては、業界の統計資料を参考にし、適正な額を見積もります。