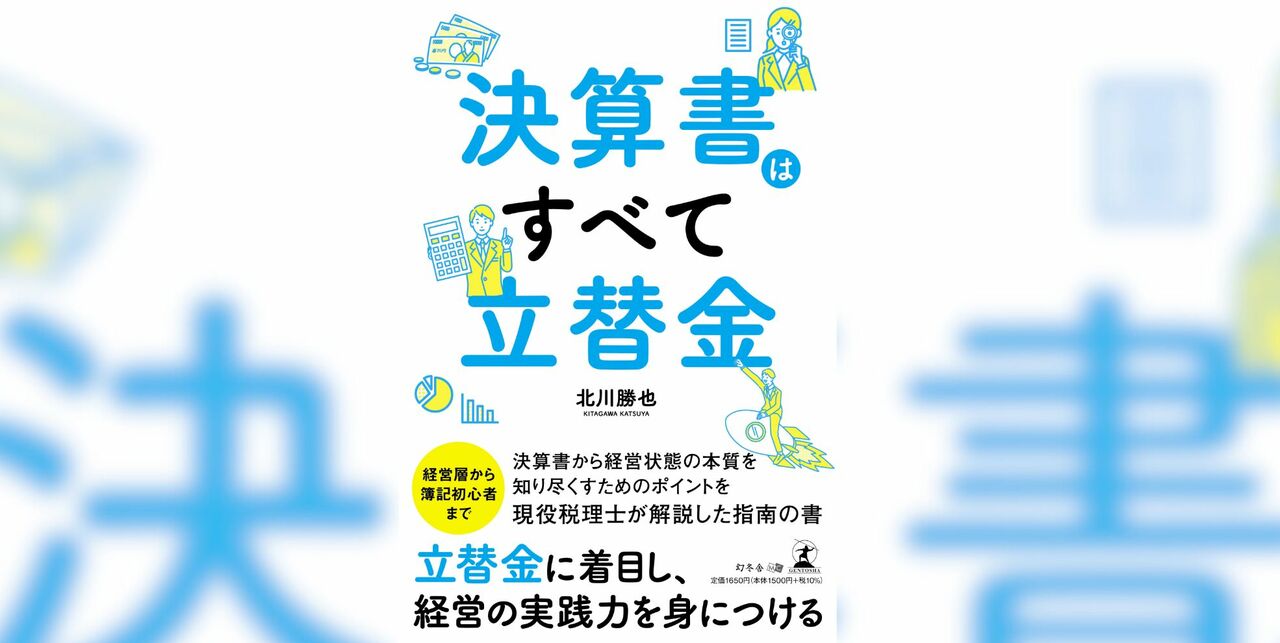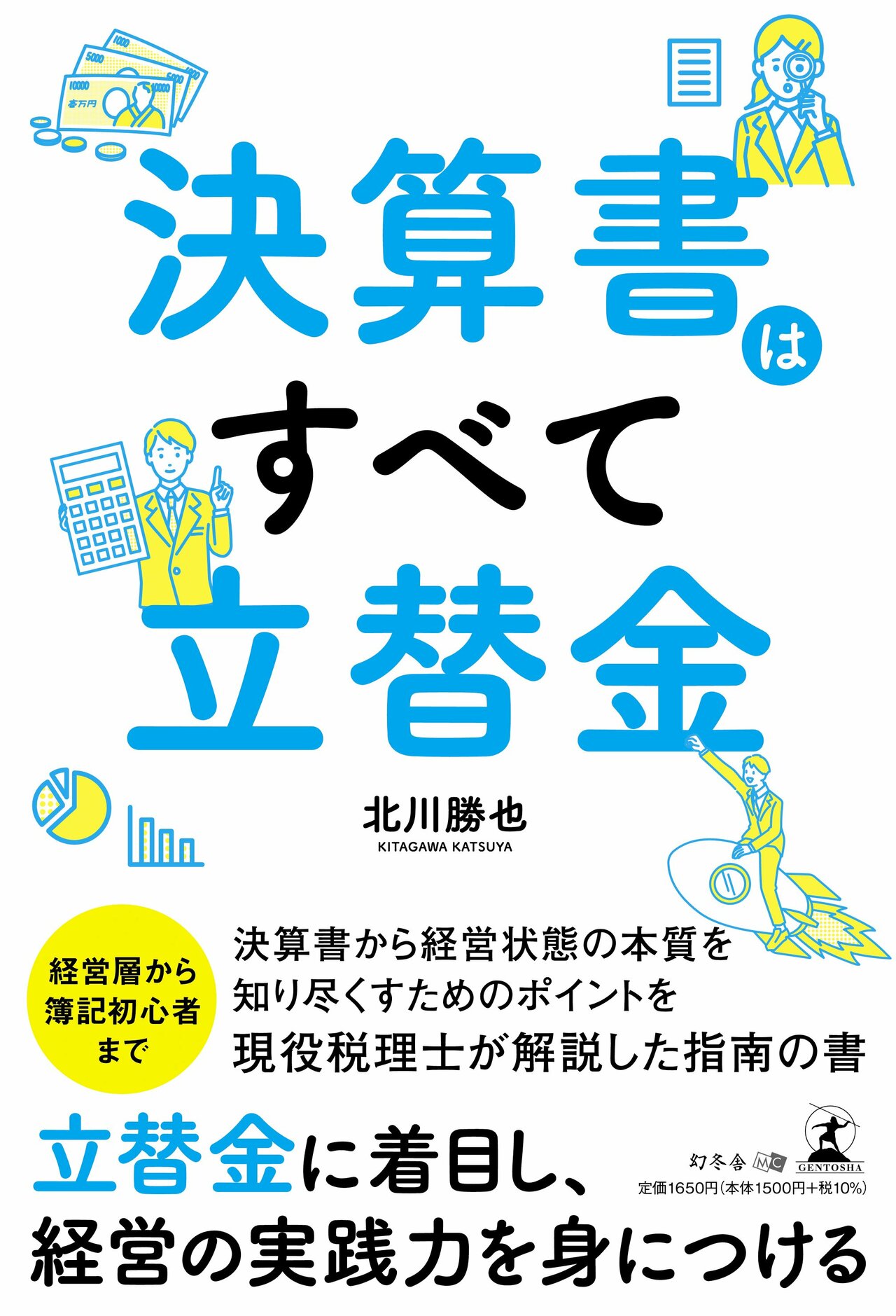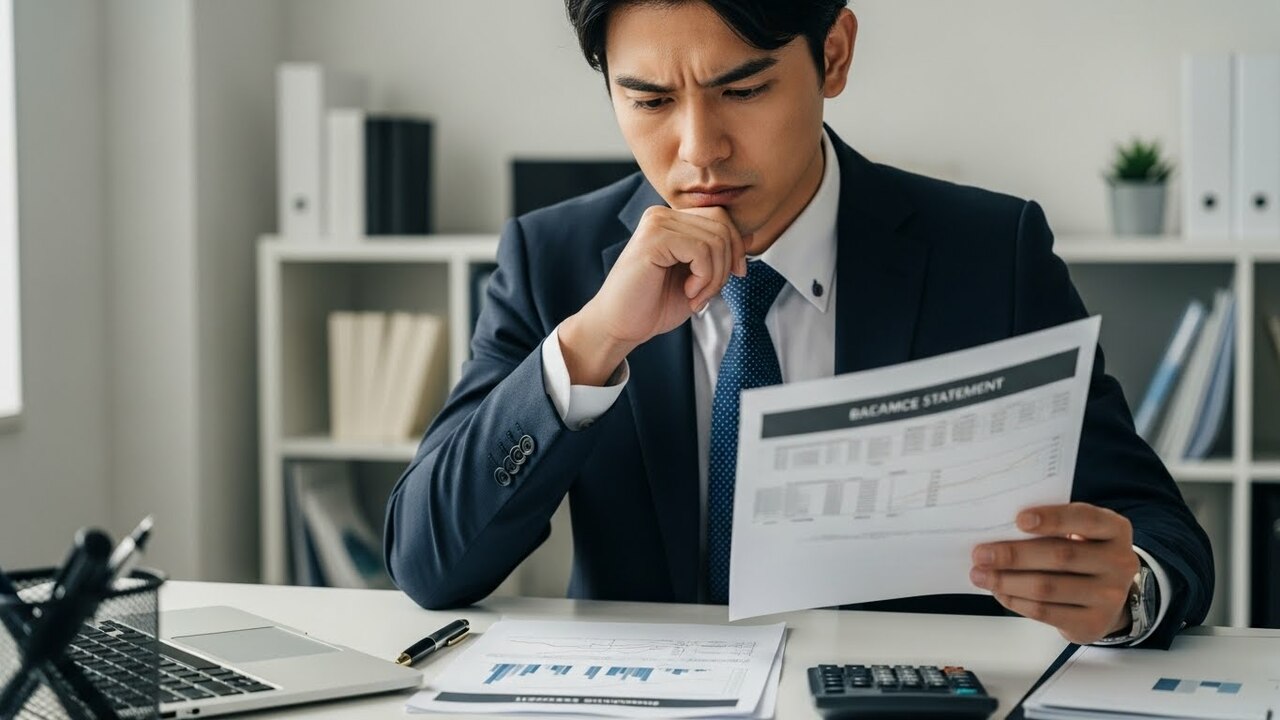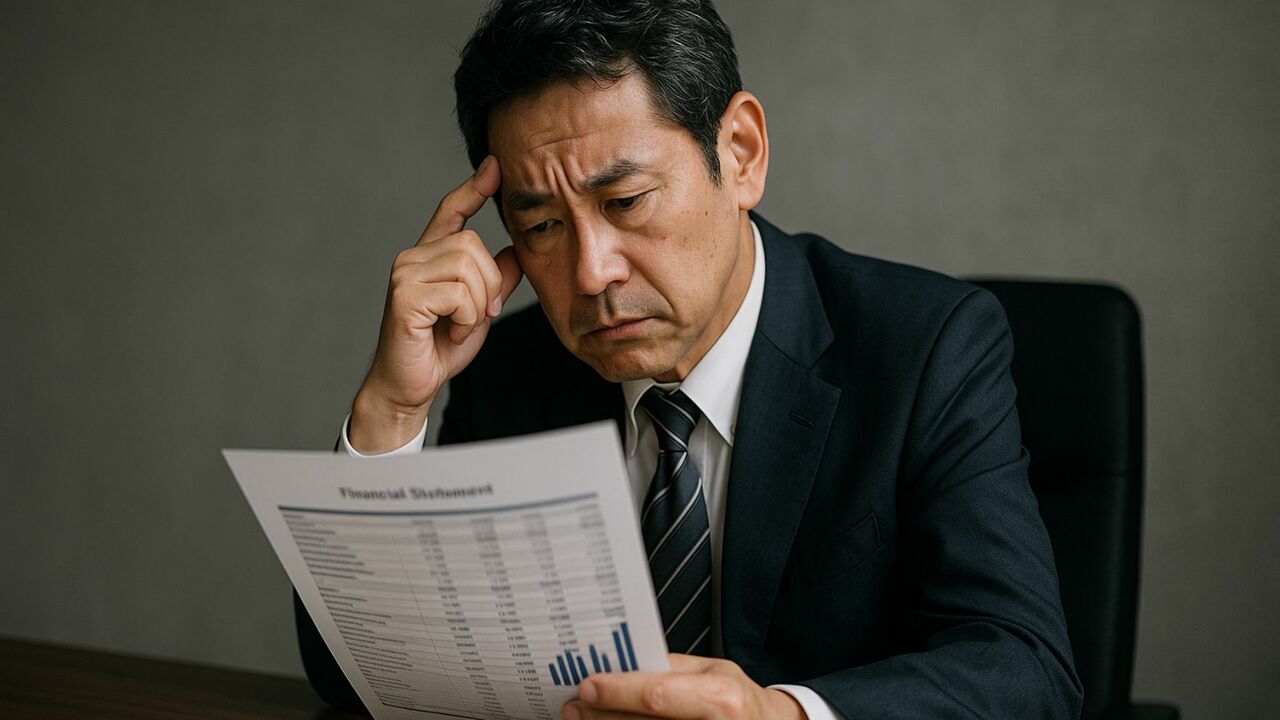【前回の記事を読む】ただ競合より低価格に設定しても、その先に利益は生まれない。成功のカギは「立替金の視点」…現役税理士が解説する経営術
第2章 利益の本質とその再定義
4 利益を最大化するための視点
4-3 三つ目の視点 顧客想定利益の顕在化
三つ目の視点は、「顧客想定利益」の顕在化です。
ここで重要なのは、単に商品やサービスの付加価値を向上させることや、お客様の満足度を高めることで利益を増やすことではありません。重要なのは、利益に対する正しい認識を持つことです。
利益は、実際のところ、取引先や供給者との関係が大きく影響します。利益の大きさは、企業の努力だけでなく、その立ち位置やパワーバランスによっても決まります。同じ活動をしていても、利益を出せる企業とそうでない企業が存在するのは、このためです。
利益を出すためには、取引先や供給者との間での立ち位置やパワーバランスの調整が重要です。これは従業員ではなく、経営者が果たすべき役割です。
また、お客様は商品やサービスの選択を行う際に、それが企業によって提供される価格に見合ったものかどうかを無意識のうちに判断しています。
お客様は「企業が提供する商品やサービスに対して、自分が想定する『顧客想定原価』以上の金額を支払っても良い」と感じることができる金額、すなわち「顧客想定利益」について、意識的に考えているわけではありません。
しかし、競争環境によって価格は適正化され、事業内容や規模、地域、さらには取引先や供給者との関係性を踏まえ、統計資料等から、お客様から「立替金の回収(売上)」できる金額、そして「立替金の支出(費用)」する金額は予測でき、その差額として顕在化するものが「顧客想定利益」です。
このように、利益とは競争の中で顧客の意識的・無意識的な判断の結果として顕在化する「顧客想定利益」なのです。重要なのは、この顕在化した「顧客想定利益」が、競争によって適正化された「立替金の支出(費用)」を前提としていることです。
したがって、企業は自社の「立替金の支出(費用)」を計算する際に、恣意的な支出の増減や特殊な要因(減価償却、保有資産、節税投資など)を考慮し、実質的に適正化した「立替金の支出(費用)」を算出しなければなりません。
数式で表すと、「立替金の回収(売上)」≧適正化された「立替金の支出(費用)」+「顧客想定利益」であれば、問題のない状況といえます。
しかし、同族経営やグループ経営においては、恣意的な支出の増減や特殊要因が含まれているにもかかわらず、それを除外せず、「顧客想定利益」を認識しないまま経営計画を立案すると、多くの問題が生じる可能性があります。
例えば、優良企業であっても、償却済みの資産や保有土地の恩恵による一時的な利益が隠れている場合があります。
逆に、赤字企業であっても、実際には「立替金の支出(費用)」以外の支出、例えば高額な役員報酬や個人的な支出、不良資産の償却による赤字がある場合、実質的には「顧客想定利益」以上の利益を獲得している可能性もあります。
したがって、利益を最大化するためには、「顧客想定利益」を正確に理解し、適正な「立替金の支出(費用)」を計算して経営戦略を立てることが不可欠です。これにより、企業は持続的な成長と安定した利益を確保することができます。