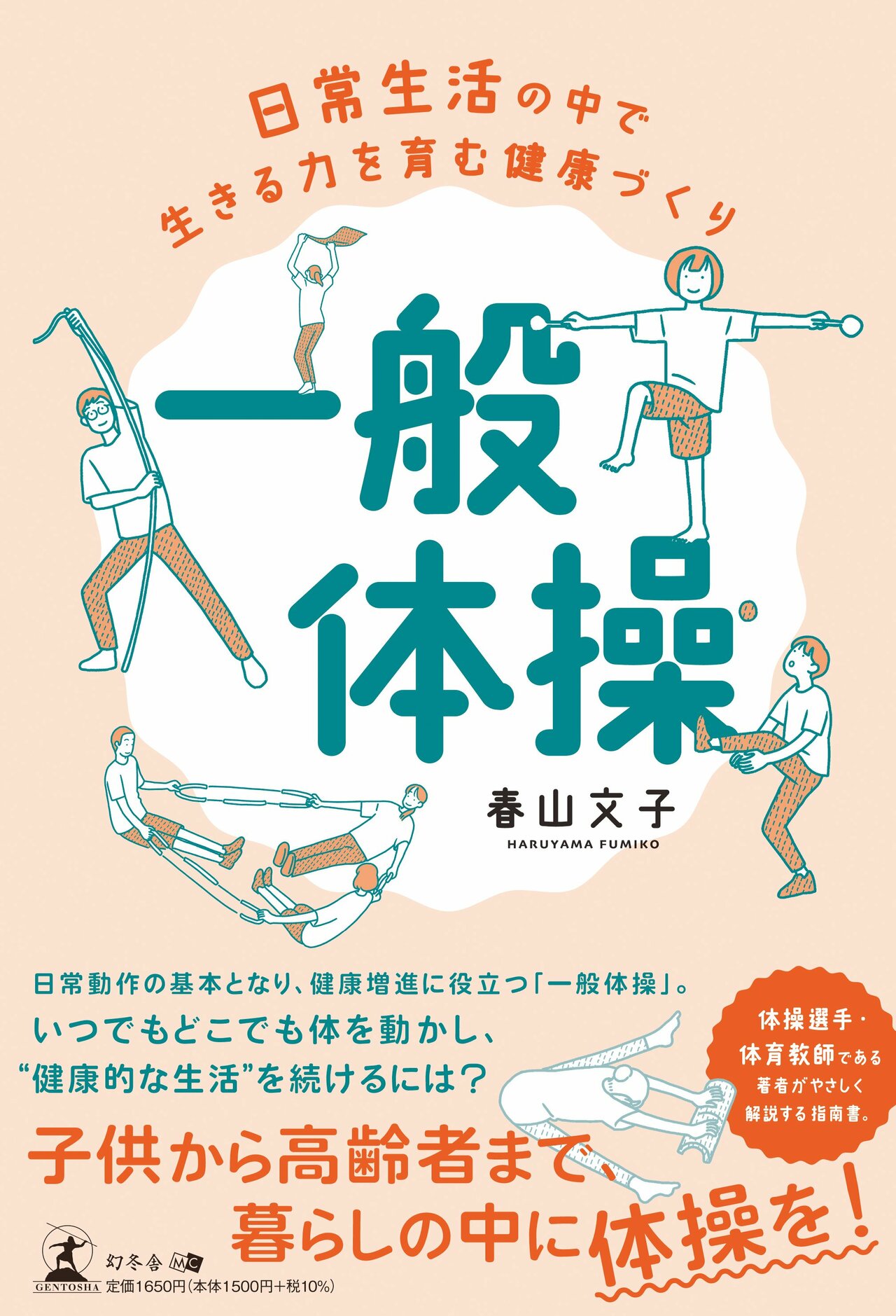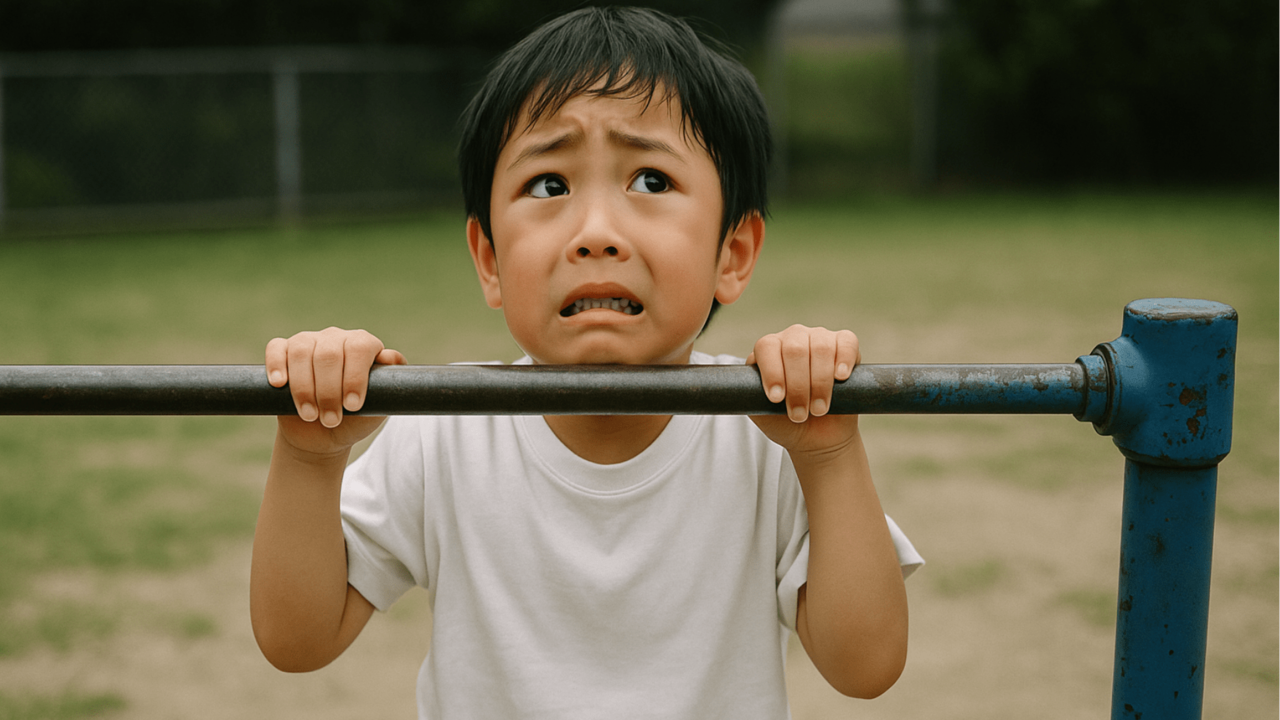第2章 生活動作を段階的に確認
第2章では、生活の動作を次の4段階に分けて確認してみます。
生活とは、生存して活動することを言います。ADL(activityofdailyliving)という言葉をよく聞くと思いますが、一般的に日常生活動作と呼ばれています。
生活の中で多く行われている動作について、4項目に分けて確認しやすくしました。
生活動作の4段階
1. 初段階の生活動作(生涯必要な動作)
2. 第2段階の生活動作(外部と関わる生活動作)
3. 第3段階の生活動作(地域社会に参加協力動作)
4. 第4段階の生活動作(健康維持に必要な動作)
以上の項目ごとに生活動作を確認して生活の充実に役立てる示唆となるようにしてみました。
生活動作の4段階 その前に
各項目に入る前に、なぜ4段階に分けたか、また、姿勢と呼吸の関わり方についても説明が必要であることに気づきましたので、初めに触れておきます。
社会体育での一般体操の基礎づくりは、生活動作から取り上げていますが、実動現場での動きを見て気づいた1つ目は、「動作は当たり前の動きで無意識に動いている」ため動き方や内容について説明が必要であるということです。
2つ目は「姿勢と呼吸の関わり」についても説明が必要だと感じ、簡単な聞き取りや記入方式で現況を調査した結果を踏まえて健康体操講座に役立てていることです。
以上の1と2の気づきから4区分に具体化して理解しやすくして、自覚しながら動けるようにする方法としています。
1つ目の気づきでは、一般体操はやったことがない、「はじめてです!」という方々から生活動作に対する意識が変化したとの感想が聞かれるようになりました。
また、生活様式の変化がからだの動かし方に影響している代表例に、和式トイレの減少があります。しゃがんで用をたす機会が減り、しゃがむ姿勢が苦痛になっているため、和式トイレが空いていても、わざわざ洋式に並んでいる光景もよく見かけます。
また、重い荷物を持たない、便利な交通網によって歩かない、手料理も簡単に、など生活環境の変化が身体機能に影響を及ぼしています。
2つ目の「姿勢と呼吸の関わり」についても、階段や坂道を上がったときにハーハーと息切れしている人が多いのも気になります。
呼吸を意識するのは深呼吸のときくらいかもしれませんが、動きと呼吸の関わりについての知識やトレーニング不足が見受けられる現状を踏まえ、生活動作指導に役立てる狙いで細分化して説明しました。
生活姿勢と呼吸についてのマメ知識
生活で主に使われる姿勢臥位姿勢=仰向け(仰臥位)、腹ばい(伏臥位)、横向き(側臥位)
座位姿勢=正座、あぐら、横座り、脚伸ばし(長座位)、膝づき座(起坐位)、腰掛ける(各種椅子・石・材木)立位姿勢=両足立ち(立位)、片足立ち、中腰(しゃがむなど)
呼吸は、脳の呼吸中枢が肺の周りの筋肉を動かすことで行われ、動作目的により自分でコントロールすることができます。
👉『日常生活の中で生きる力を育む健康づくり「一般体操」』連載記事一覧はこちら
【イチオシ記事】彼と一緒にお風呂に入って、そしていつもよりも早く寝室へ。それはそれは、いつもとはまた違う愛し方をしてくれて…
【注目記事】(お母さん!助けて!お母さん…)―小学5年生の私と、兄妹のように仲良しだったはずの男の子。部屋で遊んでいたら突然、体を…