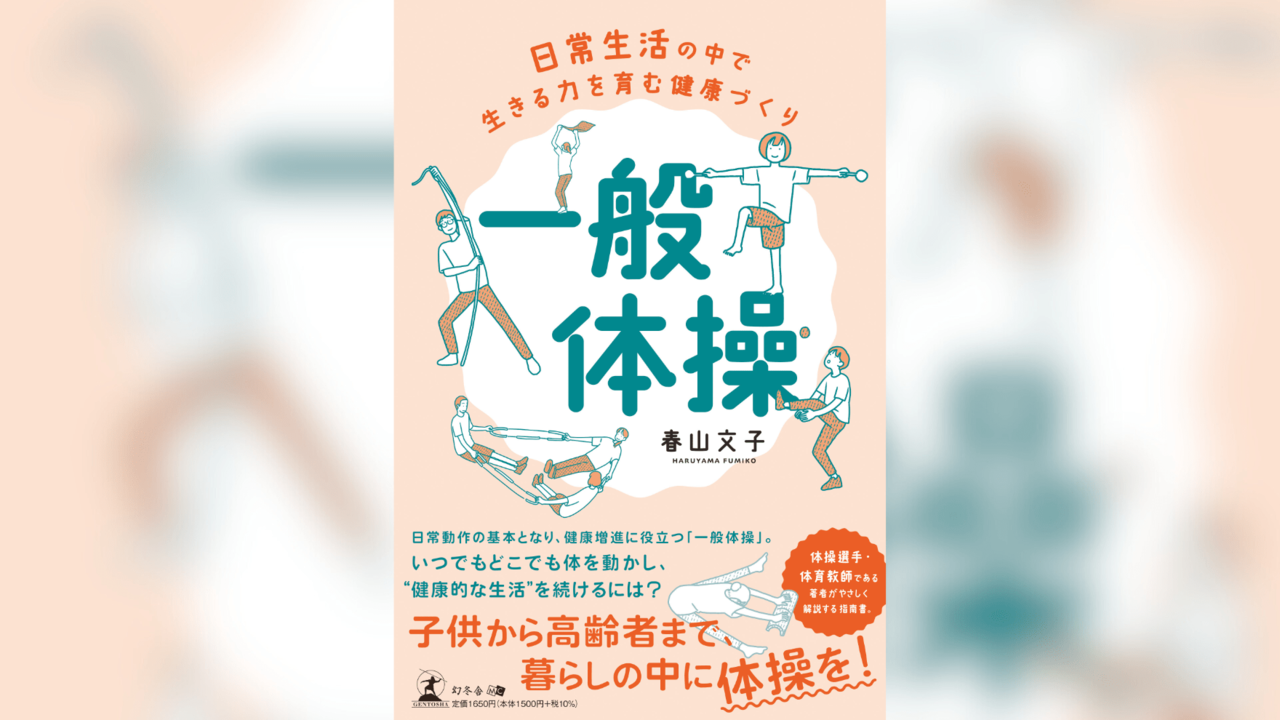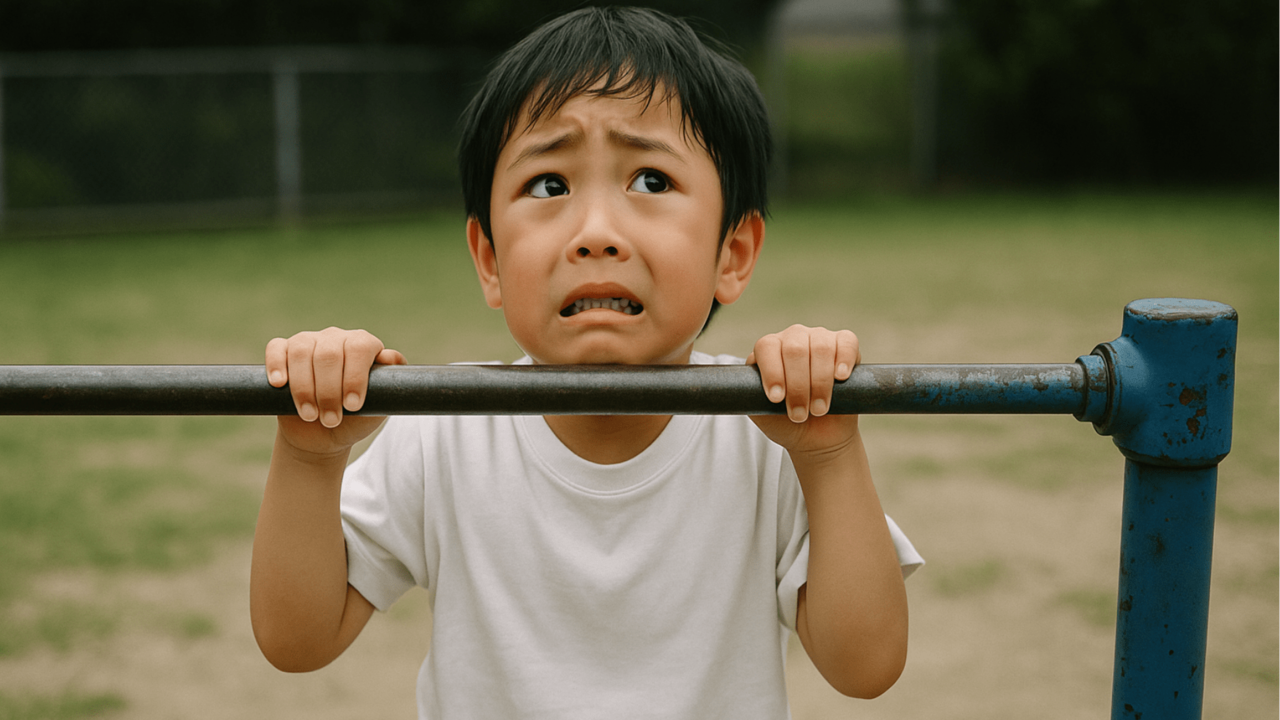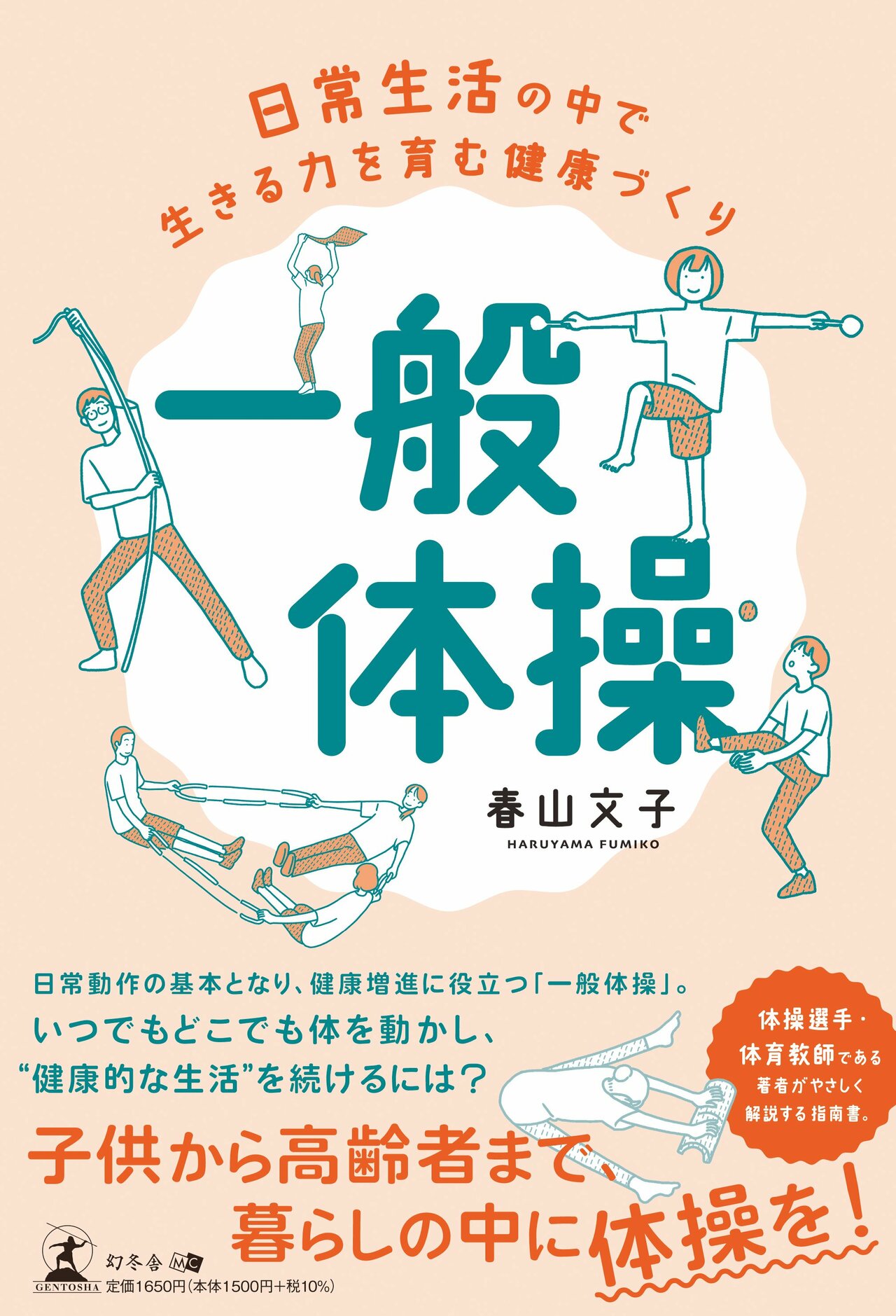【前回の記事を読む】【生涯学習としての健康づくり】老若男女みんなの日常生活に役立つ運動習慣の大切さと実践
第1章 生きる力の土台づくり
第1章の生きる力の土台づくりとして、以下の1~4について説明をしています。
1 基礎づくりでは動ける喜びを知る
2 日常生活の中で多くの動作を体験し習慣化する
3 動作内容をバランスよく選択して偏りに注意する
4 基本動作の「一連の体操」
1 基礎づくりでは動ける喜びを知る
人間は、他の動物のように、生まれてすぐ立ち上がり歩くことはなく、未成熟状態で生まれることから、順序立てた学習が必要であることは言うまでもありません。一人で歩くようになるまでには、おおよそ1年近くかけて筋力や機能づくりをします。
寝返りや一人座りから、手と足を使って自由にハイハイで移動する時期があり、つかまり立ちをし、やがて一人で歩けるようになるまでには、何度も何度も繰り返し筋力と機能を強化しています。一人歩きができたときの喜びは、親も本人も忘れません。自分の意志で自由に動ける喜びは生涯保持したいものです。
現代の便利な生活では、動く努力を忘れたような弱いからだが気になっています。
バギーに乗った乳幼児が足をぶらぶら動かしている光景、転んでも立ち上がらず助けを待つ光景、子どもも大人もモータリゼーションの環境では階段、坂道を避け、便利な交通によって歩く機会が減り、基礎となるいろいろな動きや動作が減少しています。
繰り返しの頻度も少なく、できるだけ力を必要としない、軽薄短小で強度の弱い行動を選ぶのが当たり前になっているので、私は繰り返すことで身につくからだづくりを強調したいのです。いつでも動ける喜びは、元気な明るい声や楽しんでいる行動に表れるものです。
ゆっくり繰り返し動いて十分な時間をかけて土台づくりに努め、いつでも、どこでも対処できるからだを保持していくことを望みます。土台となるからだは、その後の動作につながり、影響を及ぼし、自信をもって自由に一人で動ける喜びや、積極的行動に変わっていきます。