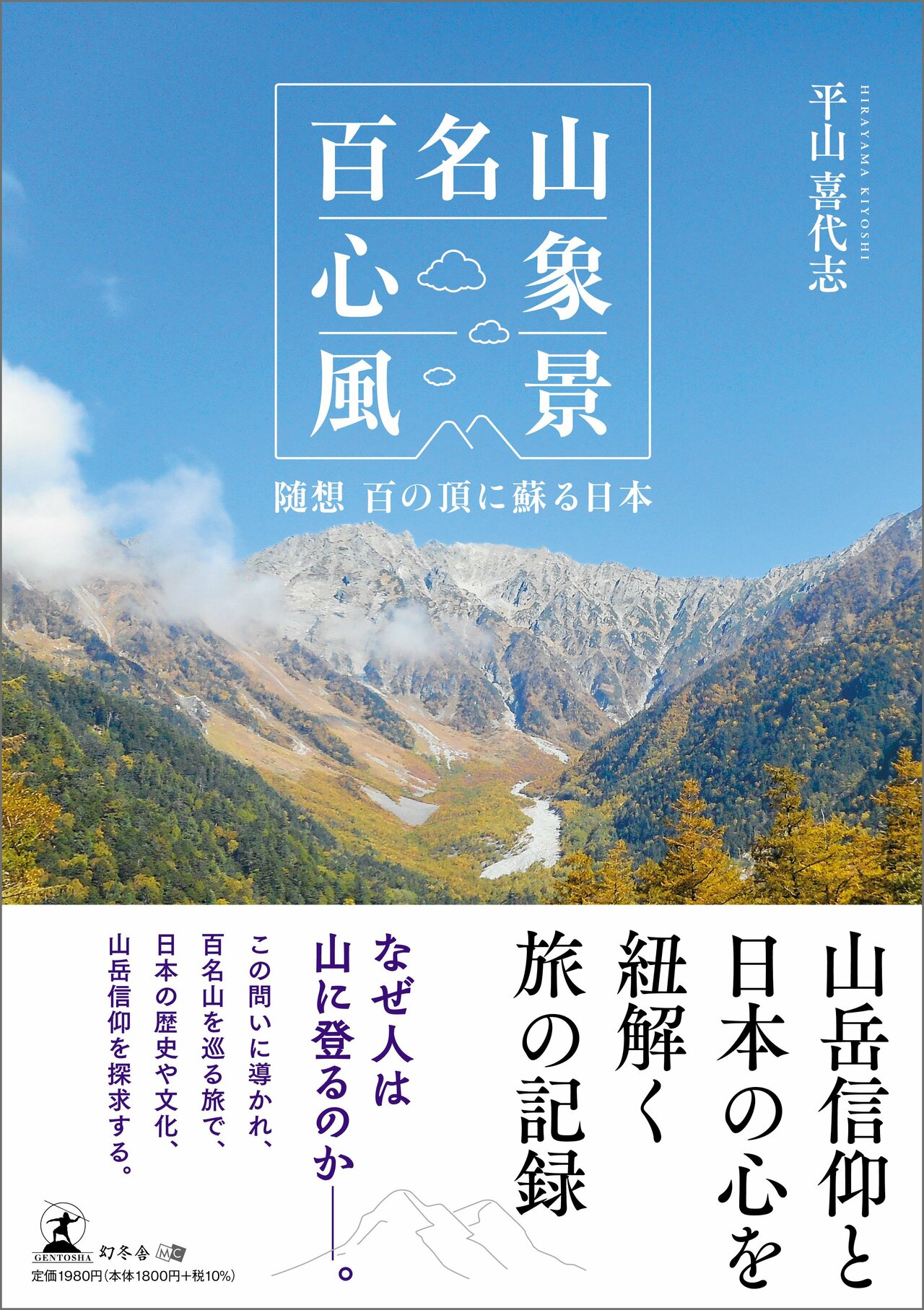第2項 主役の構想
①藤原不比等
山と宗教の脈絡を探っていたら、思わぬうちに日本の歴史に辿り着いた。山と一体の神仏を語れば、歴史的流れを放擲する訳にはいかない。歴史は国家の運営及び民族の活動の変遷である。かいつまんで中心人物及び関連性のある歴史的事象を注釈した。
飛鳥期に至る大和政権以前、首座を務めたのは天皇(大王)であり、脇侍役は支持勢力の有力氏族と任じている。統治形態を簡略すれば、天皇を中心に複数の強盛氏族が合議で政治的決裁を行う部族社会の特徴を示した。
天皇家を支えていた氏族の中に祭祀を統括した中臣氏がいて、後に藤原姓を賜った鎌足(614~669、藤原鎌足)を輩出する。祭政一致の本質を見抜いた藤原氏が一頭地を抜き、平安期の政体を主導した背景が見え隠れする。
この後、度重なる政変を利用して、有力貴族を排して天皇近臣で一番隆盛を誇ったのは藤原氏であった。約400年にわたり側近政治を差配した結果、史上例を見ないほど藤原の誉れを上げた。数多い俊英の中で歴代天皇の信任厚く、家門の基盤を確立した人物を精察すると、不比等(659~720)が浮上した。
後述するように、彼は今日に至る「国の原型」創造に関わったことで大功を治めた。国の原型とは現在に整合する不磨の国家体制、法典、国史を確立した功績を意味する。人間は社会的動物といわれ、社会性の実体である制度、法律に一旦馴致すると、世代が交代してもその縛りから逃れられない性質を有している。
千年前の社会制度を軛(くびき)と轅(かなえ)とは思わずに容認し、頑なに拘泥する傾向を現す。人間は進化の特徴である言葉と文字を駆使して、高度な科学的、文化的発展を遂げた。それでも、一旦身につけた原初的生存様式は安易に断捨離しようとはせずに、個人も国家も因襲と変革のはざまで呻吟し続ける。
【イチオシ記事】「私、初めてです。こんなに気持ちがいいって…」――彼の顔を見るのが恥ずかしい。顔が赤くなっているのが自分でも分かった
【注目記事】「奥さん、この二年あまりで三千万円近くになりますよ。こんなになるまで気がつかなかったんですか?」と警官に呆れられたが…