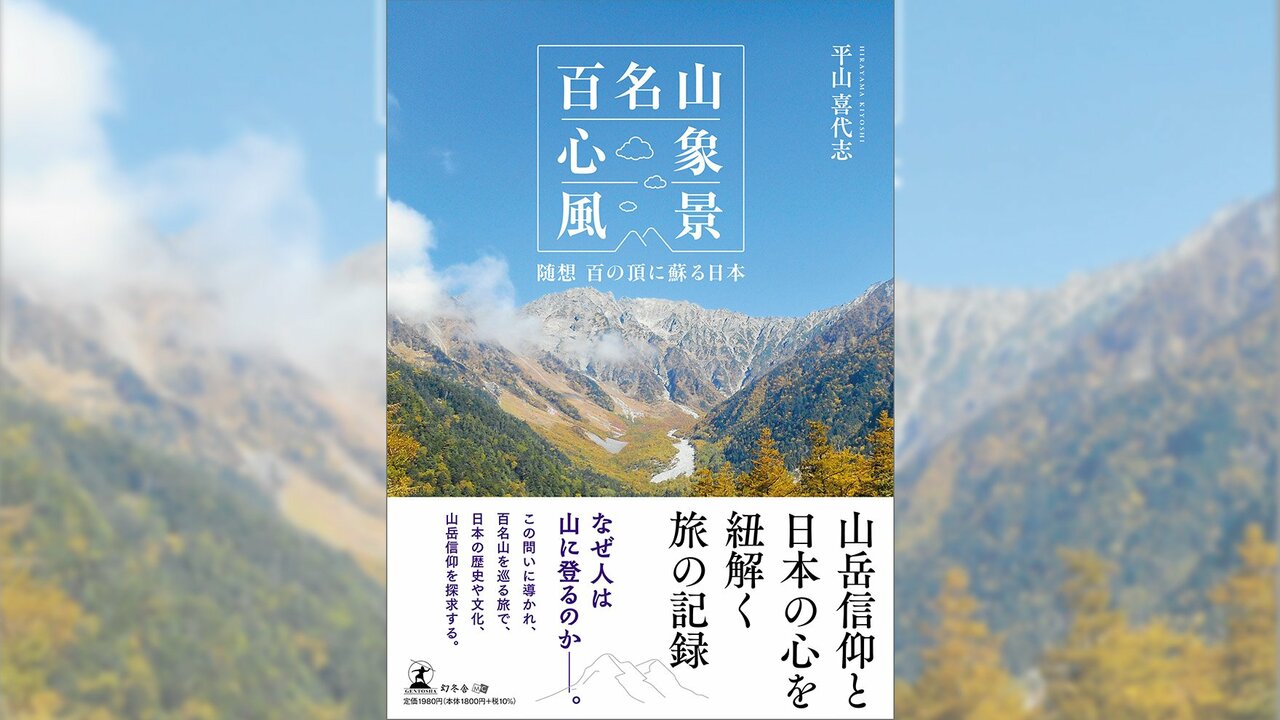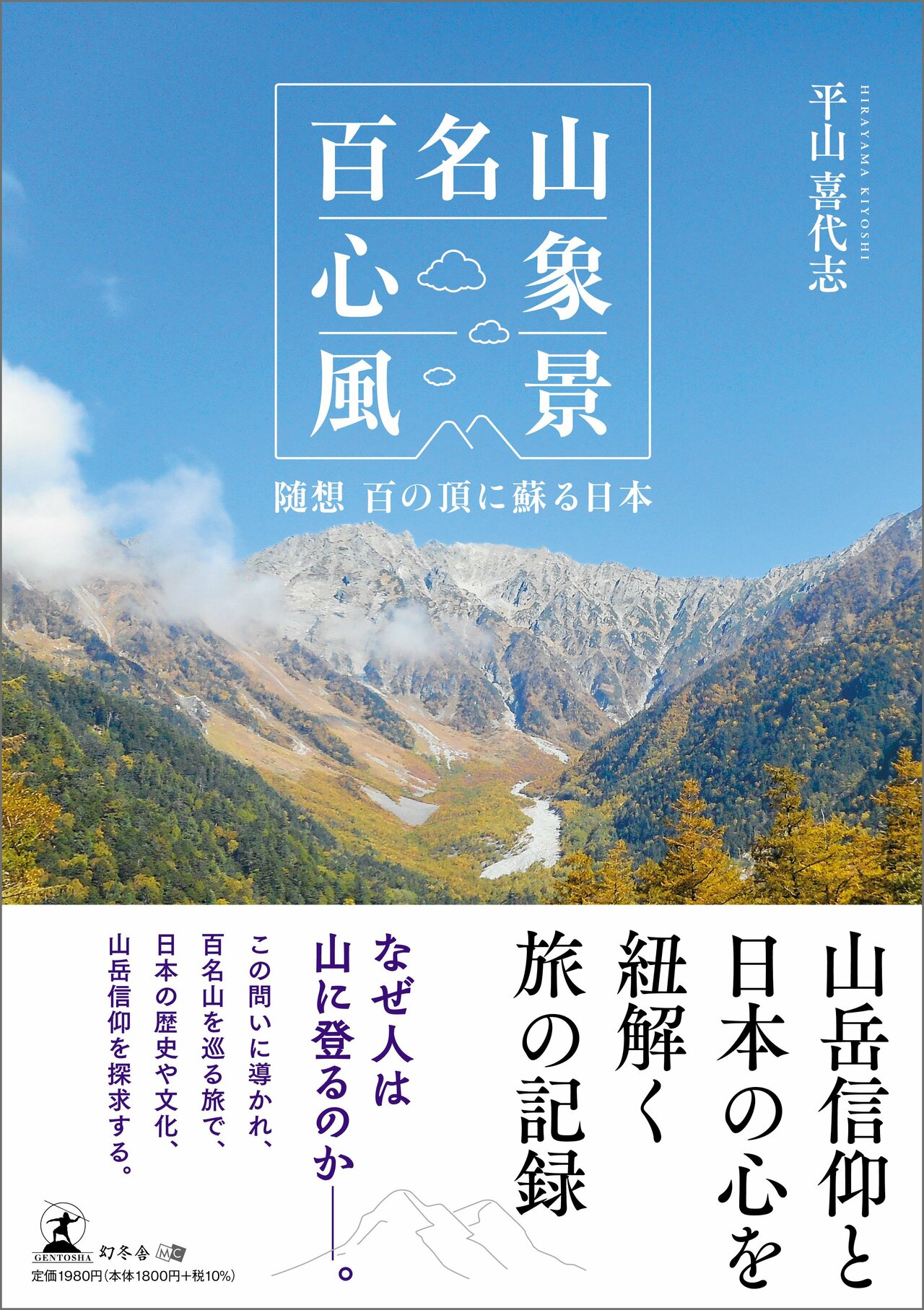【前回記事を読む】抗争や生殺与奪の歴史に正統性を持たせたい『古事記』『日本書紀』編纂では、神話化・こじつけ・誇大修飾は必須だった。
第1章 日本民族及び国家の成立
第2節 国家の成立
第1項 神話由来
④記紀神話の国造り
初めて、地上で興国を達成した素戔嗚尊は、祭神として須佐神社(出雲市)に祀られ、歴史の要所に現れる。又、緑樹の薄い山々にスギ、マツ等の木を植えたことで、素戔嗚尊は木の神にもなっている。これは樹木を大切にする日本人の文化と整合する。
このように、日本の神社(神宮)は天の原の神々を起源とし、信仰、崇敬の対象として拡大した。この経緯から神社は当初から公式の権威を賦与されていて、その典型を須佐神社に窺える。
これに類似する神社展開は権力構造が変わる度に出現する。宇佐神宮(宇佐市)はその好例である。当神宮の祭神は第15代応神天皇・比売神(ひめがみ)・神功皇后である。神功皇后は応神天皇の母で、熊襲征伐で勇名を馳せている。武力で霊妙を帯びる活躍をした人物が神様として神社に奉祀される一つの事例が生まれた。
因みに、武略により政権を奪取した鎌倉幕府以降の武士階級が軍神、守護神を祀る宇佐神宮、八幡宮系の神社を信仰するのは、ある意味摂理に適っている。忘れてならないのは、神武天皇から大和政権までの歴代天皇は、『日本書紀』で語られる神話上の存在で、実在性は分からない。神話だけに実態は不明でも、全て架空の空想物語とも考えづらい。
恐らくそれぞれの天皇は、神格化された人間をこと寄せて誂えたように読める。文字による確証が得られない大和政権までの歴史は、複雑に交錯した口承にしか頼れず、編者も論理的構築には手を焼いたに違いない。
高千穂峰に降臨した瓊瓊杵尊の曽孫にあたる神日本磐余彦尊(かんやまといわれひこのみこと)(後の神武天皇)はやがて日向の地を離れ、東征して大和に向かおうとしたが、難波には上陸出来ずに熊野から大和に入り、橿原宮で第一代天皇に即位したという。
この時の道案内役が八咫烏である。神話が伝える建国である。この神武天皇の偉業に対し、明治政府は神武天皇を御祭神として橿原神宮を創建した。

この後、第10代崇神天皇は三輪山(桜井市)を中心にした政治勢力を築き、5代後の応神天皇と息子の仁徳天皇は河内を基盤にして巨大な前方後円墳(天皇陵)を残した。しかし、九州に降臨した勢力と大和の勢力の間には不連続性、不整合があり、王朝交代説や騎馬民族征服といわれる新説が生まれる由縁となった。
降臨後も、国家に偉大な貢献をした神々の後裔や天皇は活躍した分野に従い、様々な形態を取りながら、神社に最高の栄誉である祭神として祀られる構図が顕現してくる。
先の国譲りの交渉で功績のあった武甕槌命と経津主大神は、それぞれ鹿島神宮と香取神宮の軍事の祭神として奉祀される先例となっていた。最上位の社格であるこれら二つの神宮は、大和政権が東夷征伐の軍事的守護神として崇敬していたもので、後世幕府の将軍や武人も神領を寄進、幣物(贈物)を奉納している。
武力を司る神を祀る神社なので、天下を掌握した天皇・貴族等の宮廷人、又は武将から厚い庇護を受けた。権力者と神道はいつも相互に相手を必要とし、不可分の存在と暗黙知していた。
一方、釈迦の教えが基本の仏教は、国家の庇護の下に思想統制の手段、鎮護国家の役割を果たし、蜜月関係が続いた反面、次第に新たに勃興した独自の宗派と政治権力との間に深刻な対立を抱える。世界有数の仏教篤信国の日本ですら、仏教は外来宗教であり、神道は固有の教義と認識する文化的背景がある。
この対比は中国に於ける儒教(道教)対仏教の関係に似ていて面白い。長期的視座で宗教を捉えると、どこの国でも自国宗教は国粋趨向性が発現し易い。