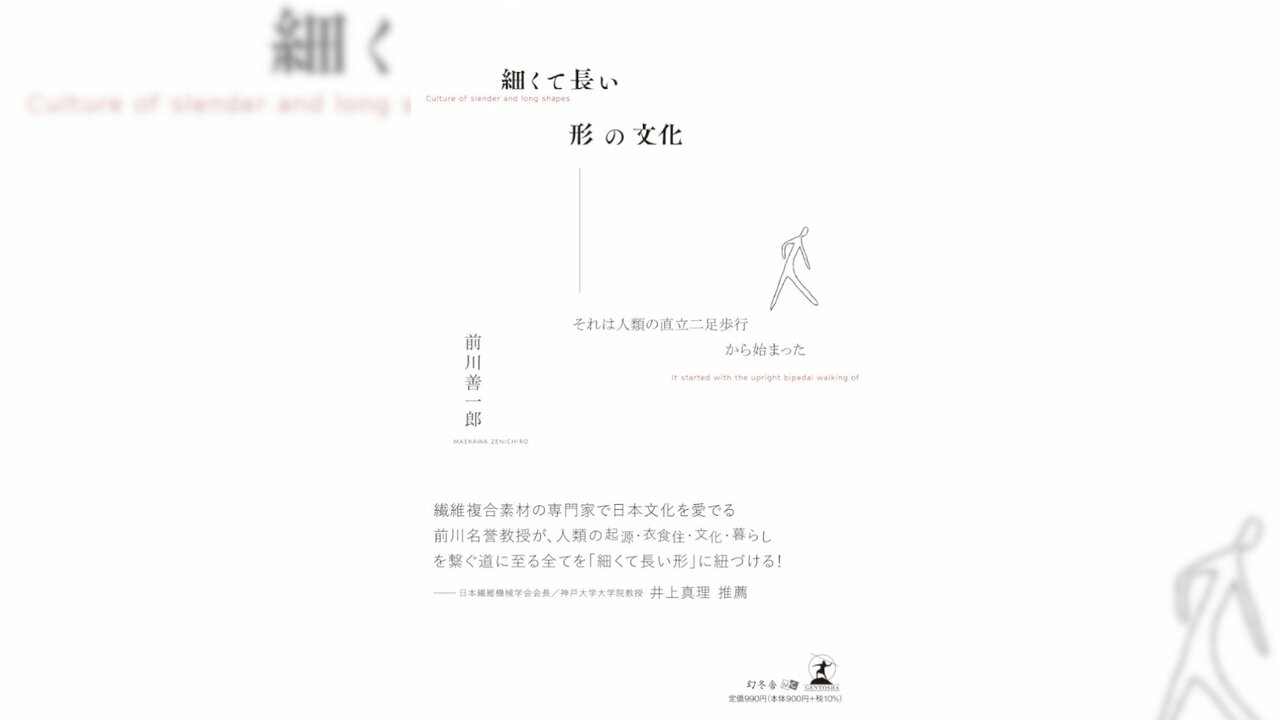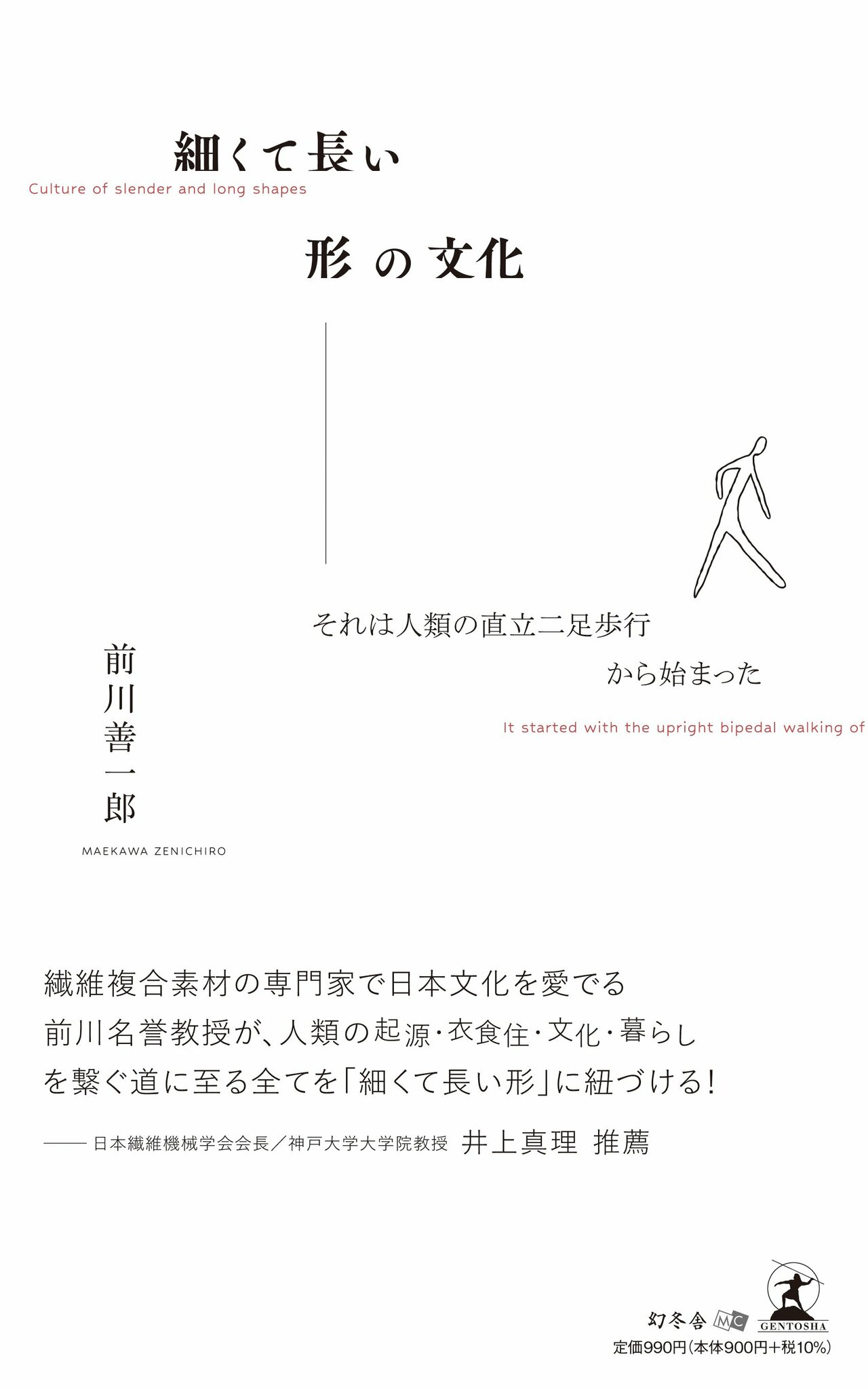【前回の記事を読む】人類の文化発展の鍵――衣食住から音楽まで、全ての分野で“ある形”をした材料が使われている。その形とは…
第2章「細くて長い形」を使う文化
Ⅰ 「細くて長い形」を使う文化に貢献した二つの贈り物
1 直立二足歩行からの贈り物―人間の手と脳
人間の手の不思議
地球の長い歴史の中で、約六五〇〇万年前に恐竜時代が突然に終焉を告げて哺乳類の時代に入ったが、人間が属する霊長類の祖先である原猿類は、四〇〇〇万年前に早くも地球上に現れている。そして現在に至る長い歴史の中で多種類の霊長類が現れた。
霊長類は主として樹上生活を送ったため、樹木を握るいろいろな手が出現した。
しかし、霊長類の最後に現れた人類は、大地を歩く生活を送るのに相応しい手の形に進化をとげ、霊長類の手と明らかに異なる人間の手が二〇〇万年前頃に出現した。
日頃、何気なく使っている手であるが、手に注目して、手をいろいろ動かしてみると実に複雑な動きをすることがわかる。
手を前に曲げた後に反らせて、一八〇度近く裏返したりできる。手は、五本の指と、一四個の関節と、二七個の骨がつながっている。
手首にはサイコロのような骨が八個あり、靭帯によってつながっているので、手をひねると裏返すことができる。手にとって重要な動きに対立運動がある。
親指の腹と他の四指の腹を合わせる運動のことで、四本全部でも、一本ずつでもできる。口の広いビンのふたを開ける時には指を総動員して掴み、ペットボトルのふたでは人指し指と親指で掴む。
さらに、手のひらが力を抜いた状態で窪んだアーチ形をしている。手のアーチと対立運動によって、掴む、包み込む、握るなどの運動を効率よく行うことが可能となる。