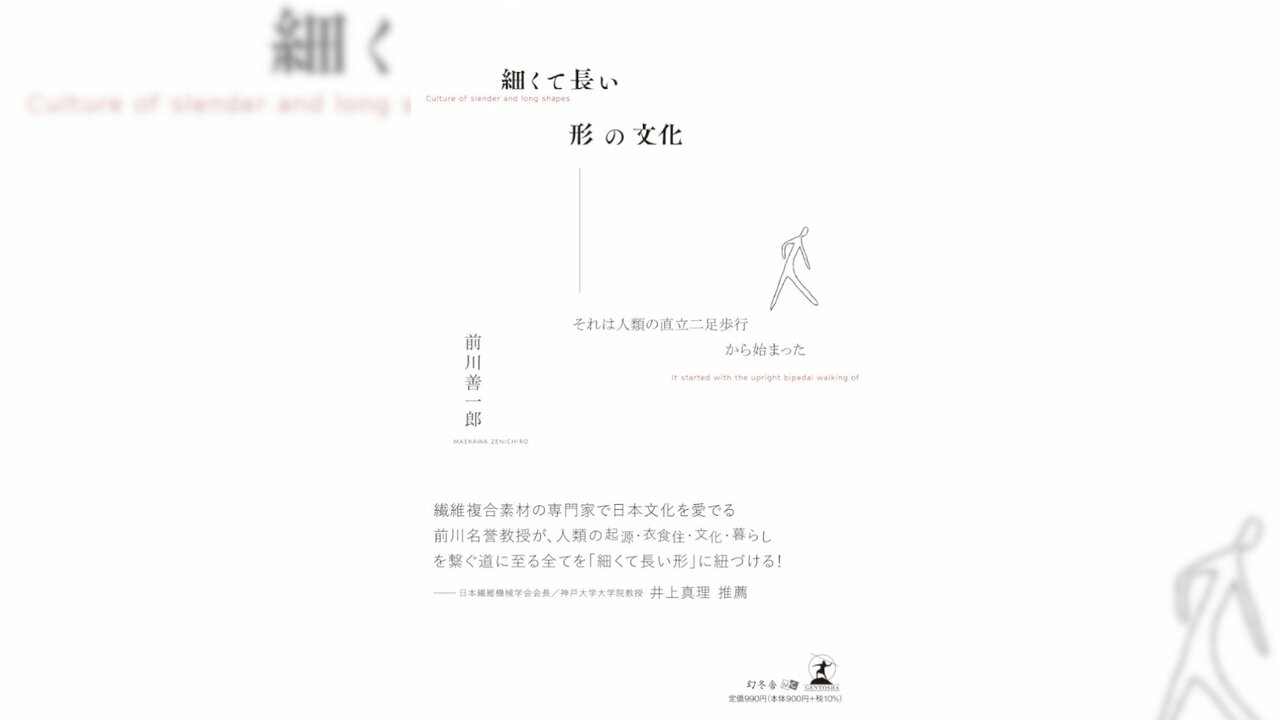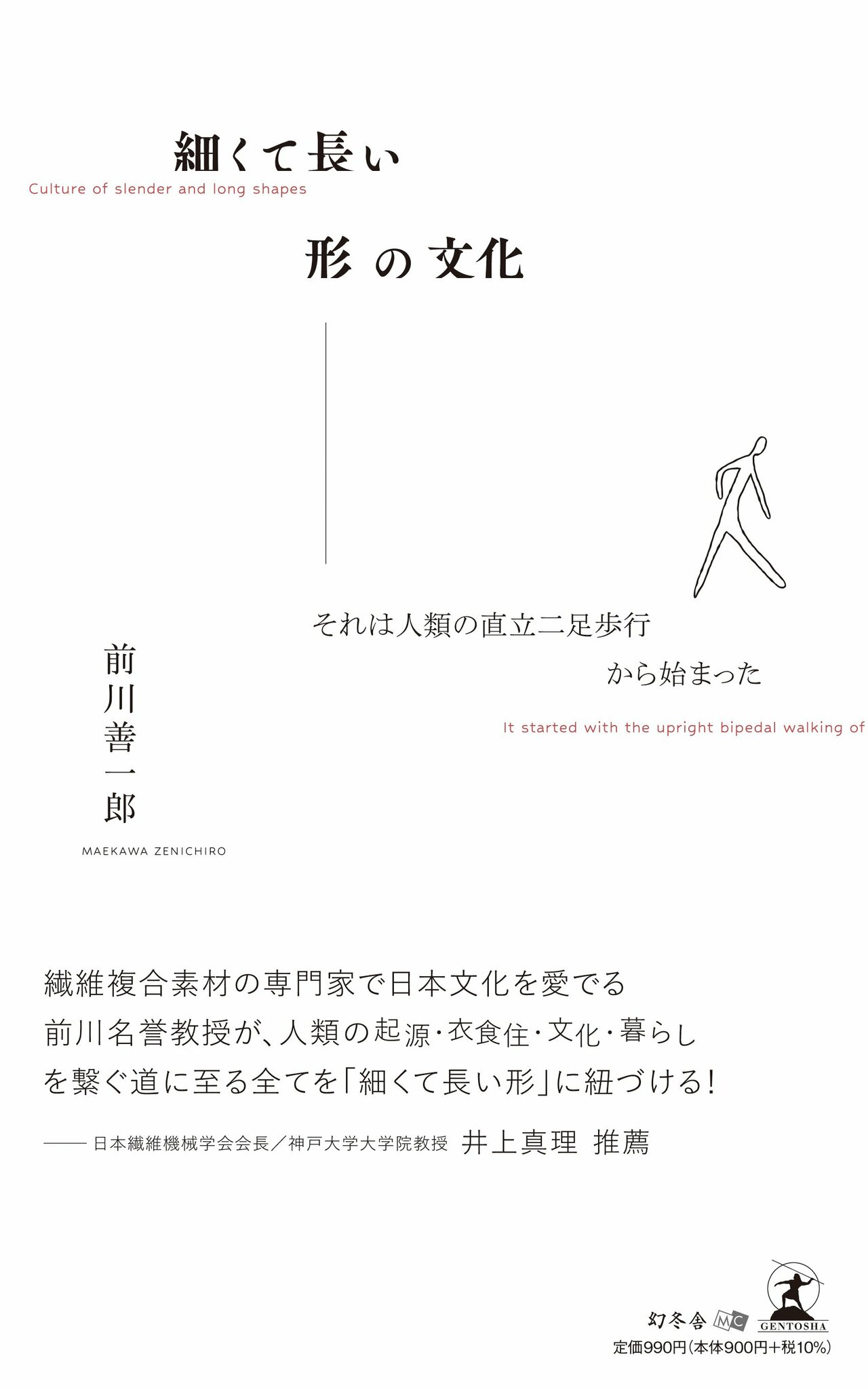【前回の記事を読む】細長い建築や道具の魅力をアスペクト比で解き明かす! 「細くて長い形」の秘密と安定感・機能性の不思議な関係とは?
第1章 「細くて長い形の文化」は直立二足歩行から始まった
Ⅲ 「細くて長い形」の程度を測る尺度―アスペクト比(縦横比)
アスペクト比が一〇〇以上の世界
人類が自然の中に作り出した「細くて長い形」をしたものとして道がある。人類が生活するところに必ず道が作られるため、道の長さは無限になる。
そこで、道の代表選手として、日本人になじみの東海道五十三次を取り上げよう。東海道五十三次は、江戸時代、江戸日本橋から京都三条大橋に至る東海道に置かれた五十三の宿場をつなぐ全長四八七・八kmの街道である。街道の道の幅は約一一mであるので、アスペクト比は四万四〇〇〇程度と、数万の大きな数値となる。
さらに、自然にはアスペクト比が数億になる「細くて長い形」をしたものが身近にある。絹糸は衣料を作る大切な素材の一つである。絹糸は、蚕がさなぎを作るために、蚕の口から吐き出す糸であり、その長さは一〇〇〇mを超え、糸の直径は一〇マイクロメートル程度である。ここで、一マイクロメートルは千分の一mmの小さい単位である。その結果、絹糸のアスペクト比は一億位の非常に大きい値になる。
調べる対象物はまだまだいくらでもあるが、ここまでの調査だけでも「細くて長い形」の世界が奥深いことがわかっていただけたと思う。以下の章では、アスペクト比がおよそ四以上の「細くて長い形」をしたものに焦点を当てて、①「細くて長い形」をしたものを「使う」視点から(2章)、②「細くて長い形」で「伝える」視点から(3章)、③「細くて長い形」をしたものを「歩く」視点から(4章)、この三つの視点から「細くて長い形の文化」を順番にたどっていこう。