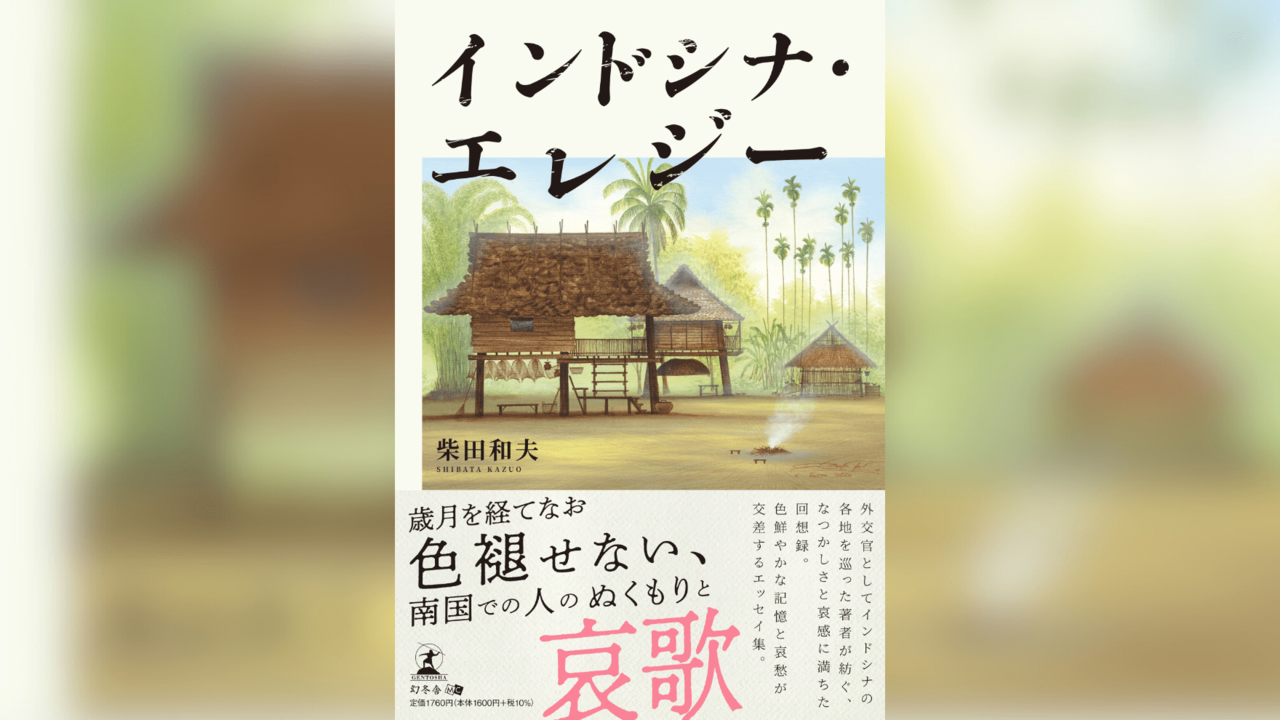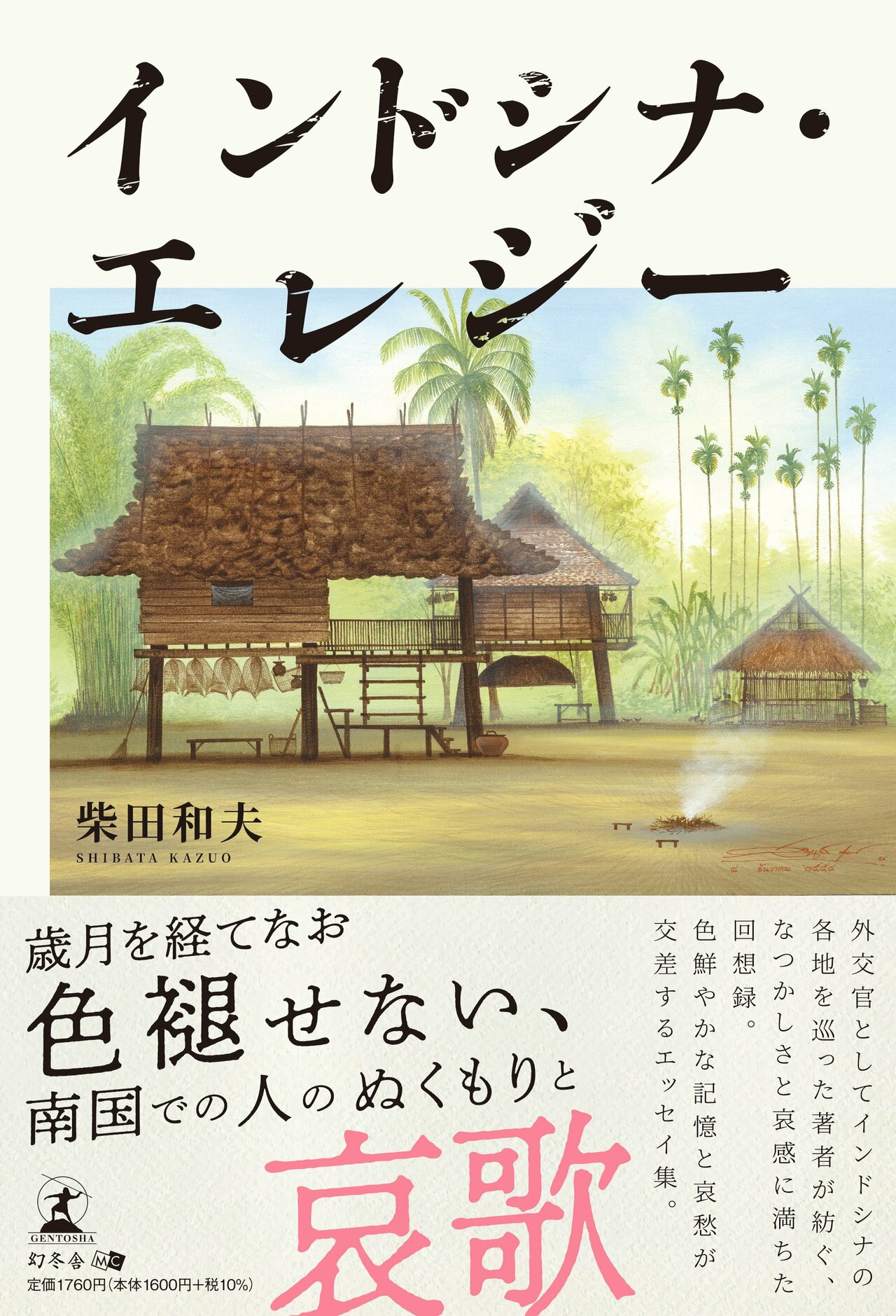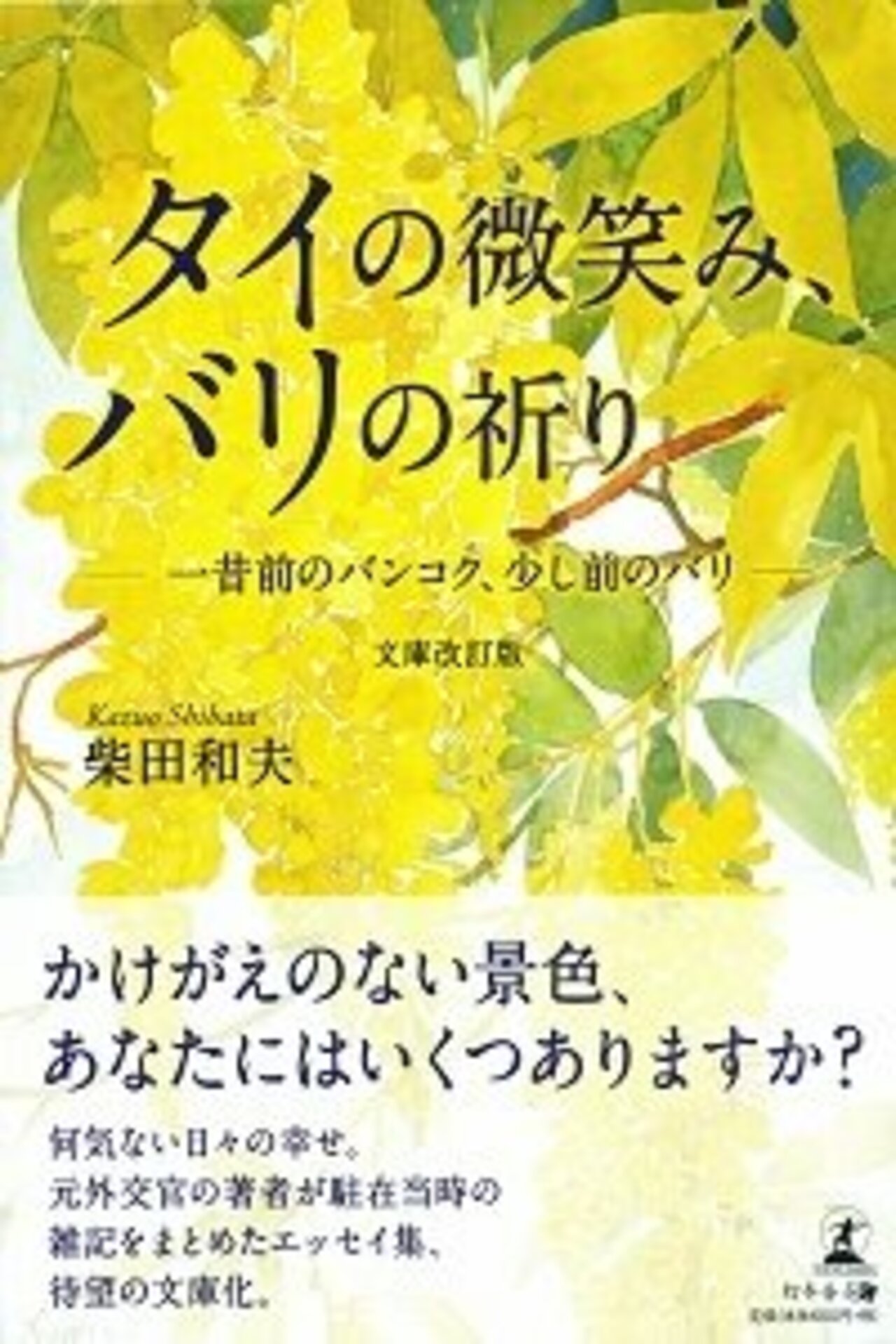【前回の記事を読む】外交官として過ごした東南アジアの日々…今も忘れられぬ人々と風景が胸を締めつける
プロローグ
その昔、インドシナのどこかの国のホテルに投宿した際、偶然にTVで見かけた映画のなかに印象的なシーンがありました。その映画は、第二次世界大戦後、ベトナム民主共和国の独立をめぐり、宗主国のフランスとの間で起こった独立戦争でもある第一次インドシナ戦争に関するものでした。
映画のなかで、フランスの一小隊が、ある村の偵察に出撃した際、隊員の一人が被弾し重傷を負って断末魔の悲鳴を上げるシーンがあったのです。
地獄とも思える痛みに堪え兼ねて呻(うめ)いている隊員に対し、若き小隊長は、やおらその隊員のズボンを下すと、自らの口をその下腹部に持っていったのです。私にとってそのシーンはあまりにも衝撃的かつ驚愕的でした。
耐えることのできない激痛に身を捩(よじ)り、やがては息絶えてしまうであろう部下にほんの一瞬でも痛みを忘れさせようと考えたのでしょうか。
その小隊長の取った行為、仮に、私が小隊長と同じ立場に立たされた場合、果たして死の間際にいる部下の痛みを和(やわ)らげることが目的で、そのような行為に及ぶことができるのか否か甚だ疑問ではあります。
古くは中国の元(げん)によるベトナム侵攻、第二次世界大戦、ベトナム戦争、カンボジア紛争など、種々の悲劇に見舞われたインドシナ、そのインドシナの辿った歴史を個人的に反芻(はんすう)する際、私の脳裏にdejabu(既視感)として表れてくるのは、まさにそのシーンなのです。
「上海エレジー」という歌があります。松本隆さん作詞、南こうせつさん作曲によるものですが、アジアの歌姫で哀愁を帯びた声のテレサ・テンが歌う「上海エレジー」を聴く度に、異国情緒が掻き立てられ、なぜか胸がキュンと締め付けられるようなしんみりとした気分になってしまいます。
私の青春時代、「あがた森魚」というかなり風変わりな芸名を持った歌手が、「赤色エレジー」という歌を自作自演していました。その歌手の面妖怪奇な独特の風貌、そして、その歌詞の内容の放つ衝撃度の強さで、私にとりきわめて強い印象を残した曲の一つです。
歌の主人公の「幸子と一郎」の哀切に満ちた裏ぶれた人生を想起させるかのような歌詞と哀愁を帯びたメロディ。当時の私は、その歌を聞く度に憂鬱(ゆううつ)な気持ちが先立ち、好きになることはまったくありませんでした。