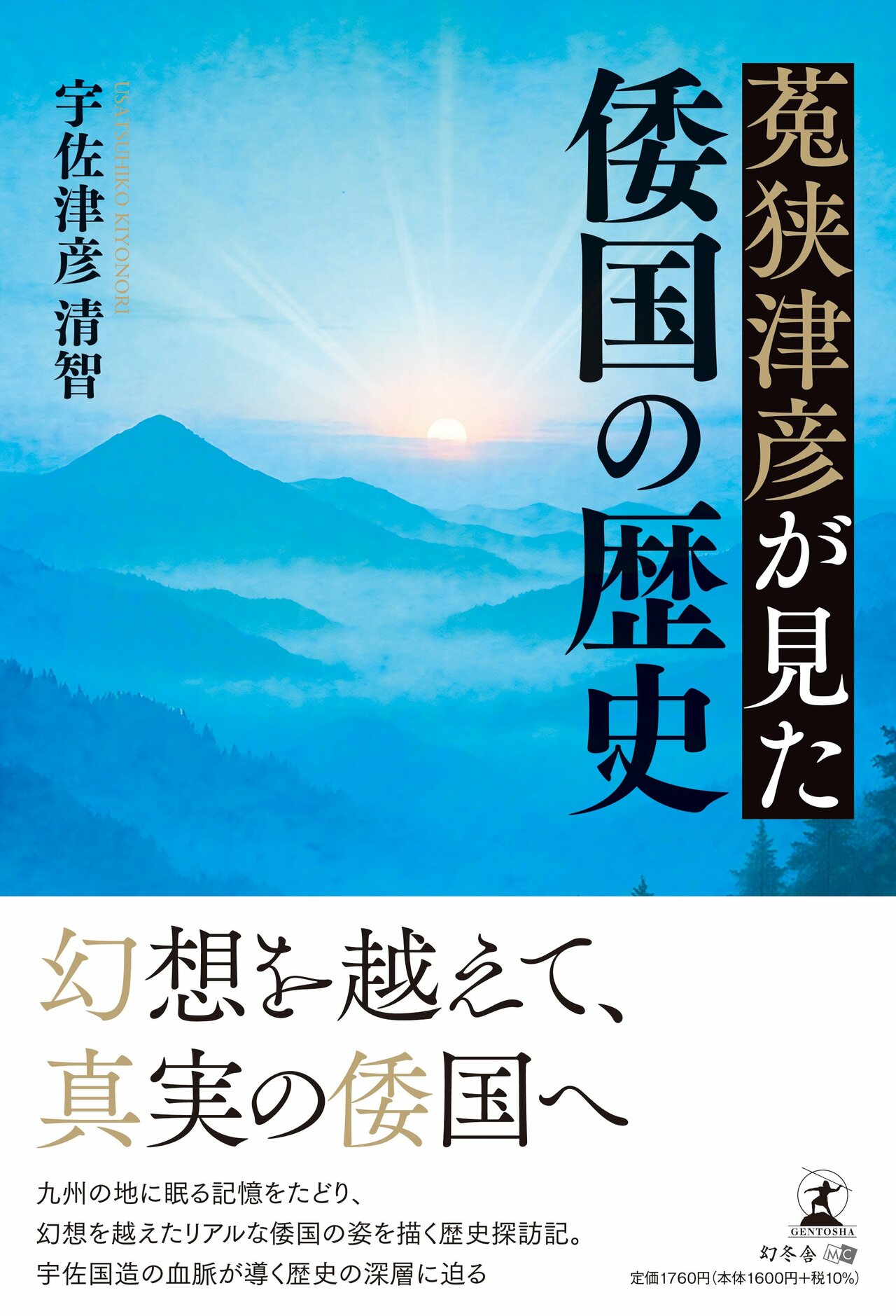次の危機は、弓削道鏡の偽託宣事件に宇佐池守が宇佐宮宮司時代に巻き込まれた時だろう。八幡神は驚くべき託宣を告げるが、この辺は歴史報告書12を読んでもらいたいと思う。
弓削道鏡がなぜ皇位に就けるのか、ここまで読んでくるとその謎が自然と解けるのではないだろうか。八幡神の託宣がもし振れていたら、池守も罪を被せられていたかもしれない。しかしこの事件を乗り切ることで、小宮司という地位が延喜式により確定し、次の時代に進んでいくことができた。
宇佐家最大の危機は、源平が相争い、宇佐宮が兵火で炎上した平安末期だ。この時は宇佐公通が大宮司に就任しており、九州一円の領主として大きな権力を有していた。彼は大宮司職を得るために絹六万疋を高陽院(かやのいん)に献上している。そのような宇佐家に緒方三郎惟義が反旗を翻すが、ここは歴史報告書05で触れていきたいと思う。
以降は歴史報告書としてはまとめていないが、南北朝時代に本家宮成家が南朝方についたことから九州探題と険悪な状態となり、宇佐家が粛清されてもおかしくはなかった。
この後大友宗麟と大内家との争いでは、宇佐の家々は大内家に与することで、大友宗麟に焼き討ちされる。やはりこの時も宇佐八幡宮は炎上したが、八面山山麓の宇佐家庶派の家々や菩提寺もことごとく灰燼に帰すのだった。それでも先祖達は何とか命を繋いでいった。
明治時代、維新の改革のなかで、宇佐八幡宮は到津家のみが社家として存続を認められ、その他の家々はこの時に社家を返上させられている。また農地改革により、多くの荘園を失った。そして最後に大東亜戦争があり、戦後はGHQの指令の下で再び多くの田畑を没収され、宇佐家にかつての姿を見ることはできなくなった。
わたしにはこの歴史報告書以外は何もないが、これを伝えることがわたしの使命だったのかもしれない。