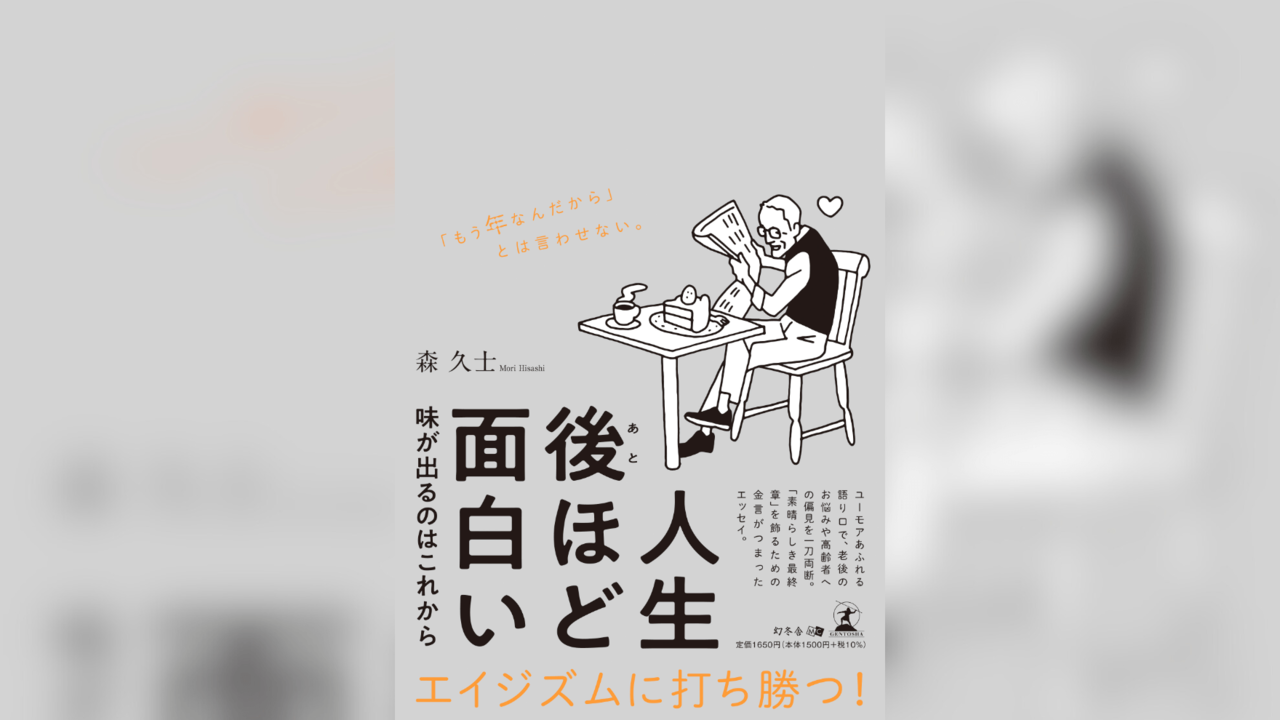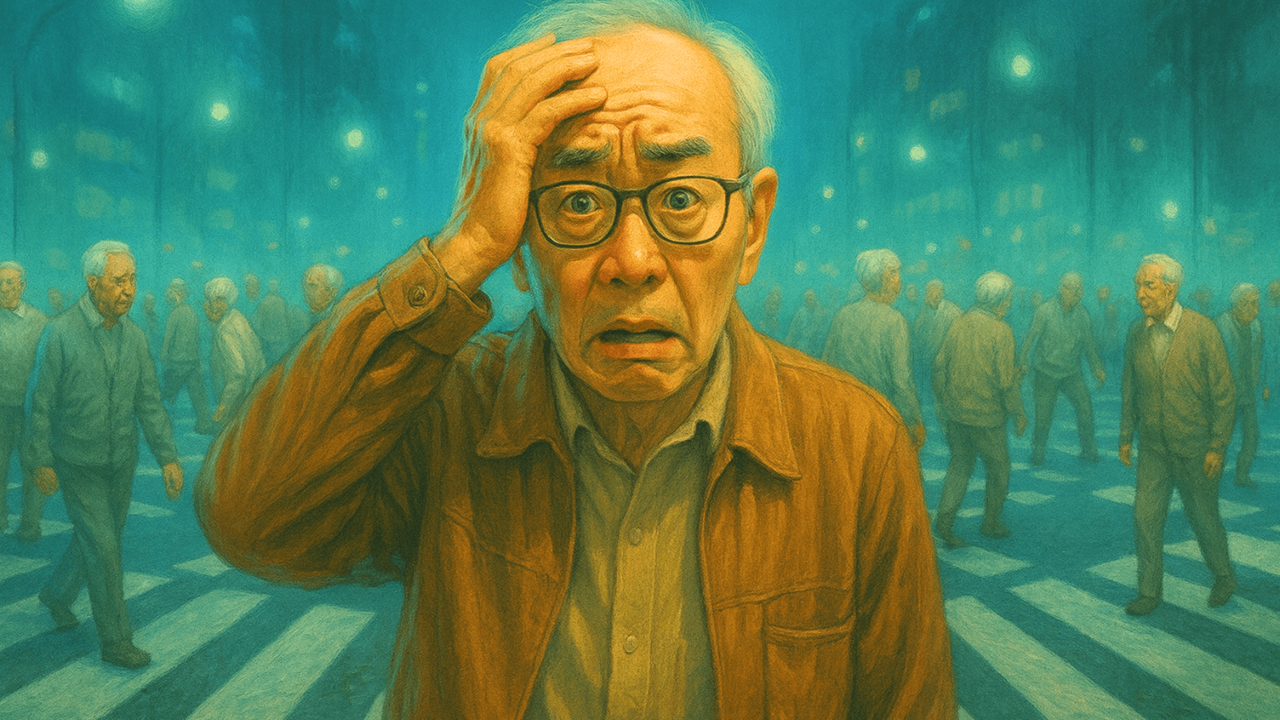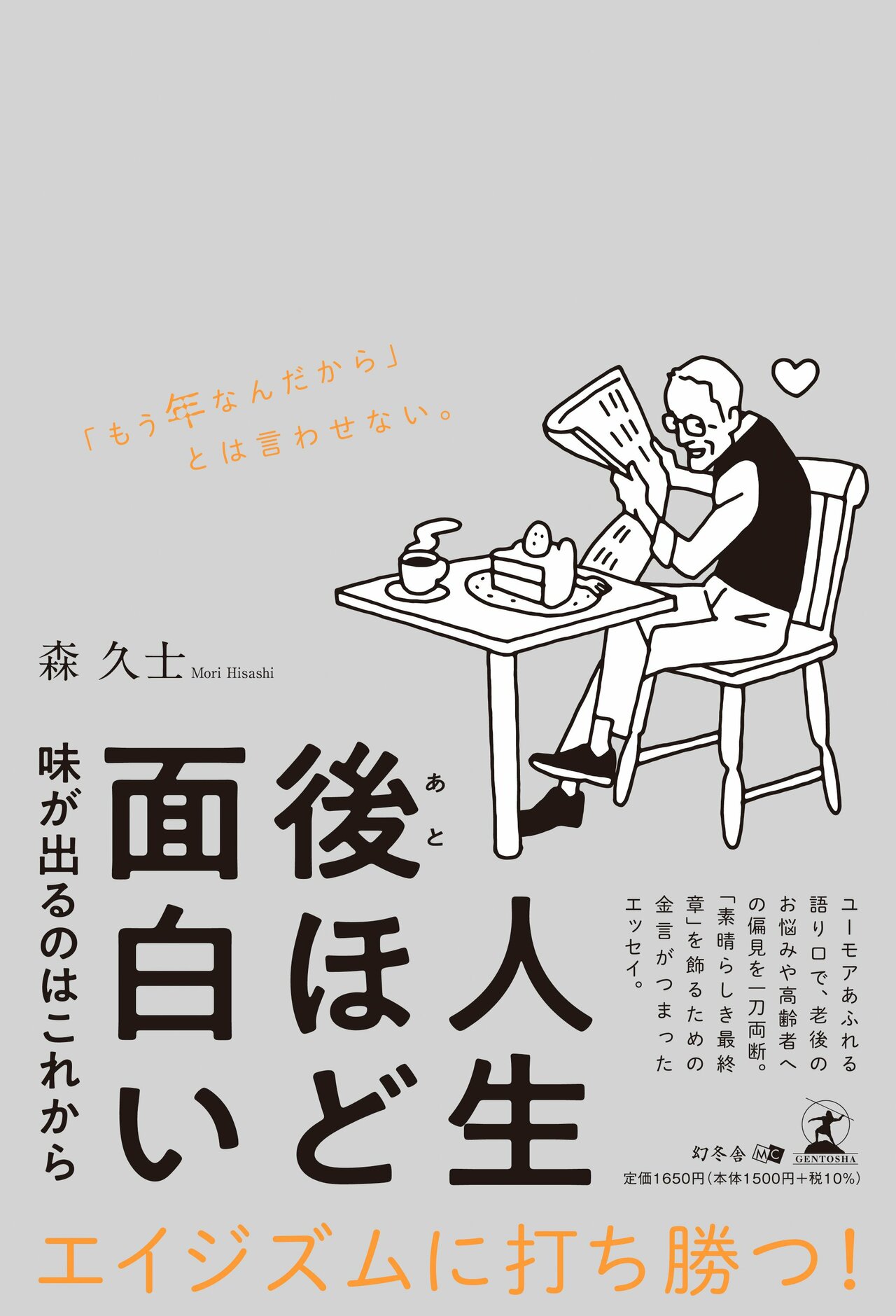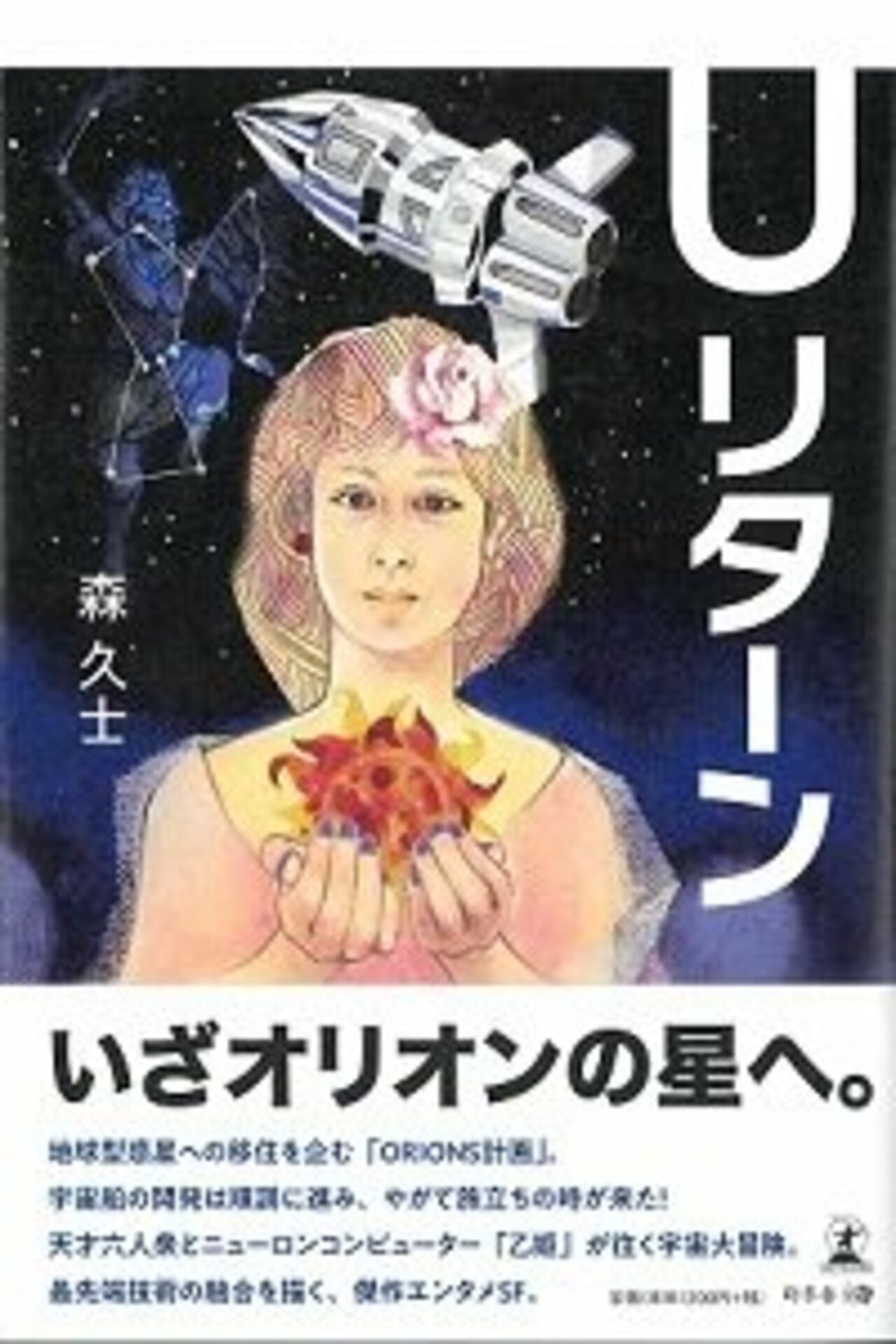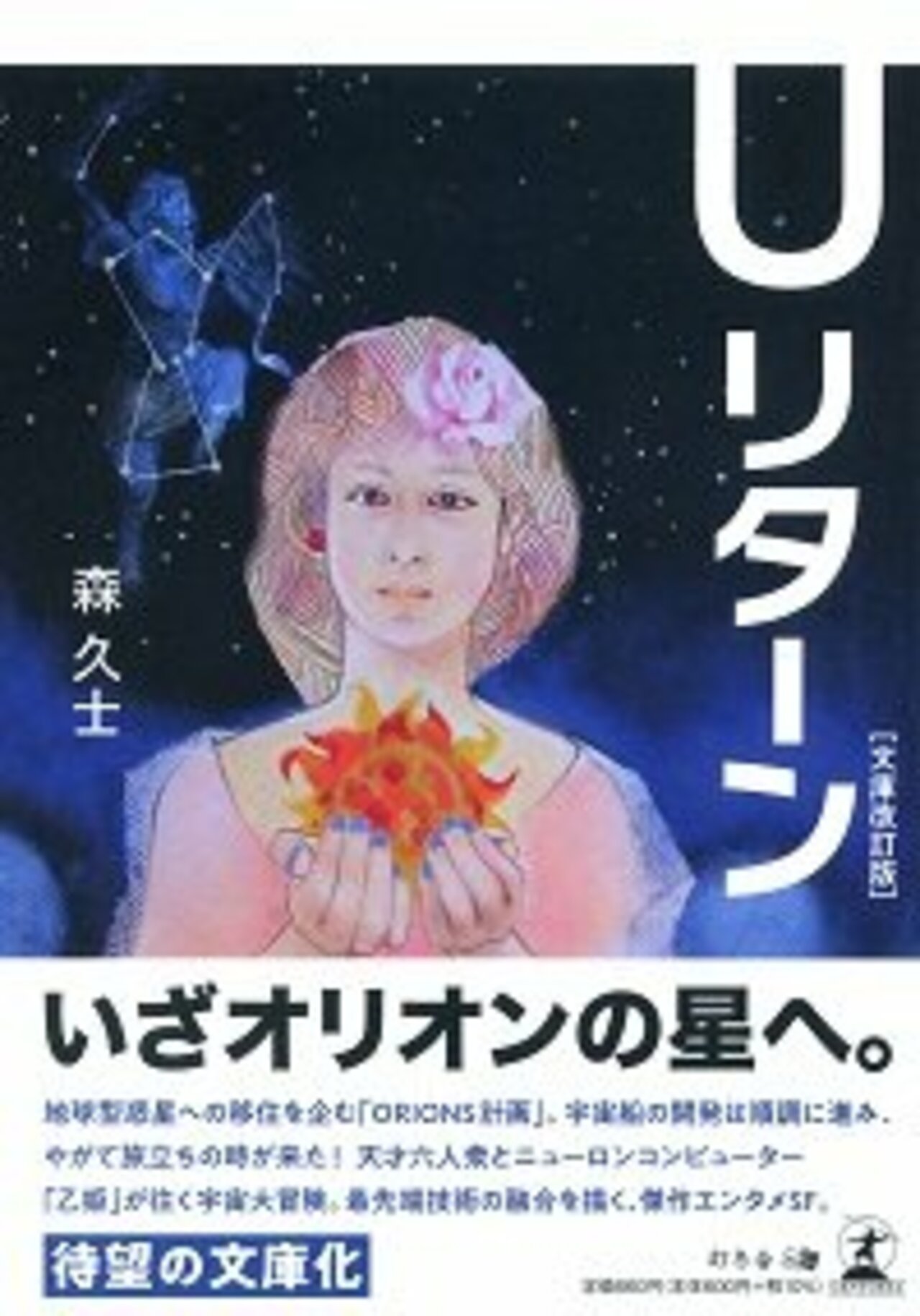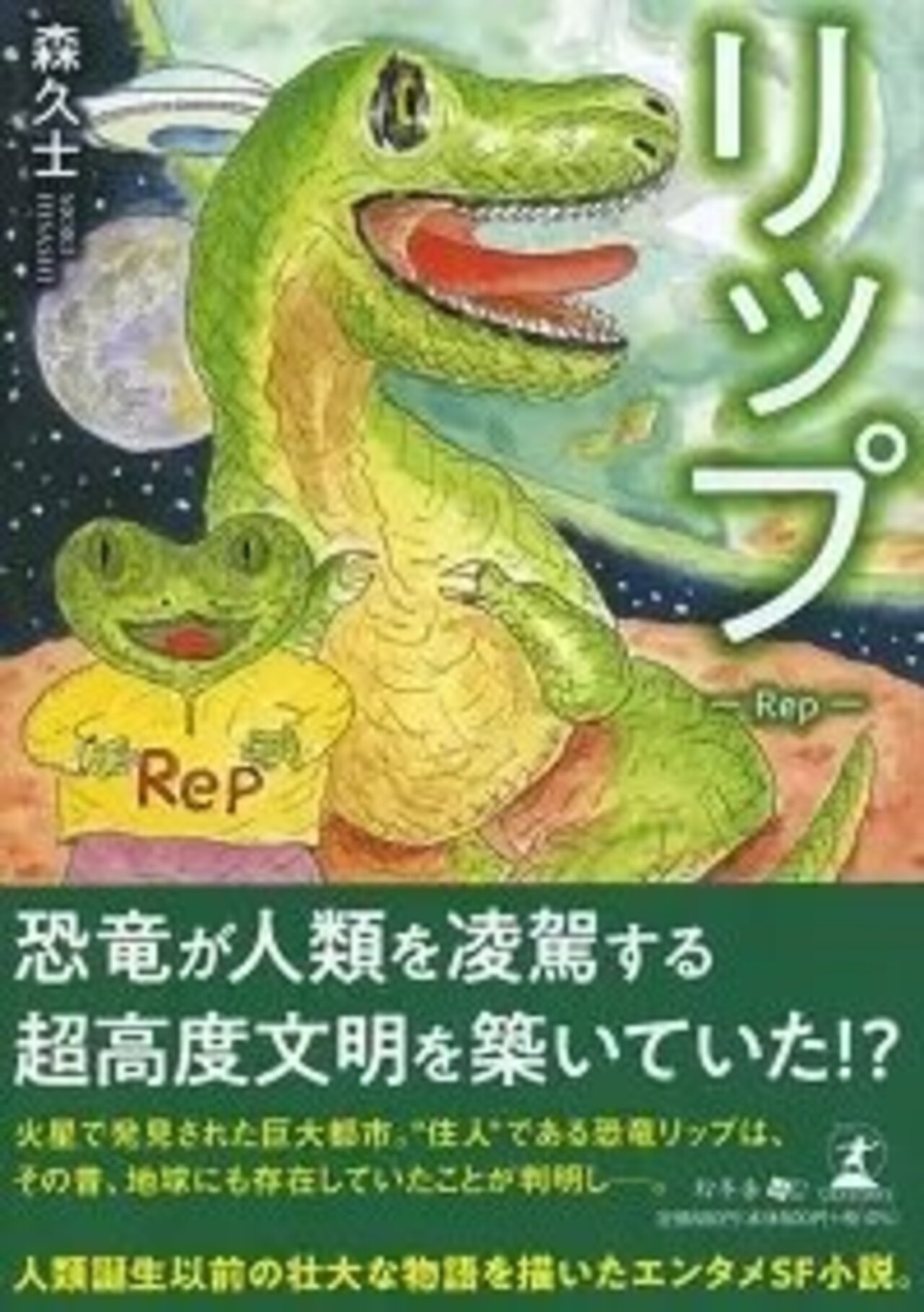【前回の記事を読む】20世紀最後の大晦日前日、幼なじみの住職のために寺に集まった真紀夫たち。しかし除夜の鐘をどう撞けばいいか分からなかった
第1章 人生後になるほど面白く
徳久が「除夜の鐘のことはいいとして、お前たちもうじき定年だよな」と話を変える。
真紀夫が「もう59歳だな、残りは後1年だよ。定年延長で65までは働けるが、管理職から特別職に格下げで週4日で残業なしだからな。給料も今の半分以下になるから続けるかどうか思案中だよ。女房は当然働きに行くものと思っているがな」と迷いを言うと、
信二が「うちも一緒や。女房はどうも俺が家にいたら困るような言い方するんだ。老後の資金が心配だからまだ当分働いてくれなきゃって。俺は市民農園借りて畑をやりたいと思っているのだが、この前シルバー人材センターのパンフレットがテーブルの上にそれとなく置いてあるのには参ったよ。賢、お前のところはどうだ」
「俺は元々出世はしないように現場をやってきたから、今までどおり身体が続く限り働ける。現場は人手不足で俺なんか貴重品だから、定年の話などまったく出てこないから何の心配もない」
信二が「賢ちゃんは、昔からちょっと変わり者だからな、いつも社長と喧嘩していたみたいだな。それで出世できなかったでないの」と冷やかす。
賢治は「出来なかったと言ったら語弊があるぞ(笑)俺は偉そうなやつがいると逆らいたくなる個性があると言ってくれ」と言い返す。
「はははは、まあいずれにしろ人生も残り少なくなったな、俺は死ぬまで坊主やるしかない。昔は坊主丸儲けなんて言ったが今では寺の維持をするだけで一杯一杯だよ。貧乏寺でも、無くなれば地域の人が困るからこのままやるしかない。坊主以外には何も出来ないしな」と、徳久が頭を左手でくるくるとなでる。六十肩で右手は頭にも届かない状況である。
生まれてから20歳頃までは出会いと勉学の時代ですね。言葉や文字、社会のルールや人格の形成などの基本的なことを、そして遊びや友人作り、社会に出てからの働き方など忙しく人生出港の準備であった。
20歳から40歳頃までは、人生の創成期ですね。仕事に就き技術を身に付け人脈も出来社会に貢献出来るようになり、結婚や子育てなど社会での中心的役割が始まる年齢で、長い人生の内で最も充実して希望が持てる時でしたね。