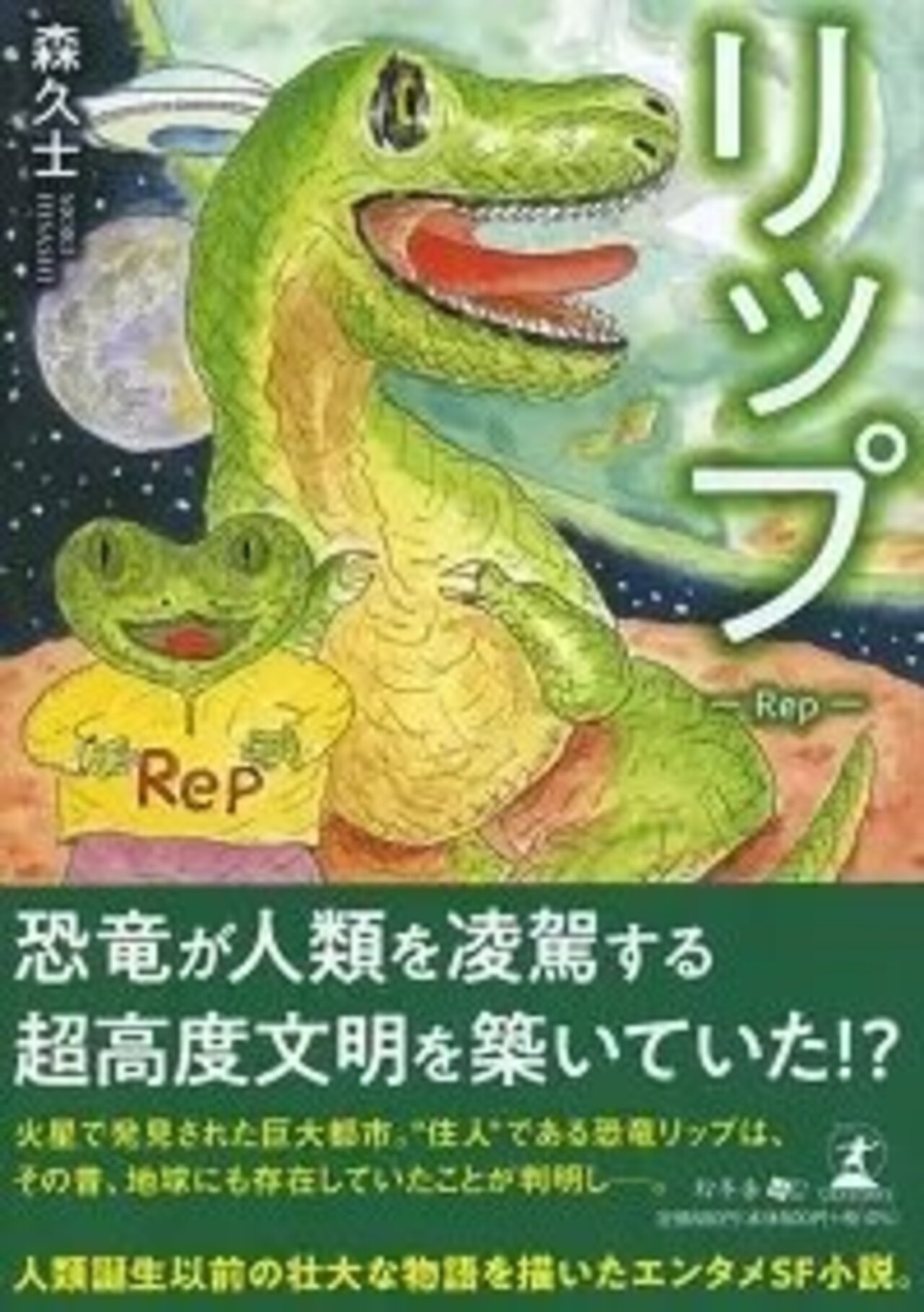【前回の記事を読む】人生100年時代の幕開け――人生後ほど面白く、味が出るのはこれからが本番
第1章 人生後になるほど面白く
20世紀最後の12月31日、同級生が除夜の鐘撞きに集まった。天心寺の住職徳久から「六十肩になってしまい除夜の鐘が撞けないから手伝ってくれないか」と助けが入る。
何代にも亘る檀家であるので真紀夫は「それはいかんね。仲間を連れて出かけるよ。了解了解」と電話で軽く約束をする。
真紀夫は「俺ももうじき定年やな、ぼちぼち町内の行事の手伝いを覚えなくては」と思い住職の頼みを聞いて同学年の連れに連絡を入れる。
「信くん、どうだ、元気しているか?」
「あー、まあぼちぼちってところかな。どうした珍しく電話なんかしてきて」
「住職の徳久に頼まれて、年越しの除夜の鐘を撞いてくれと言われたのだが、付き合ってくれないか」
「そりゃあ、どうせ紅白が終わったらいつものように神社とお寺にお参りに行くつもりだからいいけど。住職どうかしたのか」
「住職が六十肩になって除夜の鐘が撞けないと言ってきたんだ。そこで、何人か集めて鐘撞きやってくれとのことだ。信二やってくれるか」と真紀夫。
「了解。どうせ檀家だし鐘撞きも面白そうだから付き合うよ。そうだ賢のところも墓あったよな、俺から電話してみるわ」
「そうか、人数が多い方がありがたい、今年の除夜は寒いと天気予報で言っていたからな、じゃあ頼むわ」と真紀夫は電話を切る。
住職と真紀夫、信二と賢治は幼なじみで、子供の頃は住職と寺の中を走り回り、先代からよく怒られたものであった。そして、住職の母親のお庫裏さんからはいつも菓子をもらっては慰められていた。
そんなことで、住職からの頼みを断れない3人は寺に出かけることになった。
お参りすることはあっても除夜の鐘撞きは初めてのこと、作法も何もわからない。ただ108回突くことぐらいである。
毎年恒例の行事になっている30日の餅つきの後、3人は町内の喫茶店でお茶を飲みながら、賢治が「真紀夫、お前除夜の鐘を撞いたことあるか? 俺はガキの頃いたずらで鐘を撞いたら徳久の親父にひどく怒られたことしか覚えていないが」と不安を漏らす。
「俺も一度も撞いたことない。あんなもの紐引っ張ってゴンとやればいいだけじゃあないの」と真紀夫が軽く答えるが、信二も少し心配そうに「俺もないが、何か作法があるんじゃあないの」というのを聞いて、賢治が「だよな、何かありそうだな。住職に聞きに行くか」とみんなで出かけることになった。
そして3人は昼から墓の掃除をしがてら寺に出かけた。久しぶりに4人の元悪童の集まりである。