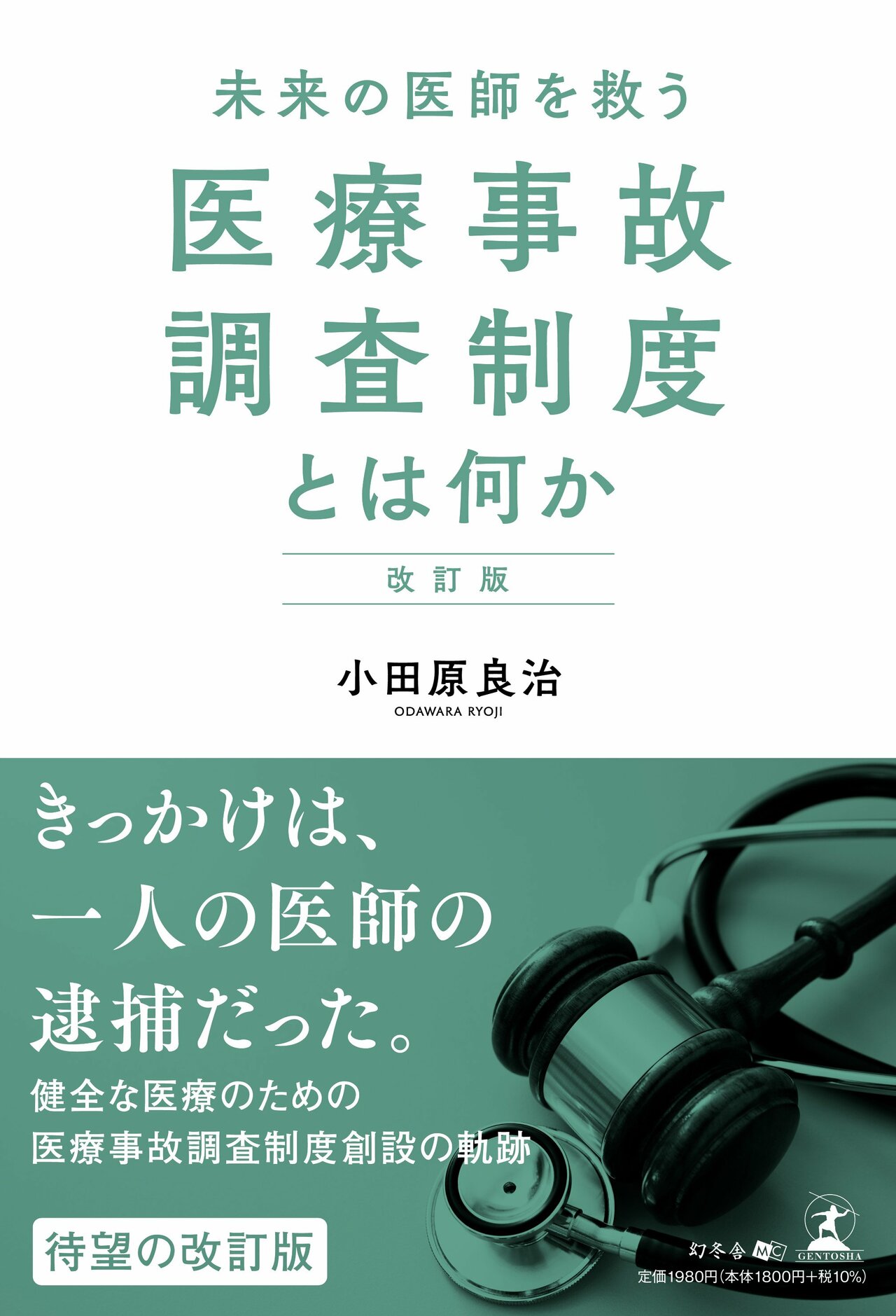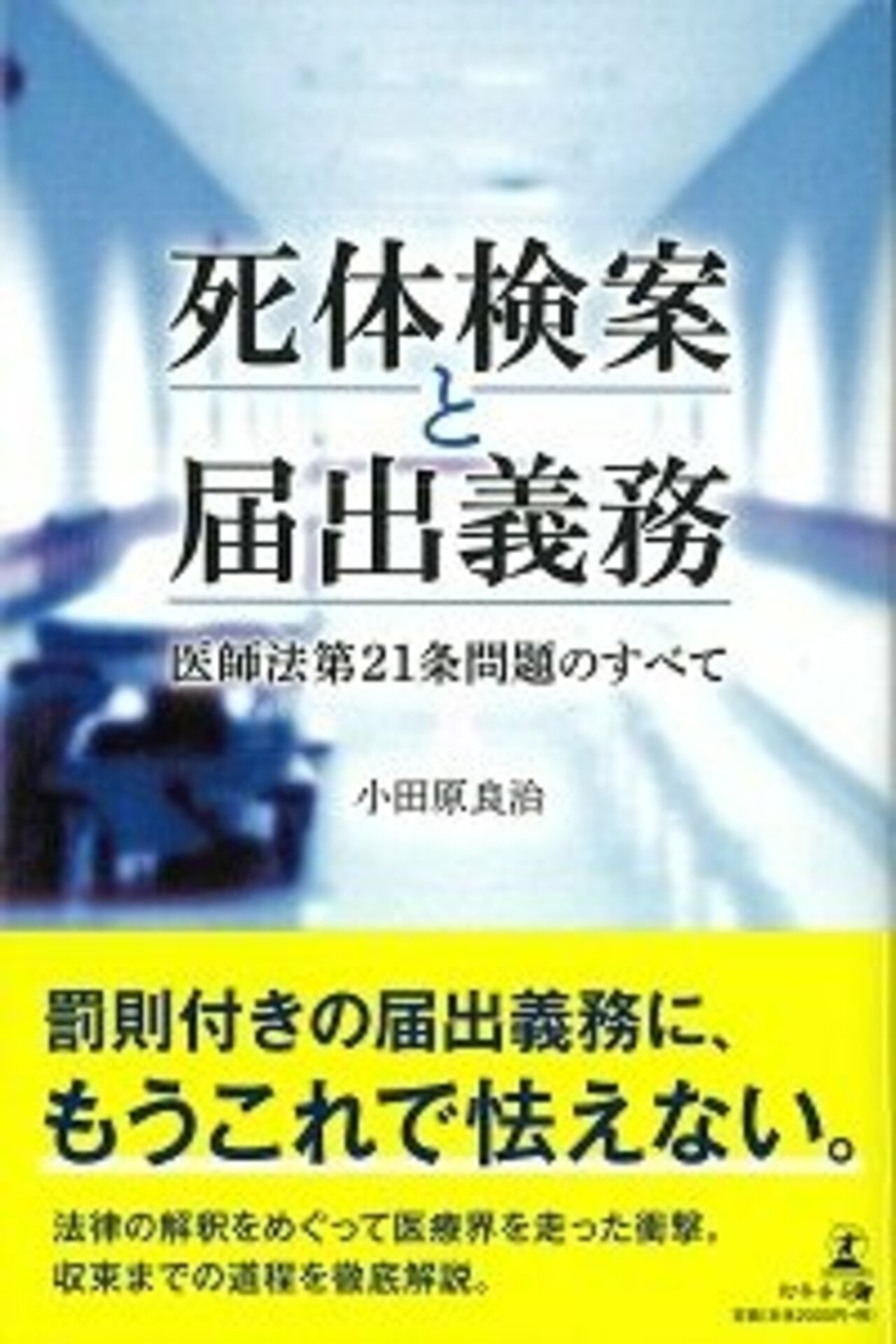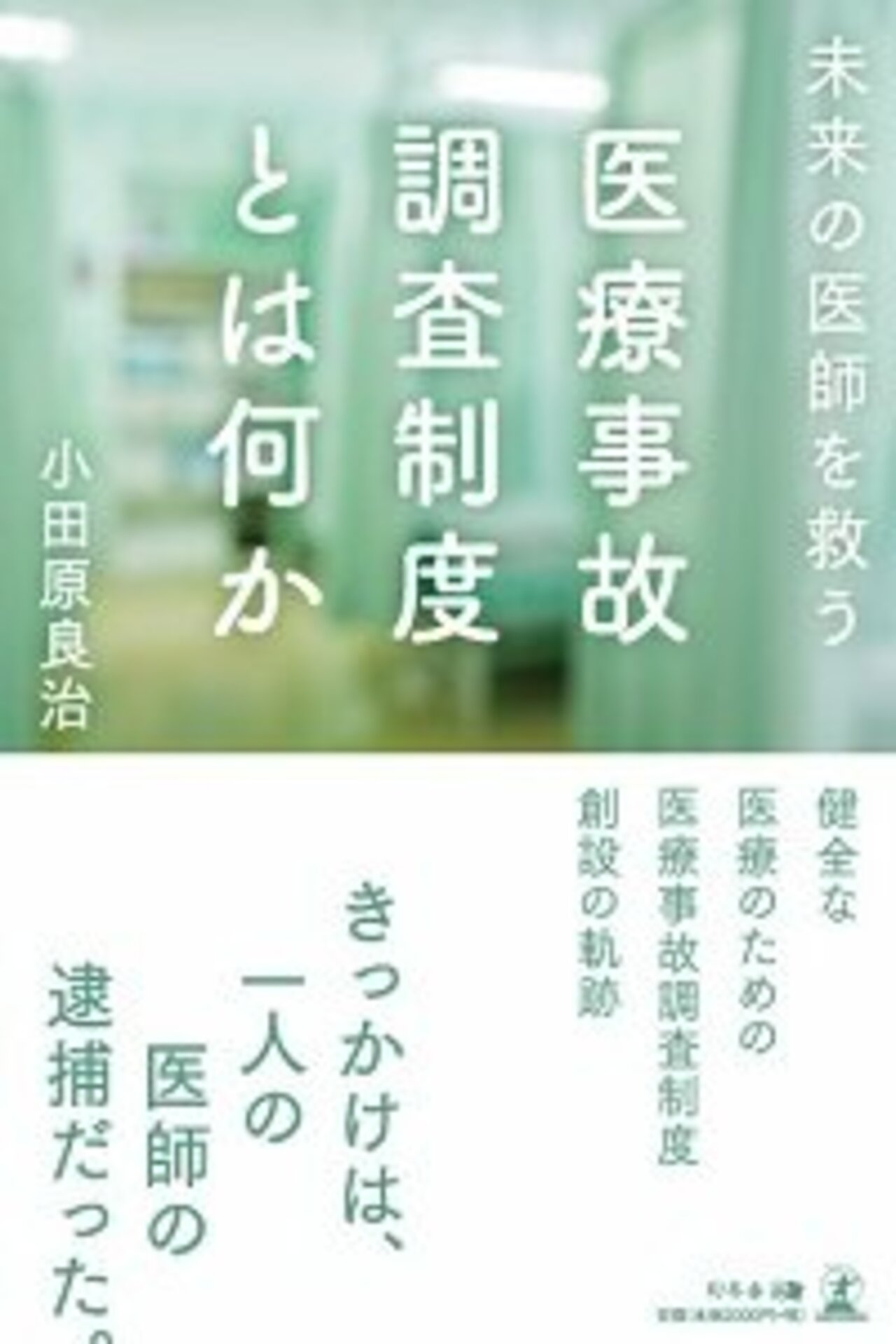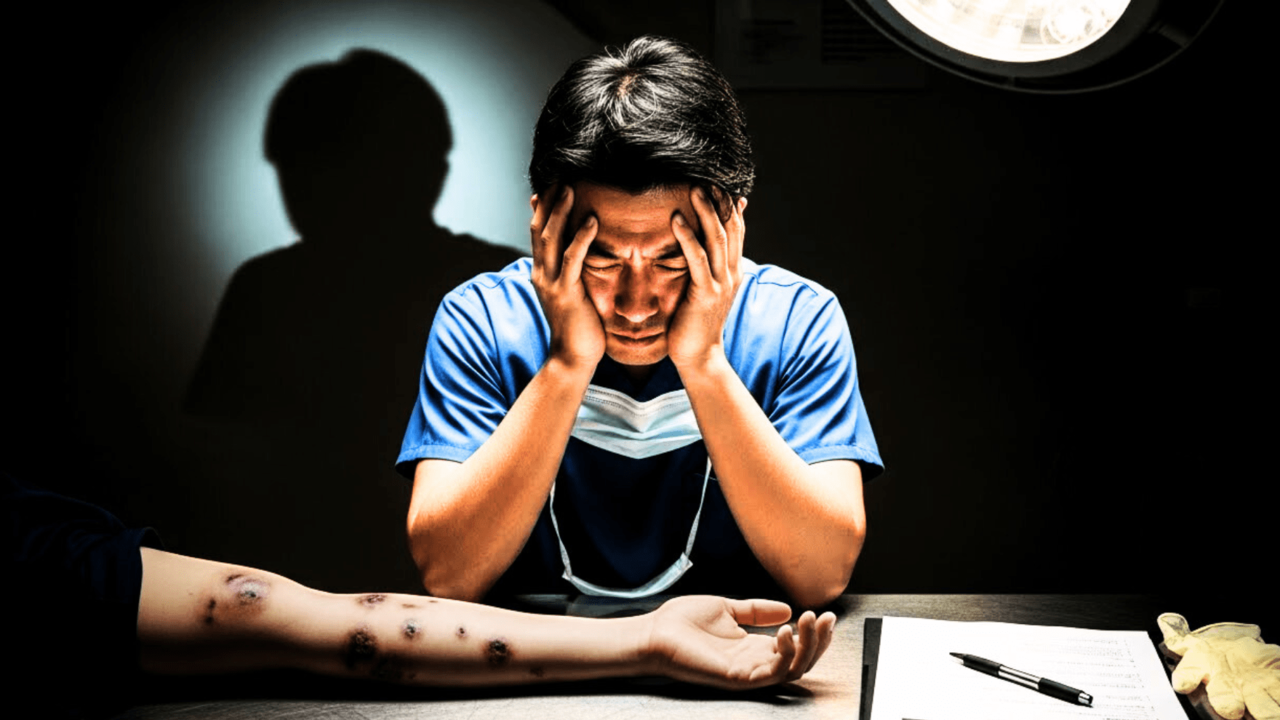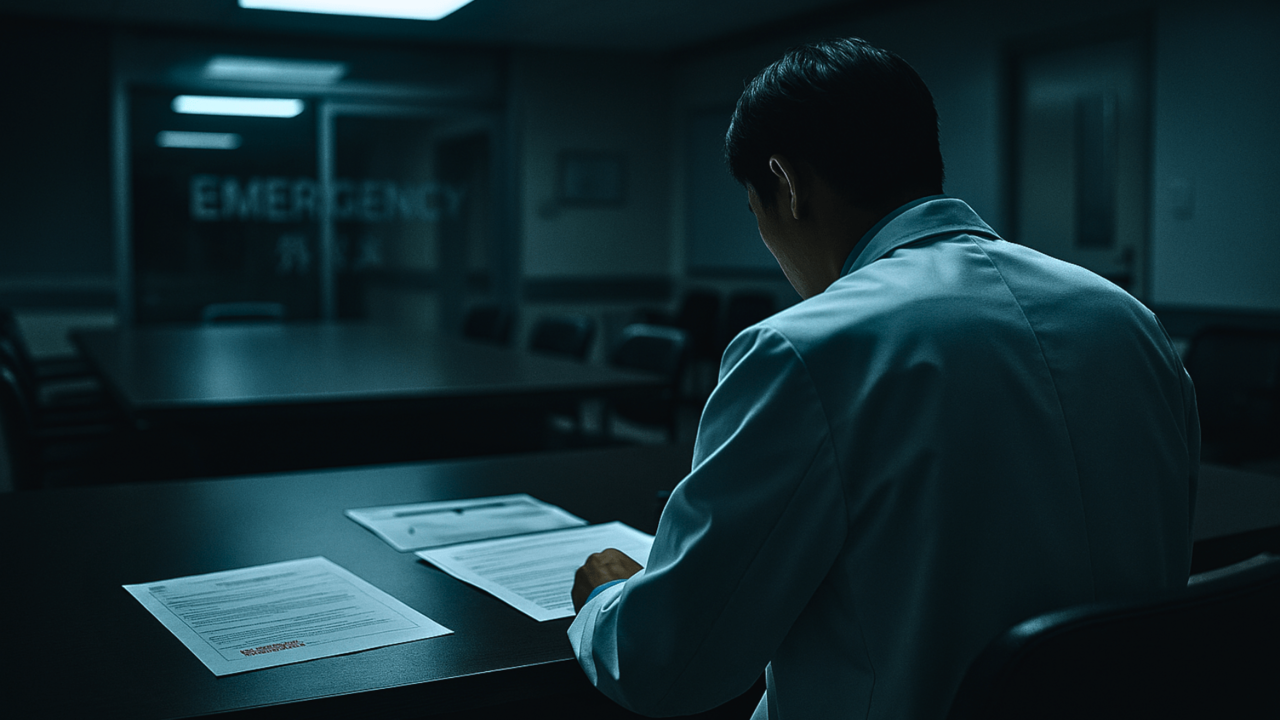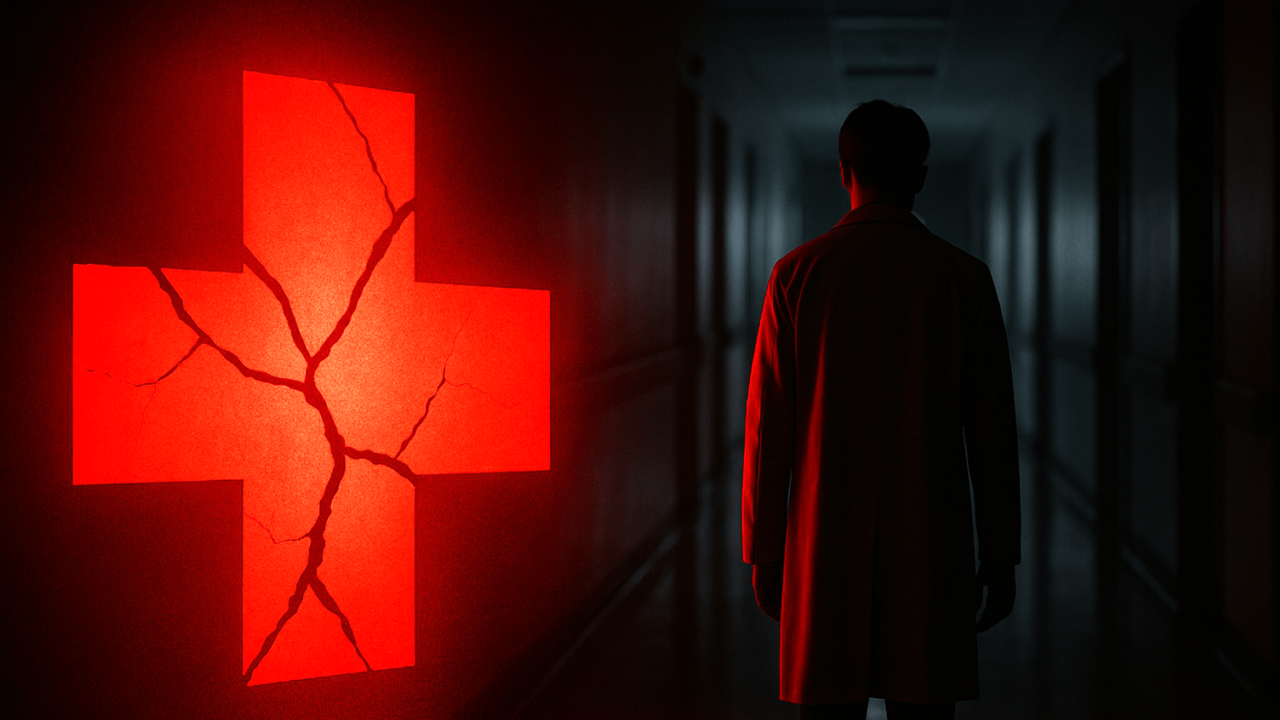(3)異状死体の届出義務に関わる判例
医師法第21条は、もともと、警察捜査への協力規定であり、この法律が問題となることもなかったので、判例も少ない。
旧法時代の判例としては、大正7年大審院判決があるが、現在の条文となってからの判決として著名なものは昭和44年東京地裁八王子支部判決、東京都立広尾病院事件判決、福島県立大野病院事件判決ぐらいである。
医師法第21条の解釈を確定させたのは、東京都立広尾病院事件最高裁判決である。東京都立広尾病院事件最高裁判決は、医師法第21条の解釈を確定させた重要な判決なので(5)項で詳述したい。
(4)異状死と異状死体
法医学会「異状死ガイドライン」は元来、臓器移植推進のためにつくられたガイドラインであるという。同「異状死」ガイドラインは、「病気になり診療をうけつつ、診断されているその病気で死亡することが『ふつうの死』であり、これ以外は『異状死』」と定義している。
この「異状死」に該当するものとして、【1】外因による死亡(診療の有無、診療の期間を問わない)、【2】外因による傷害の続発症、あるいは後遺障害による死亡、【3】前記【1】または【2】の疑いがあるもの、【4】診療行為に関連した予期しない死亡、およびその疑いがあるものを挙げている。極めて広範囲のものが「異状死」に該当する。
しかし、これは法医学会という一学会の見解に過ぎない。「異状死」とは、「異常な経過をたどった『死』」であり、「異常な死体の状態」を表したものではない。一方、「異状死体」とは、「死体」の異常な状態を表したものであり、「異状」の文字がそのことを明確に示している。
昭和44年東京地裁八王子支部判決も、医師法第21条にいう死体の異状とは、死因についての「病理学的異状」ではなく、死体に関する「法医学的異状」であると述べている。