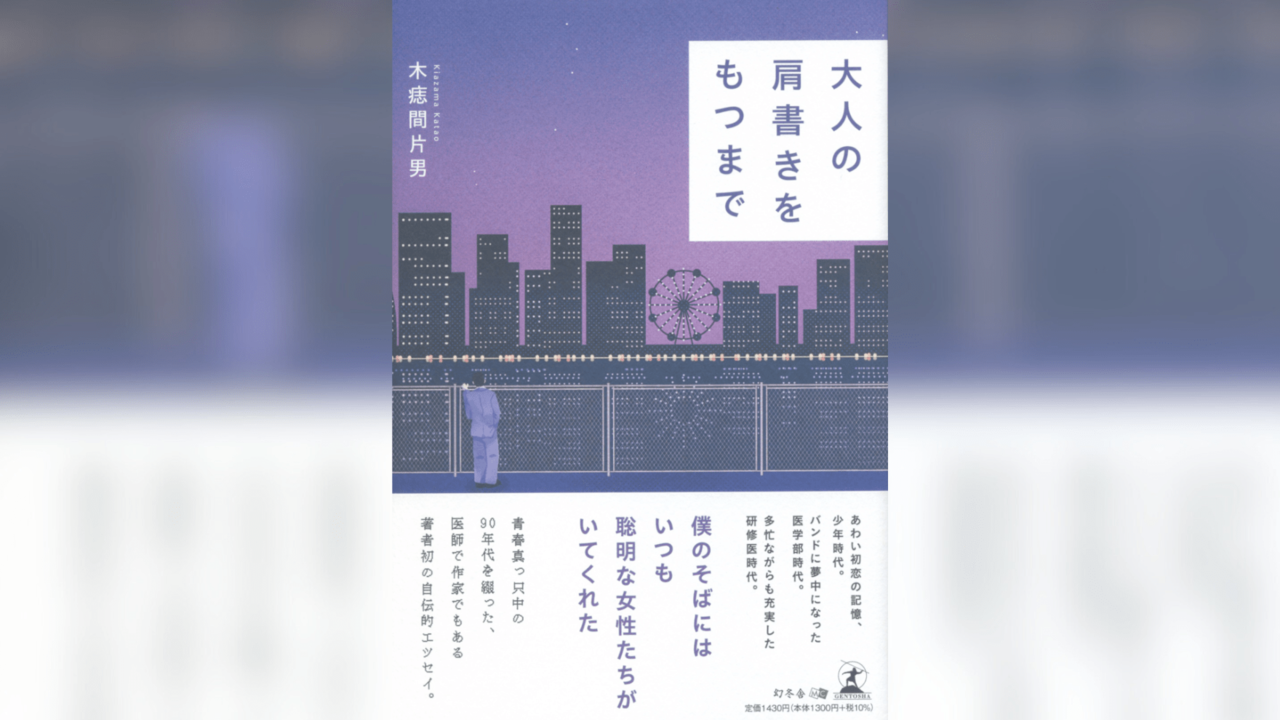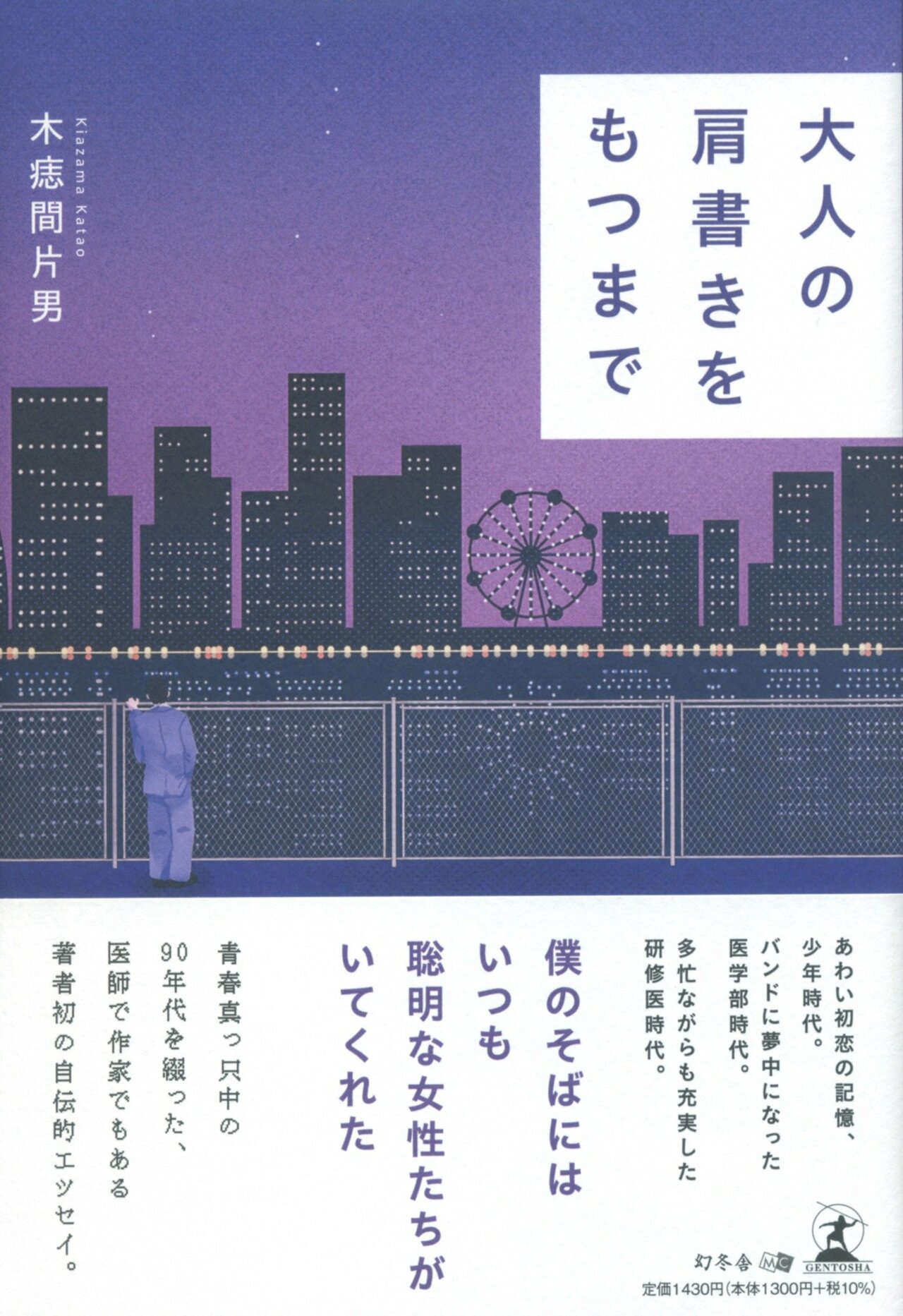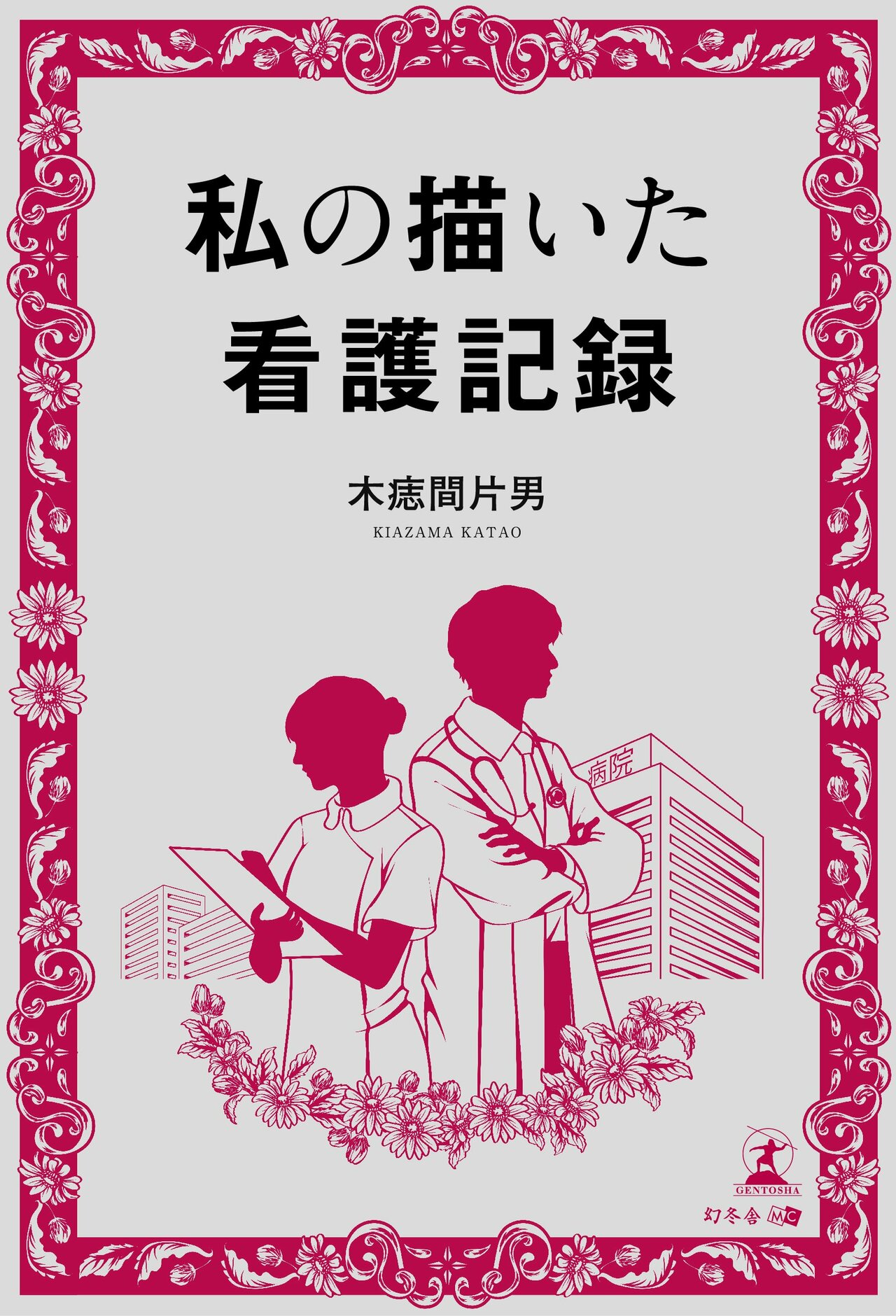【前回の記事を読む】こんな初恋を経験した僕だったが、思い起こせば、それ以降もたくさんの人と出会ってきた。そして、その先には別れがあった
第1章 中学・高校編
きっかけはインドア派芸術女子 「放課後も一緒にいたいから同じ塾に通って」
僕にとっての幼いころの夢はいったい何だったろうか?
野球の選手でも宇宙飛行士でもない。もちろん医者でもなかった。古い記憶をたどってみると、小学校の卒業文集に“建築士”と書いた記憶がある。あえていうならちょっと図工が好きだったから、その場で思い付いた職種を書いたのだろう。
誰にでもあった幼いころの夢……、あるのが当たり前とされた素敵な夢……、でも僕にはなかった。
こもりがちな中学当時の僕は、家で音楽を聴きながらマンガを読むか、たまにアニメ映画を観に行くか、くらいしかやる気がしなかった。それは、小学校時代の“習い事”において、何をやっても平均か、それ以下という自分の能力に早々と気付いてしまったからだ。
ピアノはバイエル止まり、柔道は白帯から脱出できず、習字なんてものはすぐ辞めた。少し上達したのがそろばんだったが、それもどんなにがんばっても2級の壁を越えられなかった。
勉強に運動、図工に音楽、どれをとっても特に秀(ひい)でたものはなかった。思春期のころの僕は、自分のことを「暗くてつまらないヤツ」としか認識できなかった。きっとそれが、周りから見た己の印象だと思っていた。
どんな中学生でも暇に任せて嗜んでいた趣味(とは、ぜんぜん言えないけれど)、すなわち、音楽やマンガやアニメにもっと芸術的エッセンスを加えることがカッコいいと思ったのは、サブカル的といおうか、オタク系といおうか、深いインドア趣味を有していたクラスメイトの女子との出会いがきっかけだった。
その子は、はっきり言って地味だった。背が高くて発育は良かったけれど、おかっぱ頭にメガネ、無口なほうだけれどときどきボソッとトリッキーなことを言う。学業成績は、けっして悪くない。
クラスに一人くらいいたであろう、質素で控え目だけれど、そのキテレツさとマニアックさによって、けっこう目立つという子が。大川朋子(おおかわともこ)は、そんなタイプだった。
彼女の席次が僕の前だった時期があり、そこで僕らはけっこう気が合った。きっかけは、彼女が夢中で読んでいたマンガ本を借りたからだ。その本は、小山田いくの『すくらっぷ・ブック』(秋田書店)だった。知っている人はほとんどいないと思うが、信州小諸市を舞台にした中学の学園マンガである。
出会い、恋愛、友情、そして、時にはケンカなんかが描かれていて、恥ずかしいほどの純度 100%の青春群像ものだ。自分とは真逆な羨(うらや)ましいほど充実した学園生活が描かれていて、僕も夢中になって読んだ。借りては読み、返してはまた借りるを繰り返すやり取りのなか、感想を述べ合うことで二人の距離は縮まった。