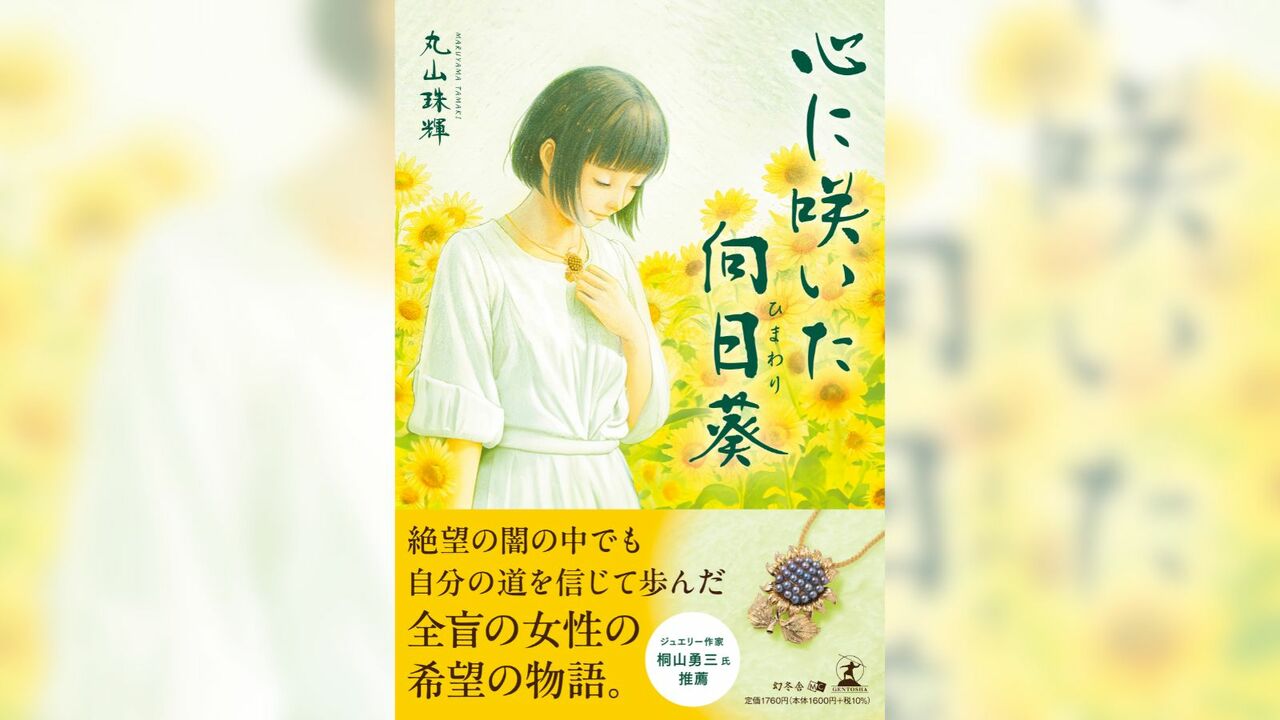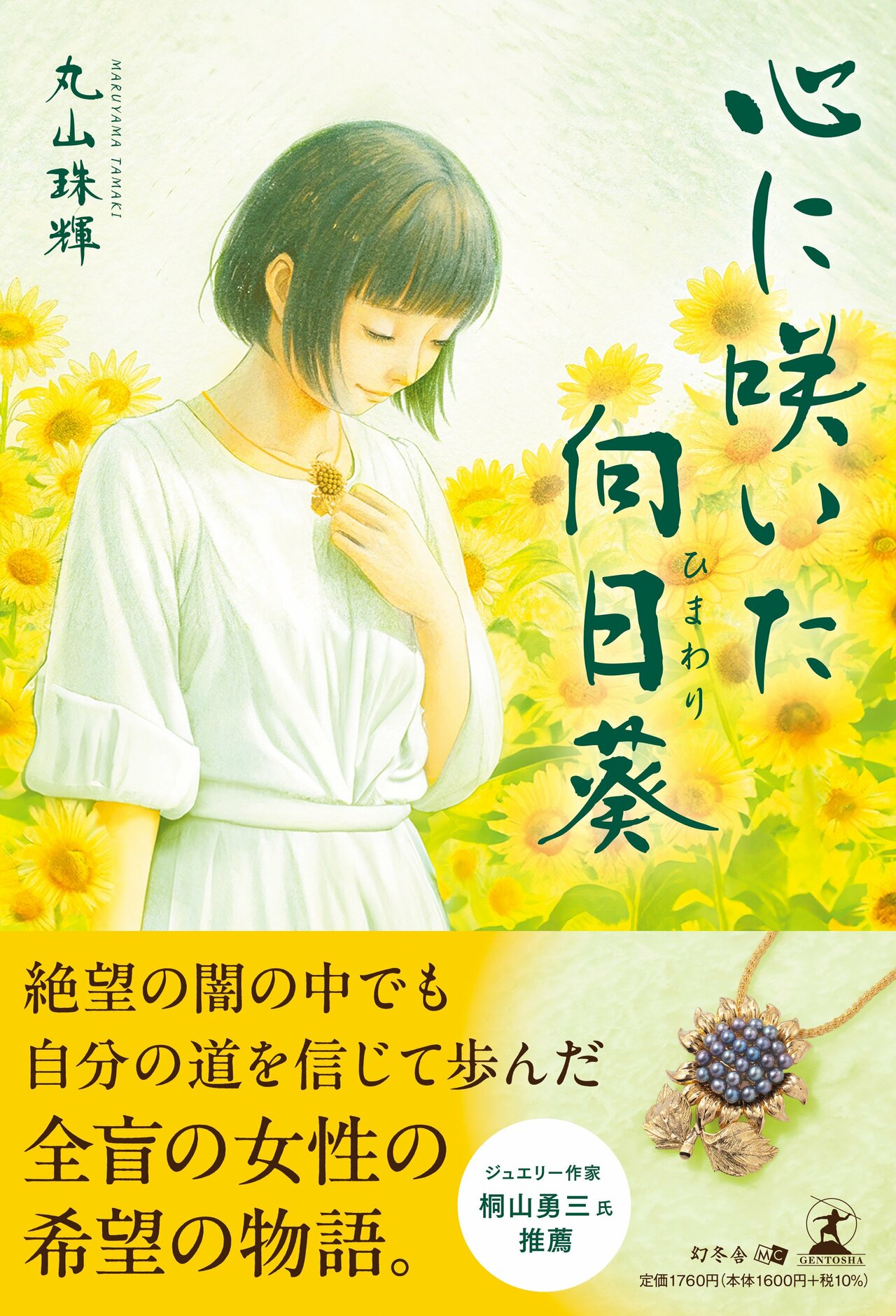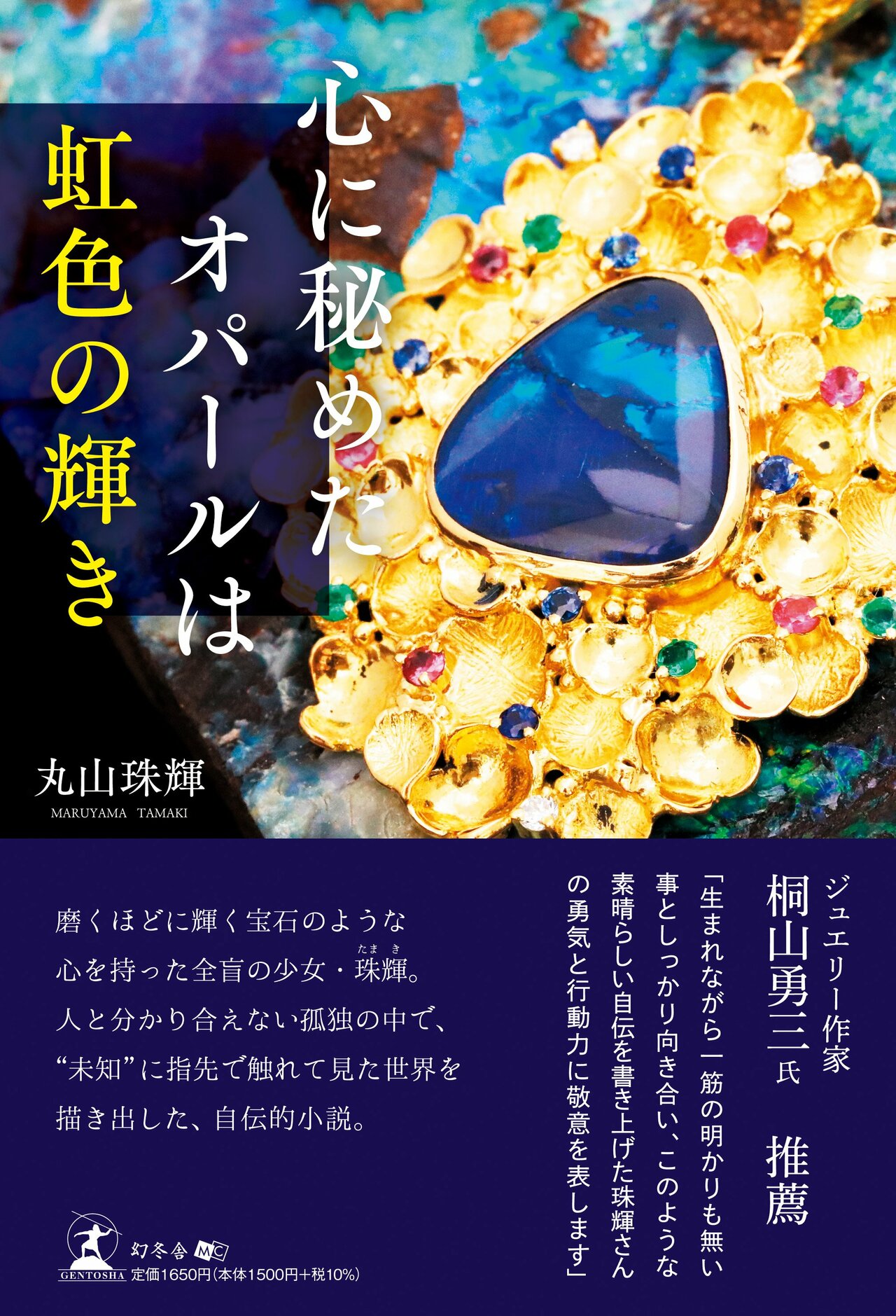【前回の記事を読む】寺の前に捨てられていたのは"生まれたばかりの赤ん坊"だった。紙切れには「許しておくれ」と書かれており…
第五章 謙志郎の生い立ちに励まされる珠輝
三
子どもの世話が一旦落ち着いたところで朋来が、
「二人とも聞いてくれ。赤ん坊は今から警察かお役所に連れていって、孤児院にでも入れてもらう。いいな」
すると、
「お上人、赤ん坊をこのお寺で育てることはできないのですか」三吉が言うと、
「そうですよ。この子は今日からおいらたちの弟ではいけないんですか」と千太が言った。
「赤ん坊を引き取るというのは簡単なことじゃないんだ。第一、お乳はどうするんだ」
朋来にそこまで言われると、二人は返す言葉がなかった。
「お上人、もしもお役所がよいと言ってくれたなら、このあたしにも一肌脱がせてくださいませんか。できることならこの子の道筋が決まるまで、面倒見たいんですよ」
「お富さんにそこまで言ってもらえるのは嬉しいんですが、とんでもない迷惑をかけることになりますよ」
「そんなことは承知の上ですよ。あたしだって二人の子どもを育てたんですよ。店が忙しいときには小僧さんをお借りしますけど……」
「皆忙しくなるんだぞ」
「かまいません。おいら弟ができてうれしいからじゃんじゃん働きます」
千太の言葉に皆の顔がほころんだ。その後、役所で朋来が謙志郎の親権者として認められ、朋来は謙志郎に「寺坂」という名字を付けた。子どもの親がいつの日か我が子に会いたくなった際、坂の上にある寺が思い出せるようにとの気遣いからだった。
それからの謙志郎の面倒はほとんどお富さんが見てくれた。どこどこの夫人が子どもを産んだと聞けば、なりふりかまわず頼み込み、もらい乳もいとわなかった。謙志郎の一歳の誕生日祝い膳もお富さんが先頭に立って調えてくれた。
近所の人々からの差し入れもあり、小僧たちは普段口にできないご馳走(ちそう)や甘い物に大満足だった。二人の小僧も兄さんよろしく謙志郎をかわいがった。
貧しい寺ではあったが、取り巻く人々の心は温かい愛情に満ちていた。お陰で、謙志郎は風邪一つひくことなくすくすくと育った。
しかし、謙志郎が満四歳の誕生日を迎えると間もなく、彼はこの寺と温かい人から離れ、幼くして世の中という大海に投げ出されることになった。