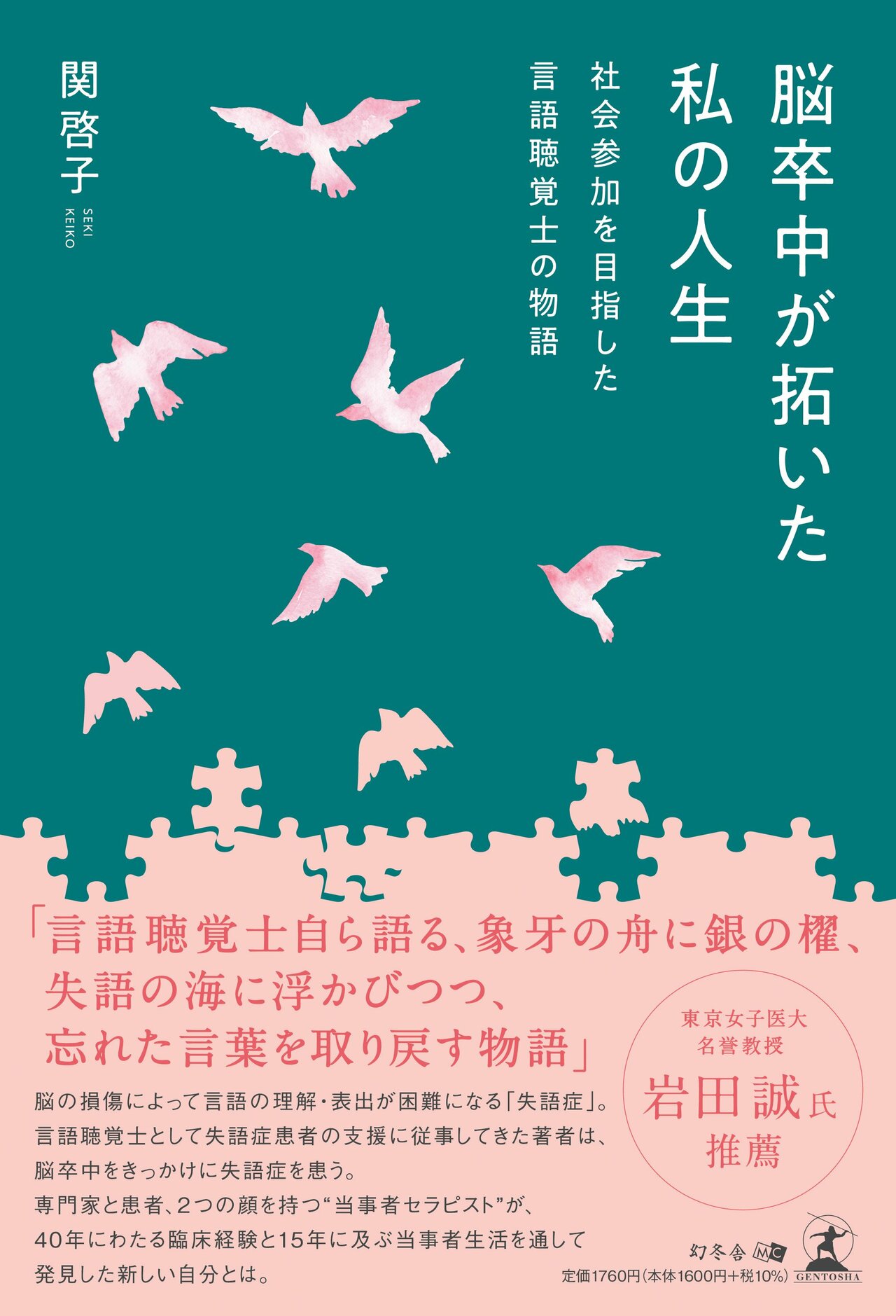その不思議な巡り合わせの妙に感動する思いです。私の生活は毎朝の論文抄読会を軸に回り、時にはひとつの論文とその解釈を巡りI先生と長時間にわたり熱くなって激論を交わすこともありました。
また、先生と半分冷戦状態で英論文を執筆したこともあり、そのたびに思わず掘ってしまった自分の「論理の穴」を先生に指摘され、自らの浅はかさに恥じ入り、頭を冷やすために自室に籠って我が論文をじっと眺め、その後長時間にわたり推敲に専念したものでした。そのような折に、私は目標を設定することで難関を乗り切ることができました。
議論が膠着状態に陥った時、私は熱くなると、「来週の〜曜までに仕上げてきます!」などと完成目標の期日を公言するようなことがありました。それまでに尻尾を掴まれないよう十分注意深く考え、一気に論文を完成させてI先生を驚かせたものです。
さらに、独力でデータを分析し考察を進め、短期間のうちにマイナーな国際誌に論文を投稿し受理されたこともありました。そうしたやり取りが楽しくて私は夢中でI先生との「意地の張り合いの毎日」を過ごしました。
このように「小競り合い」を繰り返しながらではありましたが、今振り返るとこの時代は私のST人生のうち最も輝かしく最も充実し、ワクワクしながら日々研究に打ち込んだ熱い時期でした。
(1) マイケル・S ガザニガ著、杉下守弘・関啓子訳『社会的脳』青土社、1987
【イチオシ記事】帰ろうとすると「ダメだ。もう僕の物だ」――キスで唇をふさがれ終電にも間に合わずそのまま…
【注目記事】壊滅的な被害が予想される東京直下型地震。関東大震災以降100年近く、都内では震度6弱以上の地震は発生していないが...