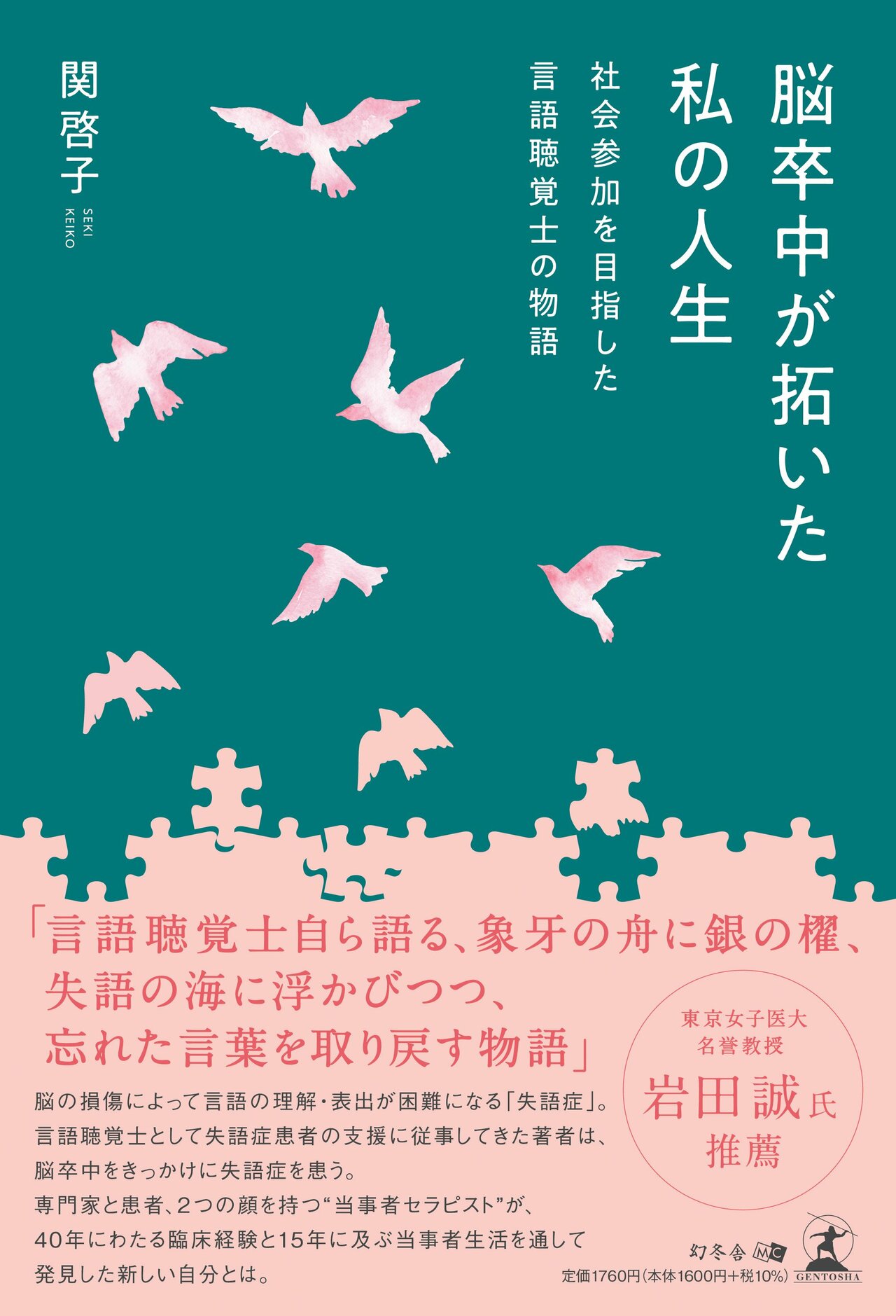【前回記事を読む】限界年齢ギリギリの挑戦! ぶっつけ本番でST養成校に合格し、神経研での研究人生へと進んだ奇跡の記録
第一部 社会に飛び出せ ―数奇な私の人生―
Ⅰ.突き進む「言語」の道
一人前のSTを目指した養成校での修行の日々
そして自分の検索目的に合致しそうな内容のタイトルの論文を探し出せたら、その論文の掲載誌が図書室の蔵書であるかをチェック(その可能性は極めて低い。図書室蔵書なら、掲載誌の書架に行って直接論文に当たることができる)し、所蔵していない場合は論文タイトルと著者名・掲載誌の巻号ページをメモし、図書室司書の担当者にコピー請求を海外に依頼して別刷が届くのを待つ、という途方もない苦労の末論文に対面するという流れでした。論文の到着を待つこと数か月、忘れた頃に別刷が届くという、今思えば非常に効率の悪いアナログ的な文献請求の方法でした。
届いた数編のMITと関連論文を手に入れた私は、これらの原版を検討し、日本語に翻訳するためその言語特質に応じた方法を考案し、本技法の日本語版(MIT-J)(1)を開発することができました。
また、神経研時代には、このMIT日本語版(MIT-J)と並行してもう一つの大きな仕事をしました。
それは、国際的に定評のあるWestern Aphasia Battery(WAB)という英語による失語症検査法の日本語版作製委員として、部門の関係者や国内の同業者とともにこの標準化・開発に関わったことです。
言語検査の開発という性質上難しい内容で、私は夫の任地札幌(後述)でこの仕事に関与したのですが、1984年に日本語版が無事完成し、本邦3番目の失語症検査法として世に出すことができました。
特に、私のライフワークとも言えるMITに関して、新卒の頼りないSTが患者さんとの出会いから始まり、わずか1年で技法を確立し効果を確認し論文化まで達成できたことは、大変思い出深い懐かしい出来事です。
この成果はS先生の基礎的な手ほどきのおかげと言っても過言ではないと思います。この間には悲喜交々いろいろなことがありましたが、先生から事務能力を高く評価され信頼を受け長期にわたり温かく接していただき、自立した一人前の研究者にまで育てていただいたことに今では心から感謝しています。