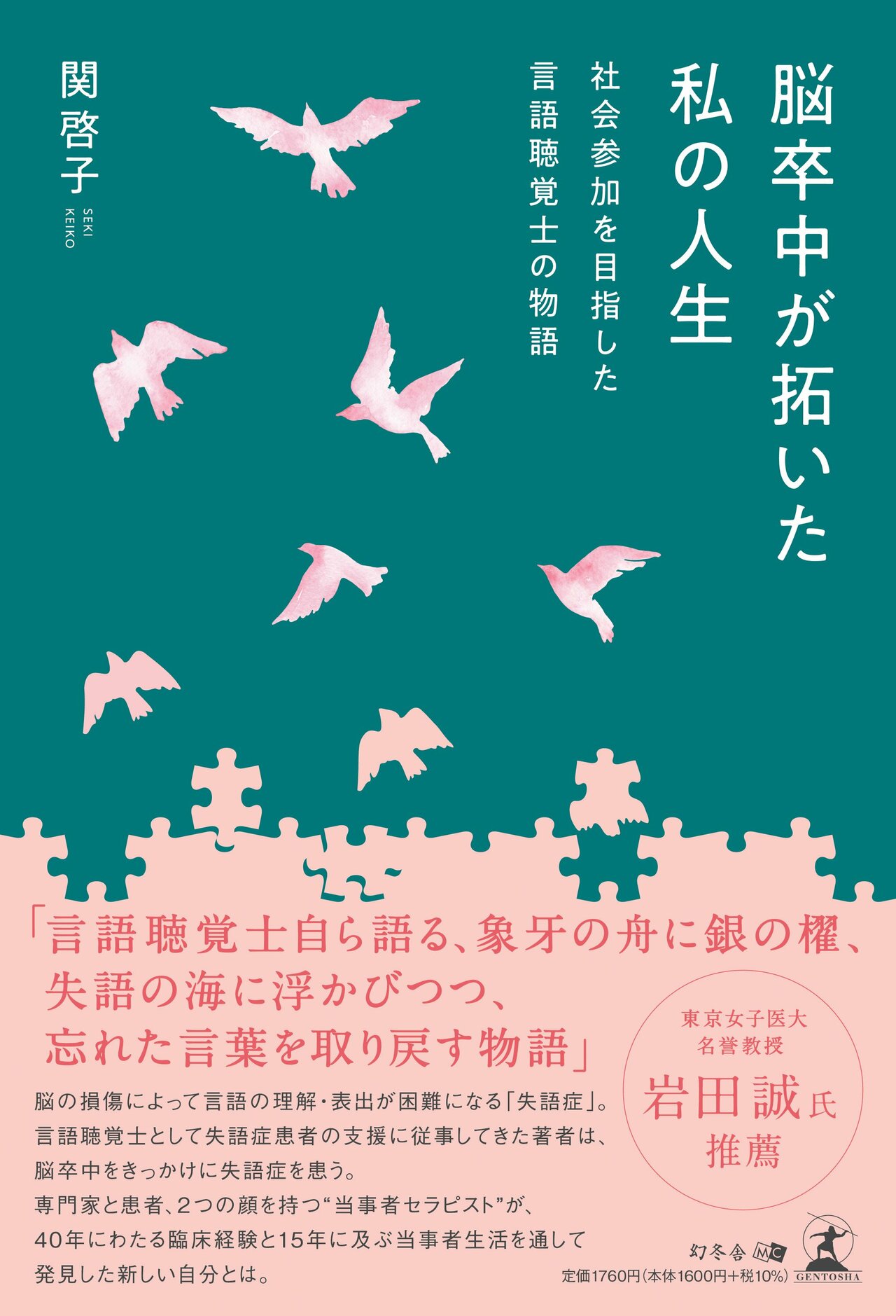【前回記事を読む】失語症患者を支援してきた言語聴覚士。自身も失語症を患い、当事者になった――。単身赴任先で脳卒中に襲われ…
第一部 社会に飛び出せ ―数奇な私の人生―
Ⅰ.突き進む「言語」の道
言語聴覚士を目指して
それから長い年月が経ち、失語症などの高次の認知機能の障害、いわゆる高次脳機能障害の臨床と研究・教育に長年打ち込んできてリハビリの業界内で徐々に名前が知られるようになったその当人が、2009年に脳卒中に襲われたことはかなり衝撃的なニュースとして同業者の間に広まったと聞きます。
この仕事に興味を持ってくださる方の参考になればと思い、私のSTとしての山あり谷ありの数奇な人生と、対象としてきた病気である脳卒中罹患後の思いと生き方をこれからさらに詳しく述べようと思います。かなり長くはなりますが、ご興味おありの方にご一読いただけたら幸いです。
私が言語の専門家STを志望した当時は国家資格も正式名称もなく、この仕事は「言語治療士」や「言語療法士」や「言葉の先生」、さらに「勉強の先生」や「ゴックンの先生」などとも呼ばれ、社会的評価も保障も収入も極めてささやかなものでしたが、私は真剣でした。
当時はあまり知られていなかったこの仕事は、今では中学生にも認知されるようになったようで、私は「13歳のハローワーク公式サイト」(1)で2024年3月中にアクセスされた「人気職業ランキング」の7位(前年の28位から大躍進)に輝いたことを最近知って大変誇らしく嬉しく思いました。
その2年前にキリスト教信仰を持った私は「人の役に立つ仕事に就きたい」と就職先を検討中だったこととも関係するかもしれません。
「私という人間は未熟ではあるけれど、これから何らかの専門的知識を獲得し、それを用いて誰かの役に立てる仕事を見つけたい。できれば、その後の人生をかけ情熱をもって取り組めるようなものがいいな」と、学業の傍らいつも考えていました。
言語聴覚士(ST)は同じリハビリテーション領域のセラピストである理学療法士(PT)や作業療法士(OT)などの国家が認めた専門職に30年遅れて 1997年に国家資格化されましたが、わずか二十歳そこそこで人生経験が少なく未熟だった私は、今後到来する高齢社会において「相互理解のために欠かせない深い人間性」と「この社会に関する幅広い知識・経験」が重要と考え、専門教育を受ける前に今後歩むべき道を自分に用意しました。
よくぞこんなに計画的な行動ができたものだと、今更ながら若き日の自分の挑戦に感心します。なぜなら、私は将来STとして働くために必須と思われる要件を大胆にも予想し、それらに対応可能な人材になろうというこんなにも壮大な計画を企てたのですから。