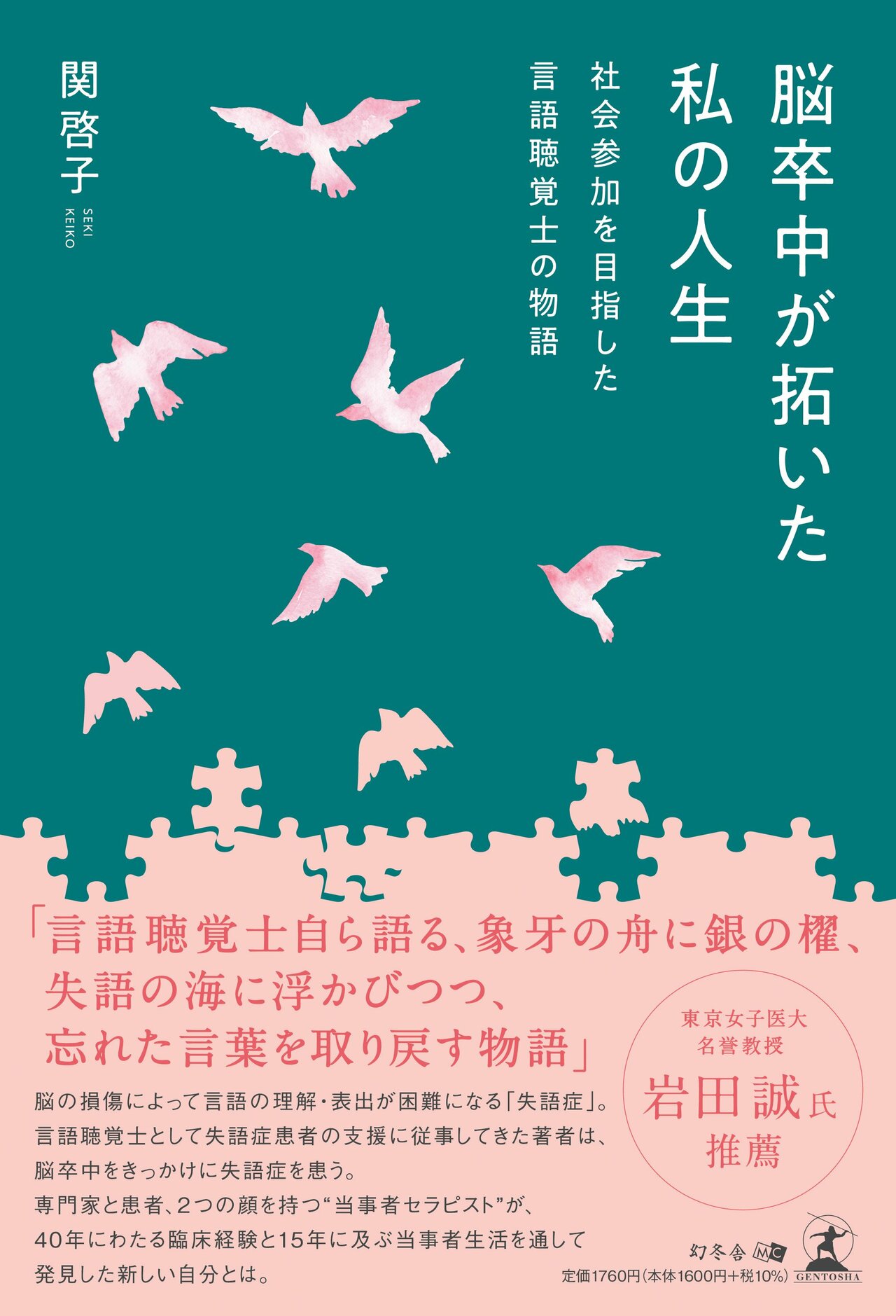お喋りを始めたばかりで可愛い盛りの10か月児の息子を泣く泣く教会仲間に託して大阪在住の姉家に送り届けてもらい、しばらくの間姉一家に息子の育児を委ね、私は勤務先病院隣の病院にお世話になりました。
そこへ妻子の不在による解放感からスキー場で高熱を出した夫の入院が重なり、一時夫婦そろっておとなしく患者として過ごしました。このエピソードを含め、夫の転勤中は概ね充実した札幌生活でした。
そして、5年半後、夫に転勤辞令が下り、私たちは札幌での実り多い公私にわたる人間関係と生活に心を残しながら東京に戻り、私は再び神経研での勤務を始めました。
神経研では、ご栄転されたS先生の後任の世界的な半側空間無視研究者I先生のご指導のもと、今度は右半球損傷後にみられる代表的な脳損傷後遺症である半側空間無視研究に従事してBIT(Behavioural Inattention Test, 行動性無視検査)という国際的に定評ある無視検査法の日本語版出版をはじめ、本領域関連の英論文を次々書いては受理され、国内学会でも役員として精力的に活動した結果、無視研究の領域では多少なりとも私の名前が知られるようになっていきました。
研究テーマにつき整理すると、この時期、当研究所でじっくり腰を据えて取り組んだ研究は、前期:左半球損傷後の代表的症状である失語症(指導者:S先生)から後期:右半球損傷後の代表的症状である左半側空間無視(指導者:I先生)、そして注意障害や記憶障害など大脳各半球損傷後の諸症状(同)まで広がり、約 15年間にわたり日々熱く研究に打ち込むことができました。
ここで強調したいことは、この時期積み重ねた失語症と半側空間無視の知識と経験は後日私を襲った脳卒中の後遺症としての高次脳機能障害にぴったり重なったわけで、換言すればこれら2つの代表的障害に関する知識と経験の蓄積が発症後の私を救ったとも言えるのではないかという点です。