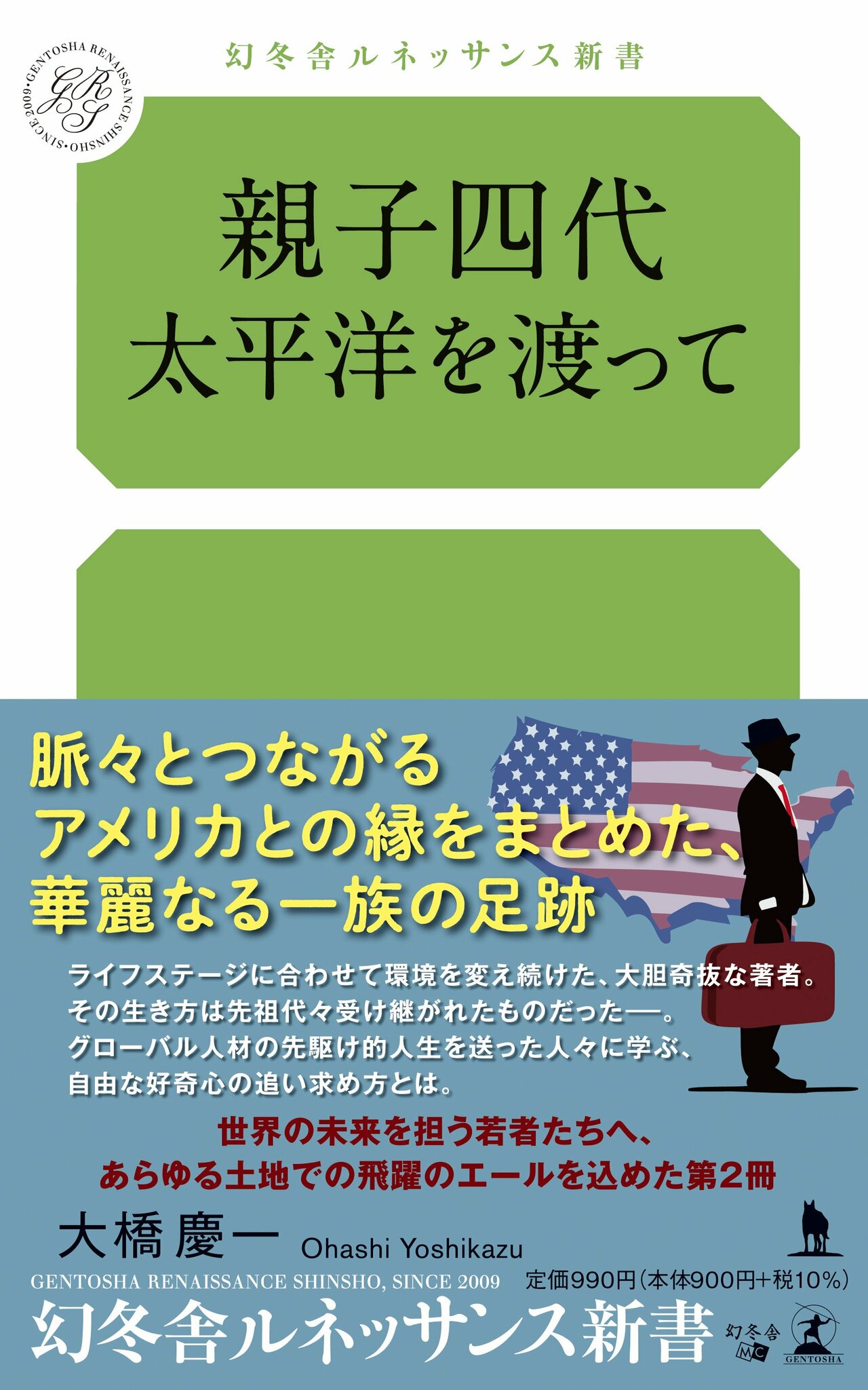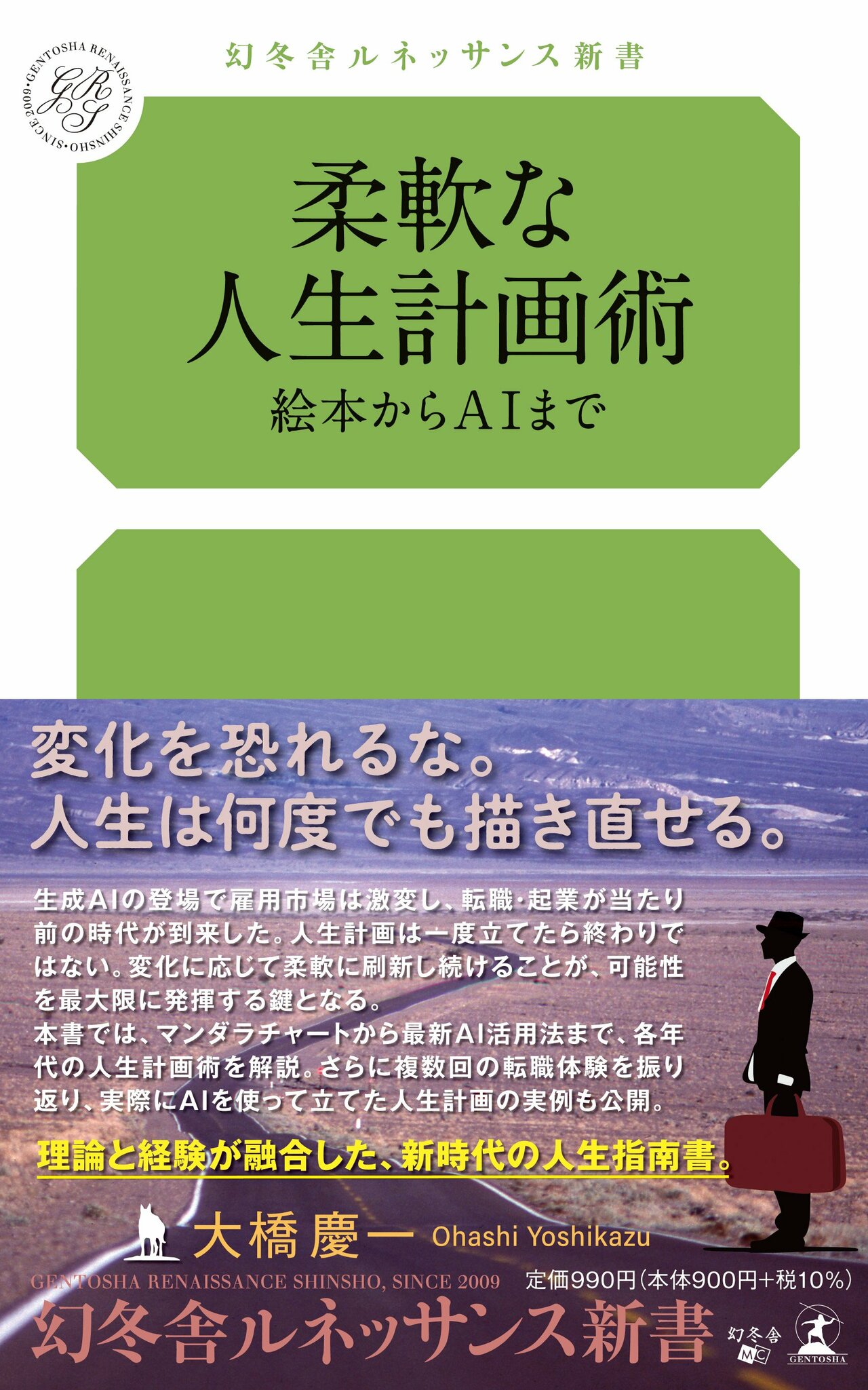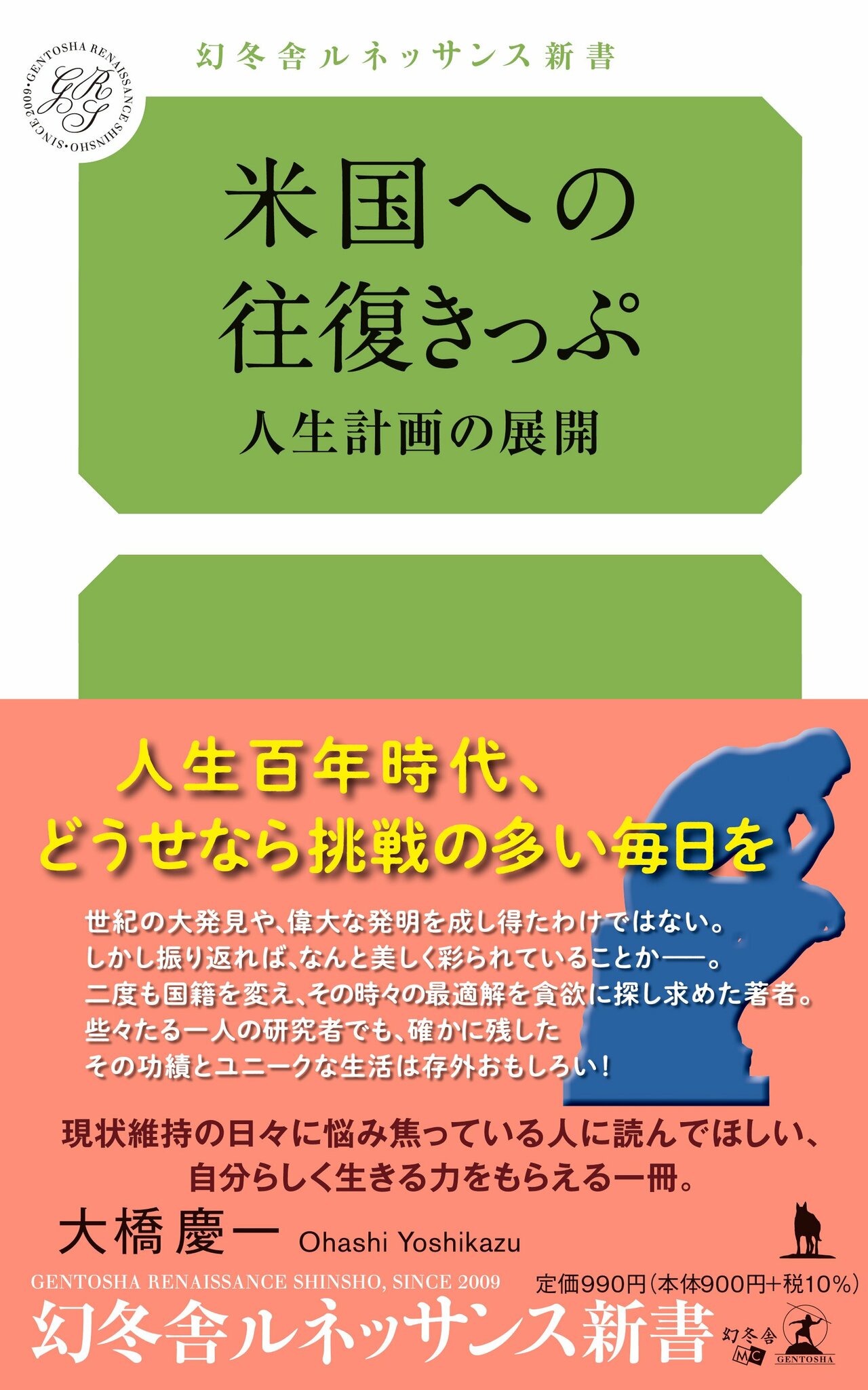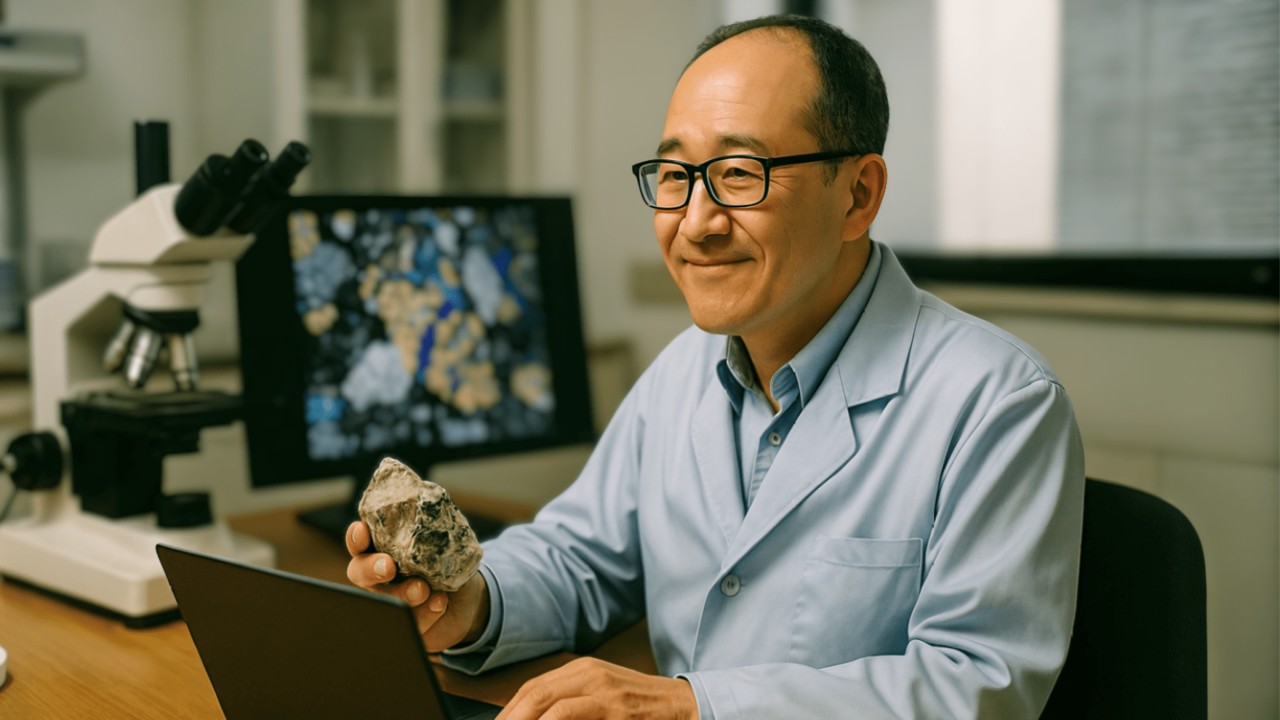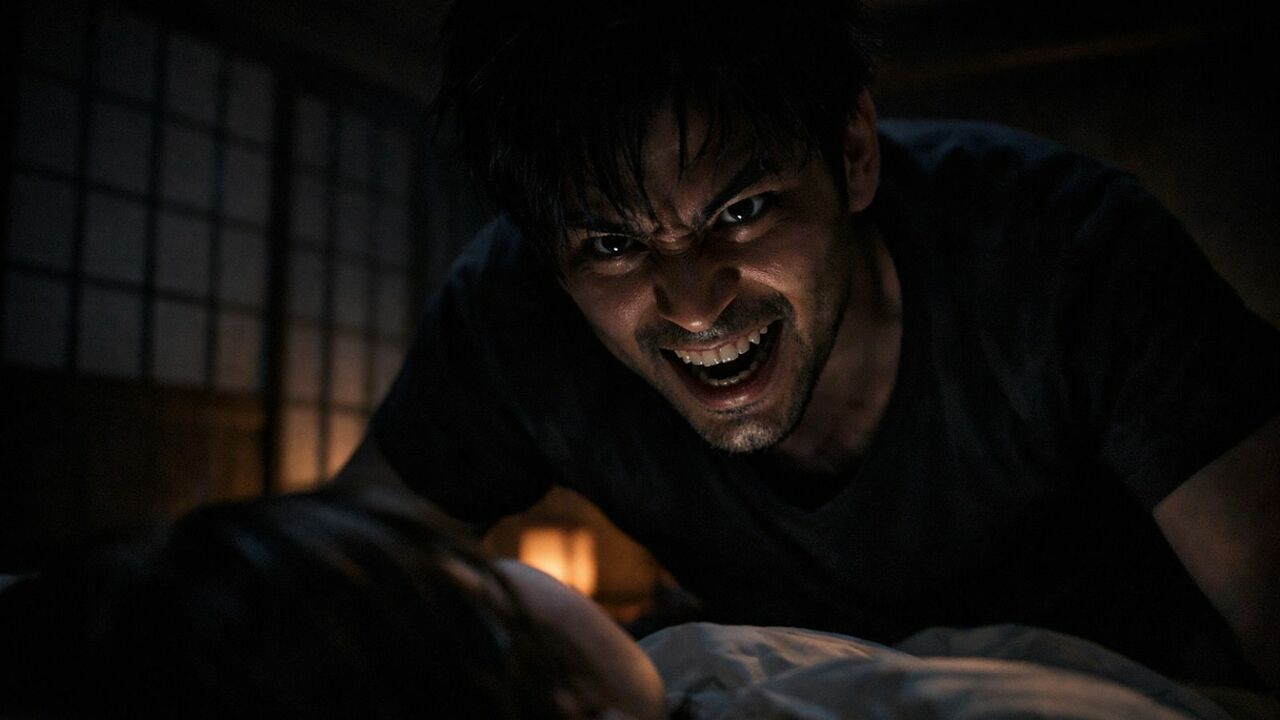人生は、「長生き」だけではなく「太生き」も
「太生き」は新語である。つい先日出版された金沢一平著『30代〜50代のための太生きのすすめ』(幻冬舎、2023)で知って、大いに気に入った言葉だ。金沢一平氏は糖尿病と骨の医学博士で、インターネット(脚注①)でも太生きについて興味深い話を書かれている。私が言いたかったのは、まさに人生を太く生きるにはどうしたらいいかということなのだ。
もう一つ私が気になっている言葉に「タテ型社会の人間」と「ヨコ型社会の人間」というのがある。(近藤勝重『60歳からの文章入門』(幻冬舎、2023)。組織の一員として周りに自分を合わせるのと、転職や引退で環境が変わることで自分の個性を活かすようになるという対比だ。
組織の中で過去―現在―未来の人生を考えるのを「タテ型」とすると、横の広がりである労働環境の変化に合わせて考えるのは「ヨコ型」になる。どのような環境にあってもなるべく「ヨコ型」でいてほしい。
私がこの本を執筆するに至った主な動機は、日本の若いみなさんに対して、一度は海外に出て他国の人々がどのような将来像を抱いているのかを直接見聞する機会を持っていただき、ご自分もより自由な人生を築くことを促すことである。機会はいろいろあるだろうが、都立国際高校(脚注②)というのも一つの方法であろう。
都立国際高校は、帰国子女や在日外国人も多く、日本に居ながらにして国際的な教育環境に触れることができる。言語も英語だけでなく、ドイツ語、フランス語、スペイン語などの欧米の言語から、ハングル、中国語などアジア系のクラスもあるそうだ。さらに、日本文化と伝統芸能、日本の伝統武術の科目もある。
多くの若者が新たな視野を得るために海外に飛び出すこと、また、ほかにどのような新しい可能性があるか学ぶことで、自らの人生をより柔軟に設計してほしいと、私は心から望む。こうした経験を通じて、新たな学びや気づきを得る喜びを感じることができるだろう。
私の経験上アメリカでは、空間的にいうと人と同じでないこと、時間的にいうとこれまでのやり方と違っていることが重視される傾向がある。周りの人や過去の前例と同じであることを重視する日本と反対である。日本にしばらく暮らしていると、アメリカのこのような姿勢はまことにいいことだと私も思うようになった。