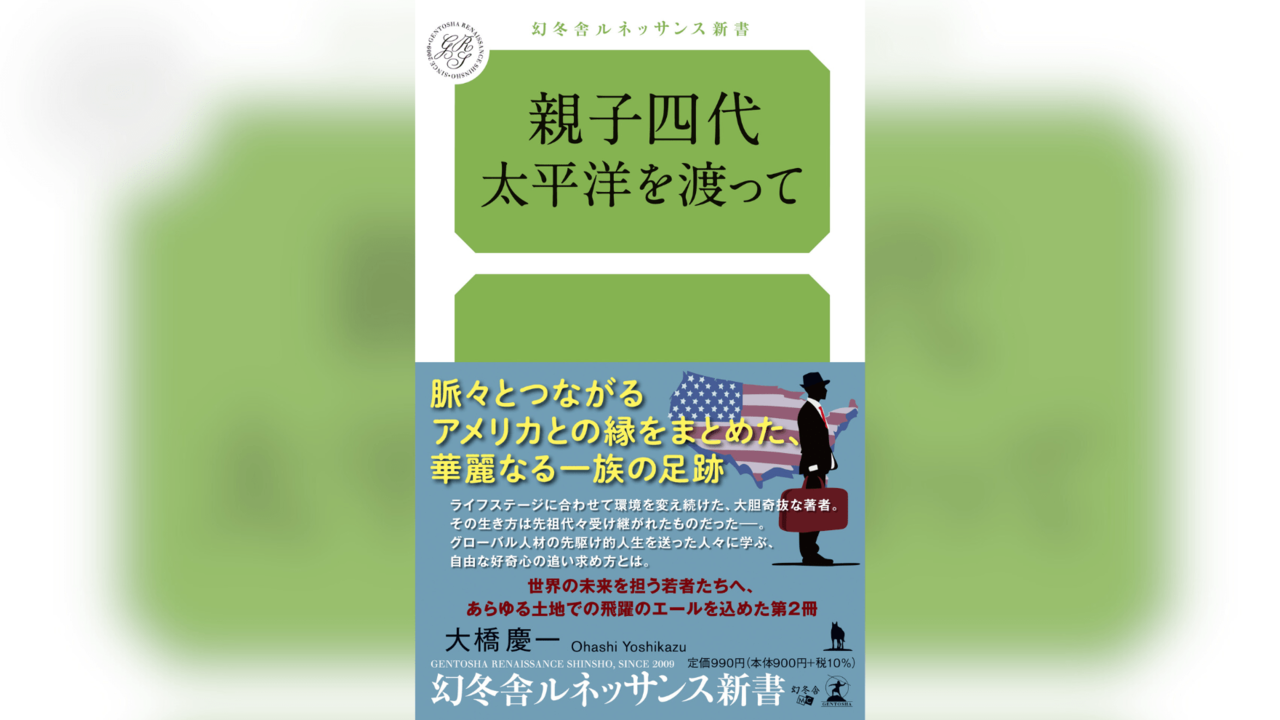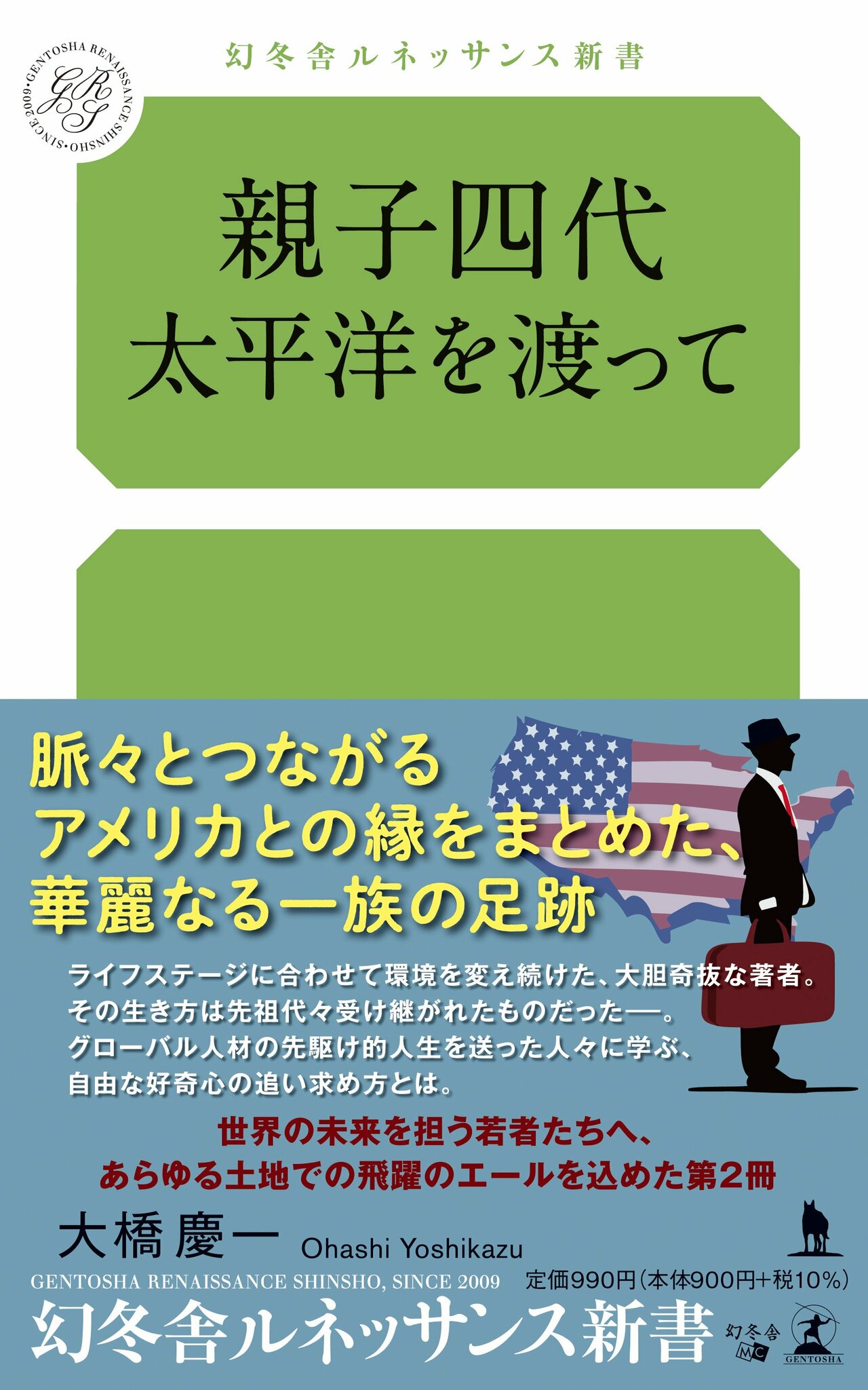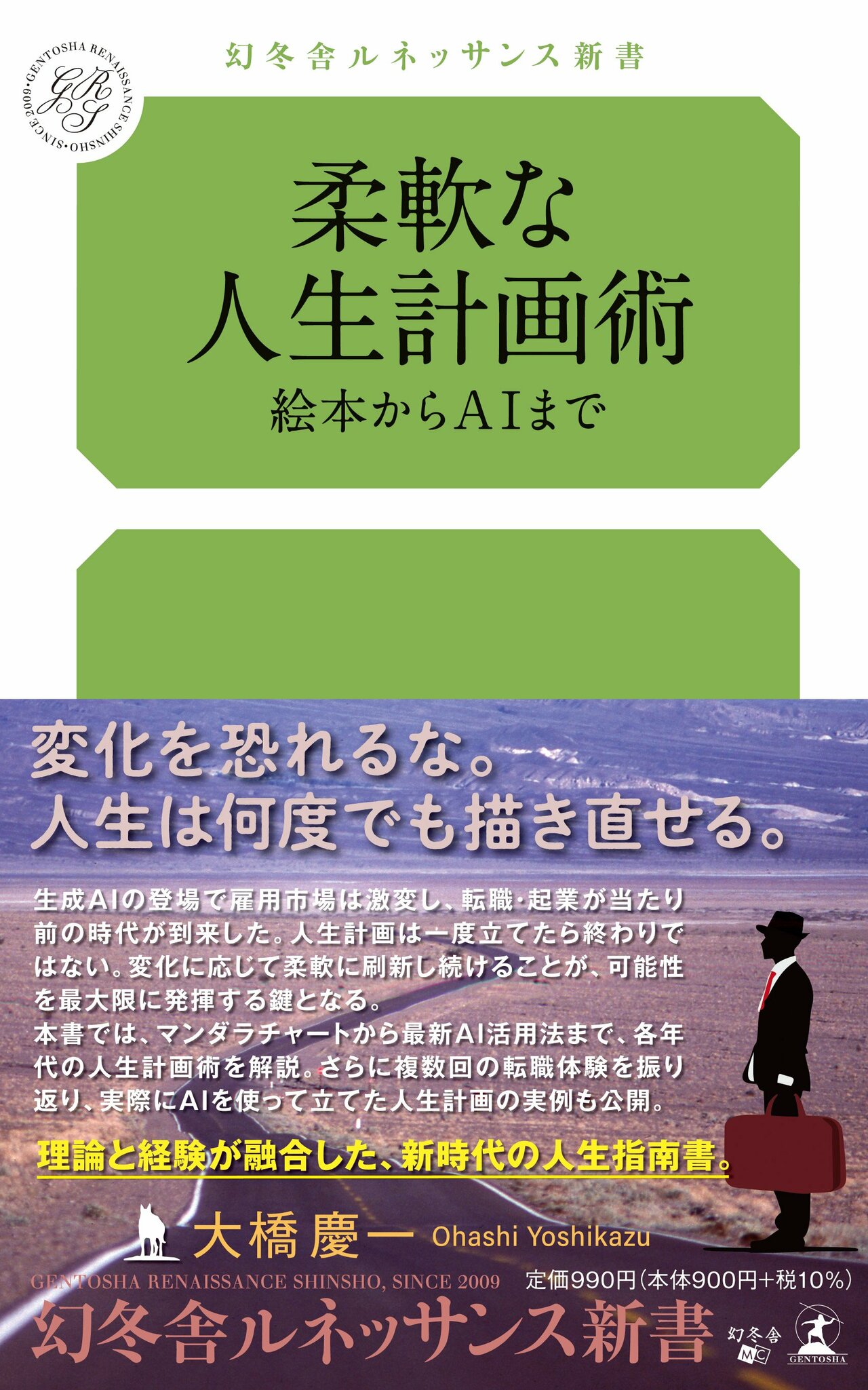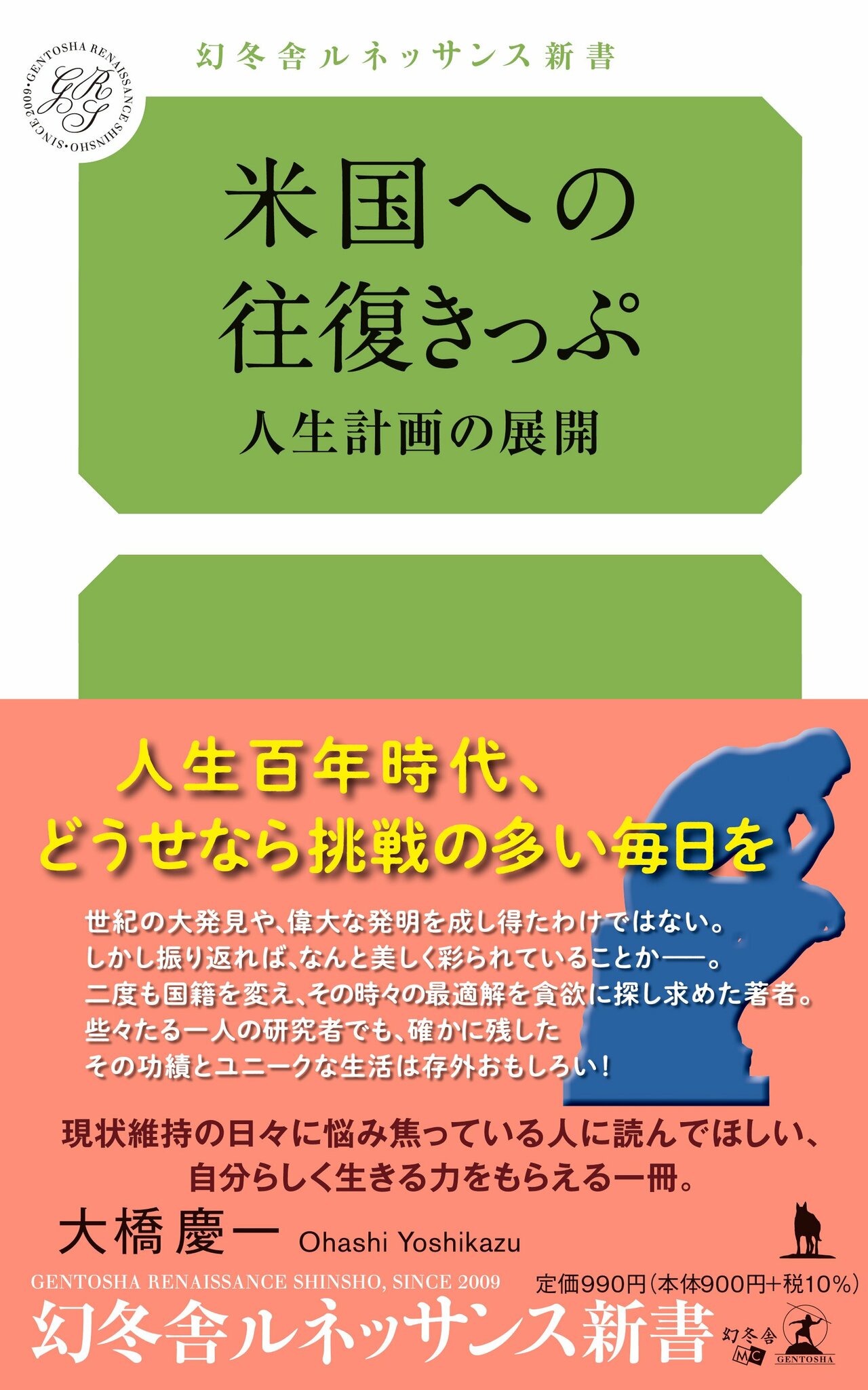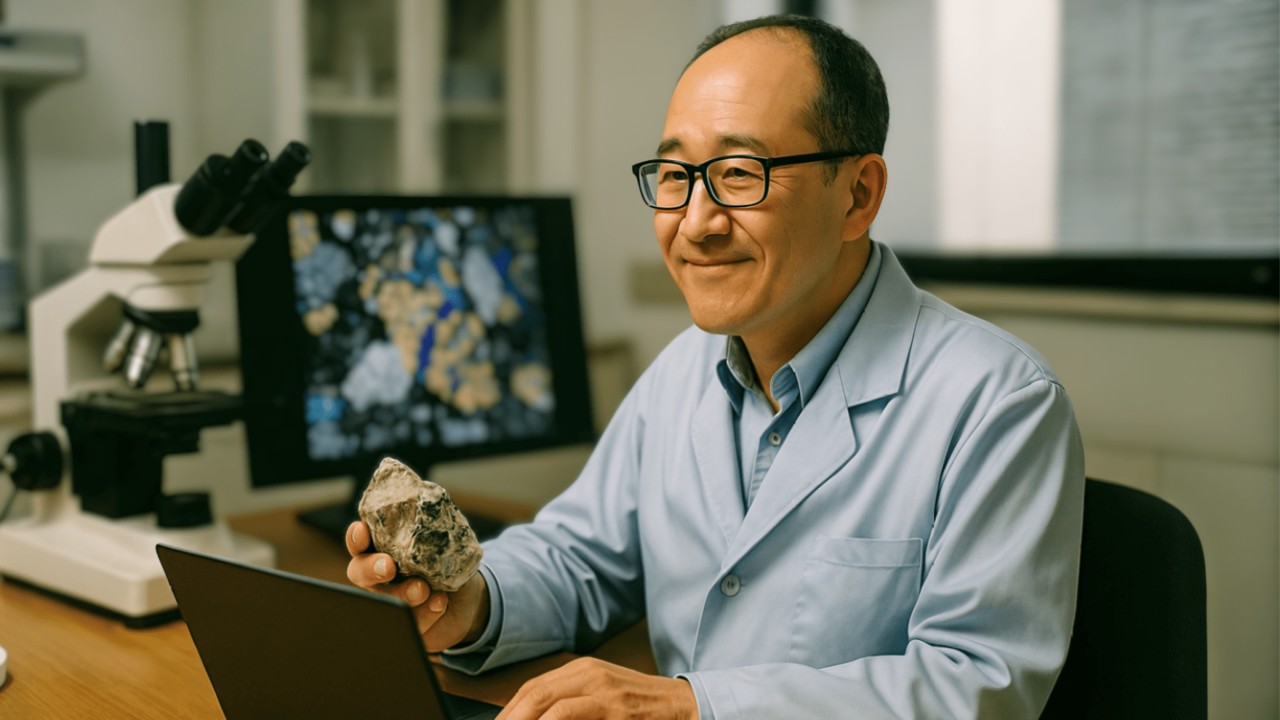【前回の記事を読む】アメリカでは、空間的にいうと人と同じでないこと、時間的にいうとこれまでのやり方と違っていることが重視される傾向がある
第一章 私と長男のこと
私自身のこと
すでに前著に詳しく書いたが、ここでは次の段階への準備を、いつ、どのようにしていたかということを中心に、私のこれまでの人生を説明しよう。
[高校から大学へ]東京教育大学(現筑波大学)付属駒場中学・高校の男子校で6年を過ごし、大学受験に臨んだ。大学での進路が決まらず、1年目(法学部志望)・2年目(工学部志望)・3年目(理学部志望)と受験して、計2年浪人。この経験で私が学んだことは、人生急ぐことはない。本当にしたいことをしようということだった。
そこで、教養学部の2年間で次に進む分野を考えて、理学部地学科に決めた。これは高校の理科の一つで地学を選び、結晶の対称を数学的に扱うことに大いに興味を持ったからだ。
東大理系の入学試験の理科は、物理・化学・生物・地学から2科目選択することになっていて、私は物理と地学で受けた。地学は他の3科目に比べて選ぶ人数が極端に少ないので、試験の難易度がかなり低いという印象を私は持っていた。
進路決定に関しては、教養学部時代の担任・中村純二先生からもいろいろ助言をいただいた。先生は、オーロラの研究のため南極で何度か越冬されたこともある超高層大気物理学者である。
最終的には、3年から理学部地学科鉱物学教室で、X線結晶学・鉱物学を選考した。学士課程のあと同じ鉱物教室の修士課程に進学した。
[将来のことを考えて渡米を実行]そのまま博士課程に進むのが普通だろうが、ここで私は考えた。明確な講座制を取っている学科なので、ここで学位を取ると、教授・助教授・講師・助手という序列の末席で、常にチームの一人としての立場しかないだろう。
私は自分のしたいことを自分のペースでしたい。そのために、博士号は米国で取って、米国で研究生活を送ろうと考えた。
しかし、教室主任の教授からは大反対された。私は、もう東大にはこだわらず、米国に留学する決心をした。行く先の大学としては、MITかCaltech(それぞれの大学については後述)の可能性も考えたが、結局ハーバード(Harvard)大学にした。東大で修士号を3月に取って、4月のはじめに渡米した。1968年のことだった。
この年、日本では大学紛争が起こり、東大の安田講堂が学生に占拠され、警視庁機動隊が学内に出動、その後全学封鎖にまで発展した。
一方、渡米した私は、その年の秋からハーバードの地学科でこれまでと同じX線結晶学・鉱物学で博士号を目指した。幸運なことに、まったく学園紛争などには関係なく、私は学習・研究生活を続けることができた。そして、それ以来40年近く米国に住むことになった。