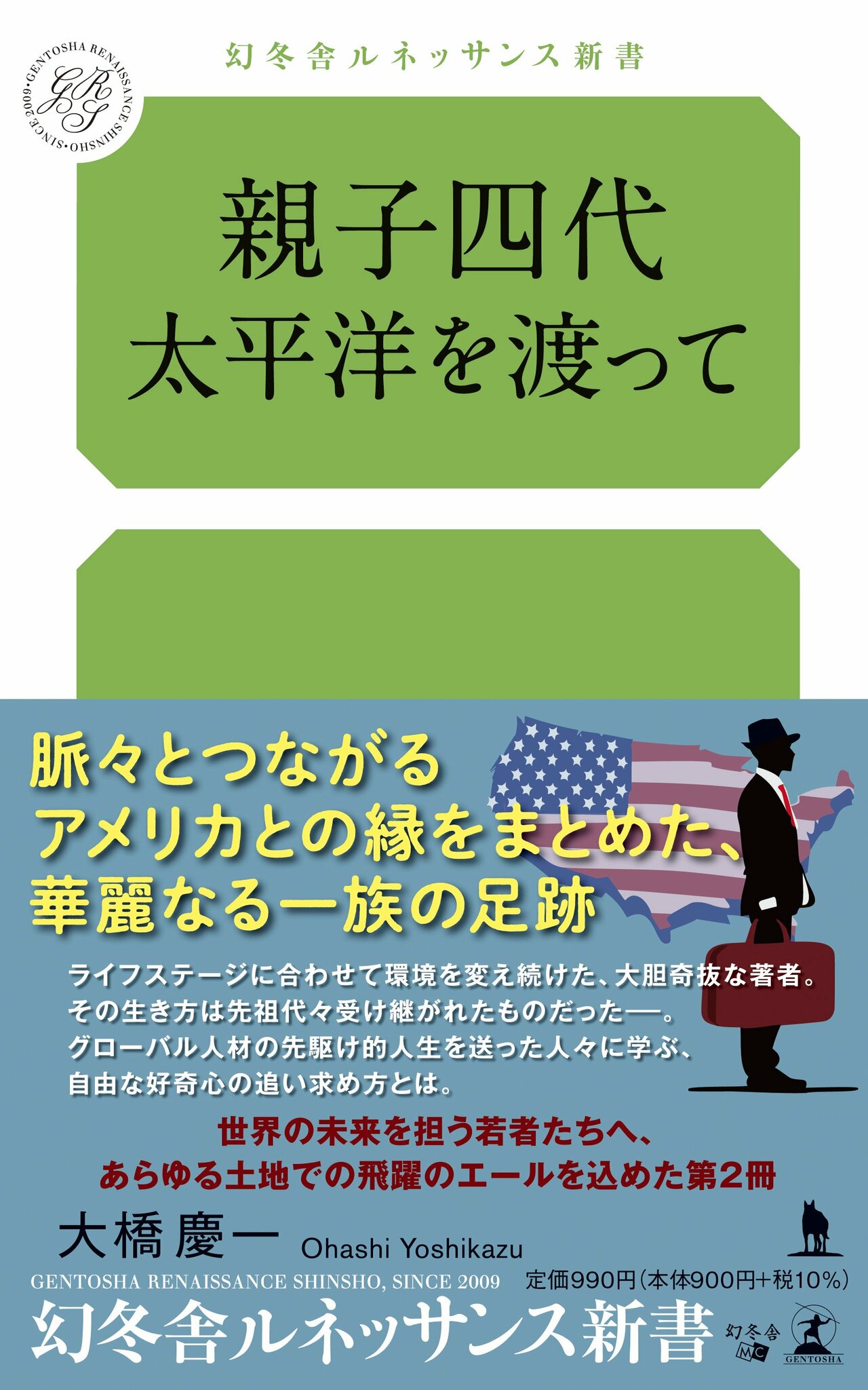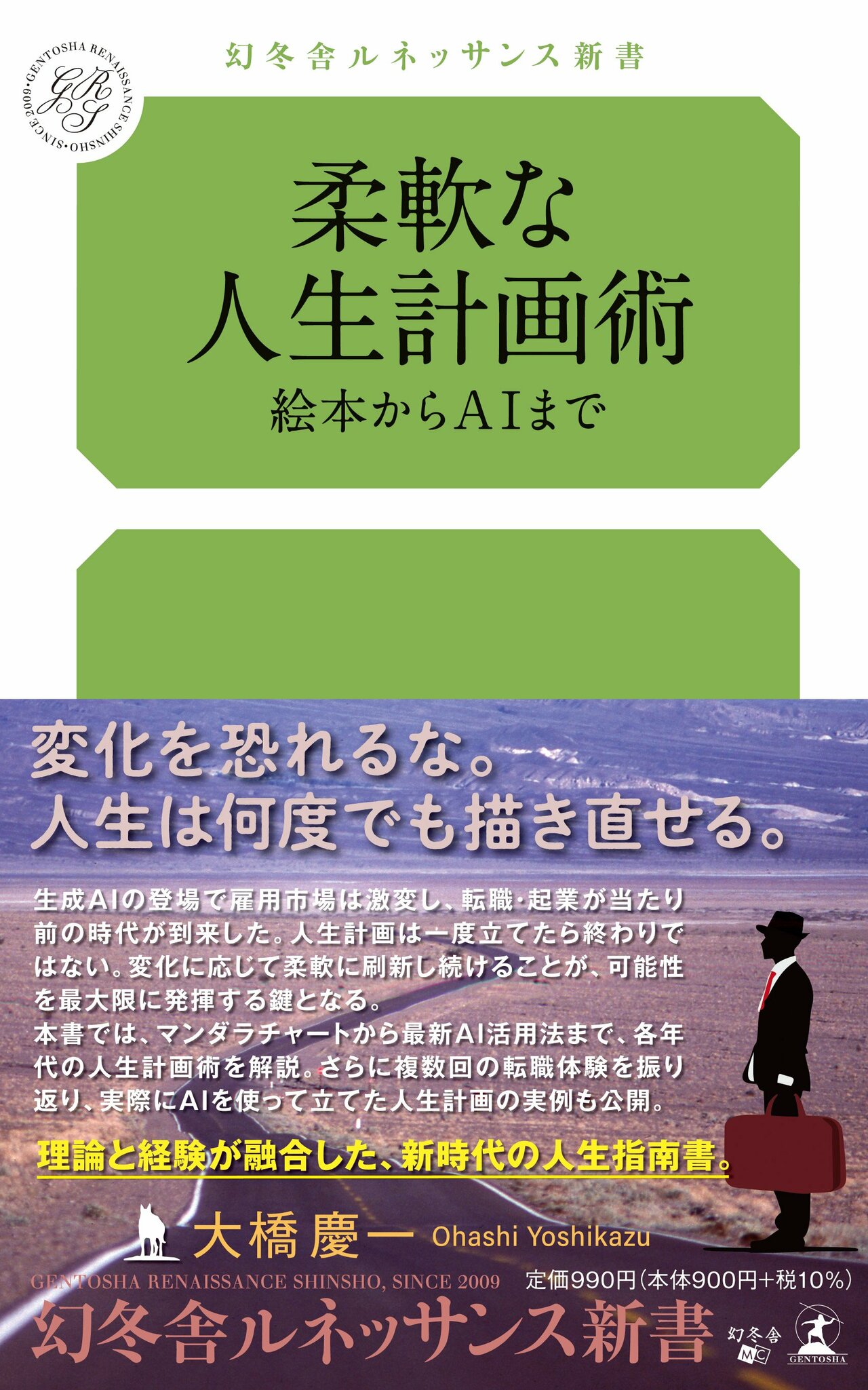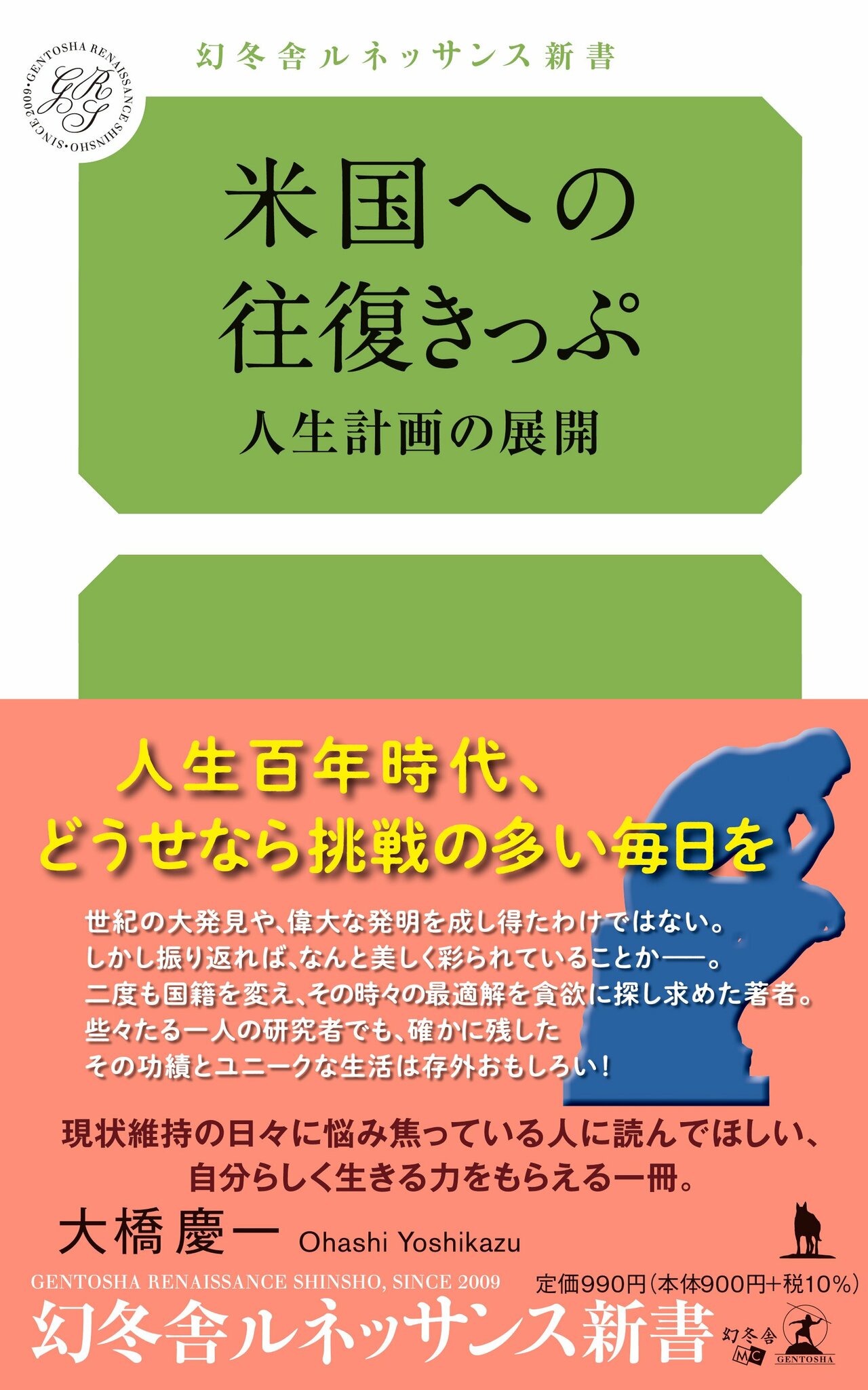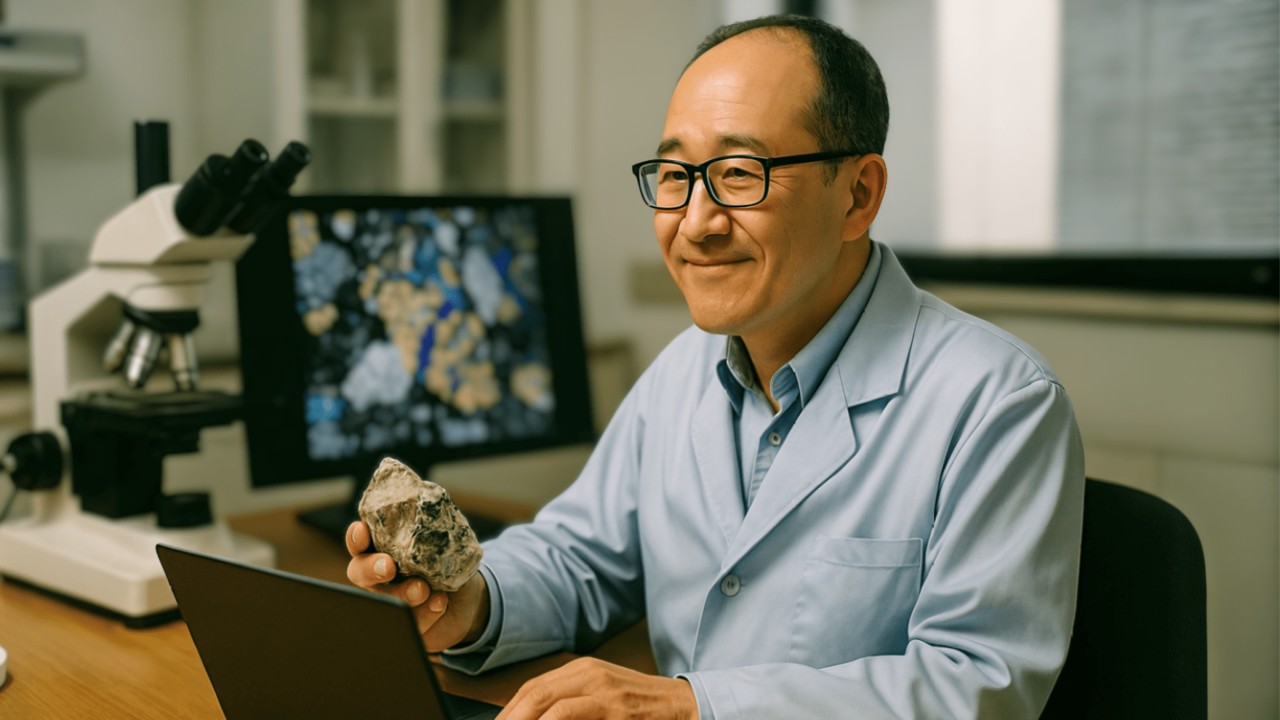[ハーバードでの研究生活、そして結婚]私の一生で、これほど集中して勉強したことはない。大学のすぐ近くに見つけた下宿には寝に帰るだけで、ほとんどの時間を研究室で過ごした。
それぞれの研究室の学生の机は指導教官の部屋の向かいにあったので、ほとんど毎日教官と喋る。日本では、指導教官と話すのは1学期に数回だったから、大違いである。
自分の勉強に加えて、まだ30代半ばの若い准教授のティーチング・アシスタントやリサーチ・アシスタントもして、私は本当にいい経験をすることができた。経験だけでなく、十分な経済的な報酬ももらった。
2年目の終わりに博士論文の研究を始めるための予備試験に合格。学業に目途がついたので、次の計画を実行することにした。私はケンブリッジから、相手は東京から出発し、ロサンゼルスで合流して結婚。3年目から大学の夫婦寮で新しい生活を始めた。これで研究室で過ごす時間が少し減った。
[論文の課題と卒業準備]東大では学士論文も修士論文も自分で決めたテーマでなく、教室で決まった研究の一つを割り当てられたが、ハーバードでは自分からやりたいことをいくつか挙げて、指導教官と話しあった。
私は単なる結晶構造解析だけではなく、その結果を使って構造エネルギーの計算をすることにした。しかし、そのためにはかなり複雑なコンピュータプログラムを開発しなければならない。
3年目が終わる頃だったと思うが、指導教官から、いまやっていることを論文にしてあと1年で卒業しろと勧められた。博士課程にかかる期間は5〜6年が普通で、7年という人もあった。4年というのは聞いたことがなかった。
論文に書く材料はいろいろあった。ワープロなどというものはなかったので、IBM Selectricという電動タイプライターを購入。そして途中原稿も最終稿も、全部タイプしてくれたのは新婚早々の妻だった。タイプライターなどそれまで触ったこともなかっただろうに、よくやってくれたものだ。
【イチオシ記事】折角着た服はゆっくり脱がされ、力無く床に落ち互いの瞳に溺れた――私たちは溶ける様にベッドに沈んだ
【注目記事】「ええやん、妊娠せえへんから」…初めての経験は、生理中に終わった。――彼は茶道部室に私を連れ込み、中から鍵を閉め…