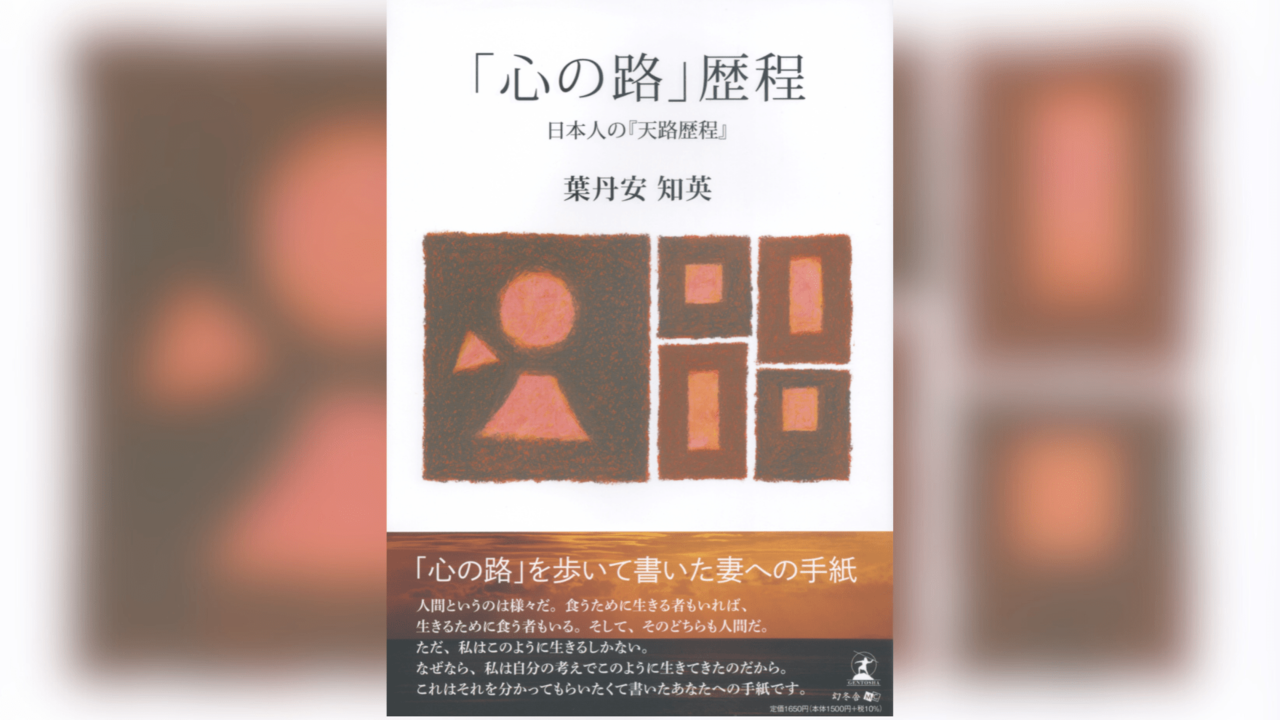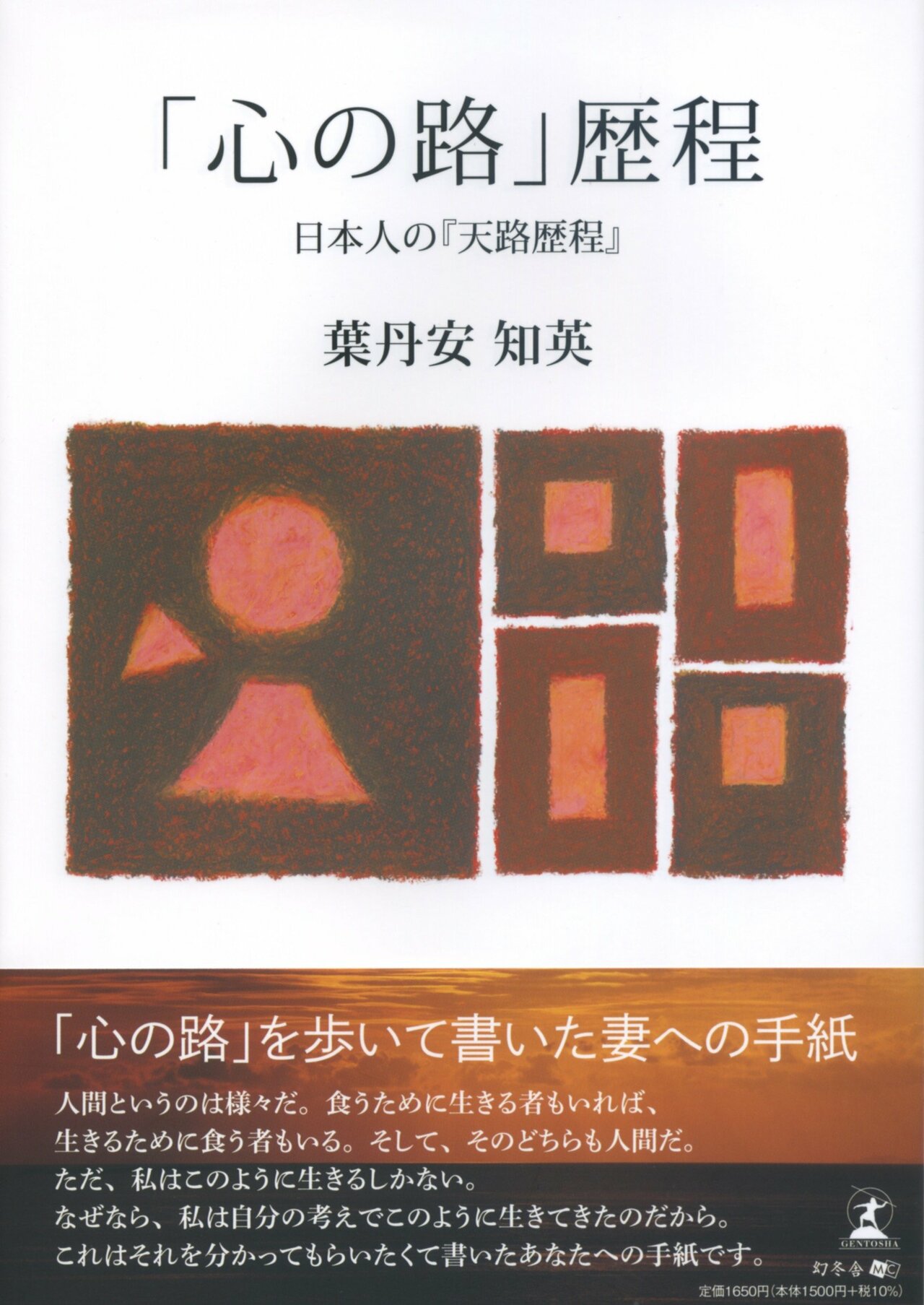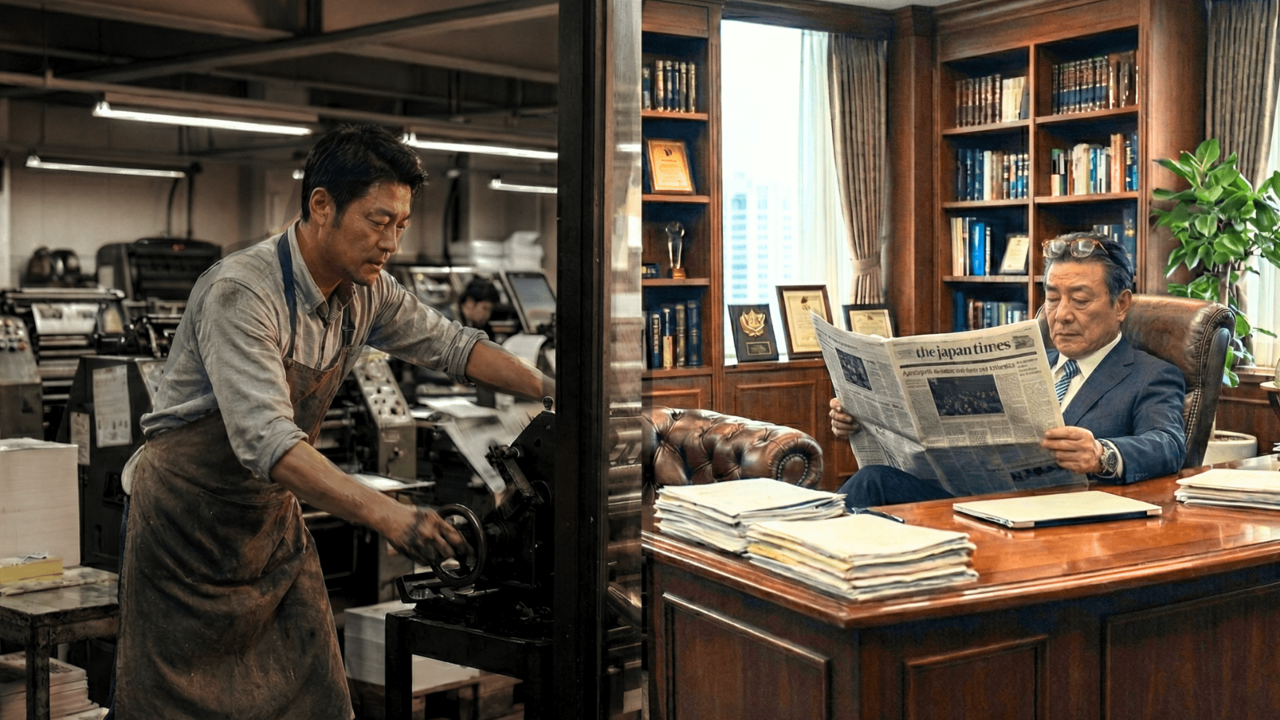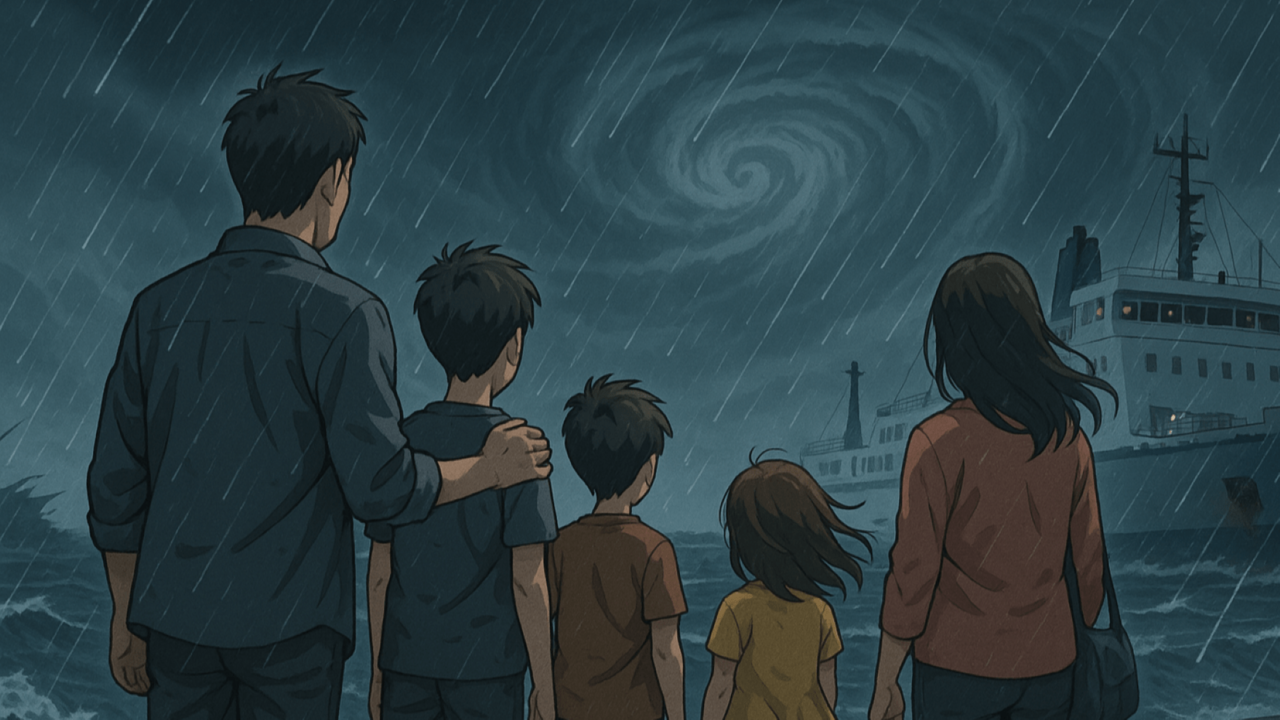【前回の記事を読む】四国のお遍路は弘法大師だけが始めたものではなく、古くから多くの人間がやってきたことを後世に虚構され形成されたものである
第一部
第一章 心の路
邊地順礼の信仰
高野山学侶衆が遍路という虚構をつくる下地となった「邊地順礼」の信仰とはなんだったのか、そしてその社会経済的背景はどうだったのか。
律令体制下に国家鎮護を名目とする社寺を保護した封戸制が衰えはじめると、経済的に急迫した社寺は天皇や貴族に経済的援助を期待し、彼らの現世利益を祈る祈祷宗教となる。しかし、都から遠い社寺が存続するためには、遠隔地という障害を克服して天皇や貴族の心を惹きつけ、寄進してもらい、参詣してもらわねばならない。
天皇の参詣があった熊野では、その地を浄土だとし、参詣回数が多ければ効験も大きいといった宣伝活動の一環として、御師による道案内や宿坊の整備、諸国巡回による師旦関係の形成などが促進された(『新編社寺参詣の社会経済史的研究』新城常三)。
熊野の信仰もまたこのような情勢下に四国辺境の地へ伝播され「邊地」を成立させ、次代に邊地を巡る「順礼」を育んだ。
「邊地」とは平安期に熊野御師、修験の行者、都の優婆塞らが辺境の道場に行乞しながら布教したことおよびその行為者を指す。その道は集落をつなぐ峠道、木樵や山師たちが歩いた山道、海沿いの「海の修験の道」などをつなげたものだ。その道を熊野の観音信仰の伝播者・御師たちが歩き、鎌倉・室町期になると修験や観音信仰の他に時宗や禅宗なども混在した「順礼」道となった。
四国は辺境の地で、その道を踏み分けてゆこうとする心には観音信仰が中心にあった。それは熊野三山を阿弥陀三尊垂迹(すいじゃく)の地として浄土に擬し、そこから観音の住む補陀落へ渡海する渇望だった。