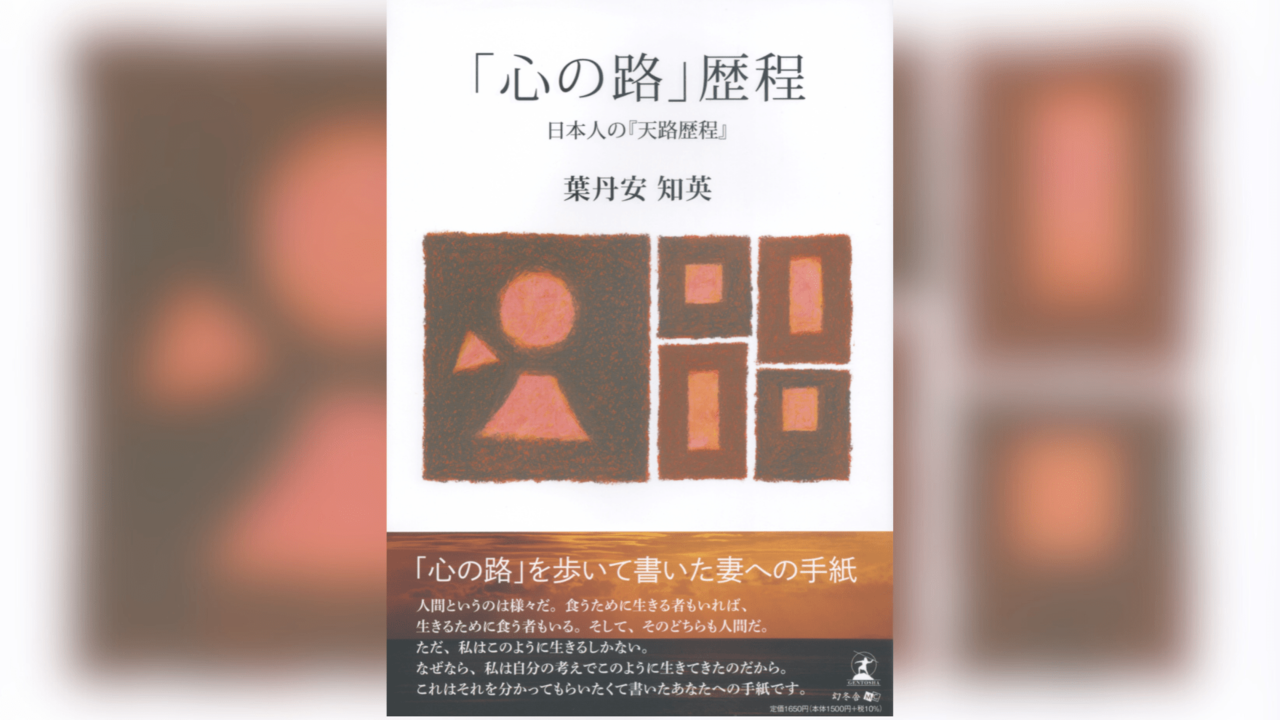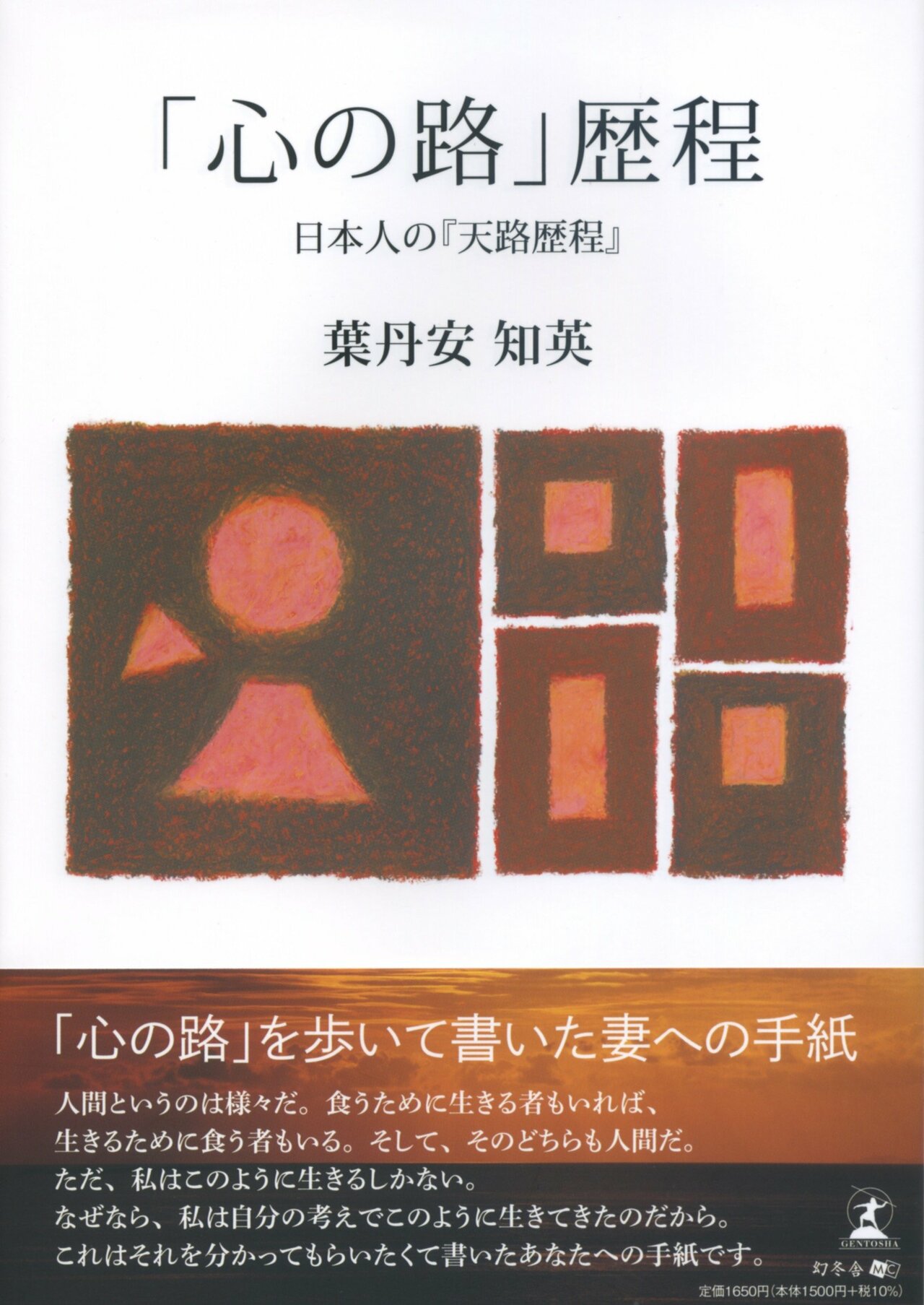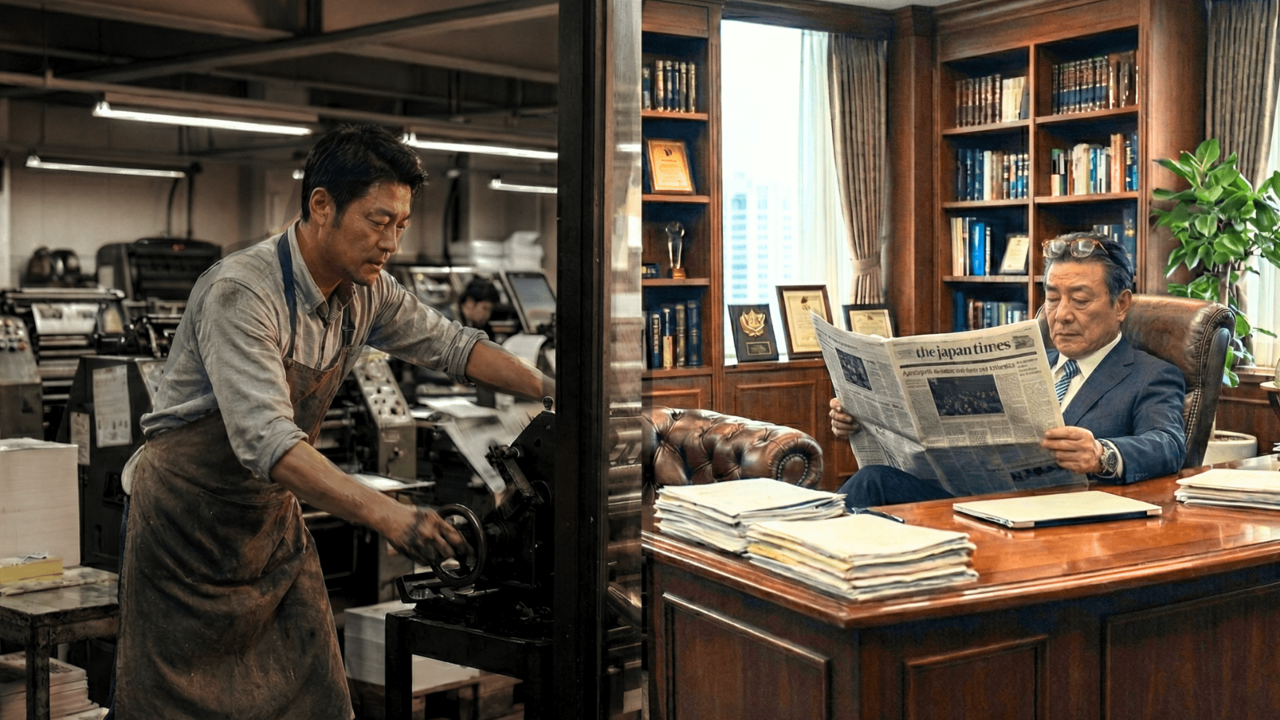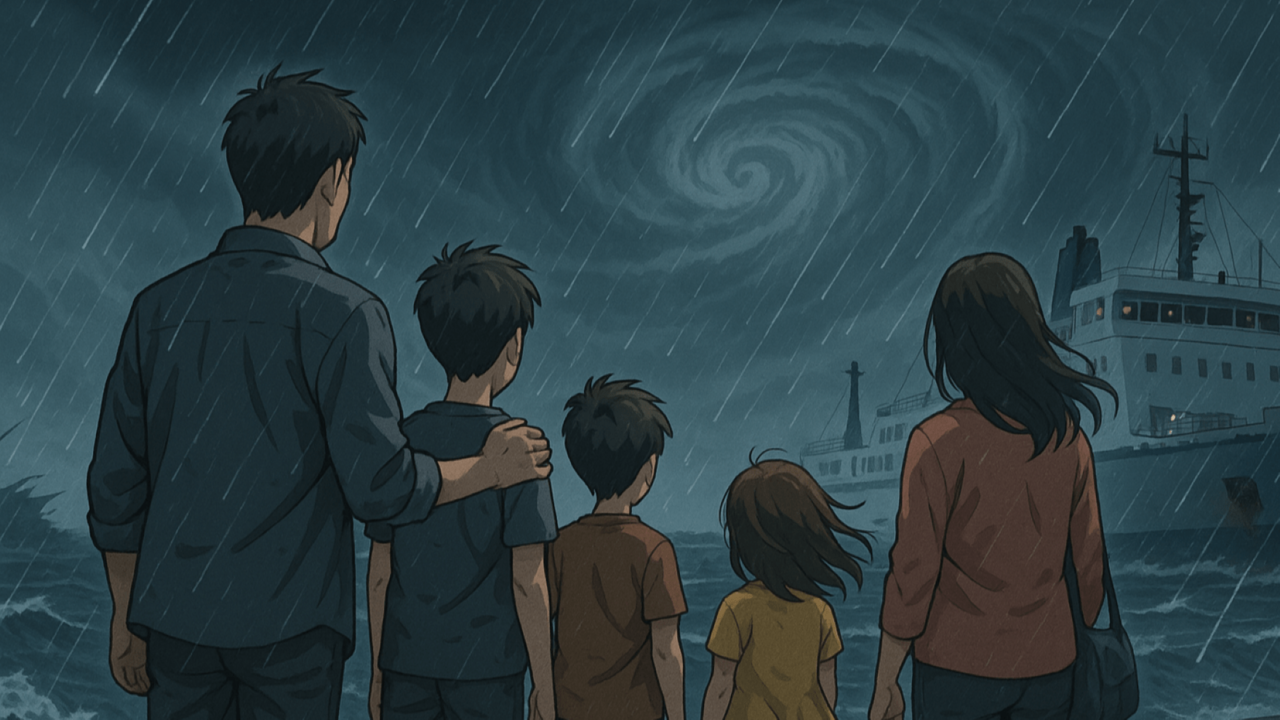【前回の記事を読む】邊地順礼の信仰特徴は複雑怪奇で、相互受容的。邊地順礼にある信仰の核は観音信仰だが他にも多くの信仰宗教が入り込み融合された
第一部
第一章 心の路
遍路に擬された信仰
邊地順礼道を歩いた真念は、行者聖として開悟し、寂本に自分の歩いた道を仏道成就の道として称揚し、元禄三年になって寂本と真念の共著『四国徧禮功徳記』が板行されるが、そのなかで寂本は、空海から高雄山寺を託された柿本紀の僧正真済(しんぜい)(『遍照発揮性霊集』の撰者)が、空海の入定後にその遺跡を慕い歩いたことに遍路は始まるとし、さらに札所八十八ヶ所の数について、集諦(じったい)に見思の惑という三界生死の苦しみを集めた八十八の煩悩があるとして、この見惑八十八使の煩悩を断滅する功徳を遍路の信仰の姿かたちだとした。
宮崎氏の云うように、寺を道とし道を寺としてすべてを捨て去った自己放下の心、そして踊り念仏しながら歩き巡る一遍の遊行は、外見上、遍路と似ており、「順礼」を一遍・時宗的に分岐したものと見れば、遍路の先行形態とすることもできなくはないが、その本質は自己を放下してひたすら他力にすがる専修念仏で、補陀落渡海の観音信仰とも遍路の弘法大師信仰とも異なる。
宮崎氏は自己放下の心の佇まいがすべてのようで、それに遍路も含めて説明しているにすぎない。
村岡氏は邊地の成立を遍路のはじめとするが、邊地の信仰には言及がなく、遍路を弘法大師信仰の道とする論理が成立していない。
八十八という札所寺数の説明にしても『四国徧禮功徳記』から借用祖述して、邊地巡礼の信仰を無視している。
村岡氏は高野山学侶衆のつくった遍路という虚構を虚構した側の説明に沿って解説しただけのことで、寂本が『四国徧禮功徳記』に述べているのを真似て、真済僧正が空海の遺跡を慕い歩いたことに遍路ははじまるなどと見てきたように記しているのは、寂本も村岡氏も共に論理以前の三百代言としか云いようがない。
八十八という数については、熊野参詣道を四国遍路道に先立つものとして、熊野への道に熊野王子が布置された九十九という数を極限数に達し、それを表した限定数と捉え、さらに遍路道の果てに熊野の補陀落渡海信仰があることに鑑み、伝播地としての四国の邊地とを結びつけて注目し、熊野の九十九王子(つくもおうじ)に次ぐ限定数として八十八を霊場の数としたのではないかとする論考がある。
見惑八十八使煩悩から寂本や村岡氏は説明するが、札所には真言、天台、臨済、曹洞、時宗といった異なる宗派の寺院が混在しており、また国分寺や一宮寺は六十六部が代参納経する寺であり、こうした寺は江戸期になって数合わせのために加えられたと考えられ、そのように遍路八十八ヶ所の霊場が形成されたとする。
数が与えられれば札所はおのずから決まっていったと思われ、論拠資料の広範と分析の正確とからして、また熊野御師たちの伝教道だという観点からも、この論考が最も信憑性が高い八十八という数の説明だ(『四国遍路』近藤喜博)。