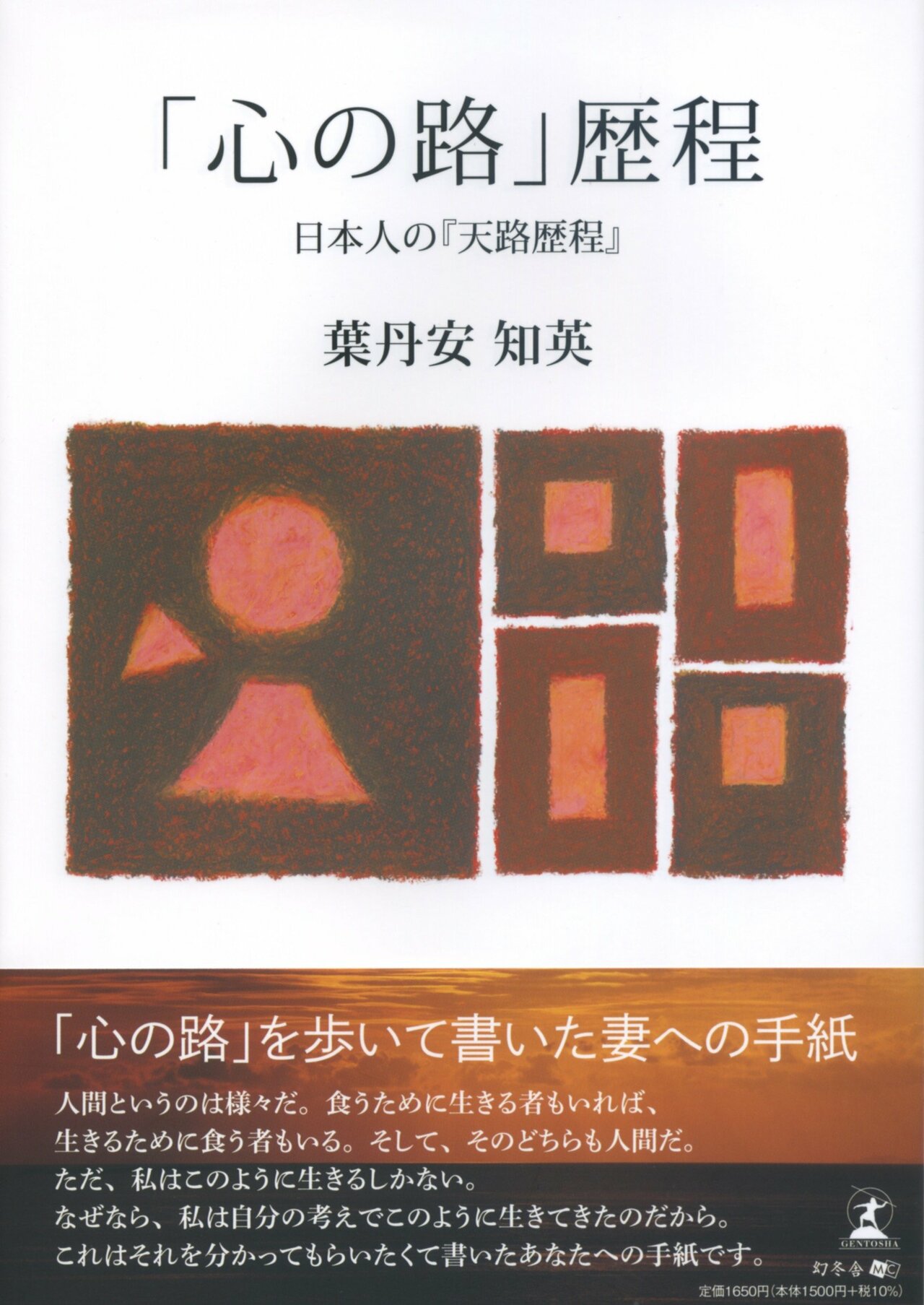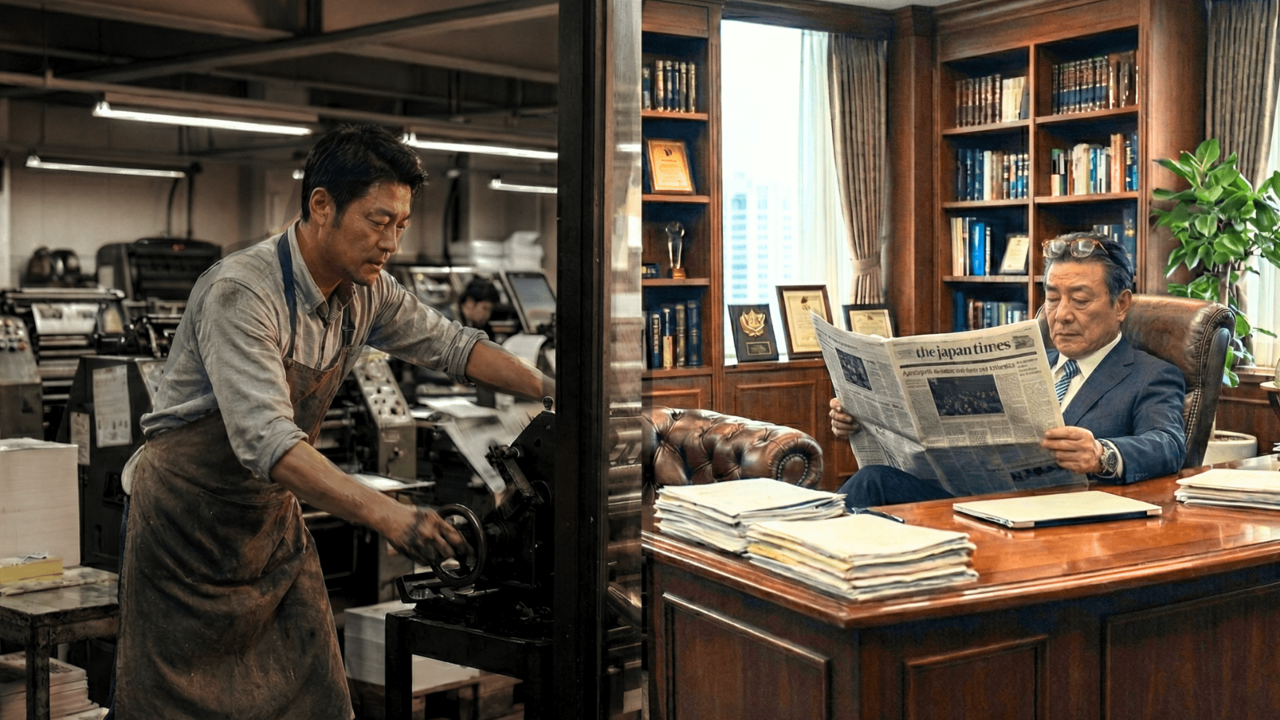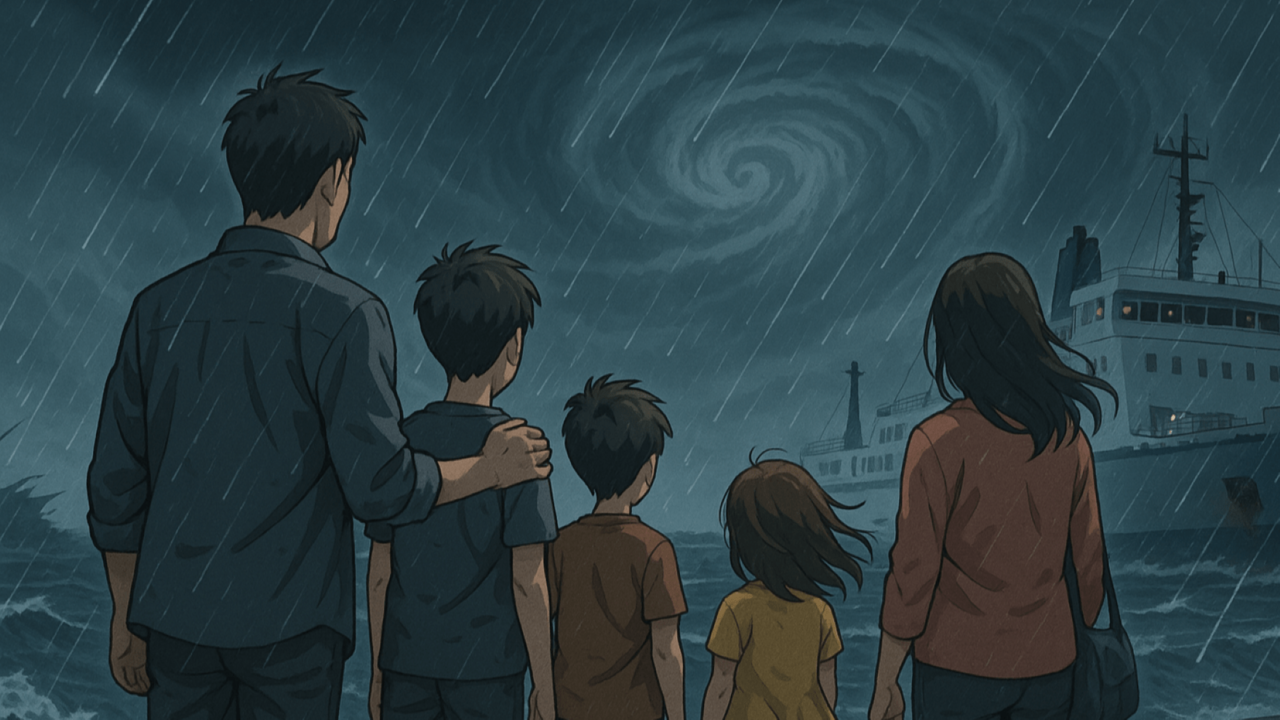さらに、縄文の融和的生活や弥生の鬼道もあり、ある種のアナーキズムも邊地順礼の信仰に紛れ込んでいる。邊地順礼の信仰は融和的包容力を下地としてその境界は融合されて、純粋無垢な信仰心として日本人の心の奥底に残っている。
遍路に擬された信仰
遍路に擬された信仰については、『一遍聖絵(いっぺんひじりえ)』などに描かれた一遍(一二三九~一二八九)を棟梁とする踊り念仏集団の「遊行(ゆぎょう)」というかたちを遍路と見立て、寺を道とし道を寺としてすべてを捨て去った自己放下の心に信心を認め、「南無阿弥陀仏」の名号を唱える者が即阿弥陀仏であるとする信仰と大師の宝号を唱える者が即弘法大師であるとする信仰とを重ね合わせ、そこに三密加持(白装束に身を固め、大師の宝号を唱え、心に仏を念ず)としての遍路の信仰の姿かたちがあるとするもの(『遍路』宮崎忍勝)や、遍路の「邊地」としての成立過程に修験の影響と行跡を認め、役小角(えんのおづぬ)、勝道(日光二荒山)、空海、聖宝(修験道当山派の祖)、観賢(高野山第四代座主、空海に大師号を申請)への流れのなかに遍路の始原的意味を求め、とくに観賢の寄与があるとして、そこに遍路の信仰や修行の成立があるとするもの(『現代密教講座7』村岡空)などがみられる。