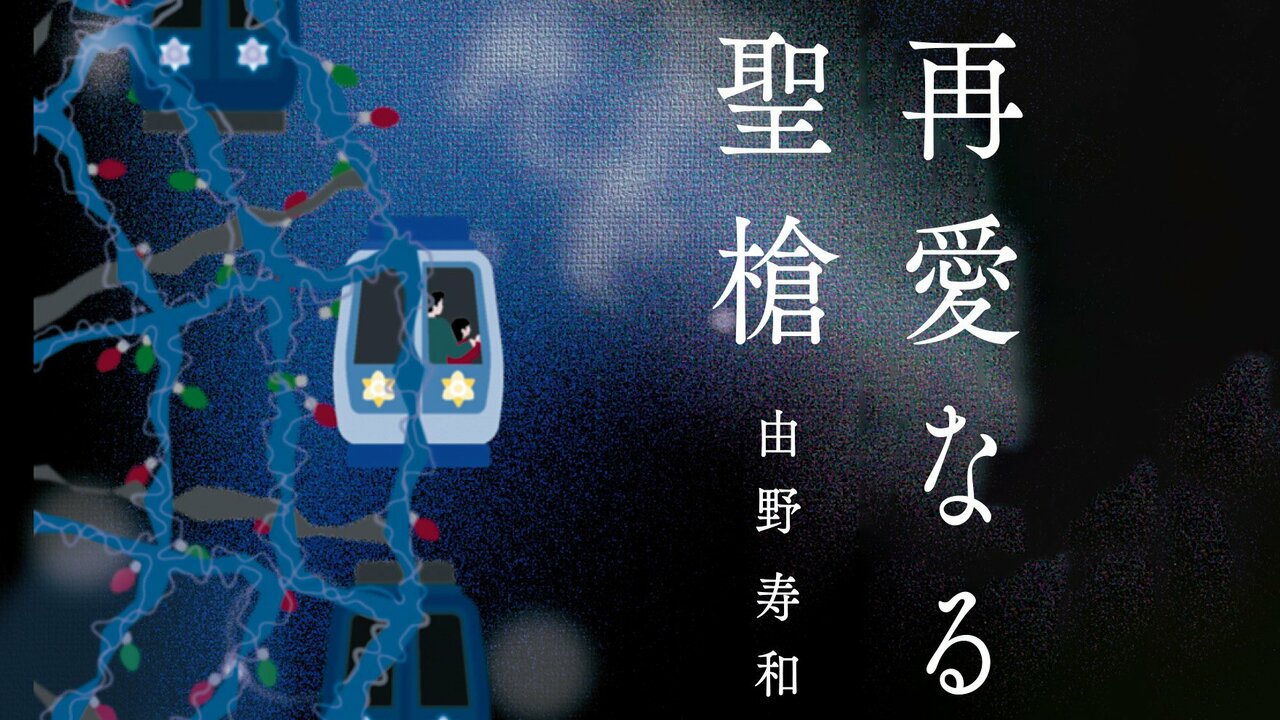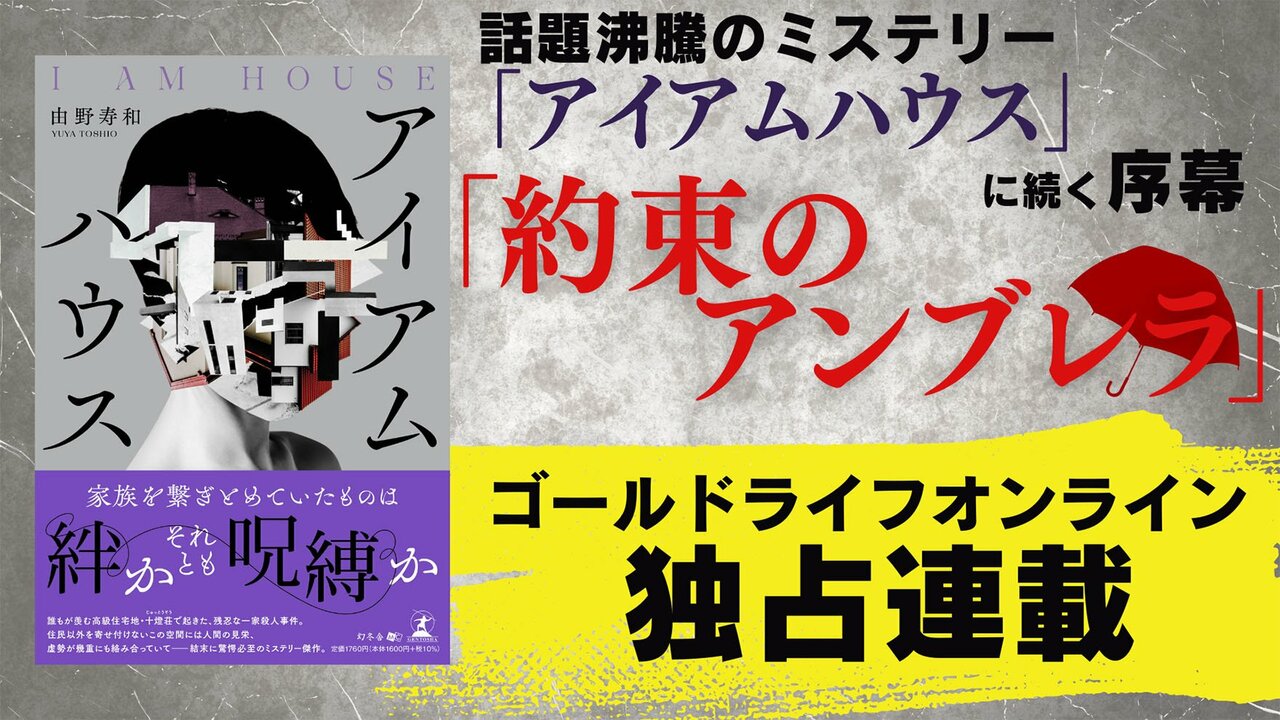一 午前…… 十時三十分 クリスマスイヴ
惟子が時間に遅れるのは今に始まったことではない。交際していた大学時代からそうだった。 かつての惟子は本当に綺麗だった、と仲山は思い出す。いくら遅刻しようが、わがままを言おうが、大抵のことは容易く流せた。理由は単純に可愛いからだ。残念ながら今は違う。
容姿端麗なマドンナは、冷たい大人になった。だが仲山も、別れた妻に恋愛感情は持っていない。子どもがいるからこそ、糸が切れていないだけだ。
「五分の遅刻、か」
そもそも今日は十二月二十四日だ。街はいつにも増してゴミゴミしている。つまり電車の遅延など予測できるはずだろうと、杜ず 撰さんな計画性で全く成長のない惟子に仲山は多少イラついた。
そこで仲山は時計の針に目を落とす。待ち合わせ時刻を三分過ぎていたため、周りを大きく見渡してみた。入場ゲートがここまで混んでいるのだから、ガヤガヤと賑わう園内はどれほどだろう。想像しただけで人酔いしそうな心地になる。しかし、凛の顔を見ればそんなことはどうでもいいと思えるはずだと、仲山はポケットの中から紙を一枚取り出し、ももの上に広げる。そこには一時間刻みの予定表が書き込まれていた。
十一時五分到着と書かれている。惟子が五分遅れるであろうことを仲山は予想済みだったのだ。彼はやはり病的に神経質な男といえる。ただし、惟子と離婚となった理由はそれだけではない。
「パパ!」
その時甲高い声が響いた。ハッと仲山は振り返ったが、どうやら人違いだ。そもそも自分は凛の顔がわかるのか。そう仲山は不安を覚えた。惟子と別れた時、凛はまだ四歳だったのだ。そして惟子が子どもの写真を送ってくることもなかった。
「パパ、か……」
凛は自分をなんと呼ぶのだろうか。パパ? お父さん? それを考える仲山の心臓の鼓動がどくどくと早まっていく。
「ねえ、ちょっと。仲山」
想像した娘の明るい声とは裏腹に、冷たく苗字を呼ぶ声が聞こえた。そう、惟子だ。彼女は出会った時からずっと、仲山のことを苗字で呼んでいた。
ベージュのトレンチコートにボブヘア、化粧は薄めで淡泊な表情を作っている。その隣には手を引かれて歩く女の子がいる。間違いない、凛だ。鮮やかな黄色いコートを着ておめかしをしている。顔はどことなく惟子に似て淡泊だが、目は少し自分に似ているような気がして、仲山は笑みを作った。
「おう、久しぶりだな。電車混んでただろ」
意外とうまく挨拶ができた。連絡は定期的に取っていたが、気まずくないはずのない元女房との再会にしてはなかなか爽やかといえるだろう。
「ええ、久しぶりね。あなたが娘に会いたいなんてどういう風の吹き回し? って最初は思ったわ」
「俺は父親だ。会いたいと言っても罰は当たらないだろう」
「ええ、そうだけど、あなたが父親として何かしたの? お金を振り込めばいいってわけじゃないのよ。親はお財布じゃない」
「ああ、わかってる。すまない」
と仲山は頭を下げた。