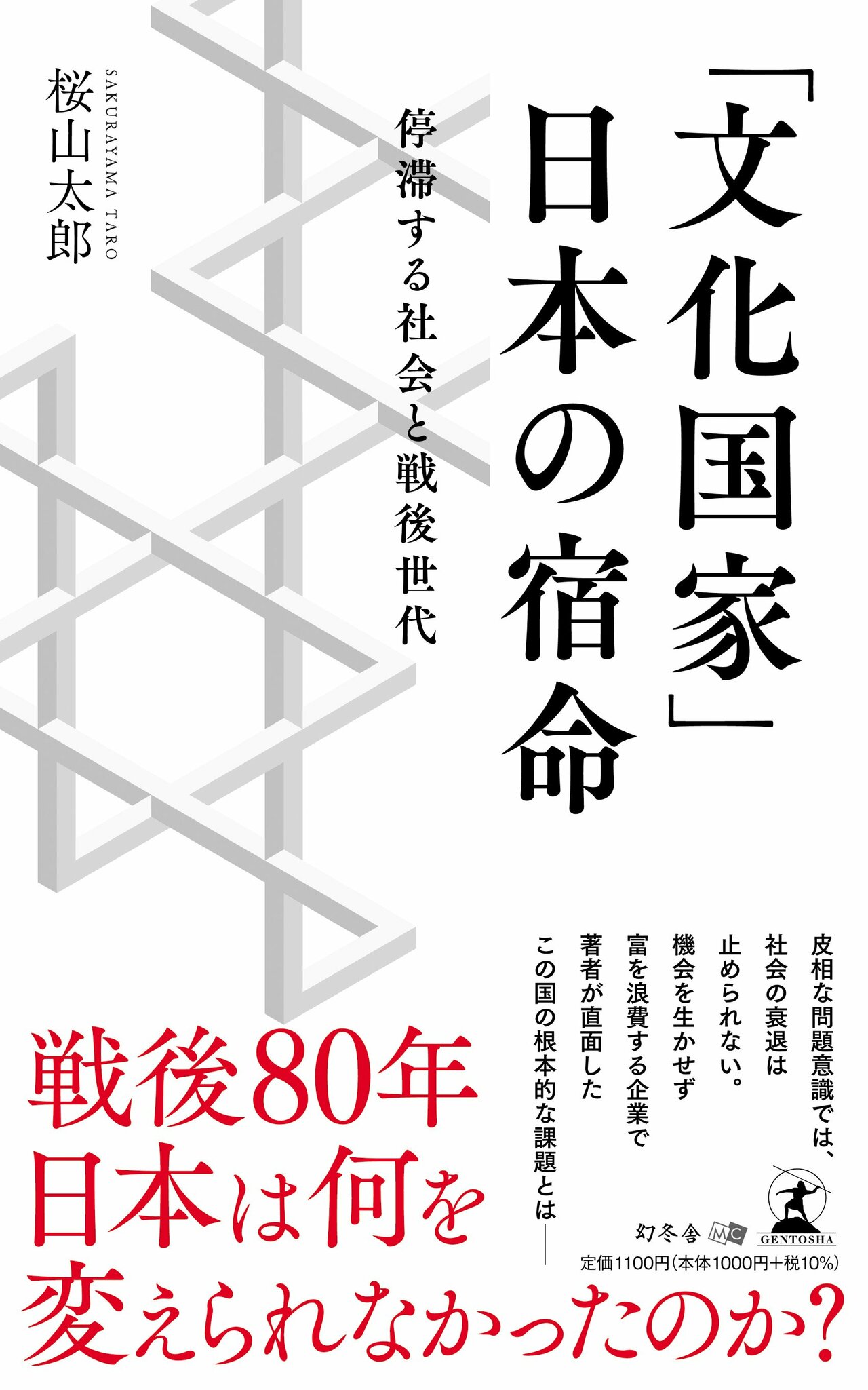ある民間の組織にいた私の周りには、研究の質が下がるのは当然だと思わせる現象が数多くあった。
個別の技術的な課題は解決できても、職務より自身の事情に意識が囚われた人が力を持っているために、仕事はいつまでも大きく結実しなかった。
自制心が乏しい、内省ができない、メタ認知能力が低い、など私情に支配された人たちの傾向はさまざまに表現できるが、本人は世間と文化を共有する常識人のつもりであり、そのことも彼らが自身の営みを見直せない理由の一つになっていた。
心理的な事情で失敗を繰り返す組織で働いていると、人間が内心で何を望んでいるか、何を好むか、何を嫌うか、何を軽蔑するかといったことが極めて重要であるのが実感できた。個々に情念があり、それは文化と結びついており、自分は正しいと信じながら否定されるべきものを他人に求める傾向が、私も含めて多くの人にあった。
情念と文化のコンプレックスは、研究職の世界に限らず多くの組織で失敗や浪費の原因になっている。
よくある話を例にすれば、女性は男性より劣っていると思いたい人々の情念と旧来の組織文化が優位にある組織で、女の人が活躍をするのは難しい。しかしその事情が不合理の原因になっていても、情念や文化を冷静に扱えない集団では実態や因果関係が言語によって共有されることは少ない。
社会の改善と発展を促すキーワードとして、デジタルトランスフォーメーションや脱炭素といった言葉が現代ではよく使われる。
しかし人間はデジタル化や脱炭素化のできない生きものとして存在しており、次元が高いか低いかは別として、人の情念も有史以前から続いている生物学的な条件と不可分の関係にある。多様な事実と向き合わず、一般化した問題の見方、あるいは何々が悪いといった言い方に頼っていては、その実態を把握することはできない。
本書で扱う事実は主に平成中期頃のもので、登場人物は昭和二十年代から四十年代に生まれた人が多い。
社会の発展に寄与する立場の人間として多くの条件に恵まれながら役割を果たせなかった彼らは停滞の時代を象徴する人たちとも見なせるが、いずれも決して悪人ではなく、戦後の日本における文化の影響を多くの人と同様に受けて育った人たちであった。
わかりやすい文脈で語られる問題より現実は複雑だということを考えるために、私の身近にあった一連の事実について随想風に述べてみたい。