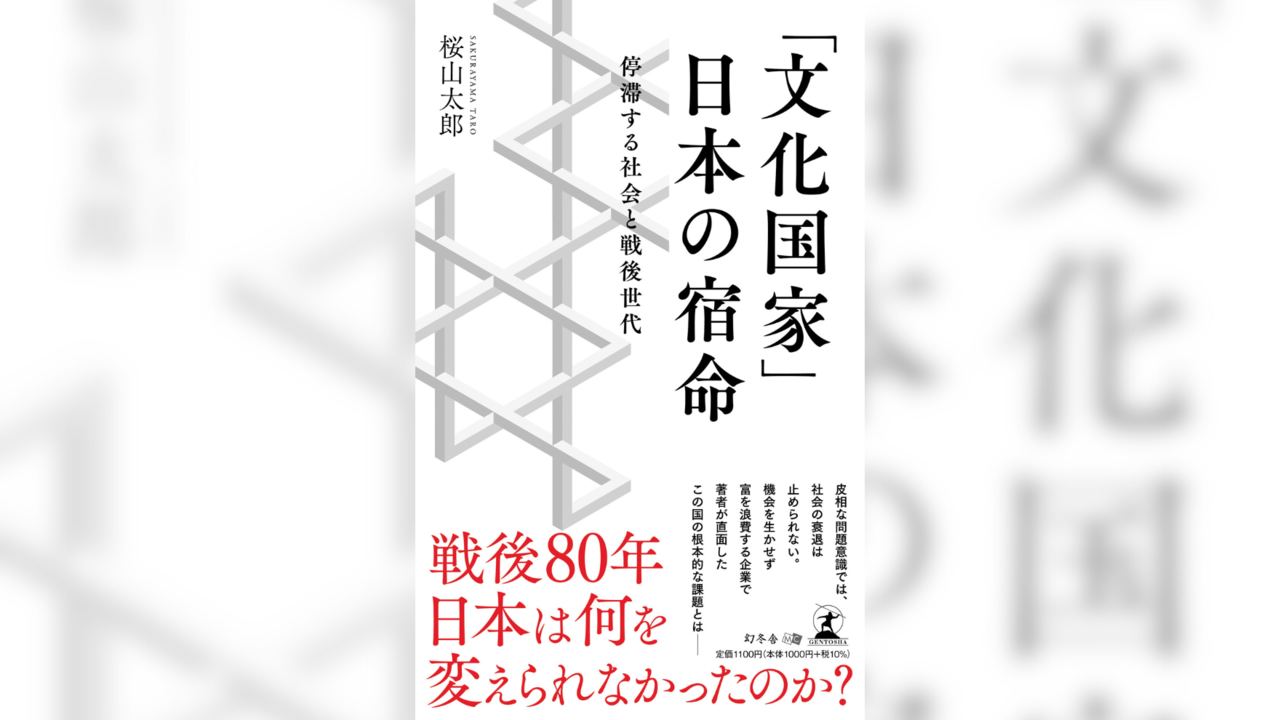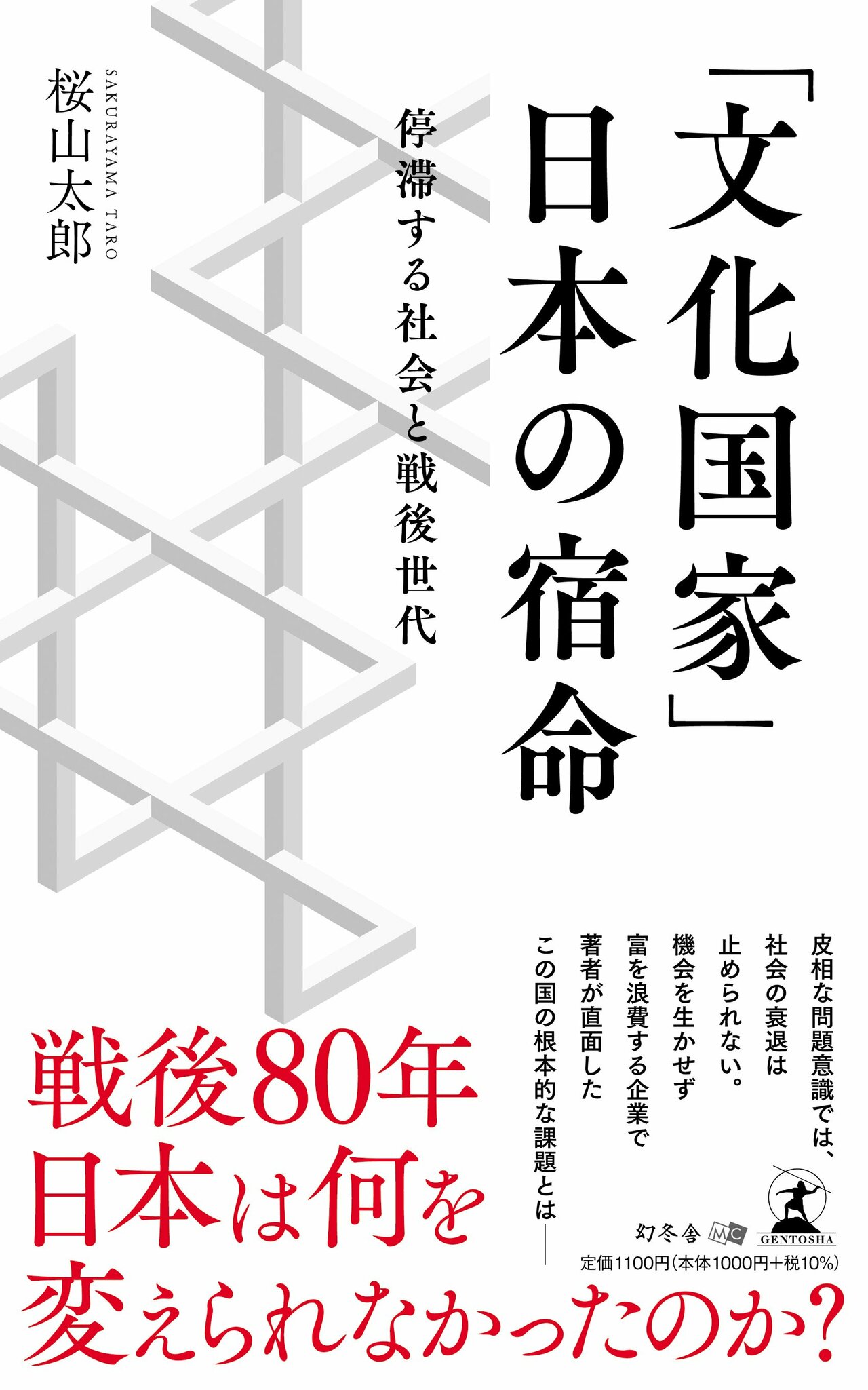はじめに
「日本」をテーマにして何かを述べようとすると、議論に偏りが生じやすい。以前からそう思っていたにもかかわらず、本書のタイトルは表題の通りになった。
日本と日本人について論じた言葉は数多くある。美化することに重点をおいた論じ方があれば、問題視するのが当然といった口調の意見もあり、事実と観念性をどのように交えるかに関しても人によって違いがある。
日本的なものがあると漠然と信じている点では似ていても、着眼点や価値観は明らかに異なっており、多様な見方が散漫に放置されているその状況も、今の日本における現実の一つだといえる。
日本列島や日本語、独自の長い歴史など、同じ日本という概念を支えているものは数多く認められる。
しかし日本人は均質な集団ではなく、性格や考え方の多様性は内外の人が思うよりも高く、その実態をよく認識できないまま一つの日本という曖昧なイメージを共有しているのが、現代のこの国の実情ではないかと思われる。
宮本常一が『忘れられた日本人』で記述したように、昭和前期までの日本は都市化の進んだ地域とは異なる常識や文化を有する人々が各地に暮らしていた社会であった。
日本人だから何々、という言い方は実際にはあまり成り立たず、全体主義に向かって世界の強国を相手に戦争をしていた頃も、日本は国内に多様な現実を抱えていた。
敗戦で新しい憲法ができ、米国流の消費文明が全国に普及し、同じ情報を国民に提供するテレビなどのメディアが発達して、日本は文化の共有度の高い社会になった。
多様化の必要が唱えられるほど社会の同質性が高くなったのは戦後になってからであり、反戦平和の国是と同様、内外のさまざまな条件が可能にした現象であった。
しかし社会的な条件や文化を共有していても内心がすべて同じになるわけではなく、人は共通性と相違を冷静に扱う余裕までは簡単に共有できない。
筆者のいた職場では、むしろ自覚されない文化と私情の双方に人々の思考や営みが支配され、それが原因で対立や衝突が起きていると理解できる出来事が頻繁にあった。
大岡昇平の『野火』の終幕に、「戦争を知らない人間は、半分は子供である」という言葉がある。
筆者の周りにいたのは戦後の豊かな日本で育った人たちであり、だから子供のように争っていたのだともいえるが、同様の事情は戦前の社会にもあった。
国家を破滅の淵に追い込む戦いの連鎖を日本が断てなかったのは、当時の要人が自らの文化と行動原理を見直せず、個々の立場と考えで解決を夢見たからであった。