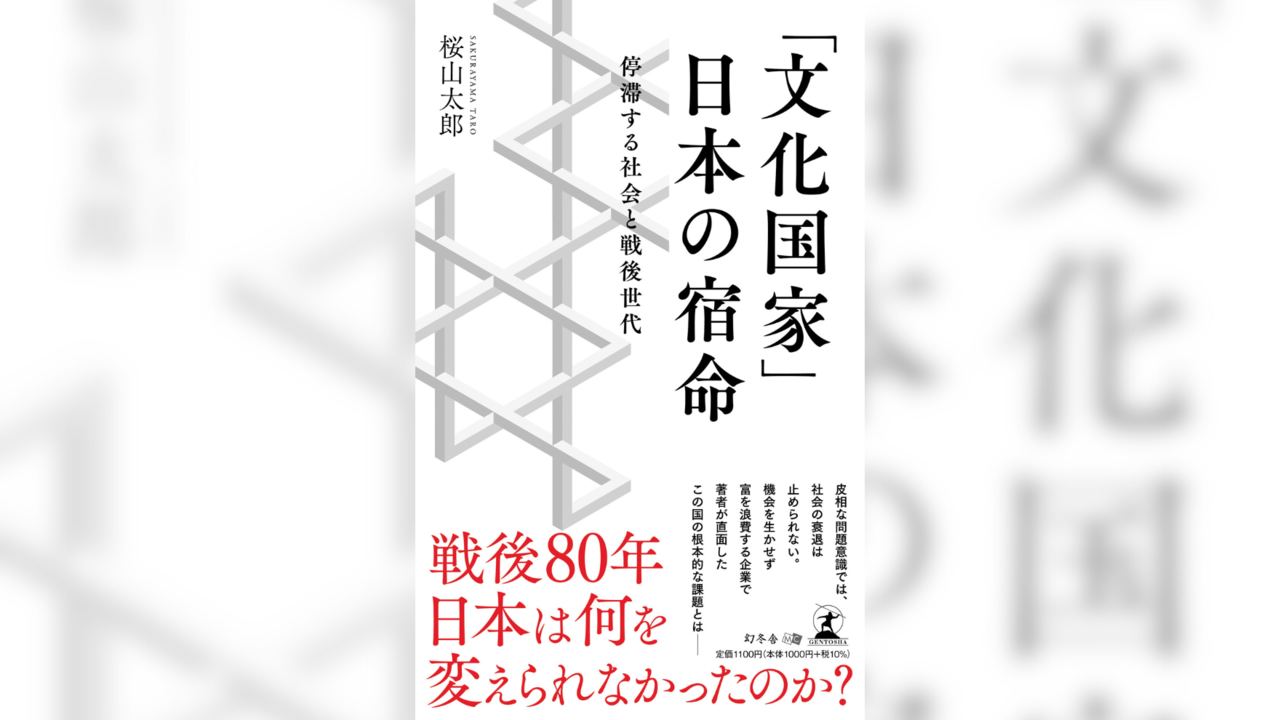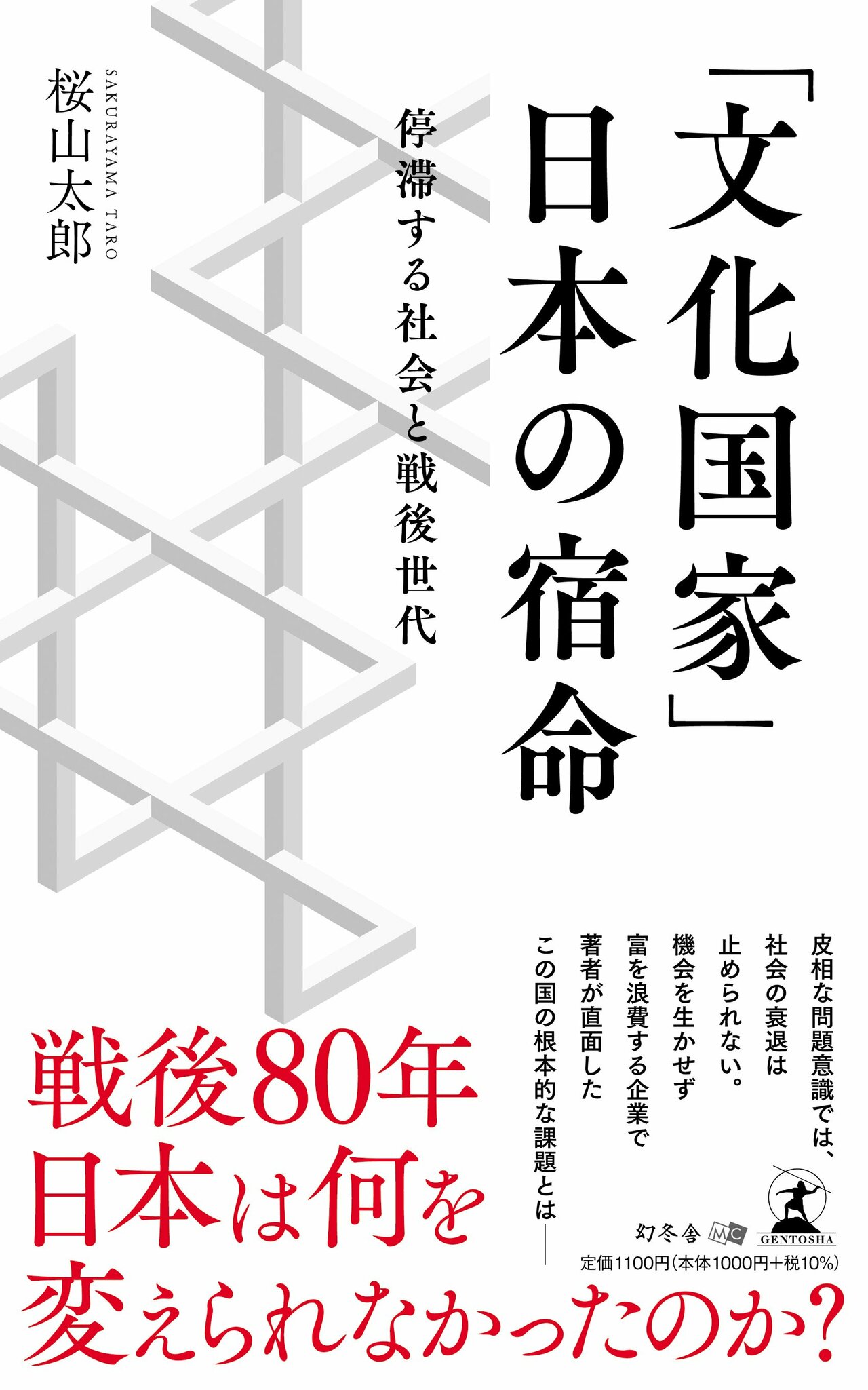【前回記事を読む】幸せなおじさんたちの罪――。社会問題を語る「バブルおじさん」は、果たして若者世代と同じように問題意識を共有できているのか?
第一章 幸せなおじさんたちの罪
―崩壊する「科学技術立国」の現場
問題意識と語られない情念
岸田文雄氏が首相に就任して「異次元の少子化対策」というフレーズを使い始めたとき、私は面白い表現だと思った。
以前から「異次元の」という言葉が世間で使われすぎており、「百年に一度の」と同じでいずれ若い人たちが気軽な誇大表現として使って終わりになるだろうと予測していた矢先に総理大臣が政治的スローガンとして大真面目に口にしたのも面白いと感じた理由だが、次元の低い方も異次元に含むのであれば、意外に使える表現ではないかと考えたからであった。
実際に少子化に限らず世の中で問題とされる事態では、低次元な面こそが核心だと思われることが多い。
そして次元が高いと思われていることと次元が低いと感じられることを同じ口調や文体で述べるのは難しく、発言の内容や態度で品位や良識が世間から問われる立場にある大臣や国会議員は、その困難を踏まえて整理された言葉を発するのが仕事になっている。
研究職という責任がそれほど重くない立場にいた私の場合、トラブルの多かった職場の実態を他者に伝えようとしたときに、その難しさを実感した。
私のいた組織がなぜ敗者になったのかについて述べようとしても簡単にまとめられそうにないのは、その理由が多岐にわたっていて既存の文脈に収まらないからであり、事態の言語化の難しさは考えてみると当時の敗因の一つでもあった。
研究をする能力が近年日本全体で衰えていることを示唆するデータがある。
社会の望ましい発展のためには科学や技術の向上を図る必要があるという認識は多くの人に共有されており、研究開発力の低下を国力の衰退と関連づけて問題にするのは容易だが、少子化と同様、表向きの議論では語られないところにもその原因はあり、それは投じる国費を多少増やした程度では解決できないのではないかと思われる。