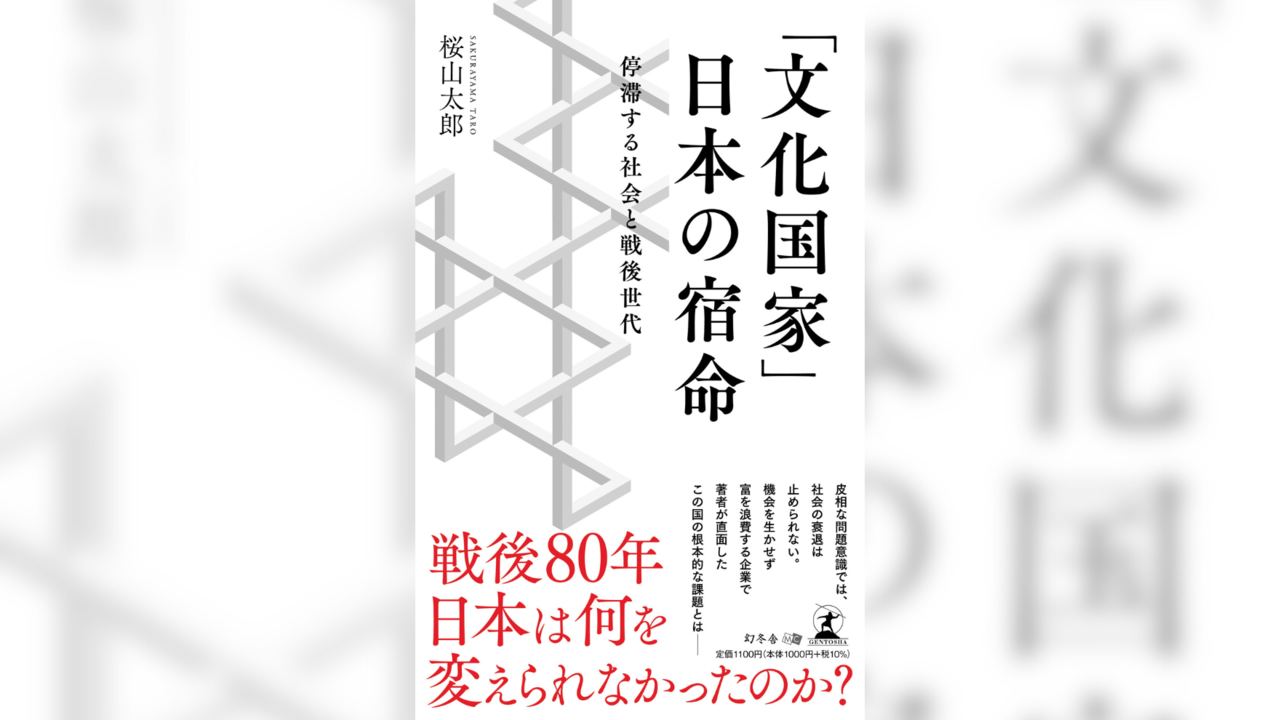【前回記事を読む】二人きりの残業、上司の手が迫った瞬間に響いた拒絶の声――目撃した私は…
第一章 幸せなおじさんたちの罪
―崩壊する「科学技術立国」の現場
ベンチャー企業X社の事例
しかしP氏の夢は、自身の力不足を省みない性格が生み出す幻に過ぎなかった。三十代の頃に大学院で指導教官だったS教授やT氏の力で大きな仕事の端緒をつくっていたとはいえ、彼は独立してそれを発展させられる段階には達していなかった。
卓越した独創性を発揮したくても本当に何をしたいのかが彼自身の中で決まっておらず、彼が私的な願望と思いつきで何かを始めようとすると、下の負担が増すばかりであった。
自己の限界を認めないまま創造性を誇示しようとする彼は、人から聞いた話を自分の発案だと思い込むというT氏の言葉を裏付ける行為を繰り返し、さらに実験結果を私の見ている前で堂々と改ざんしたこともあった。
P氏の夢想する物語の世界は、他にも自滅する要素を抱えていた。彼は昔から教育者として成功する夢を抱いていたらしく、自分の教育力に感化された若者たちの力で、というのも彼の絶対視するX社の成功物語の条件の一つだった。
その夢のために彼は部下に純真な生徒であることを執拗に求めており、親会社の金を使って学校ごっこをする自分の営みを妙だとはどうやら少しも思っていなかった。
「理想が大事なんだよ」と語るP氏には、未来の成功者として自己を規定する人間の強さがあった。
彼が多くの人から批判されても笑顔でいられたのは、ベンチャーを成功に導いた中心人物として世間から拍手喝采される日がくるのを信じていたからであり、学園ドラマ的な設定も来たるべき未来において世の中に向かって語られる成功神話の一部になっていた。