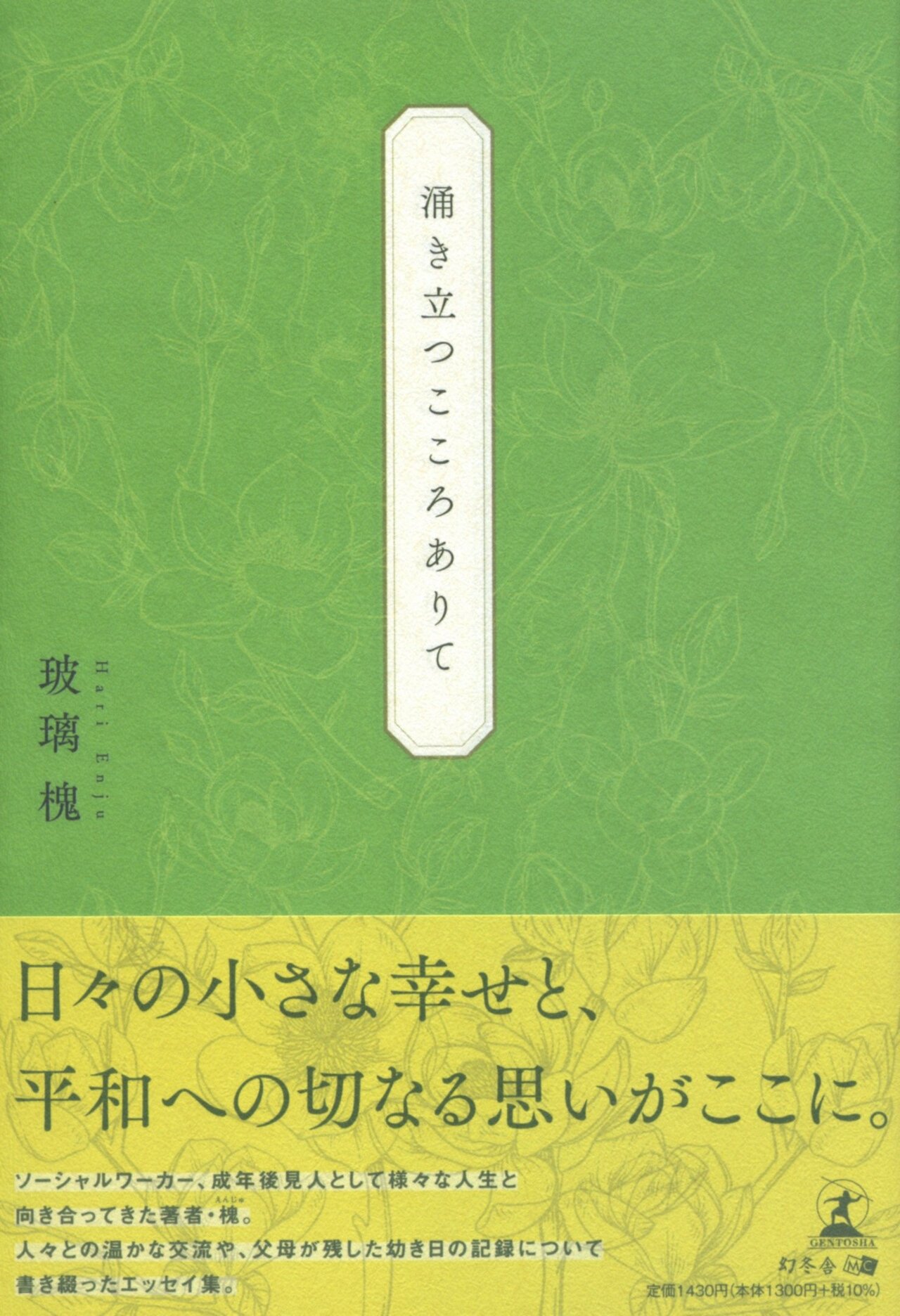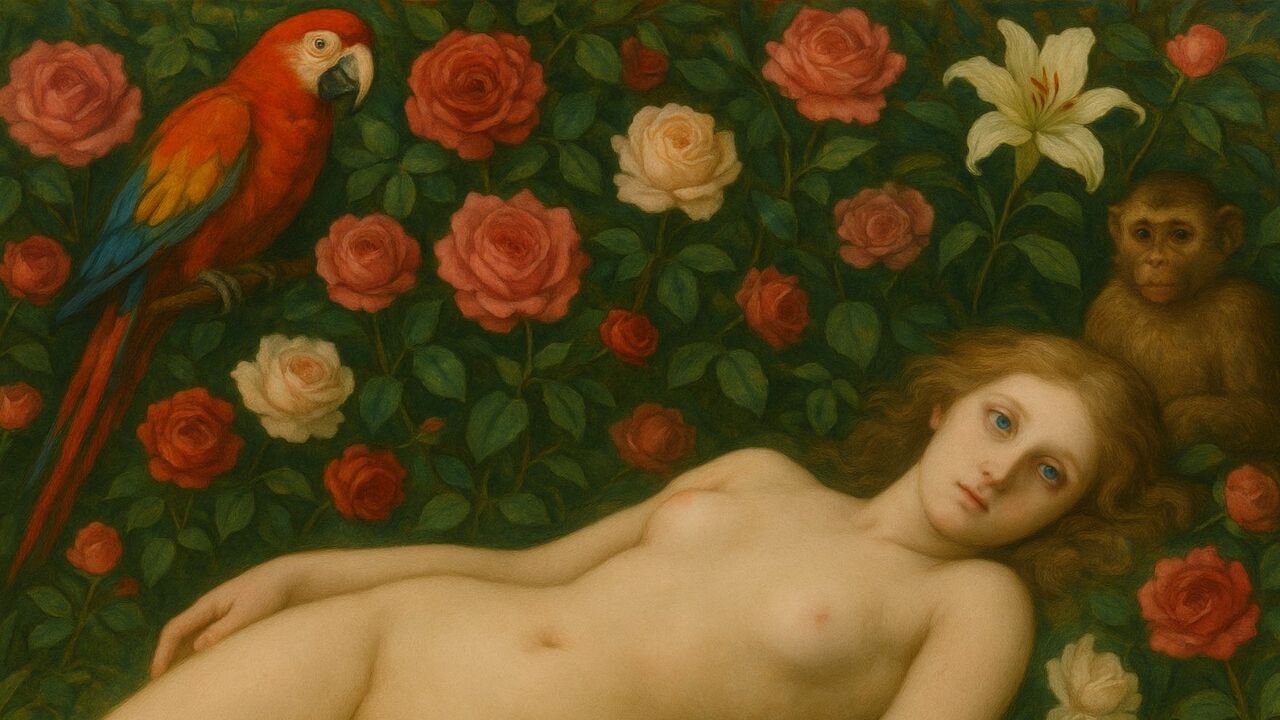夢のある就職ではなかった
これまで働いていた中学校、その真向かいの精神科の病院に、槐は事務員で採用された。夢のある就職ではなかったが、親に生活費を入れることが、槐には重要だった。出勤初日に、事務長さんが「外よりも病院は安全ですよ、安心して働いてください」と言ったが、安全の意味は分からなかった。
病院は桜の景勝地の小高い丘を見上げる低地に、多摩川支流の川を背にして建っていた。病院用の橋を渡ると、由緒ある木造の講堂と管理棟があった。プールが表玄関横にあるのも珍しかった。患者さん用のプールだと、しばらくして知った。木造平屋の病棟が並び、南側には患者さん用の運動場や、西側には、農作業ができる田圃もあった。
槐の職場は、管理棟を通り抜け、病棟への通路に沿った「医事臨床社会活動部」の事務室である。医療事務は六人、ソーシャルワーカーが二人、部長は副院長のラン先生が兼務であった。
二人のソーシャルワーカーに出会い、人を支える、とてもやりがいのある職業だと思った。将来槐もなりたいと憧れたのだった。
医療事務で病棟にカルテを取りに行く仕事があった。病棟の入り口のブザーを押すと、小窓から看護師さんが槐を確認し、ドアを開けてくれる。入室と同時にガシャンと鍵がかけられた。槐はカルテを受け取り、ドアを開けてもらい病棟から出ると背後でガシャンと鍵が閉められた。
どんなことでも仕事には向き合った槐だが、この仕事だけは負担だった。ソーシャルワーカーになったらそんなわけにはいかないと、その時はまだ考えられなかった。
一人前に
槐は、初めて死者を送る仕事をした。
病院の東側の山の裾に、コウモリが棲む、戦時中の防空壕の洞穴が残っていた。その近くに一戸建ての霊安室の建物があり、医事係の槐は患者さんが亡くなると、お線香を上げに霊安室に行った。
入口の引き戸を開けると左側に小さなのぞき窓があり、その窓の前にはお線香を上げる棚が備えられ、窓の奥が遺体の安置場所であった。病理医の小柄な女性のコデマリ先生が、そのまた奥の部屋で、遺体の解剖をしていると聞く。
槐は遺族が通夜で泊まる部屋を掃除し、お茶の道具や布団等を用意した。一九六五(昭和四〇)年頃で冷暖房の設備もなく貧弱であった。お線香を準備し、遺族に患者さんのお小遣いと入院費を精算した。葬儀は秘かに行われ、出棺は病院用の橋のたもとの守衛室前で、医師と看護師たちで見送った。
槐はとても大切な場に立ち会い、社会人の役割を果たせたようで誇らしく思った。そして一人前になったと思った。