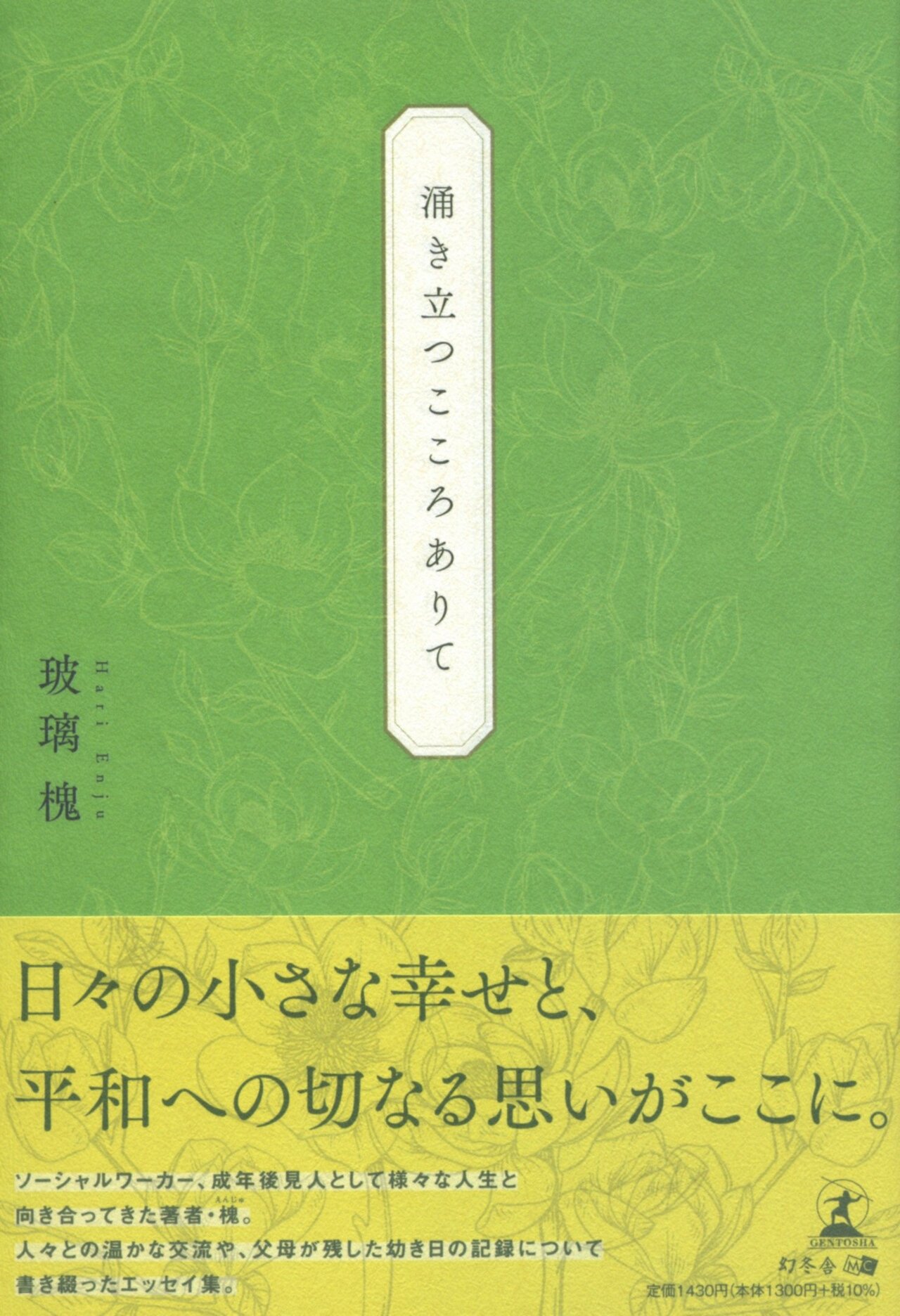【前回の記事を読む】槐は死者を送るというとても大切な場に立ち会い、社会人の役割を果たせたようで誇らしく思った。そして一人前になったと思った
第1章
ラン先生「大学へ行くか」
医事臨床社会活動部長のラン先生は、戦時中は海軍の軍医であったという。背も高く、面長な鼻筋の通った、白髪交じりで、とんがった頭を撫ぜるのが癖だった。
先生は、槐たちと一緒に掃除をする。先生は自分のロッカーを開け、男性職員に「おい、見てみろ」と、まじめに言う。ロッカー扉の内側に、薬の広告用カレンダーのセミヌードの写真だった。
月初めの一週間は医療請求事務に追われる。ラン先生が請求書を慣れた手付きで、一枚一枚点検する。仕上がった後は「おいラーメン食いに行くか」とラン先生はみんなに声をかける。食養部職員の息子さんが「しゅうちゃん食堂」を病院近くで営んでいた。
先生はお酒を「一杯だけ飲ませてもらうな」と言って嬉しそうだ。槐を「スペイン系のエキゾチックな顔だね」と言う。槐はそう言われて、途端に嬉しくなり自信が持てた。ラン先生の屈託ない接し方に、魅了されたのは槐だけではない。
病院に就職した年の、夏の終わり頃だった。
ラン先生が、槐に「大学に行くか」と声をかけてくれた。
「はい行きたいです」。
「そうか、分かった。推薦しよう」
槐は「シャガさん、ナバナさんのようになりたいです」と、同じ職場のソーシャルワーカーお二人の名前を、思わず言っていた。僅か数秒間の思わぬ会話だった。
二一歳で、明学の二部に入学した。ソーシャルワーカーの道に一歩踏み出せた。槐に光を与えてくれたラン先生だった。
槐は一日も休まずに、明学を卒業すると決めた。何気なく就職した病院で、その後の人生を決定付けることになるとは、知る由もなかったが、ラン先生は槐の将来に見通しを立ててくれた。
卒業と同時に山梨県内の病院に医療相談員として就職が決まった。寮生活用の布団を送る間際になって、槐は山を見て過ごす自分を想像した。不安な気持ちが大きくなり断ってしまった。これまでの病院の恩義に、特にラン先生へ槐は報いることができなかった。