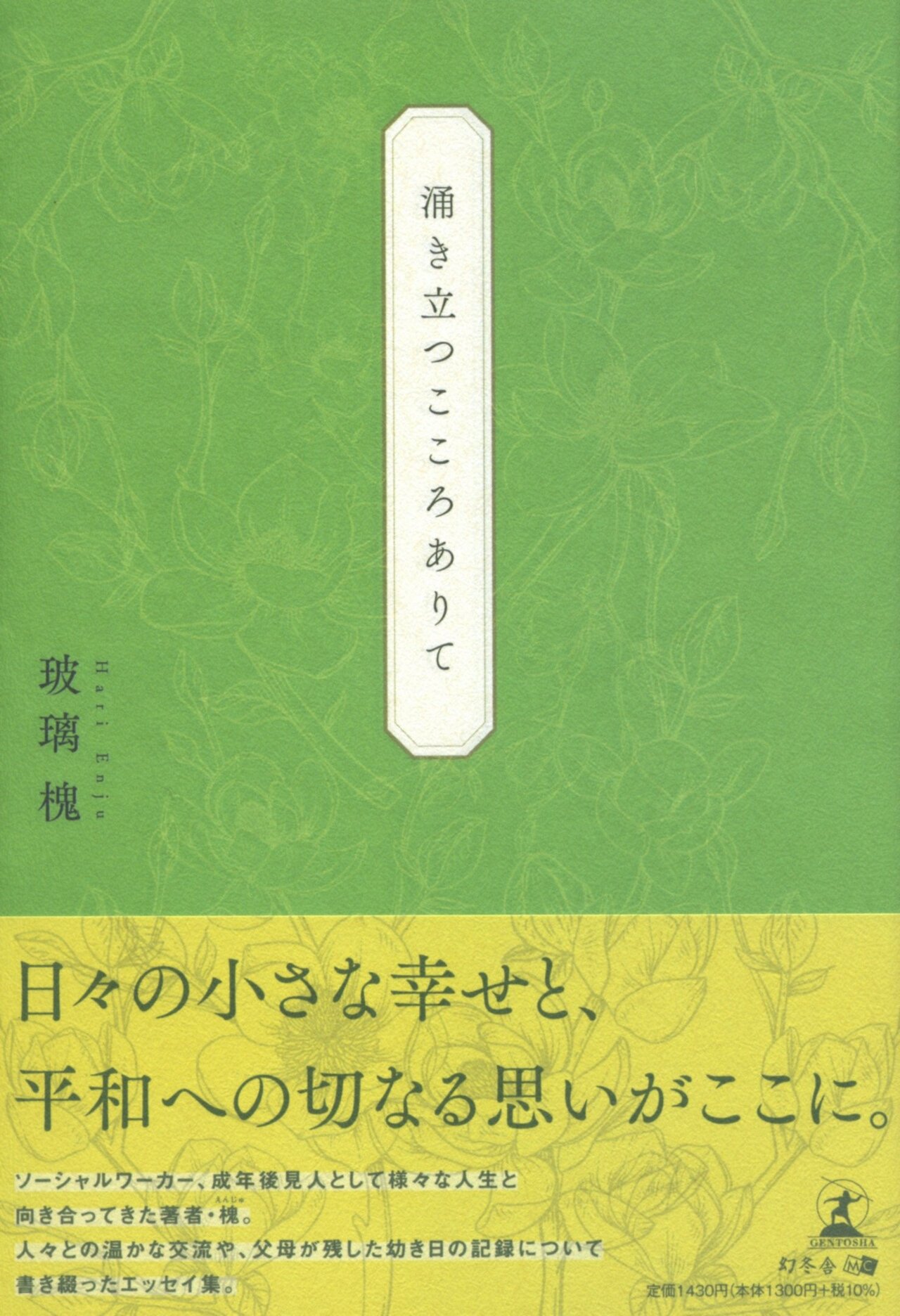アトリエのある家
医事臨床社会活動部の事務室は、午後四時半になると、シャガさんとフキさんと槐は「行ってきます」と三〇分早く、職場を退出する。シャガさんは明学で修士を目指していた。フキさんは、槐と同じソーシャルワーカーになるために明学の一年先輩であった。
槐が病院に就職したばかりの時に「浦島太郎伝説がある木曽路で、寝覚の床にある寺の次男坊です」と眼鏡越しに、優しいくりくりした目で、自己紹介してくれたのが、シャガさんとの出会いであった。
お寺で育ったシャガさんは、柔和な人柄と毛筆もペン字も達筆であったのも、頷ける。
上司のラン先生が「シャガ君は大学でオールAの生徒だよ」とおっしゃった。シャガさんは、ラン先生の弟子で、フキさんはシャガさんの弟子に思えた。
槐は明学を卒業し、転職しソーシャルワーカーになってしばらく後のことだった。
「家を建てたので来ないか」とシャガさんが声をかけてくれた。
早速に病院で同僚だったアマナさんと、多摩動物園と隣り合う丘の洋館を訪ねた。
「リンドウさん、来たよ」と二階のアトリエに向かってシャガさんが、画家である妻のリンドウさんに声をかけた。
「どうぞ上がってきて」と可愛らしい声だ。居間の九官鳥がおまけに「どうぞ」と言う。槐たちは、気兼ねなくアトリエに入った。
野に横たわる裸婦と、骸骨の絵にくぎ付けになった。全ての絵の裸婦が、薄桃色の肌と、青く透き通る、うつろな目をしていた。
裸婦はリンドウさんご自身と分かる。それぞれの絵には、描きこまれたオウムや猿に蛙や虎、バラやユリが、主役の切なくあやしく美しい裸体を、大切にするように描かれ、圧巻であった。
リンドウさんが、身近な画家で身近な詩人に思えた。
シャガさんは「リンドウさんがアトリエに入っていいと言うのは珍しい、どうして気に入ったのかな」と話された。
槐は、年賀状に即興詩を載せたことがあった。リンドウさんの目に留ったとシャガさんが話してくれたのを思い出した。何か通じるところがあったのかもしれない。
“わたしがわたしを好きになれる”、リンドウさんの不思議な魔力の絵に出合えた。こうした丘の上の、アトリエのある家に、シャガさんは暮らしていたのだった。