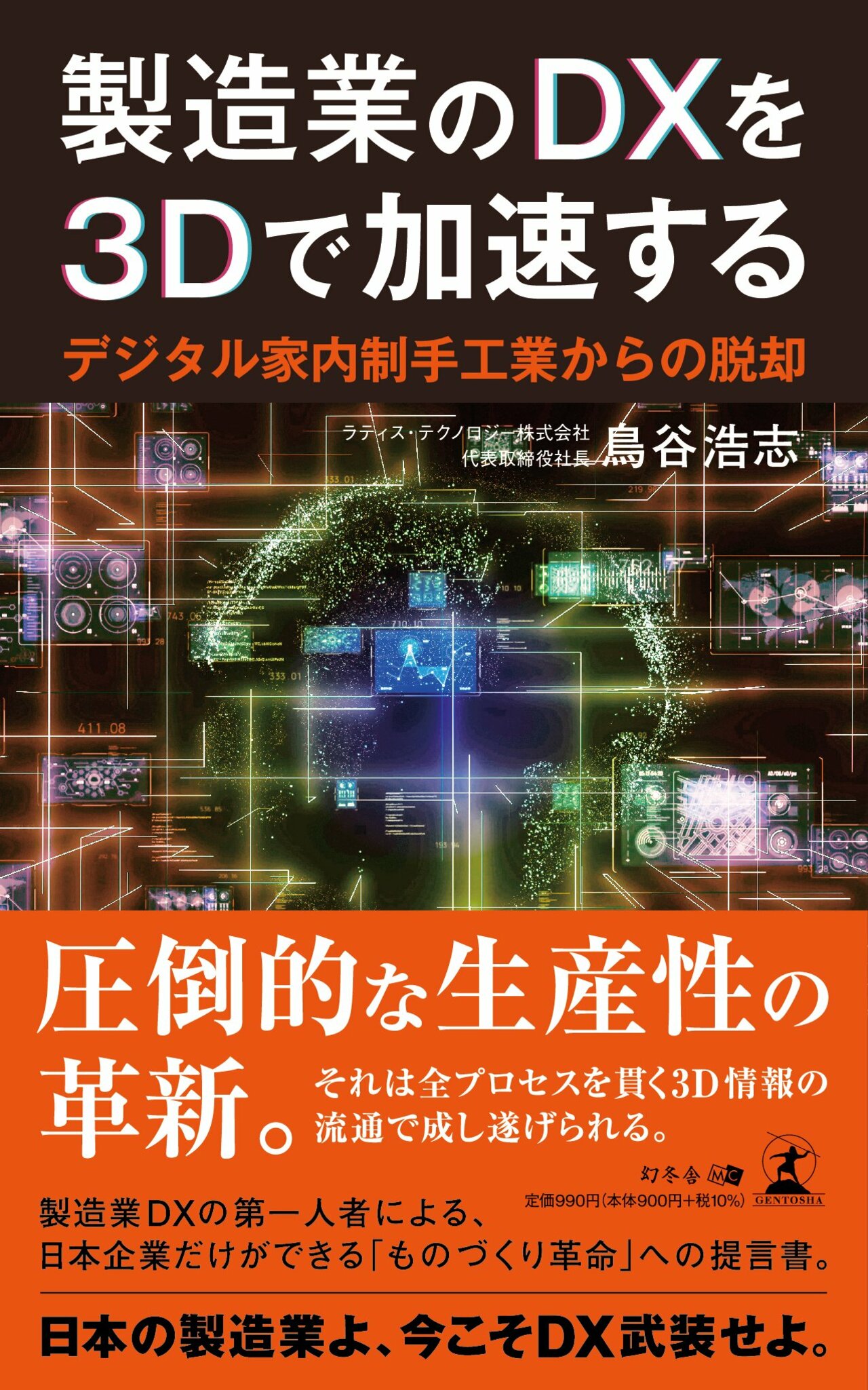Industrie4.0を振り返る
2022年の秋、Industrie4.0と日本のあるべき姿をテーマにFA業界の重鎮と対談をした(QR05)。

主役の一人は、三菱電機株式会社(以下、三菱電機)や三菱電機エンジニアリング株式会社(以下、三菱電機エンジニアリング)において、FA機器の開発設計を推進した元役員の尼崎新一氏。
もう一人は、その三菱電機とラティスの双方の販売パートナーである技術商社の株式会社立花エレテック(以下、立花エレテック)の元専務、山口均氏である。
山口氏はFA業界の黎明期からNC装置やシーケンサ(三菱電機製のPLC)の販売と普及に努め、さらに三菱電機のFA機器販売から、システムとしてのFAソリューション販売へと舵を切った方である。
尼崎氏はFA機器制御の中核を担うシーケンサの開発を主導し、その後、三菱電機のスマートファクトリーを実現するためe-F@ctoryをけん引、シーケンサのAPIを公開するなどアライアンス戦略を推進していった。
2011年、そこに現れたのがドイツの推進するIndustrie4.0であった。今ではDXという言葉にすべて集約された感があるが、Industrie4.0とは何だったのか、お二人の話から総括してみよう。
当時、ドイツを視察した尼崎氏は、アメリカのGAFAに代表されるIT企業がデータをすべて吸い上げようとすること、また、中国の製造業が低コストを武器に世界進出を始めたことに、ドイツは強い警戒感を持っていたと指摘する。
その解決策こそ官公庁が一体となったECM(EngineeringChainManagement)軸での一気通貫による効率化、Industrie4.0だったのである。そこで起きていたことを以下に総括しておく。
① Industrie4.0 とは、設計・生産・販売・保守・サービスまでをECM軸での情報の一気通貫によって、事業のスピードアップを図るとともに、新しいビジネスモデルを生み出そうというコンセプトである。
② 実際にSAP社・Siemens 社・Trumpf 社・SICK社などのドイツ企業のソフトウェア・工作機械・FA機器・センサを活用すればECM軸一気通貫が実現でき、その仕組みを輸出しようとしていた。
③ Siemens 社は自社にない技術やソフトウェア企業を次々に買収し、Industrie4.0 のコンセプトを一気に実現していく。加えて、産官学で協調し、ドイツ全体で標準化を進め、自然に効率が上がっていく仕組みを作っていった。
【イチオシ記事】一通のショートメール…45年前の初恋の人からだった。彼は私にとって初めての「男」で、そして、37年前に私を捨てた人だ
【注目記事】あの臭いは人間の腐った臭いで、自分は何日も死体の隣に寝ていた。隣家の換気口から異臭がし、管理会社に連絡すると...