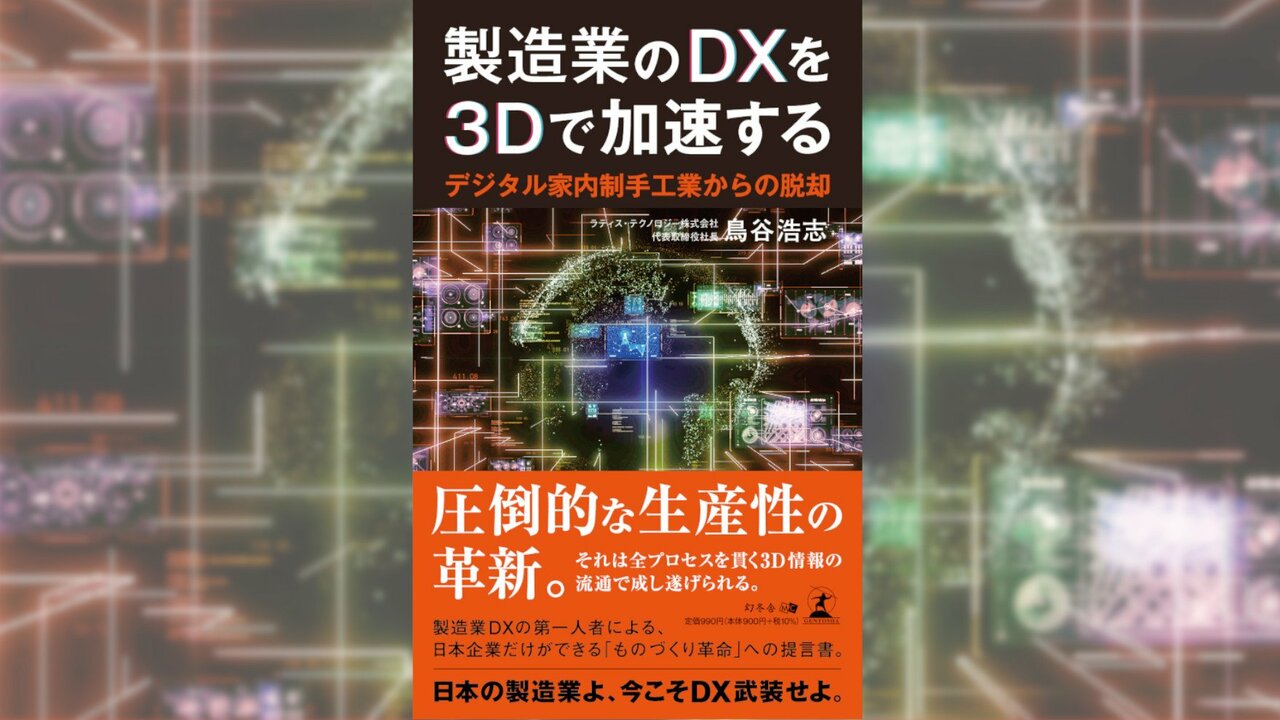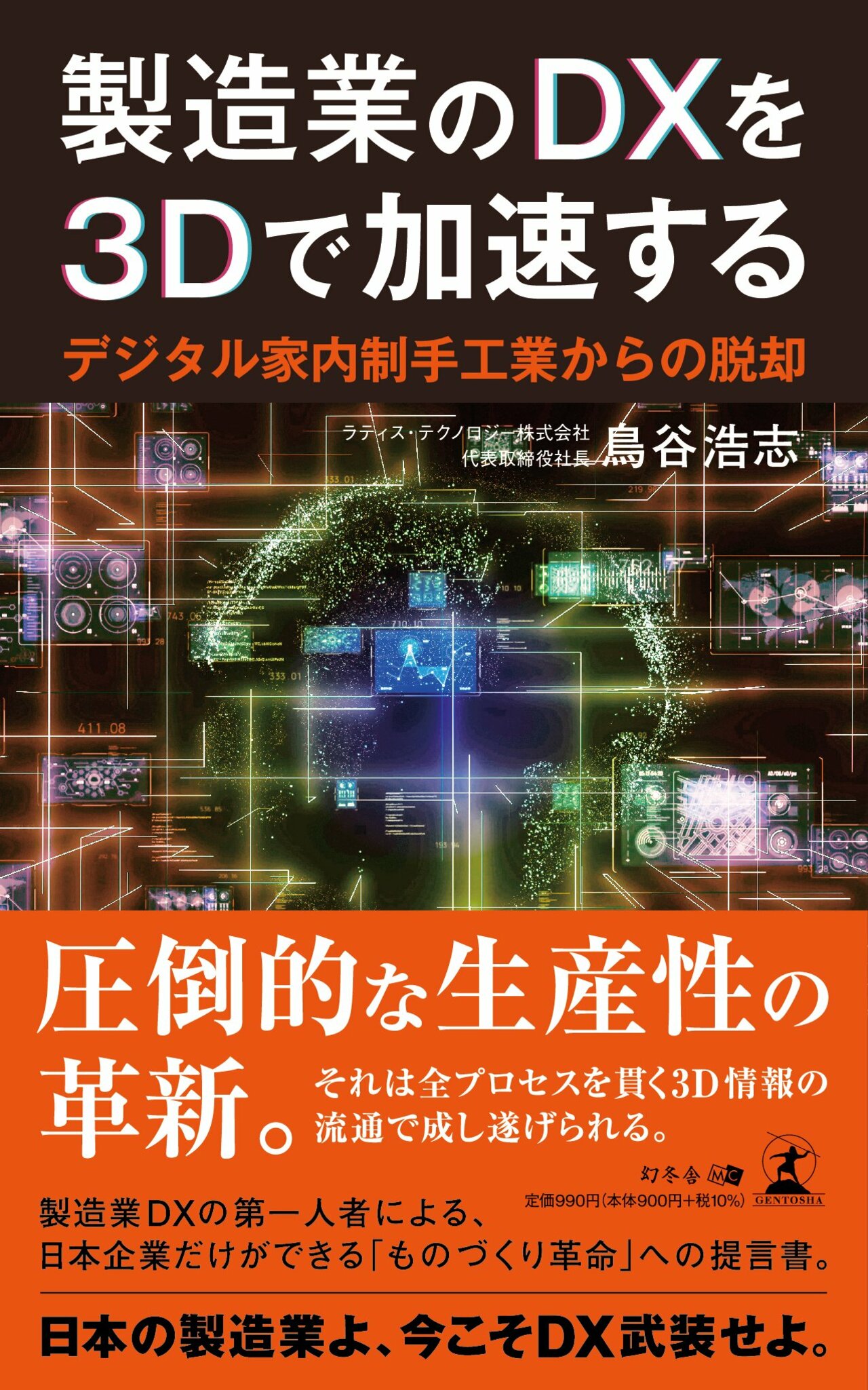【前回の記事を読む】3Dデジタルツインで製造業DXを実現、全社的な生産性向上を図る
第3章 ドイツ発Industrie4.0に学ぶ 製造業DX×3D
このところドイツとは縁を感じる。2022年11月にドイツ語圏のパートナー企業やユーザー企業を訪問、3D活用の現状と課題の議論をしてきた。その帰国直後には、サッカーワールドカップで日本がドイツに劇的な逆転勝利。滞在中に勝たなくてよかったと思ったものである。
最近のドイツは、ロシア産ガス供給減少への懸念によるエネルギー価格の高騰や新型コロナの影響でサプライチェーンが混乱し、物価も高騰。経済の見通しは冴えず、12月にはクーデター未遂事件が発覚するなど不穏な出来事もあった。
それでも何か学ぶことはあるだろうと、帰りのルフトハンザ航空の中で読んだのが、『ドイツではそんなに働かない』(隅田貫著、角川新書、2021年)である。

ドイツから学ぶこと
当書は、労働時間が日本より年間300時間短く生産性が1・4倍のドイツについて、その働き方を日本と比較しながら書いたものである。特に以下の3点が記憶に残っている。
①ドイツには「人生の半分は整理整頓である」という諺があり、整理整頓に時間を費やす。その結果、探し物が減るなどにより、生産性が上がる。
②ドイツは仕組みを作って定着させることを得意とする。たとえば、企業が従業員を解雇しやすくし、国は失業保険を減らす一方、職業訓練を推進、雇用あっせんを強化することで失業率を下げるというハルツ改革に2002年から着手し、社会全体の生産性を上げた。
③ドイツ人は「人は人、自分は自分」と割り切る。ただし、人へのリスペクト、つまり異なる考え方をする人に対し「そういう考え方もあるよね」と尊重する習慣がある。相手の意見に耳を傾け尊重し、相違点を明確にした上で互いの溝を埋め、落としどころを探るというディスカッションができる。
ものづくり変革を促すIndustrie4.0のコンセプトはドイツで生まれた。このIndustrie4.0が設計と製造に関する情報を整理し、産官学でシステムを整備し、製造現場でも利用できるように双方で議論を尽くしていくものだと考えると、これがなぜドイツで生まれたか合点がいく。