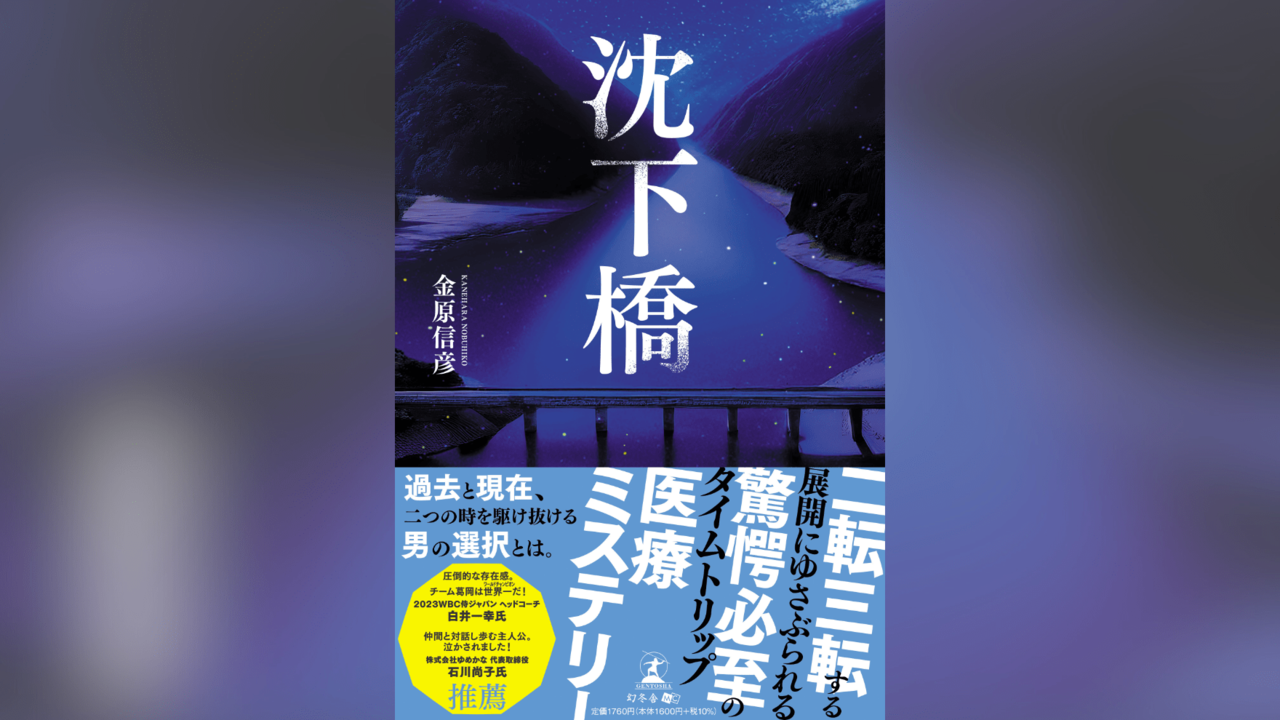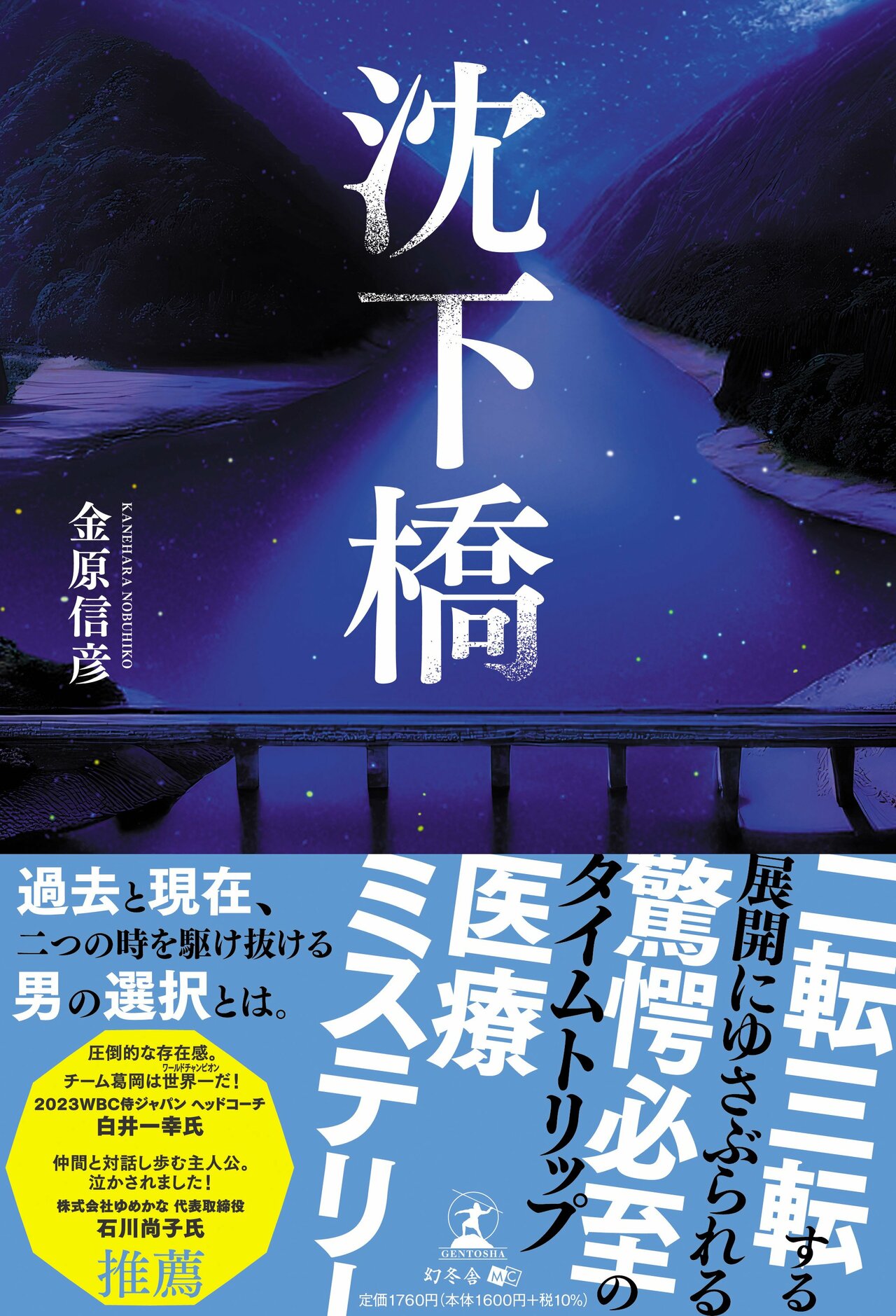【前回記事を読む】自分が経験したはずのない夢――小学生の自分の前には母の死化粧。沈下橋の言い伝えとともに驚愕の医療ミステリーが幕を開ける
第一幕 邂逅
一九九四年三月
その晩、哲也は泥酔した。
少し前に、渋沢製薬中央研究所の同じ建屋にいる直属の上司、研究所所長の奥貫和俊(おくぬきかずとし)から、医薬品営業本部東京支店への異動の内示を内線電話一本で通告されたときには、まだ現実感がなかった。
そして三月上旬の今日、四月一日付けで人事異動が発令された。左遷といってもよいその辞令を見て、哲也は自分の置かれている立場の厳しさをはっきりと自覚した。
中央研究所所長の奥貫は、次の株主総会で取締役研究開発本部本部長に選任されることになった。
代わって、研究開発のライバルである塚田耕治(つかだこうじ)が奥貫の後釜に座った。哲也は医薬品営業本部東京支店付学術担当という異動だった。研究者としてのラインを完全に外された左遷、降格人事だった。
(もう白衣を着ることもなくなる……)
その日は一人住まいのマンションにまっすぐ帰る気にはなれず、神田駅近くのビルの地下にある行きつけの小料理屋で痛飲した。
「葛岡さん、大丈夫? 今日はちょっとピッチが早すぎないですか。何かつまみを出しましょうか」
いつも愛想の良い小太りの店長が心配そうに声をかけた。
高知県出身の哲也は、アルコールはいくらでもいける口で顔にも態度にも出ないほうだが、立て続けに手酌で焼酎のロックを飲んだので(少し飲みすぎているかな)という自覚はあった。
「申し訳ない、ゆっくりやるよ。今日は何か良いのある?」
「そうっすね。高知は室戸の金目鯛が入ってます。あと、砂肝の唐揚げはどうですか。少し脂っ気を摂ったほうが良いでしょう」