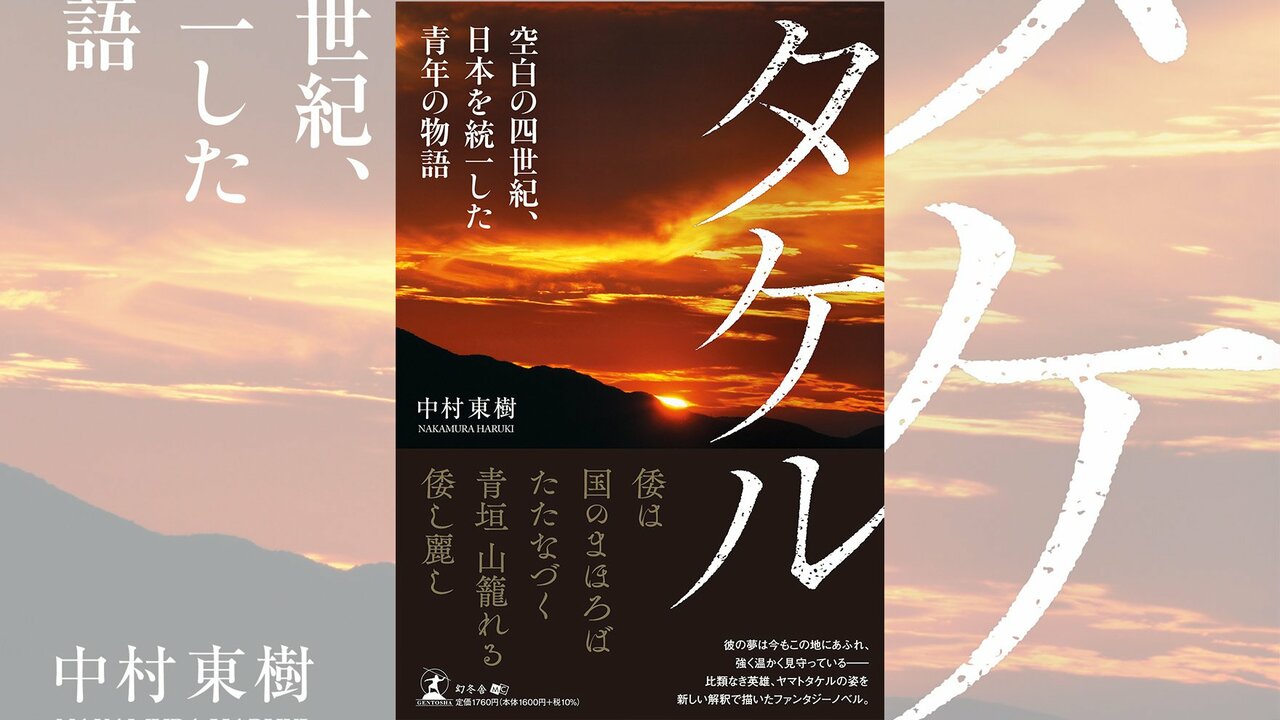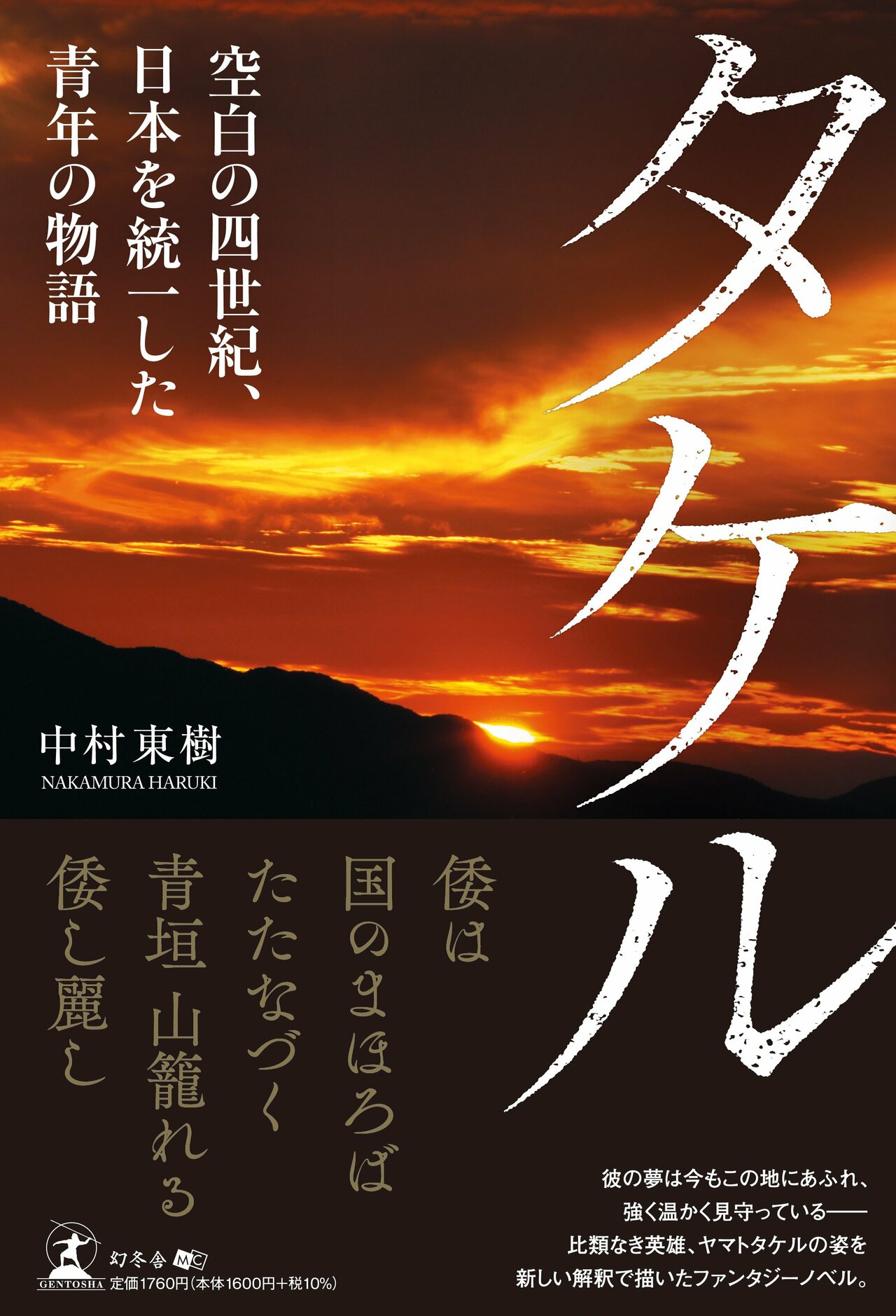【前回の記事を読む】厳しい母親に守られ、嫁に欲しいという申し込みもすべて拒絶。本人ももっぱら機織りに精を出していて…
第二話 機織り工房の皇女
3 神御衣の奉納
さかのぼること二年少し前の春のことである。 フタジは朝廷から特別に選ばれ、伊勢の五十鈴川のほとりで伊勢神宮の敷地内にある機殿(はたどの)に奉職したのだった。フタジの強い願いで、幼なじみのカンナも一緒に奉職することが許された。
纏向の居住地から伊勢まで、選ばれた五名の娘が三人の屈強な衛兵に守られて、二泊三日の行程で無事にたどり着くことができた。
伊勢の皇大神宮は、三十年前にようやくこの伊勢の地に天照大御神の御座所として定められたのである。始めは三輪山の神社に祭られていたが、神の望む場所を探していくうちに、転々と御座所を変えることとなった。その仮の行所の数は二十数か所にも及ぶとされている。
大神様の衣を神御衣(かんみそ)という。春と秋の年二回の神御衣(かんみそ)祭で、絹で織られた「和妙(にぎたえ)」と麻で織られた「荒妙(あらたえ)」の反物が奉納される。
フタジたちは、最初の一年は和妙、次の年は荒妙の織り手としてこの地に奉職したのだった。この二年の間は、伊勢の神聖な地から一切外に出ることなく、巫女として神御衣の製作に従事したのである。
伊勢の斎宮の倭姫(やまとひめ)(倭比売命(ゆまとひめのみこと))が何かと面倒を見てくれて、いろいろなことを教えてくれたのだった。この倭姫は、年はフタジより三十歳近くも上であるが、父はともに垂仁天皇で母違いの姉になる。そのせいか特別に可愛がってくれた。
伊勢の地でのフタジたちの最初の仕事は、和妙(にぎたえ)の製作に携わることであった。絹織物は現在でもそうであるが、非常に貴重なもので大王一族や有力な豪族しか身につけることはできなかった。
和妙作りの最初の仕事は、蚕(かいこ)の大好物の桑の葉を充分に与えることであった。元気な蚕を養うためには、いつも桑の葉がしっかりと育っているか見守っていくのも大切なことであった。