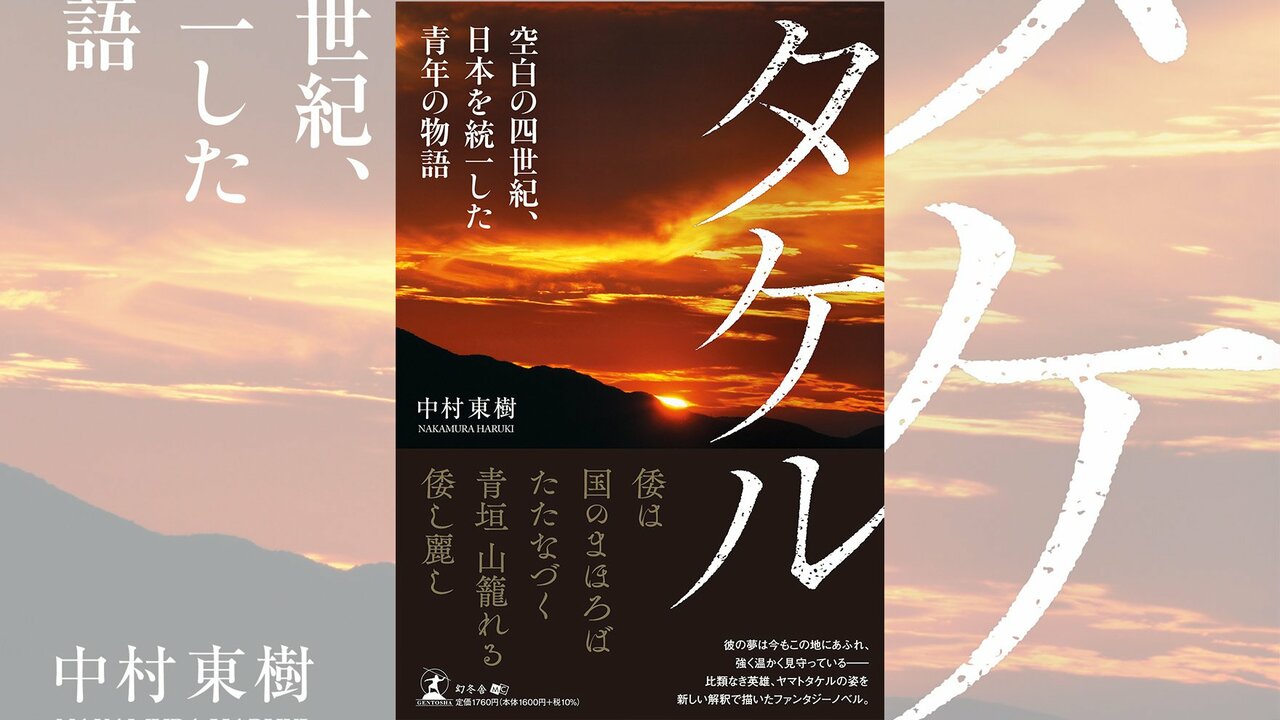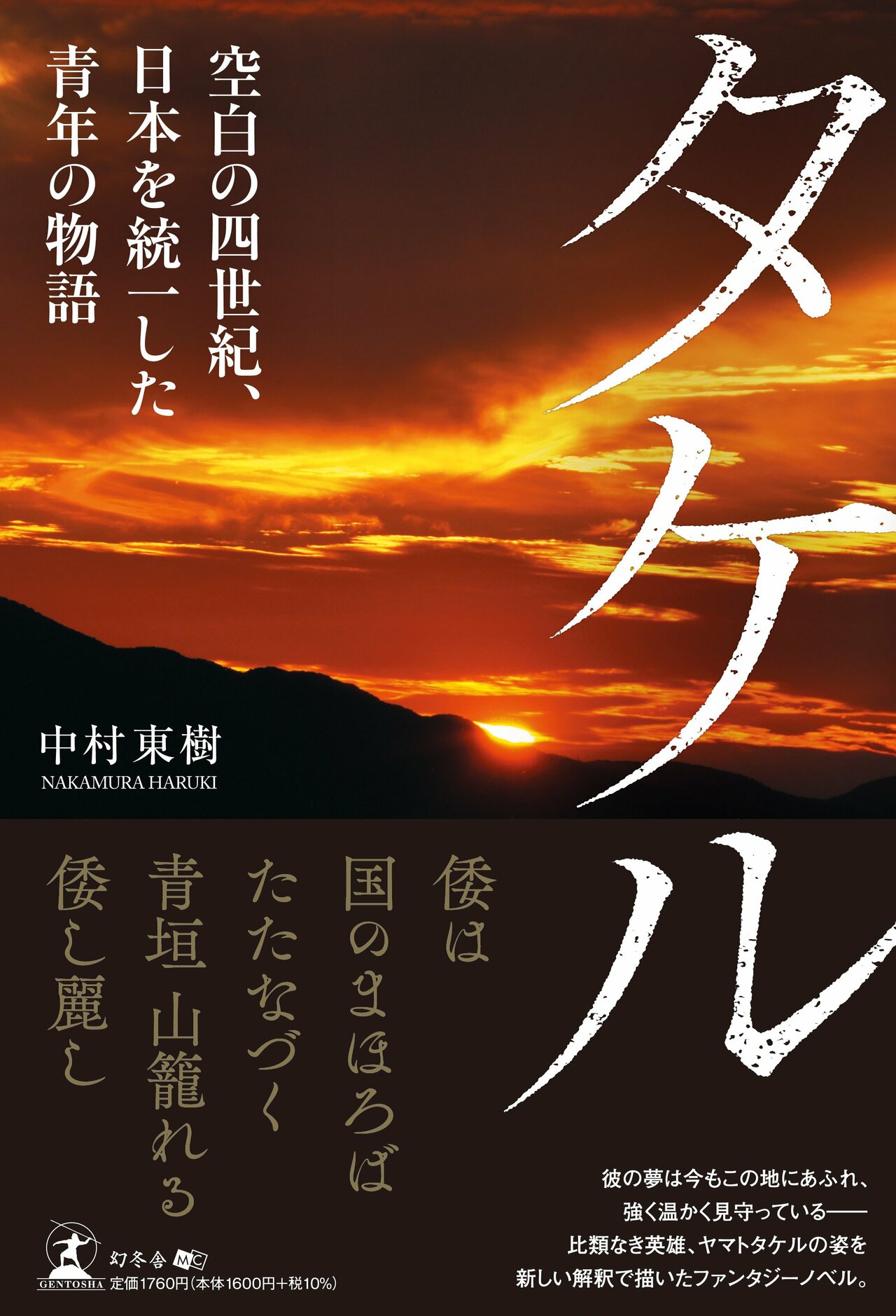【前回の記事を読む】幼なじみと共に機殿へ奉職したフタジ。最初の仕事は、和妙(にぎたえ)の製作に携わることであった…
第二話 機織り工房の皇女
3 神御衣の奉納
あの一本の細い糸からとても美しい織物が出来上がることに、フタジは喜びと誇りを感じていた。昔から伝わる機織りを自分がしっかり受け継ぐことができる喜びであった。十日間交代で五人の織子たちは和妙を織り続けた。そして見事な布が出来上がったのである。
斎宮の倭姫 (やまとひめ)は、出来上がった絹の布を手にして、大和からやってきた五人の娘たちにねぎらいの言葉をかけた。
「あなたたちが織られた和妙は、本当に素晴らしいものです。これなら天照大御神様も大喜びされるでしょう。
神様にささげる神御衣(かんみそ)は、織り子の技術や経験も大事ですが、澄み切った心、健やかな体、神へ奉納するという大役を任せられた誇りを持つことが大事です。今回できたこの衣をみれば、あなた方の心身の美しさが布に表れています。本当によく頑張りましたね。ありがとうございます」
倭姫(やまとひめ)の誉め言葉に、天にも昇るような幸せを感じたフタジたちであった。
春が過ぎて雨の季節がやってくる前に麻(あさ)の種を畑に蒔く。蒔いて数日すると発芽し、日々成長していく。四ヶ月もすれば自分の背丈以上に伸びてくる。
この時代衣服に用いられていた織物は、多くは麻(大麻(たいま)、苧麻(ちょま))を素材としたものであった。
麻は繊維として通気性があり、吸水性もみられる。水に濡れると強度が増してくる。光沢もあり、引っ張ったときに強いことでも知られる。着物以外にも、魚網、縄、蚊帳、下駄の鼻緒など多くの使途があった。種子は食用や生薬の痲子仁(ましにん)として、麻の実油は食用や燃料として使用された。
フタジたちは、二年目になると麻の種まきから栽培、収穫、そして葉や茎の繊維から時間をかけて糸を取り出して紡いでいくのである。機織りで荒妙と呼ばれる布地を作っていった。さらに布から衣服をつくることまで徹底的に学んだのである。
数日間の苦労の末、神に供える荒妙の織物が完成した。フタジの織った荒妙の布地を手にした倭姫は、手触りの良さ、肌理(きめ)の細かさ、生地の強さ、美しさに満足していた。
「あなたは生まれながらの素晴らしい機織りの才能を持っている。これ以上教えることは何もありません。これからもこのような織物をずっと造り続けてください。そして多くの娘たちにこの技術を教えてあげてください」
倭姫は、他の娘たちにも労いの言葉をかけた。
二年の勤めを果たした後、五人の娘たちはまた纏向の宮殿に帰ってきた。二年間の伊勢神宮での奉職は、素晴らしい機織りの技術を得ただけでなく、機織りの仕事を通して新しい国の礎となる自覚と誇りをもつこととなった。美しく大きく成長した娘たちの姿がそこにあったのである。