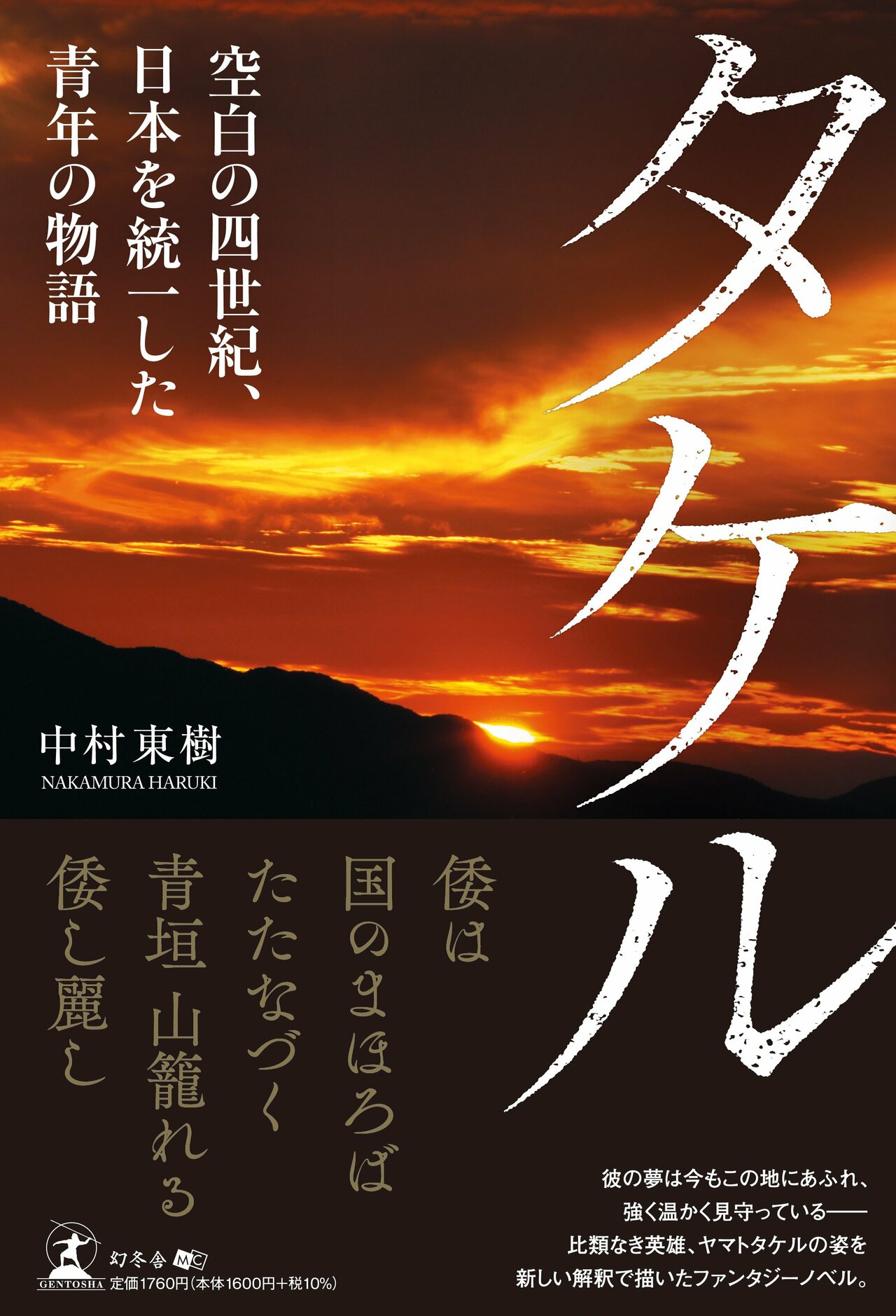養蚕(ようさん)は大昔から中国で行われていた。この蚕という動物は、何千年も前から人間に飼われている昆虫であり、言い方は悪いが絹織物の生産のためにだけ存在する動物である。
あまりに家畜としての歴史が長いために、人の手の入らない野生にもどしても、生きていくことはできなくなっている。日本では昔から「お蚕様」として、家族で大事に受け継いできたのである。
フタジたち和妙(にぎたえ)の担当となったものは、蚕の様子を昼夜を問わず交代で観察していた。孵化して五週が立つと繭を作ってくる。
これが終わると繭を乾燥してから煮ていく。煮ることでほぐれやすくなった繭の表面をみご箒(ほうき)(稲の穂先で作ったほうき)で撫で、糸口を探し出す。そして糸口をみつけて、何本か撚(よ)りながらまとめていき、目的の長さ・太さの一本の糸を繰り上げていく。撚りあわされた長い一本の糸だが、これを乾燥すると撚られた糸が接着して、強い糸になるのである。
生糸ができると今度は機殿神社内の八尋殿で、和妙(にぎたえ)の御衣(おんぞ)を織る作業が始まる。天照大御神への奉納は毎年春の候とされている。作業は十日ほどかかるので、その間はまた忙しい日々が続く。
二台の機織り機が準備されていた。機織りの基本的な手技はこの時代にすでに出来上がっており、天秤腰機(てんびんこしはた)と呼ばれる機械であった。宗像大社に国宝として保存されている金銅製のミニチュアは、非常に精巧に作られており、実際に布を織ることができるのである。
この織機は古墳時代のものとされており、フタジたちの時代には機織りはヤマト各地で行われていた。
「機織り」とはなにかと一言でいうなら、多数の「経糸(たていと)」に一本ごとに「緯糸(よこいと)」を通すための仕事である。機織り機に上下の動きが異なる二つの「綜絖(そうこう)」を用いる。そのとき「綜絖通し」という経糸を一本ずつ交互に通しておく作業がある。
二つの綜絖は、踏板と連結しており、一方を踏むと半分の経糸が上に挙がり、手元を頂点とした三角形の空間ができる。そこに「杼(ひ)」と呼ばれるシャトルを通すことによって連結された緯糸(よこいと)が通される。通した緯糸は「筬(おさ)」という櫛状の板で手前に引いて打ち込まれる。
次にもう一方の踏板を踏み込むと、もう一方の綜絖に通された半分の経糸が上に挙がり、さきほど上がっていた経糸は下に下がる。新たな空間に反対側から杼を通していく。また筬を手前に引いて打ち込む。
この作業をずっと繰り返すことによって、交互に経糸と緯糸が織り込まれて平織りの布ができていく。
原理は簡単であるが、この綜絖という道具が考え出されたことにより、いろいろな素材の糸を用いて多くの種類の布織物を、人は手に入れることができるようになったのである。
フタジは、和妙(にぎたえ)をつくるために一心不乱に作業に打ち込んだ。細い一本一本の糸が機織りをつづけるうちに見事な布に変わっていくのである。機織りの仕事や機械の原理はとても簡単だが、出来上がった布地を手にした時の素晴らしさは何事にも代えがたいものがあった。
【イチオシ記事】「浮気とかしないの?」「試してみますか?」冗談で言ったつもりだったがその後オトコとオンナになった
【注目記事】そっと乱れた毛布を直し、「午後4時38分に亡くなられました」と家族に低い声で告げ、一歩下がって手を合わせ頭を垂たれた